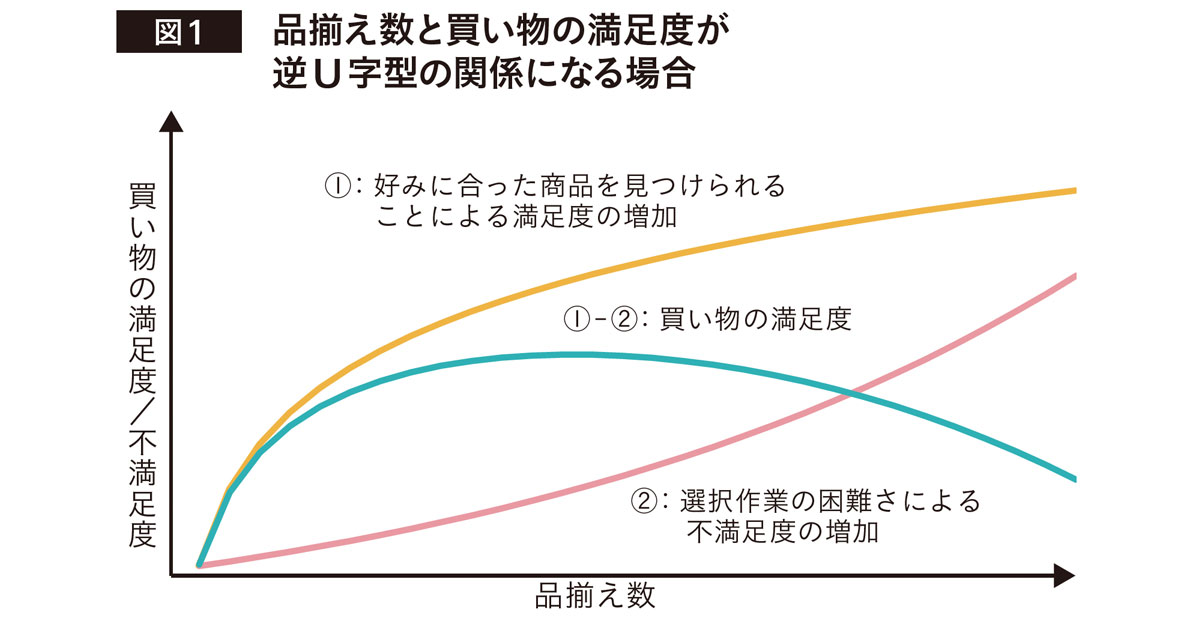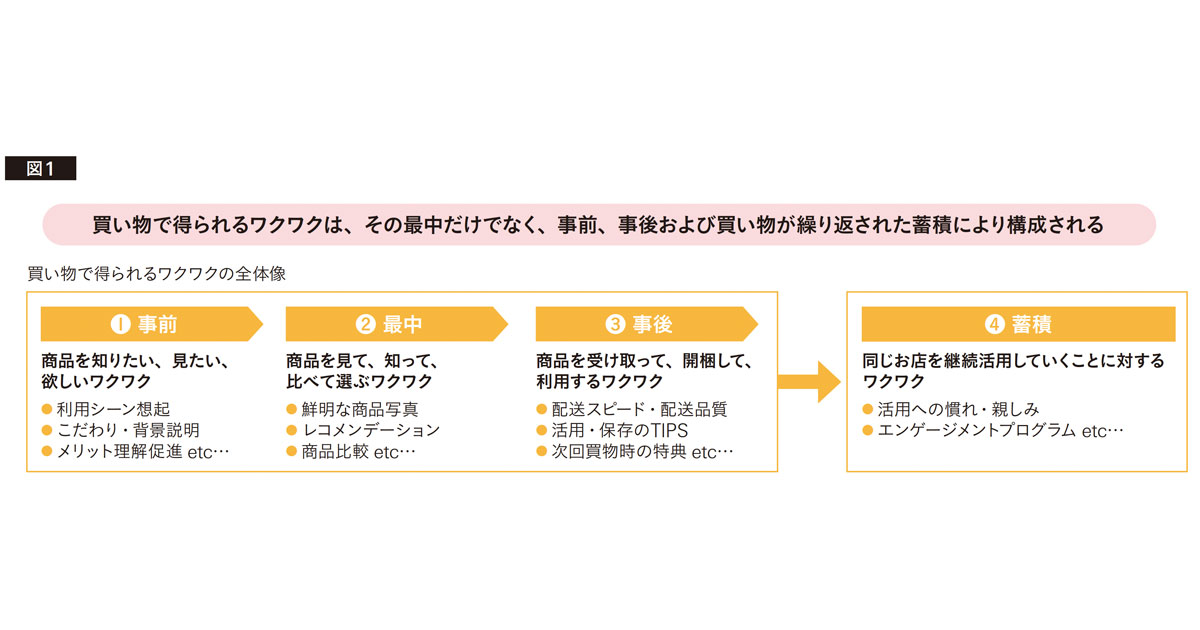資産形成の普及を通じて「投資の好循環」を生み出し、持続可能な社会の実現を目指す野村アセットマネジメント。しかし、金融サービスの利用は生活者のリテラシーが必要な部分も大きい。複雑性の高い商品をわかりやすく、かつ楽しく伝えるためには何が必要なのか。同社、資産運用研究所の稲岡夏紀氏から、同社が実際に取り組むコミュニケーションについて聞いた。
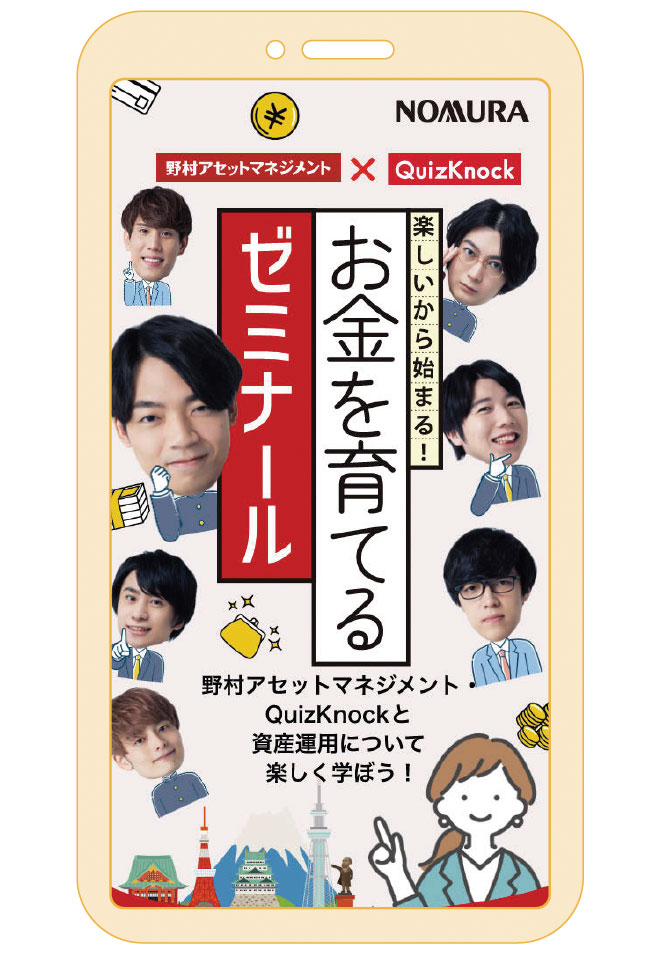
理解が難しい金融商材 言葉の難しさが知るハードルに
「資産形成/運用」「投資」⋯⋯。金融にまつわるサービスには難しさを感じる生活者も多い領域。「知識がなければ始められない」という心理的ハードルも少なからず存在するのが金融商材の特徴と言える。
野村アセットマネジメントもこの課題に向き合い、「難しさ」の低減を目指す取り組みを行っている企業のひとつだ。投資や資産形成について、生活者の役に立つ情報を発信する役割を担う資産運用研究所を設立。「人生100年」を生きる現代人の資産形成を支える活動を行っている。
学生に資産運用のセミナー? 施策の認知はどう獲得したのか
その資産運用研究所の施策の一環として行われているのが「お金を育てるゼミナール」だ。本企画は、学生を対象に実施されているもの。QuizKnockを中心となって運営する東大クイズ王の伊沢拓司氏をアンバサダーに起用し、社会へ出る前から投資や資産形成についての情報に“楽しく”触れてもらい、将来的なお金の使い方の選択肢のひとつとして知ってもらうことを目的としている。
具体的にはQuizKnockとのコラボ動画の発信や、全国を回るセミナーである「お金を育てるキャラバン」の開催などが主な取り組みだ。
しかし、成人でも投資を学ぶことに難しさを感じ、自ら情報に触れようとしない人が多い現在。子どもだと、なおさら投資への自分ごと化が十分でないことは想像がつく。このような金融情報の初心者とも呼べる学生に対して、「お金を育てるゼミナール」はどのように認知獲得施策を行っているのか。
資産運用研究所長の稲岡夏紀氏は、学生が資産形成について能動的に調べないことは想像の範囲内として設計していると話す。
「2022年4月に金融教育が高校のカリキュラムに追加され、学生もお金について学ぶ時代になっています。とはいえ、自ら情報を得ようとする学生はまだ少ないことは想定していました。そこで、引っ掛かりをつくるために起用したのが...