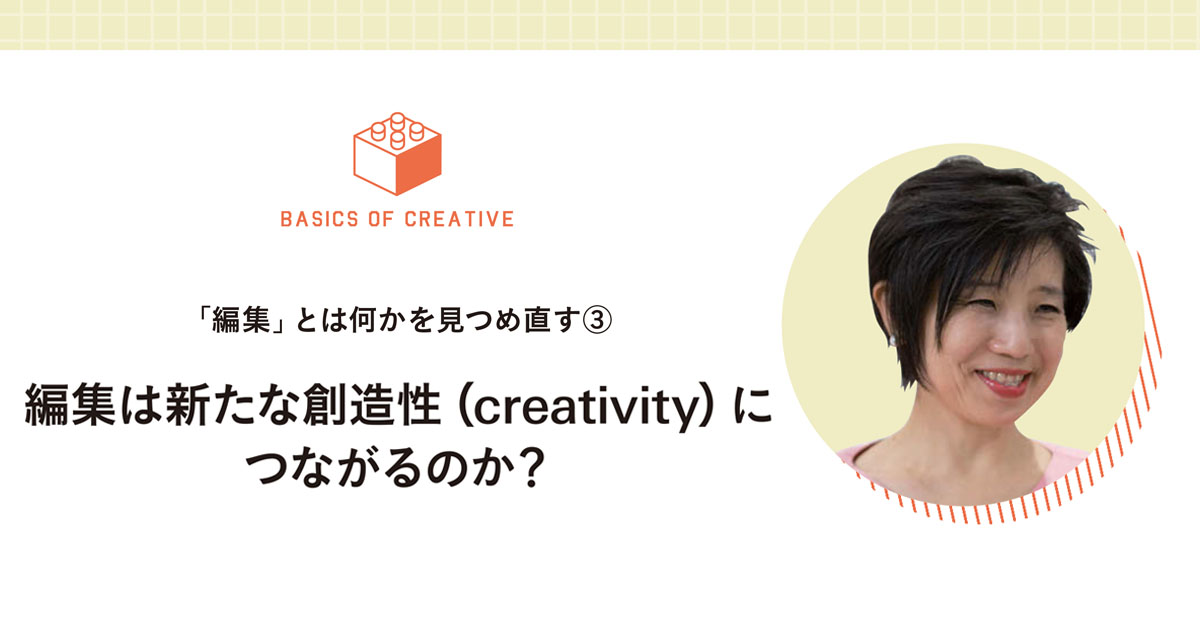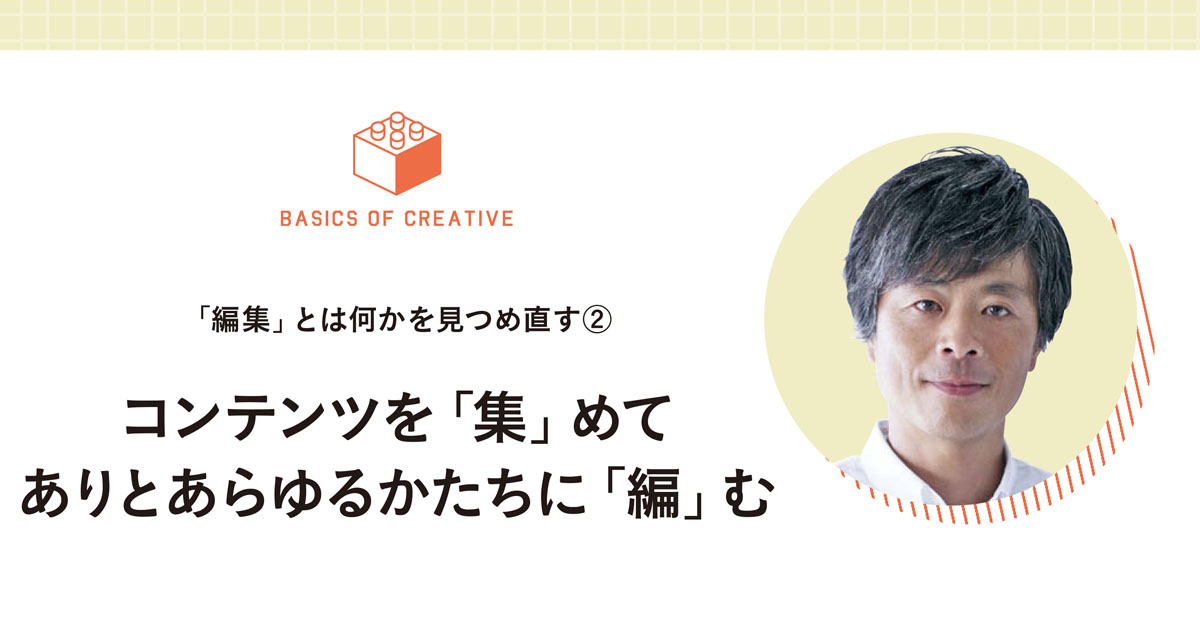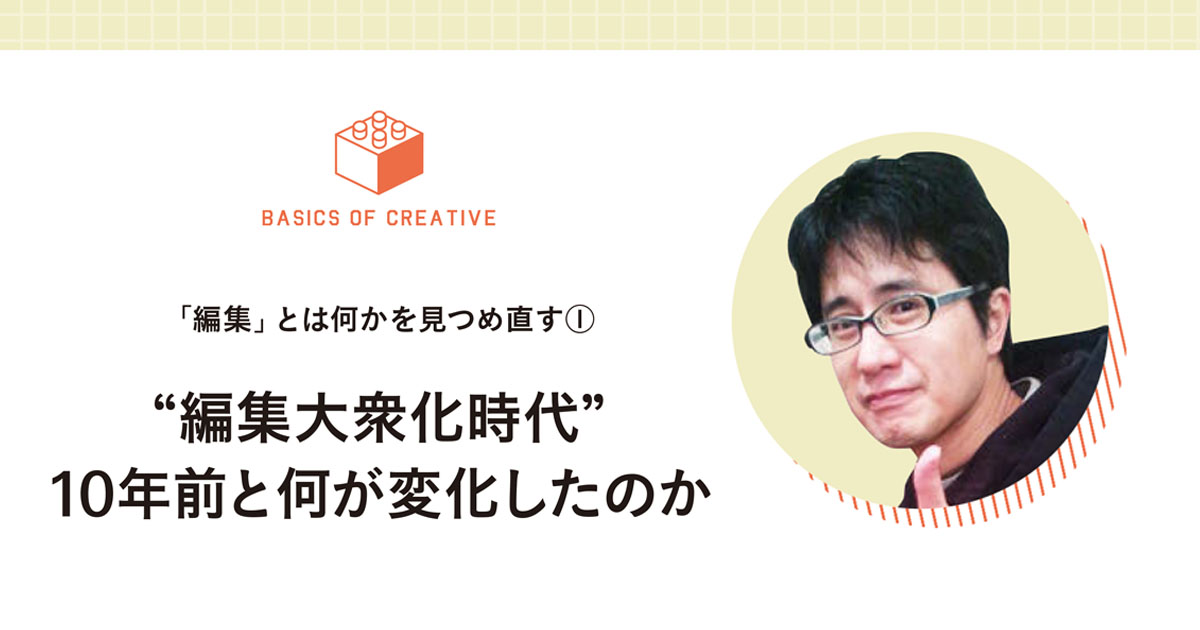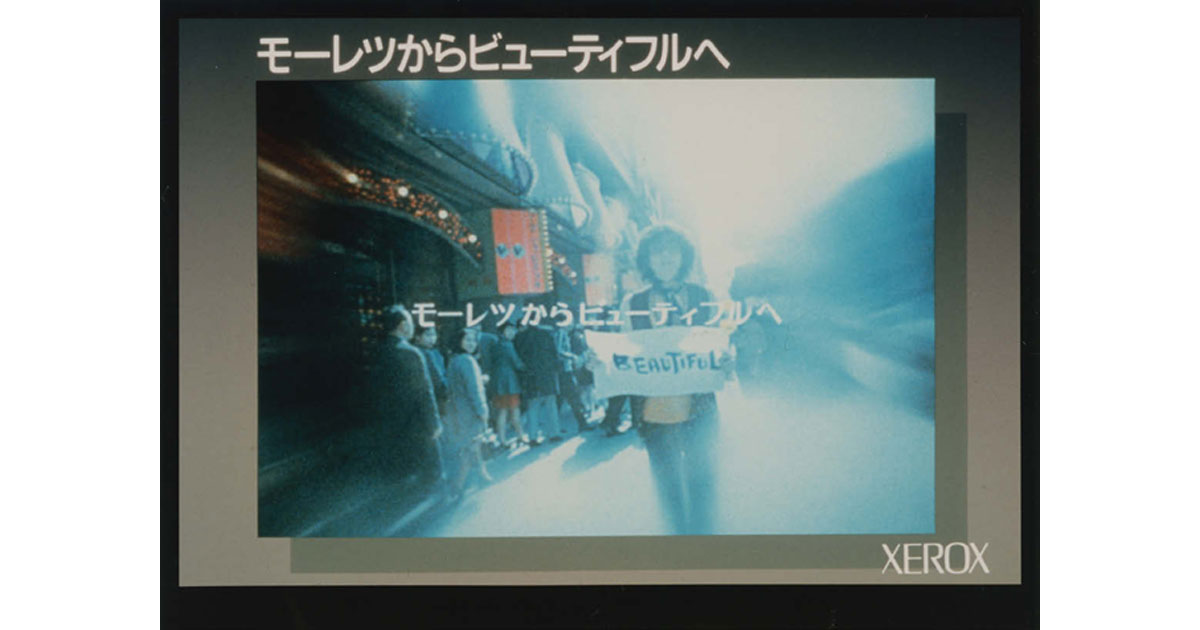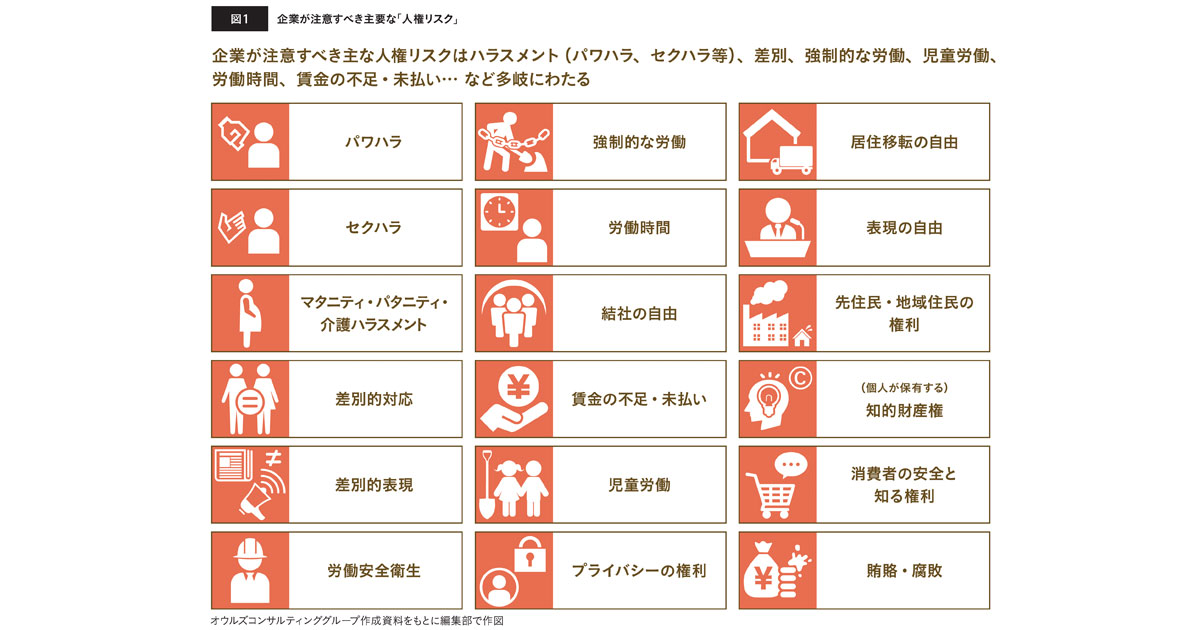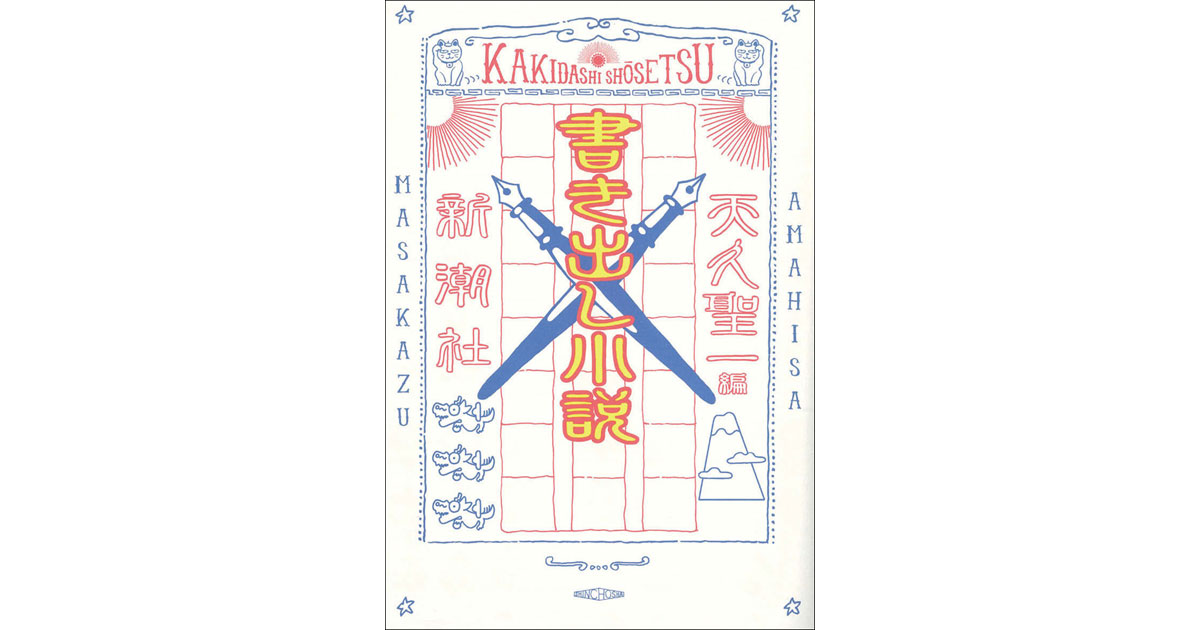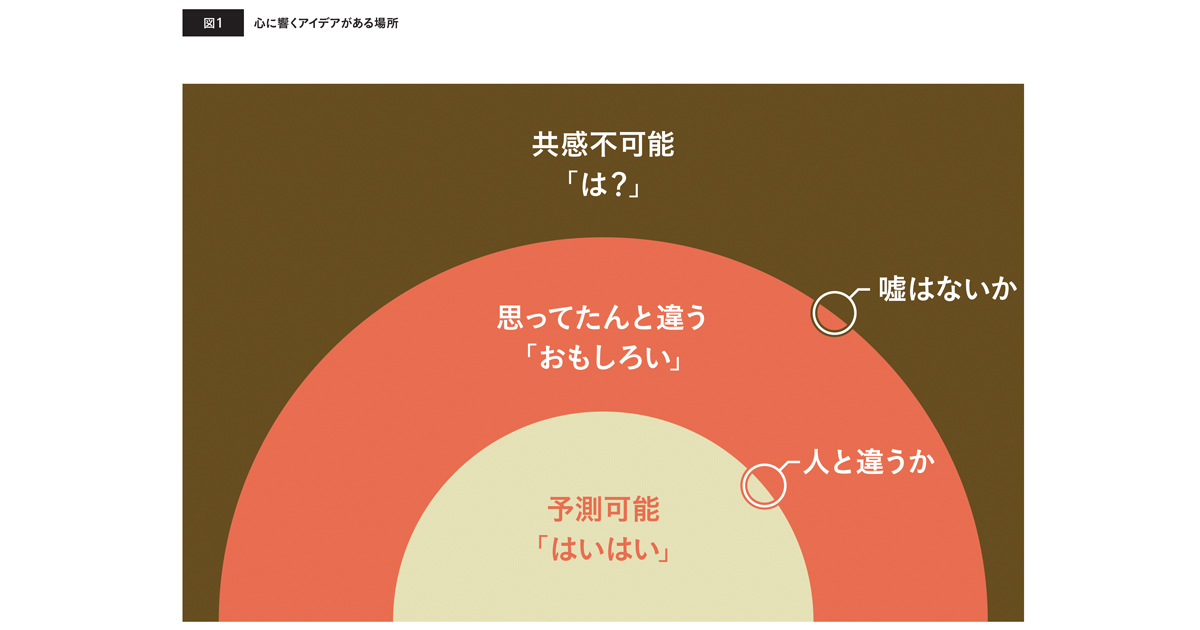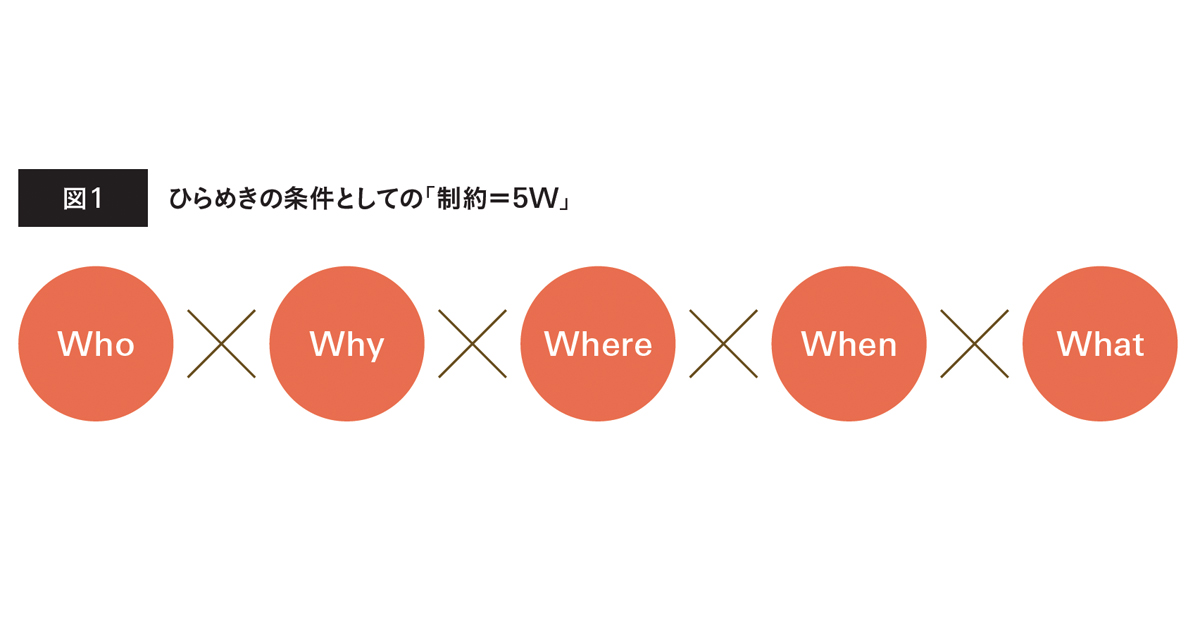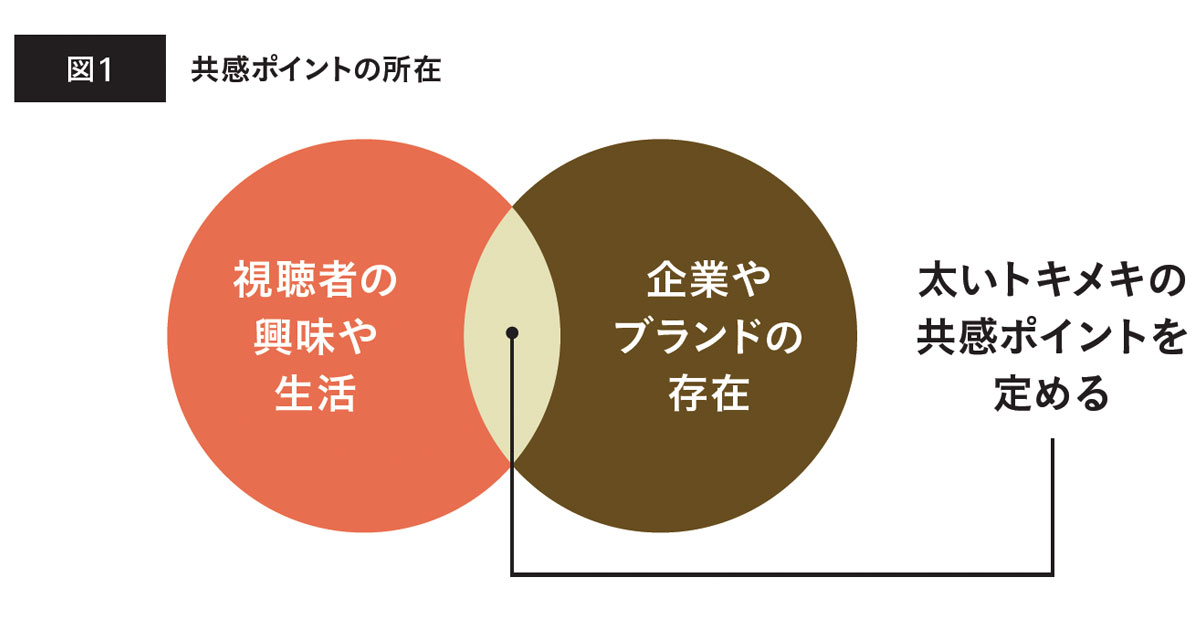「編集」とは
☑観察力を養い、自分なりに事物を解釈する力を持つこと。
☑事物の間に親近性を見つけられる想像力を身に付けること。
☑その親近性をナラティブなものに形成できること。
キュレーションが担う役割は事物同士の関係価値の提示
情報を集めて、つなげて、コンテンツにする。これを編集という行動のひとつの定義であるとするならば、キュレーションも編集と言えるのかもしれません。まさに選択して、ひとつの文脈をつくり、異なった事物や情報を集めてきて、見せる。そのような空間をつくっていくわけですから、キュレーションは編集に近しい部分もあると思います。また、出版物や情報プロダクツには、発信するテーマがどのようなものであるかという統合的な概念を示す必要があるという意味でも編集とキュレーションは似ているのかもしれません。
では、編集とキュレーションは何が違うのか。
私の考えるキュレーションは「関係価値の形成」です。例えば、Aという事物とBという事物があったとします。私の場合、事物の対象は作品を指しますが、それぞれを合わせることによって、AとBを単体で見ていたときとはまた別の意味合いが発生するはずです。AとBを並べることによって生まれる新たな意味や関係価値を見せる。これがキュレーションの担う大きな役割です。
もしかすると事物Aになり得るのはアート作品だけではなく、アートとみなされないもの、テキストやそこに落ちているペンなどもそうです。
これらを展覧会というひとつの空間に並べる。それによって、あるひとつの生活圏や時代を表すことができるわけです。ある意味「マッピング」ともいえるような行動から、どのように意味を生成させるのか。これがキュレーションには大事になります。
ですが、私が行っているのは、平面で完結する記号的な編集ではありません。つまりただ情報だけを集めて平面上、例えば雑誌や新聞などのテキストにまとめる編集ではないということです。
私が編集しているのは空間や事物、すなわちアートです。アートはひとつの作品であっても、見る人によって捉え方が変わるような極めて曖昧なもの。異なるものを同じ空間に並べたとき、自分でも想像がつかなかったような化学反応が生まれることも多々あります。この化学反応は私だけではなく、きっとオーディエンスにも同じように起きているはずです。事物と事物の間で行われる、広義で、ある種の編集という行動の中で新たな関係価値が形成され、化学反応が起こる。現時点で私が考えるキュレーションの面白さはここにあると考えています。
遠くのものと近くのものを見て両者の親近性を捉える
私がしているキュレーションという仕事を編集として考えると、スキルとしてこれを身に付けるためには、既存の概念から外れた視点で物を見ることが大切だと考えます。
今年5月~7月、金沢21世紀美術館では甲冑とライゾマティクスのスキャニング技術による甲冑断面の図面化、そして現代の甲冑とも言えるスニーカーを組み合わせた「甲冑の解剖術─意匠とエンジニアリングの美学」という展覧会を行いました。
甲冑とライゾマティクスとスニーカー。なぜこれらを組み合わせたのか、その理由は私にしか説明ができないことです。それを展覧会として伝えることが私の考える編集。つまりそれは、いつも考えていること、いつも周りにある既存の概念を疑うこと、これが私の「編集」におけるひとつの方法論だと思っています。
日常の既存の概念を疑うということは同時に...