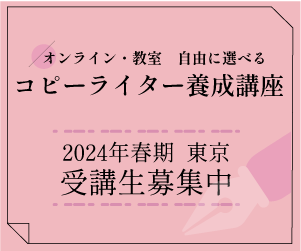コロナ禍をきっかけに喫緊の課題として進めてきたデジタルシフトの状況を振り返り、復活しつつあるリアル接点との融合など、顧客接点を再構築した新たな体験づくりが求められている。ワイナリーとWebサイトの二軸で新たなコミュニケーションの場を創出する、サントリーワインインターナショナルの取り組みについて話を聞いた。
ワイナリー起点のブランド構築 顧客とつながり続ける仕組みつくる
山梨県甲斐市に位置する「サントリー登美の丘ワイナリー」。1909年の開園以来、同社の自家農園としてぶどう栽培から製造、販売までを担ってきた。
2022年、同社はこのワイナリーを起点としたブランド開発と育成に注力する方針を掲げ、情報発信やコミュニケーションの仕組みづくりを行っている。
これまで東京本社のワイン事業部でブランドマネージャーを担ってきた前田淳志氏は、マーケティング担当の役割を持ったまま今年3月、登美の丘ワイナリーに拠点を移した。マーケティングチームや生産管理と、ものづくりの現場をつなぎ、リアルの接点とデジタルを融合。“顧客とつながり続ける仕組み”を構築していこうとしているのだ。
日本ワインだからこそ可能なリアルの場でのコミュニケーション
国産ブドウを100%使用して国内で製造されたワインを「日本ワイン」と呼ぶ。
「日本の土地で、日本人に合うワインをつくる。1907年に登場した『赤玉ポートワイン(現・赤玉スイートワイン)』は、当社の洋酒事業の原点でもあります。またグループ全体でサステナビリティ経営と向き合うなかで、ワイナリーでは100年以上にわたって循環型農業に取り組んできました。そのため単純に売上規模だけでは見えてこない価値があると、社内でも捉えられてきましたし、そうした価値・魅力を、お客さまにも届けていきたいという思いがありました」(前田氏)。
ワイン市場が踊り場を迎えつつあると言われているなか、日本ワインの消費量は過去10年間で1.5倍に。国内のワイナリー数も年々増加しているという。コロナ禍では、余暇時間の過ごし方の変化などにより若年層が流入。ワインに触れる機会としてリアルの場が機能しにくくなったこともあり、デジタル上の接点づくりは喫緊の課題だった。
「お客さまとの接点づくりは、実はコロナ禍以前からの課題でした。来園者の方々には非常に満足していただいていましたが、来園できる方の人数は限られます。また、その場で購入できるワインの本数も限られていますし、家に帰ってから、同じものを...