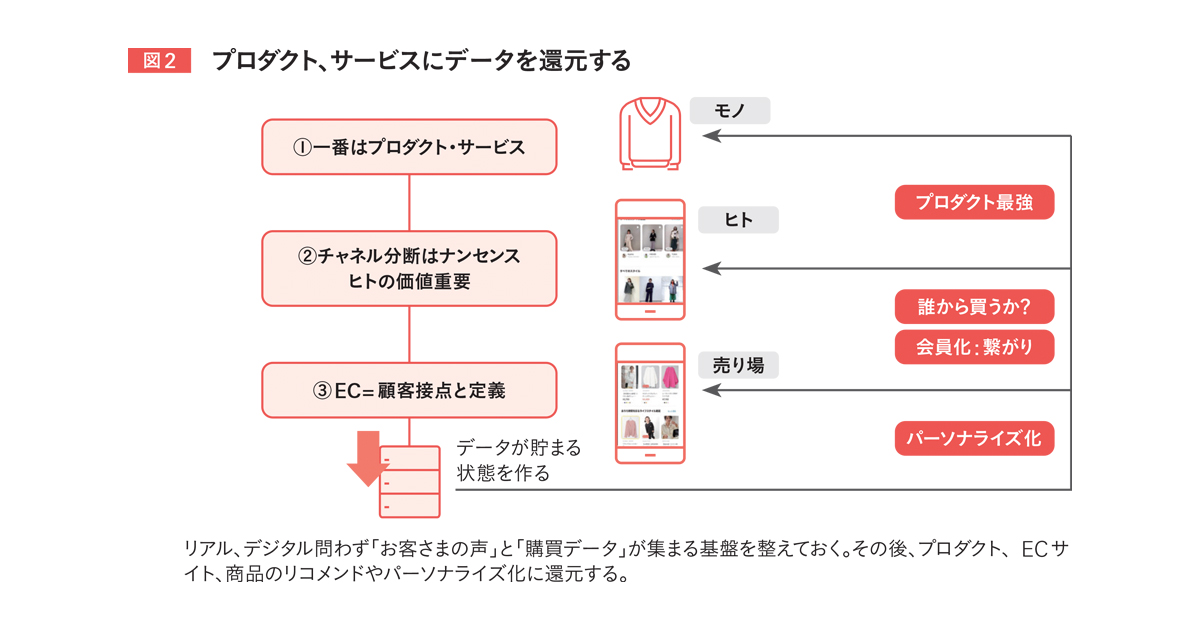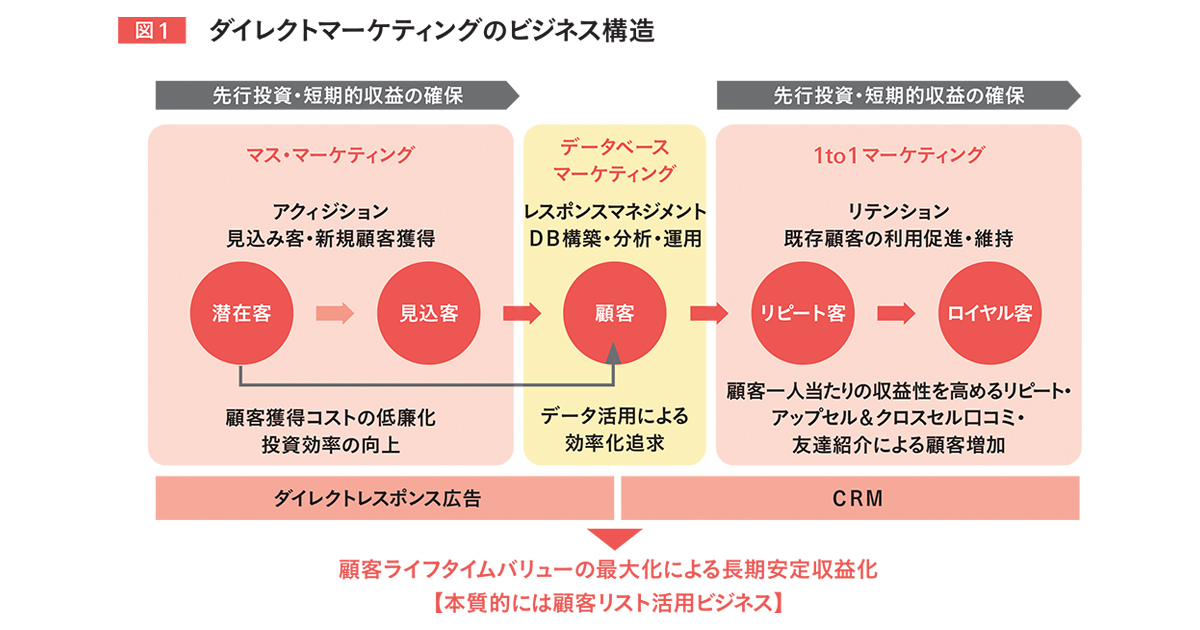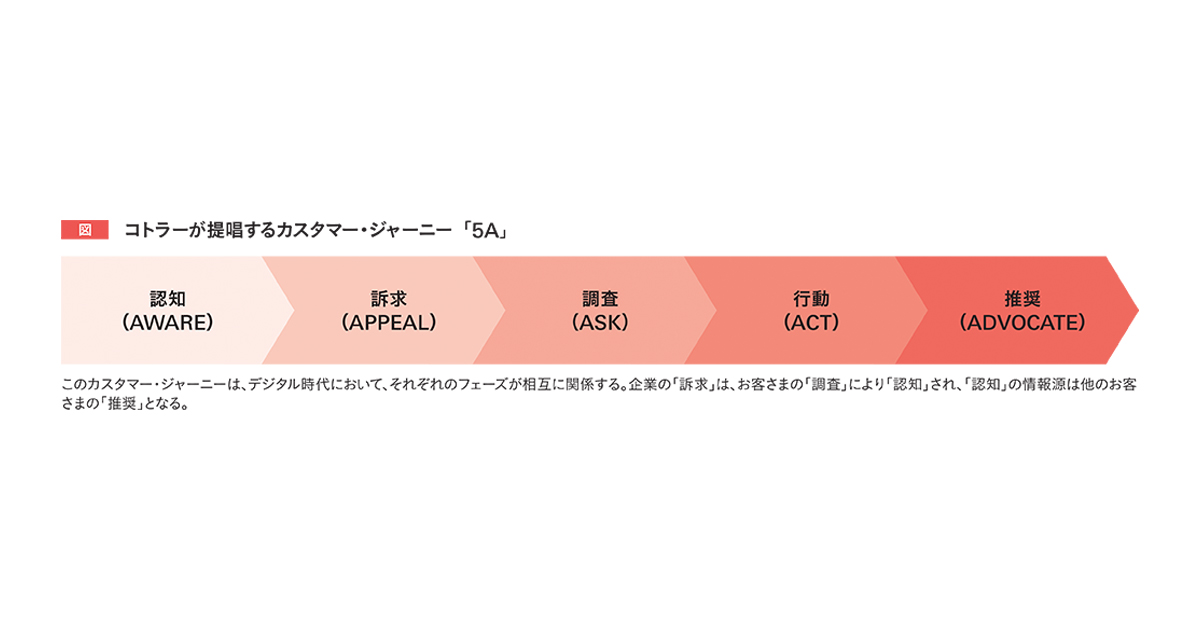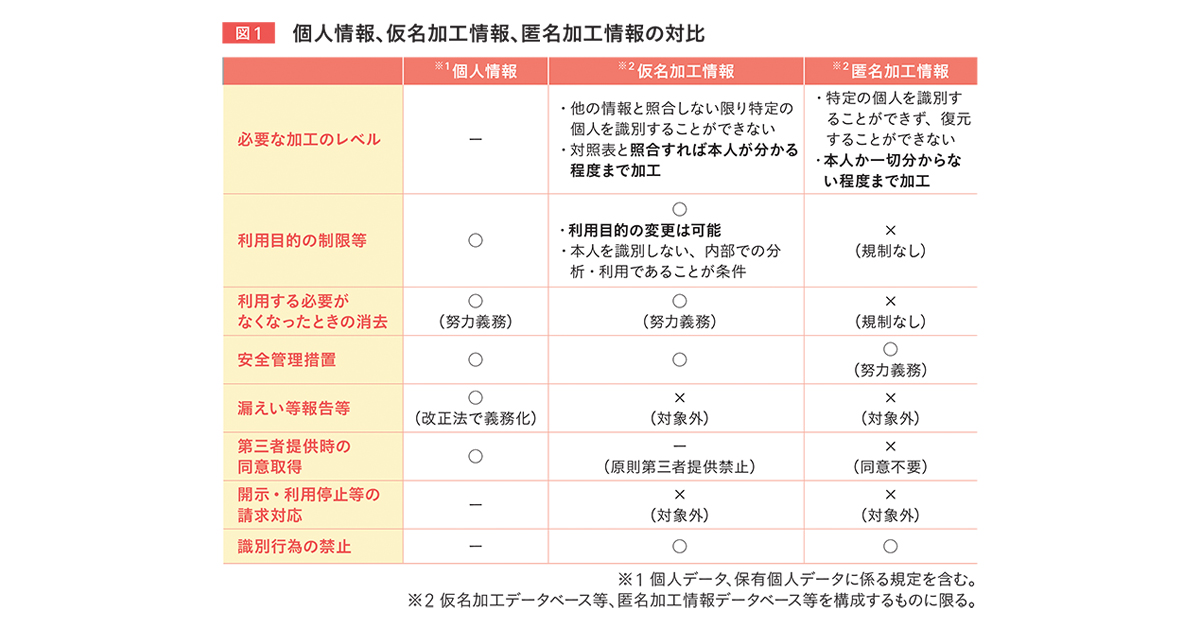国内に目を向ければ人口は縮小傾向にあり、新規開拓だけでなく既存顧客との関係性強化を目指すマーケティングの必要性が叫ばれてきた。これからの顧客との関係性について、企業はどのように捉えるべきなのか。マーケティングサイエンスラボの所長を務める本間充氏が解説する。
古くて新しいCRM ルーツは江戸時代に遡る
インターネット技術やデジタル技術を駆使する、3文字アルファベットのCRMは、IT技術の進化によって広まったマーケティングのデジタル・ツールのことを呼びます。ツール自体は新しいのですが、CRMを「顧客関係管理」と訳すと、このマーケティング活動は今に始まったことではないことがわかるのではないでしょうか。
元をたどれば江戸時代の商人は、商売を台帳で管理していました。この時の台帳は多くが顧客台帳であり、例えば「吉右衛門さんが、帯を、十文で購入」などの情報が記録されていました。商人は、この台帳を見返して、お客さまの購入予測を行い、商品を仕入れて、お客さまの来店を待っていました。従って、「顧客関係管理」は、「マーケティング」という言葉の登場よりも古くから、行われていたのです。
この「顧客関係管理」をデジタル化したものがCRM(Customer Relationship Management)です。ただし、このCRM登場には少し問題があります。それは、マーケティングに起きた不連続点の発生です。この不連続点の存在が、現代の私たちがCRMを上手に活用できない理由のひとつでもあります。
江戸時代の「商い」は、今の言葉で言うと、「顧客ごとにパーソナライゼーションされたマーケティング」です。今風に言えば、「ダイナミック・プライシング」だったでしょう。それが、昭和30年頃から始まる、「大量生産」「大量消費」時代のマス・マーケティングの登場により、江戸時代の「商い」の手法が忘れ去られることになるのです。
スーパーマーケットのレジでは、誰が買ったかではなく、何が売れたかという「ヒット商品」の記録が残るようになりました。これは江戸時代の顧客台帳とは真逆のものです。
皮肉なことに、その後ID-POSの登場により、「顧客」と「商品」の購入情報が、たまたま両方残るようになりました。このレジの進化により、実は江戸時代の「顧客台帳」の進化版、「デジタル版・顧客台帳」を生むことになったのです。ある意味、CRMの基本ツールの登場といえます。
しかし、商品を基点にした台帳に慣れてしまった私たちは、江戸時代の「商い」の手法を忘れてしまいました。その結果、古くて新しい「デジタル版・顧客台帳」と悪戦苦闘しているのです。
「企業」と「顧客」ではなく「友人関係」だと考えてみる
それでは、この「デジタル版・顧客台帳」との悪戦苦闘から脱却するためには、どうしたらよいでしょうか?
江戸時代に戻る。それは、ひとつの答えです。江戸時代の手法をITの力で、今風にDX化すれば良いのでしょう。そこで私が提案している方法のひとつが...