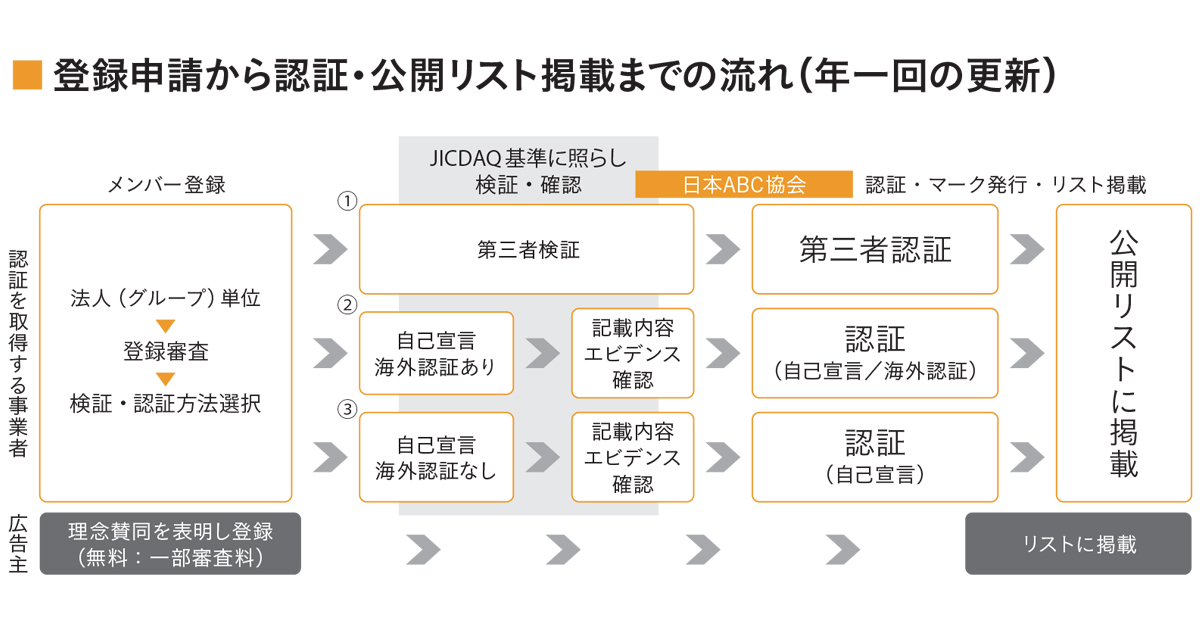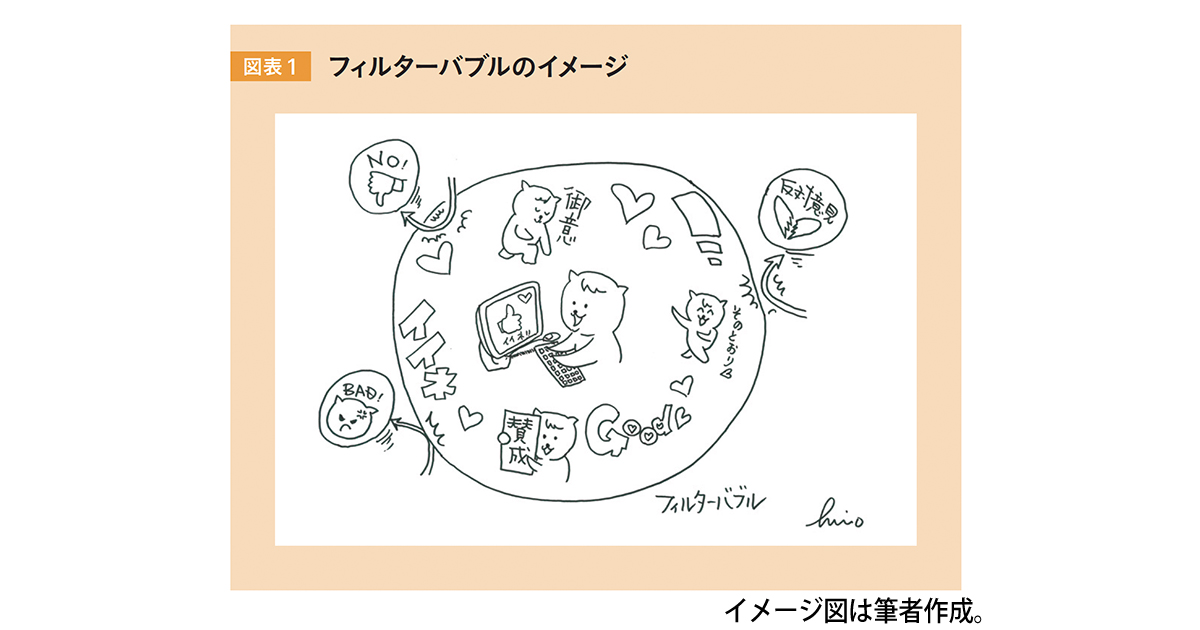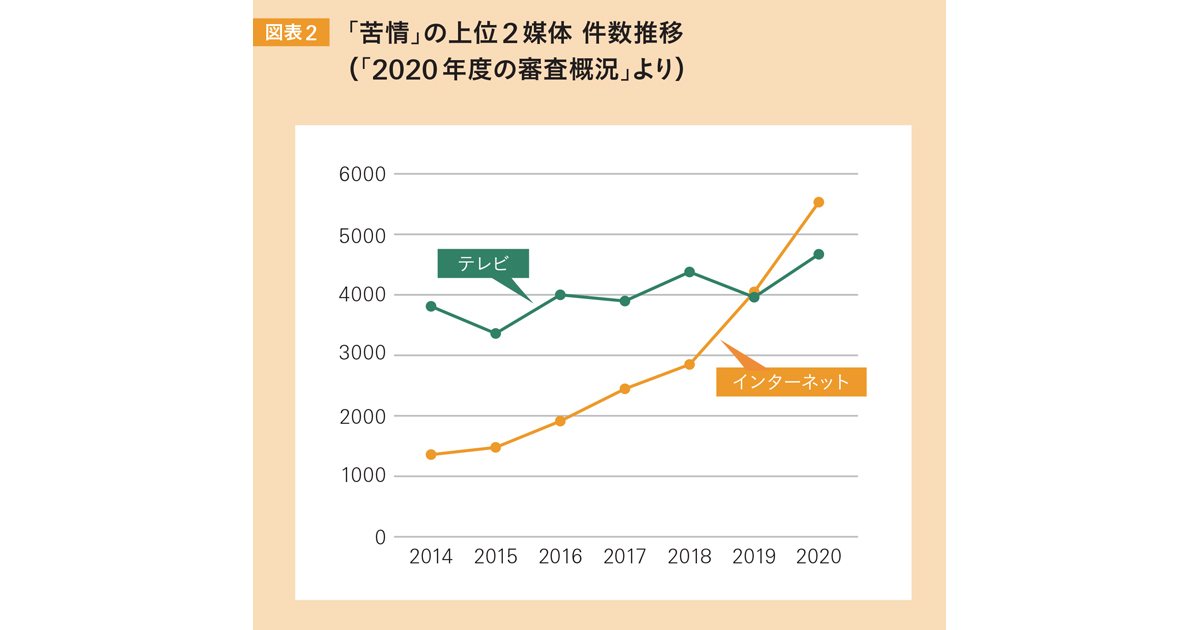日本におけるインターネット広告費は年々増加しているが、それに伴い「アドフラウド」など、デジタル特有の被害も生まれている。いま、広告活動において求められる倫理観とはどのようなものか。関西大学 教授、古賀広志氏が解説する。
デジタル広告は銀の弾丸ではない 運用型広告の落とし穴
デジタル広告、特に運用型広告が好調です。これはインターネット検索をする際に利用したキーワードや閲覧したWebサイトなどをもとに、個別に興味関心に応じた広告を届けるタイプの広告を指します。運用型広告は効果を期待できる相手にだけ安価に広告を提示し、その効果を可視化できる点からデジタル広告のなかでも期待が寄せられています。
しかし、デジタル広告は「銀の弾丸」ではありません(銀の弾丸とは、不死身の怪物オオカミ男を一撃で退治できる弾丸。そこから、経営の難問題をパッと解決してくれる万能薬の意味で使われています)。
デジタル広告の問題点としては、詐欺問題(アドフラウド)が指摘されています。たとえば、人間ではなく、不正プログラムがアクセスしたにもかかわらず広告表示(インプレッション)数を水増しする方法などが、これにあたります。
また、広告クリック数の中には、スマートフォンの誤操作によるものも少なくありません。そのために、広告は表示数ほど閲覧されていないと言われています。
社会問題にもなりうる倫理課題 マス破壊兵器とフィルターバブル
さらに、運用型広告の倫理的課題が注目されています。たとえば、米国では、適切な教育を実施せずに金銭を払えば卒業証書を発行する非認定機関(ディグリーミル)による運用型広告が問題視されました。そこでは、Webサイトの閲覧履歴などをもとに学歴コンプレックスを抱く人々を抽出する方法(アルゴリズム)が利用されました。このようなアルゴリズムは大量破壊兵器になぞらえて「マス破壊兵器(weapons of math destruction:WMD)」と呼ばれます※1。マスを「大量」から「数学」に置き換えたのです。
※1 O'Neil, C.(2016)Weapons of Math Destruction:How big data increases inequality and threatens democracy. Crown(久保尚子訳『あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠』インターシフト, 2018年)。
しかし、マス破壊兵器に騙されてしまうのは個人の責任ではありません。インターネットそのものが騙されやすい環境になっているからです。Googleなどの検索サイトは、インターネット上での私たちの行動履歴をもとに関連性の高いサイトを表示する傾向にあります。結果的に私たちは、検索履歴をフィルターとすることで、同じような情報ばかり表示される心地よい泡の中に安住し、見たくない情報が自動的に...