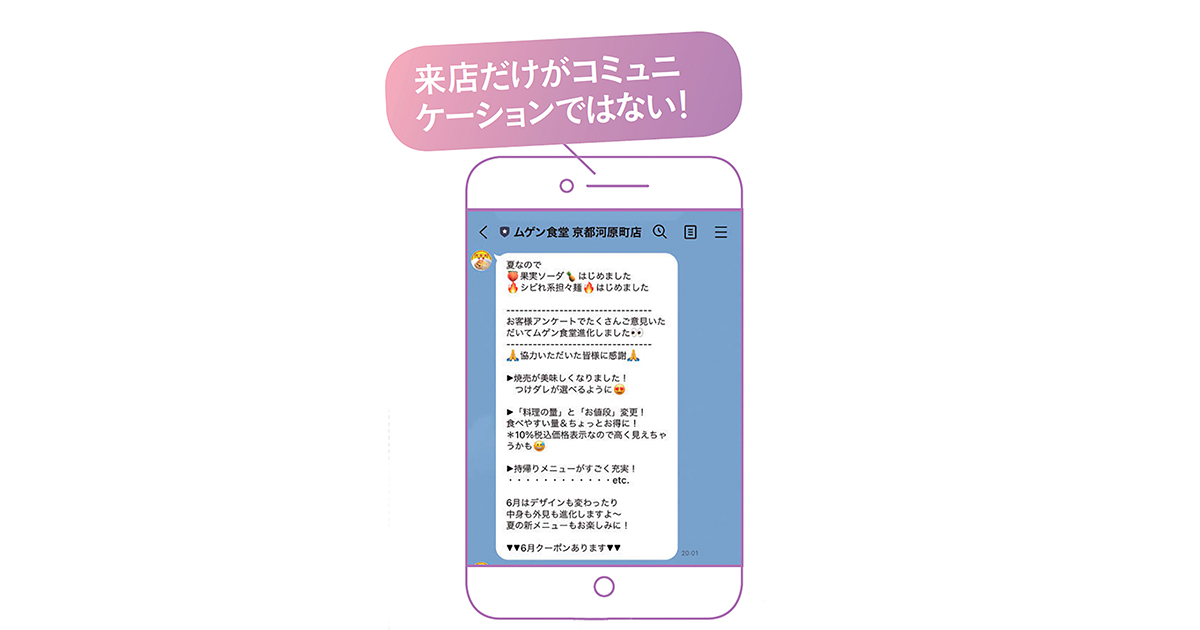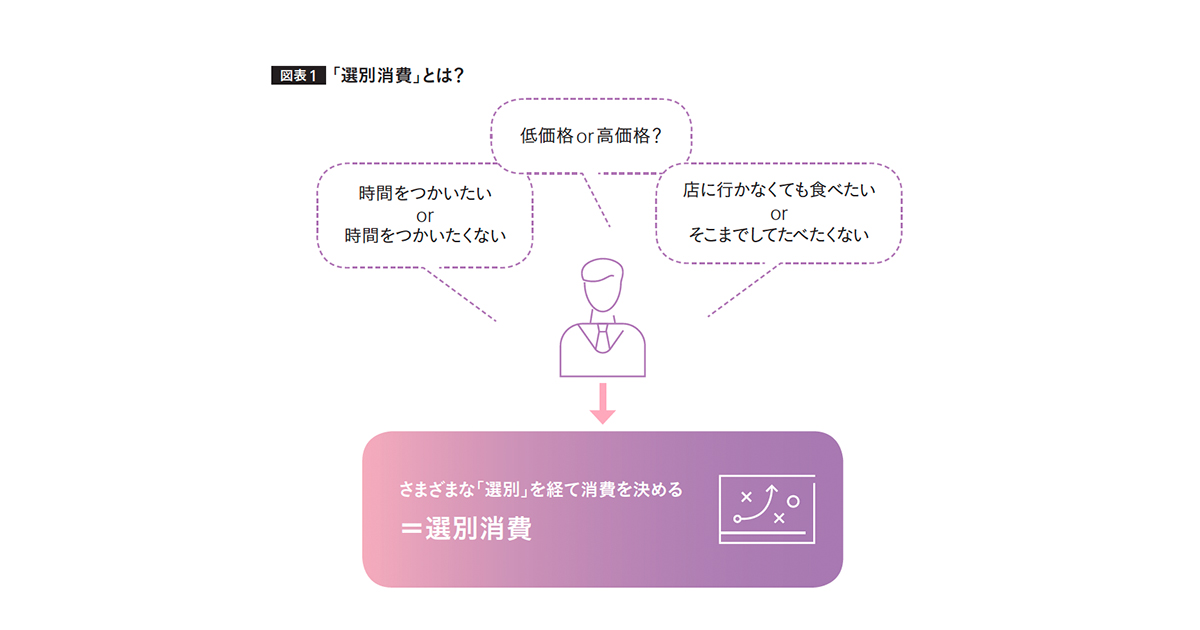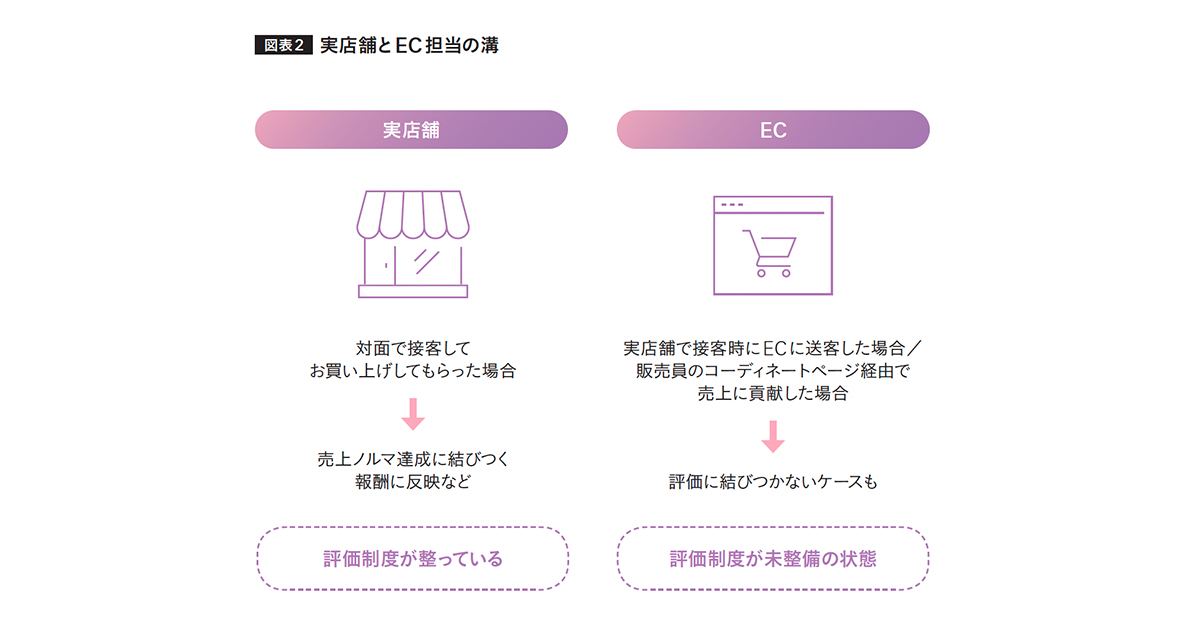来年で創業95年を迎えるオンワードホールディングスだが、ホールディングス傘下のオンワード樫山が昨年春にローンチしたD2Cブランド「uncrave」が好調だ。店舗を中心にビジネスモデルを構築してきた大手アパレルメーカーは、「uncrave」からどのような課題解決のヒントを得たのだろうか。
uncrave>>予約の点数でニーズが読めるアパレルブランド

2021年秋冬の「uncrave」のLook。8月から先行予約を受け付けているが、ここでの予約点数でそのシーズンの顧客のニーズをいち早く察知することができる。
老舗メーカーの課題
●ファッション購入の場の変化(コロナ禍で買い物の場が、ますますオンラインにシフト)
課題を解決するアイデア
●EC専業ブランドとしてローンチ。購入の場をオンラインに拡げる。
上質な商品を手ごろな価格で D2Cは実現の手段にすぎない
百貨店などの販売チャネルに重きを置いてきた大手アパレル企業においても、D2Cブランドを立ち上げる動きが広がっている。オンワード樫山も2020年2月、EC専業ブランド「uncrave(アンクレイヴ)」をローンチした。
同ブランドは働く現代の女性を対象にしており、初年度の売上予算を達成した、好調のD2Cブランドだ。ターゲットは20代後半~30代で、セレクトショップのほか、ECサイトが購買起点となる女性層を想定。SNSで情報収集を行い、そのまま商品を購入することも多い年代だ。
アパレル業界でもD2Cの潮流が強まる中でローンチされた「uncrave」だが、立ち上げの目的はあくまでも上質な素材、縫製による商品を手軽な価格で届けたいとの考えがあってのこと。「この目的を達成する手段として、D2Cという選択をすることになった」とブランドの企画担当である国府美咲氏は話す。
「アパレル業界の中でもD2Cが増えていましたし、当社の中でもEC事業を強化する動きがあったので、流れにうまく乗れた側面はあります。しかし、D2Cという売り方は商品を届ける『手段』にすぎません。あくまで私たちの目的は『働く女性たちに手の届く“上質”を提供する』ことです」(国府氏)。
とはいえ、D2Cブランドであるからこその利点も感じている。それは、顧客の反応がリアルタイムでわかることだ。「ECだからこそ、『予約』という機能がある。商品販売前の...