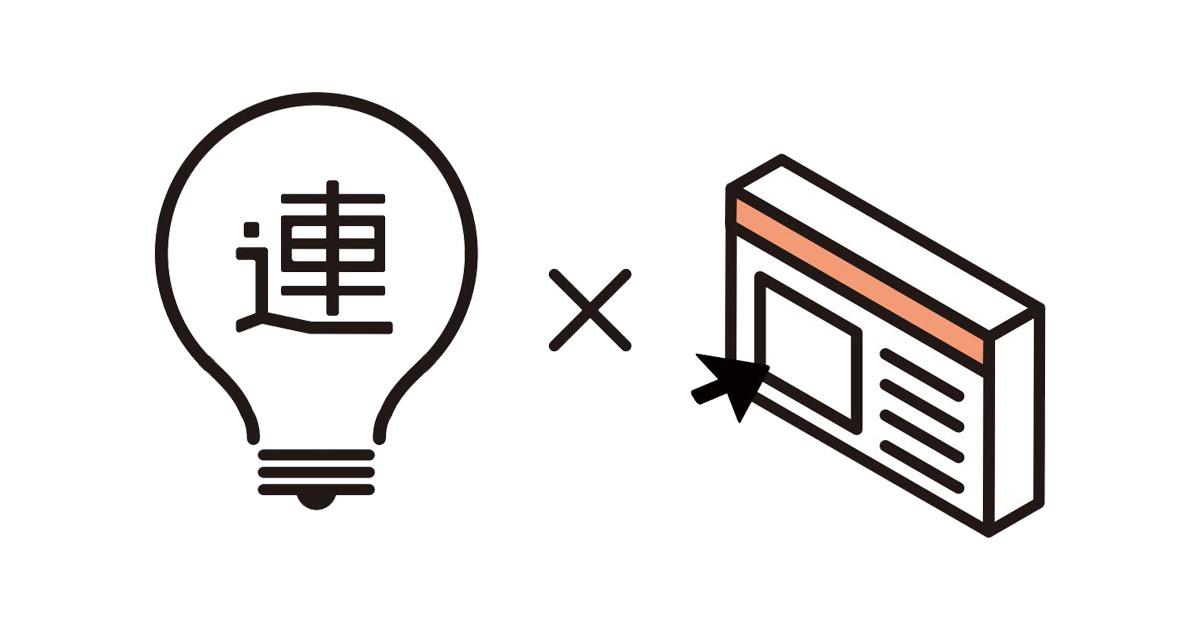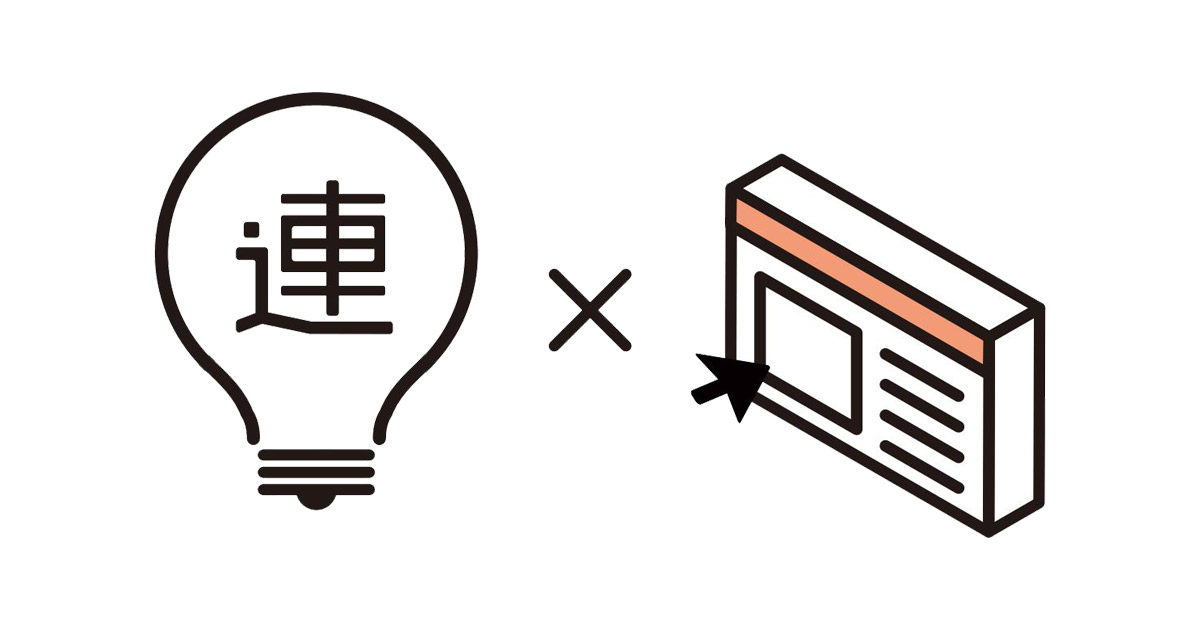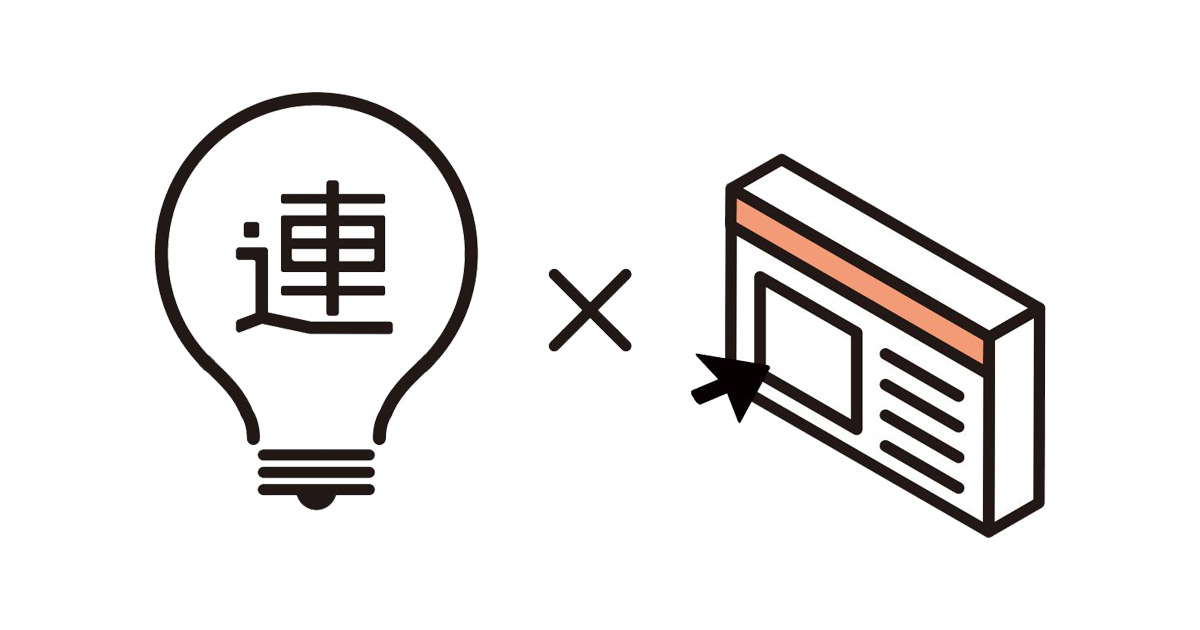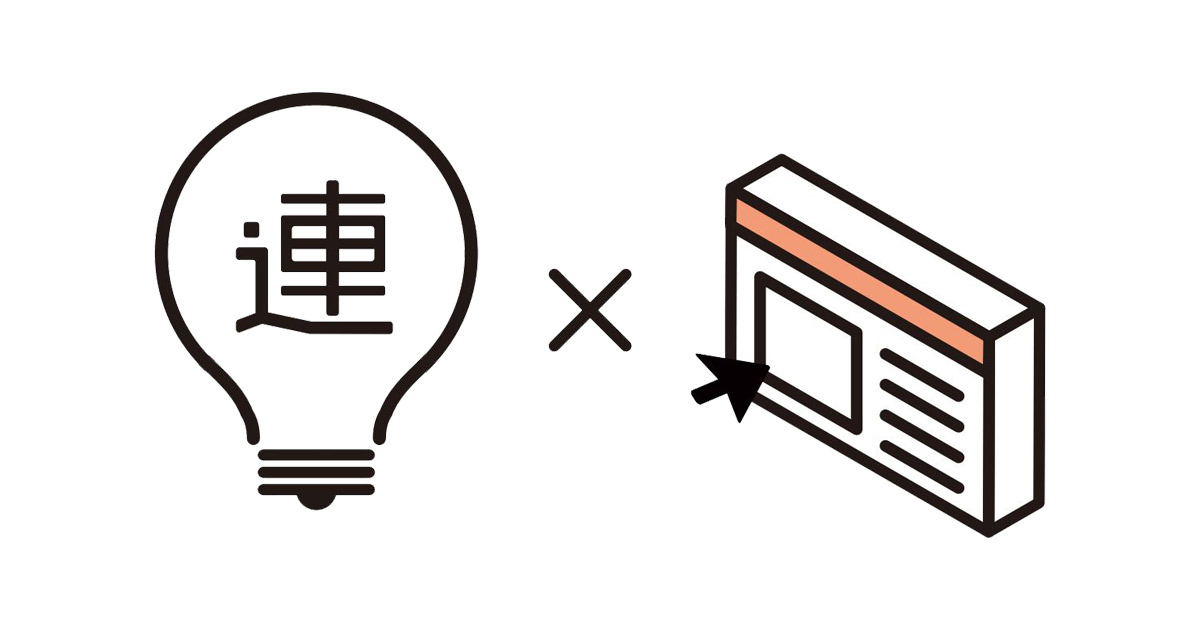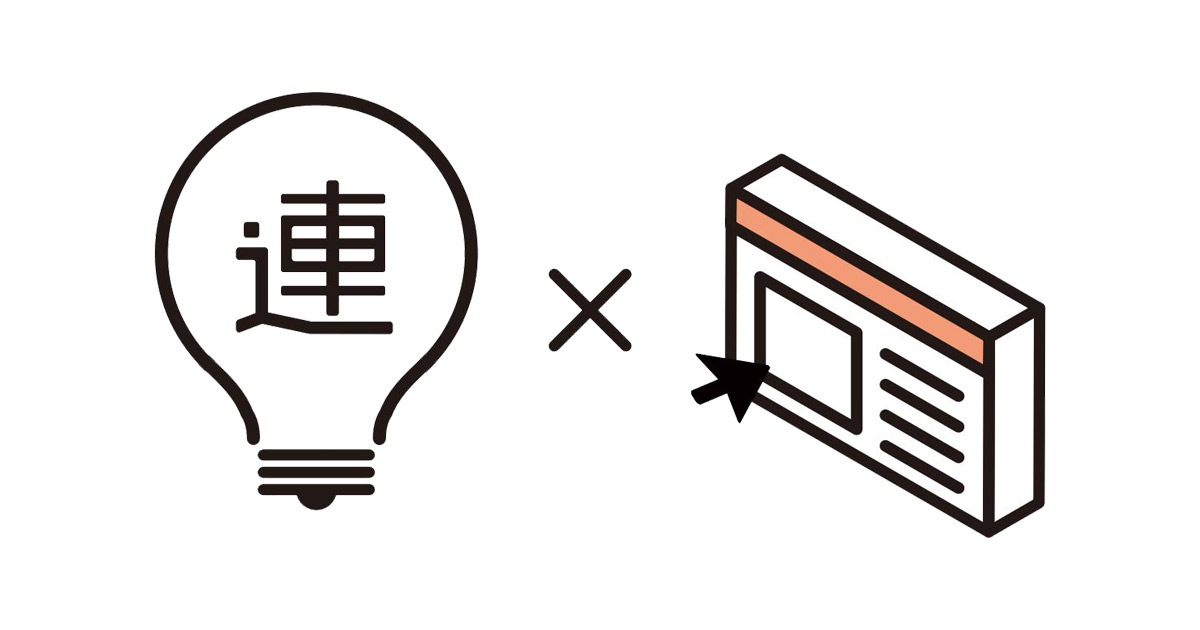前回はコロナ禍でオンラインシフトが加速するなか、モノがある製造業だからこそできる、これからのお客さまとの取引の在り方として、まずオンライン起点でビジネスを考えること。さらに、そこにおいては単なるEコマースではなく、「EXコマース」、つまり自分たちの商品に対するこだわりや創り上げるまでの物語と一緒に伝えることの重要性を指摘しました。今回は、製造業だからこそできること、残り3つの可能性について考えていきます。
感動した顧客に無駄なストレスを感じさせない
広告の世界では「消費者の知性には期待してもよいが、努力には期待をするな」と言われている。例えば日能研の広告のように、ある程度頭で回答を考えさせるような広告は実施してもよいが、まるきり何を言っているのか分からず、受け手がゼロから考えなければいけないような広告は実施してはいけないという意味である。この考えを私たちはオンライン起点のビジネスにおいてもしっかりと意識しなければならない。
例えば、これまでのオフライン店舗でお客さまが商品を手に取って購入しようかどうか迷っているシーンを想像してほしい。数ある商品の中からふと目に留まっただけですぐに購入を決断する人は少ない。実際に手に取って、あれこれ表示内容を見て、同じ商品のサイズ違いがないかなども見て、自分の生活にフィットするかなども想像したうえで、ようやく購入に至る。こうしたことがオンラインでも起こると考えることが必要だ。
これらは、Eコマースのビジネスに触れた方なら当たり前に感じることだ。それをあえてここで説明したのは、今回のコロナ禍により、新しいオンライン購買ユーザが誕生しているからだ。言わずもがな、新型コロナウイルス感染症の拡大により、オフライン店舗での購買接点が激減し、オンラインでの購買が加速している。私は現在シンガポールでアセアン各国のEコマースビジネスを見ているので、各国の取引量をコロナ前後で比べるとその大きな変化に驚きを隠せない。
これは既存のオンラインショッピングユーザの使用頻度が上がったことによるものではなく、今までオンラインショッピングを使ったことがなかった、もしくはほとんど使ったことがなかった人たちの流入が要因である。
中国では50代以上のEC利用の増加が顕著だという。シンガポールでも国を挙げてシニア層のオンライン購買を後押ししている。自社の商品をオンラインで購入する人の属性をとらえなおしたうえで、利用する際の期待に応えて、信頼や関係性の構築に生かす。シニア層が対象なら文字のフォントは大きくしないといけないし、子ども向けなら漢字を少なくした方がよいだろう。
アップルの元エバンジェリストであるガイ・カワサキ氏はプレゼンで使うフォントは聞き手の年齢の半分にしないといけないと言うが、年齢によって読みやすい文字の大きさはある。中国のアリババは彼らのECサイトであるタオバオの中にシニアに使いやすいインターフェイスを用意している。一方でレゴは子どもが見る専用のブランドサイトを用意している。