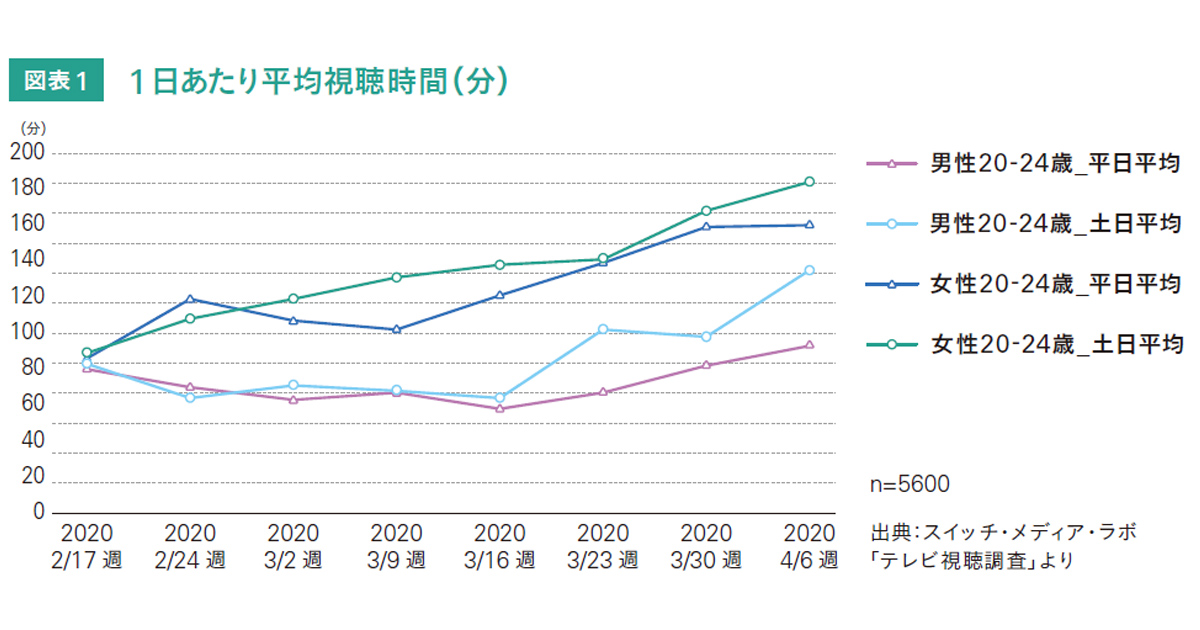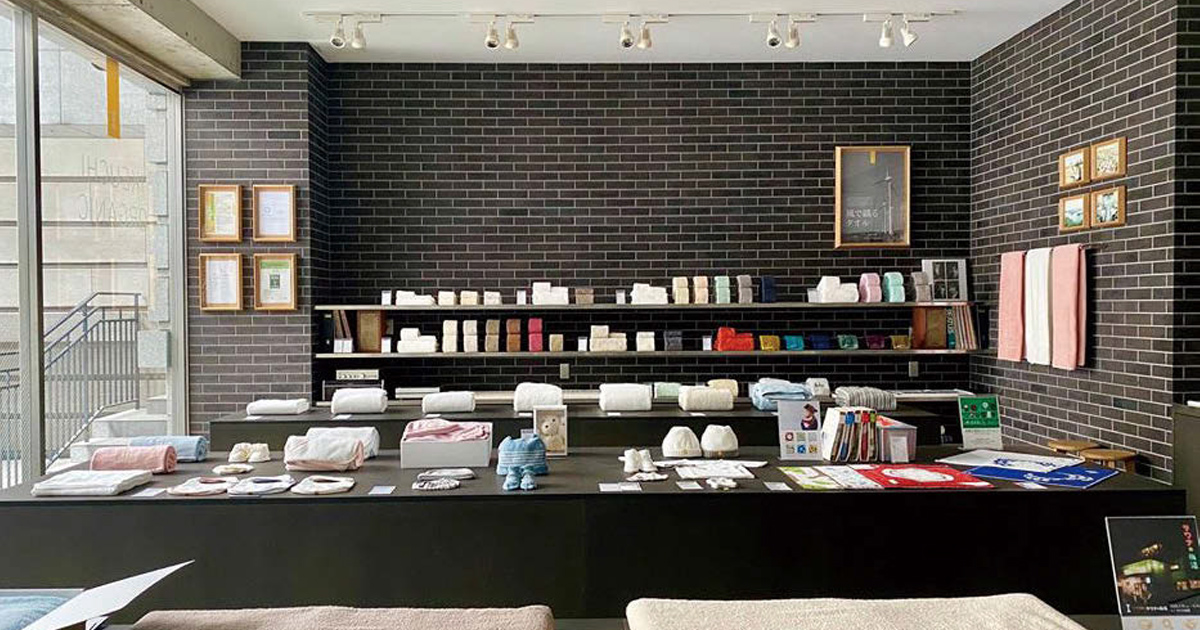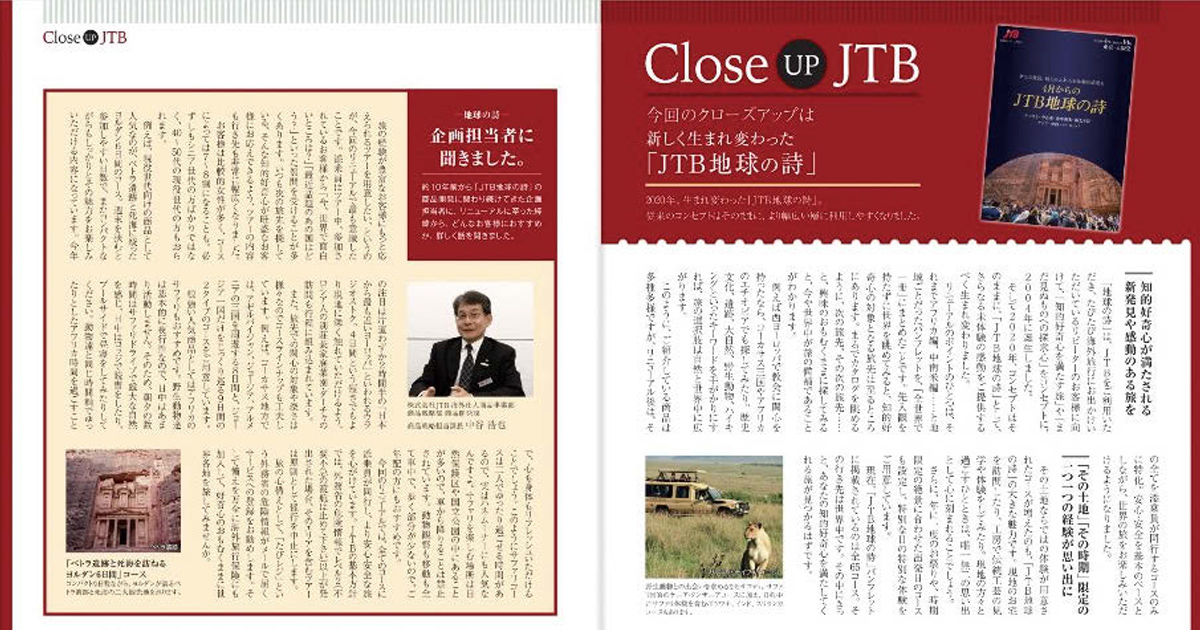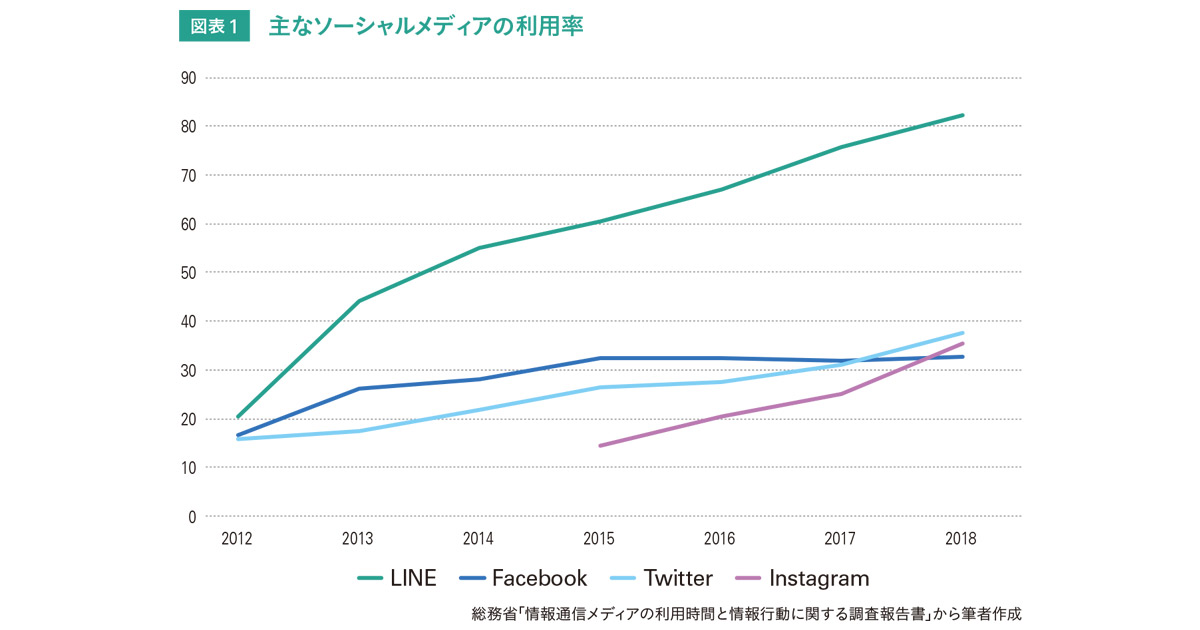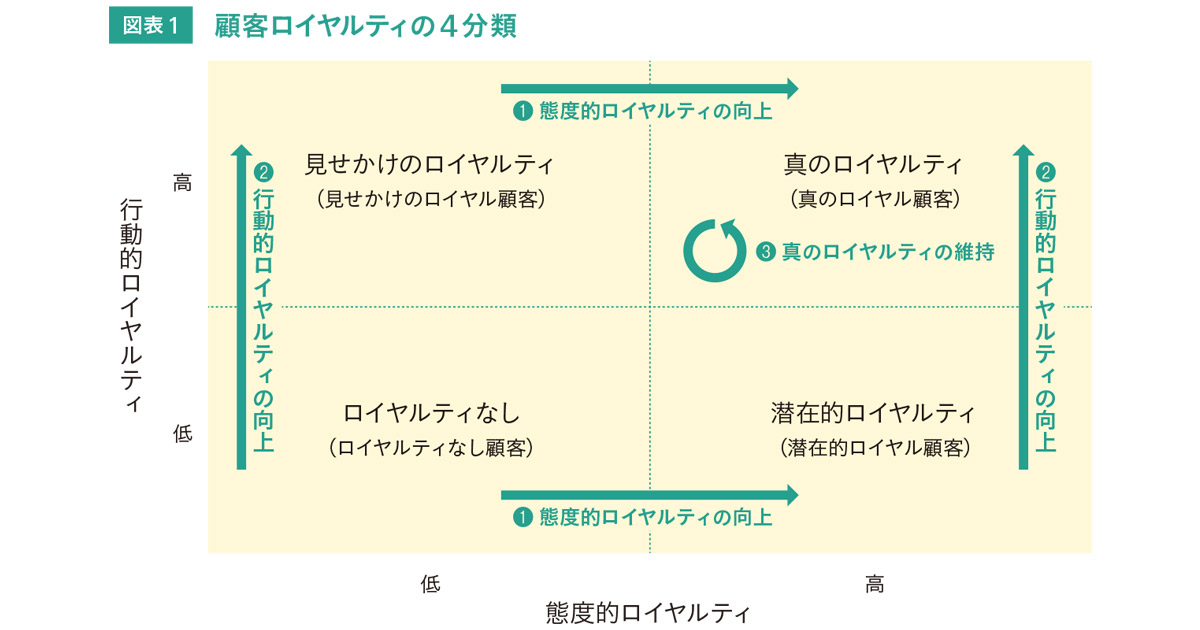各地で経済活動が再開されながらも、依然として企業・消費者双方に大きな影響を及ぼし続けている新型コロナウイルス禍。顧客とリアルの場でつながることが難しくなった時代のコミュニケーションはどうあるべきか。その方向性をパルコ 林直孝氏が考える。
【コメ兵 藤原氏から、メガネスーパー 宮森氏への質問】
コロナ禍で様々な対応を余儀なくされる中で、部署単位での変革には限界があります。そこで縦横の関係部署や組織間での連携が必要になってきますが、今以上に連携強化していくときのポイントとなることは何でしょうか。
ANSWER
個人間・部門間の越境が、今一度ポイントになってくると思います。図らずも"壁"はできてしまうものなので、それを意識して越えていくことは重要です。その点、当社では「アクション会議」という100人規模の会議で、比較的、越境が実現できていると思います。
アクション会議は6年前に当社がV字回復できた要因のひとつでもあり、当時は月曜日の朝から晩まで休憩なしでやっていた会議です。全部署の幹部や幹部候補、加えて店舗のエリアマネージャーも参加し、店長も任意で参加。会議は動画配信され、それに対し誰もが発言できるというものです。
現在はZoomへと形を変え、継続中。アクション会議を起点に、あらゆる部署がフラットな関係性の中で週単位でPDCAを回していくのです。これから都道府県ごとにコロナが収束していくタイミングは異なってきますが、すぐに対応できるように日頃から、こうしたフラットな連携を図ることも重要だと思います。
Q1 「顧客とのつながり」という面において、どのようなコロナ禍による影響がありますか。
ANSWER
業界全体に大きな影響がありました。ただ、当社は他社が休業している中、眼鏡・コンタクトや補聴器は生活必需品であり社会インフラだと考え、営業を止めるべきではないと判断しました。これには社員の雇用確保という側面もあります。この両軸の理由から、休館施設にテナントとして入っている店舗以外は、営業時間を短縮したりしながら営業を続けています...