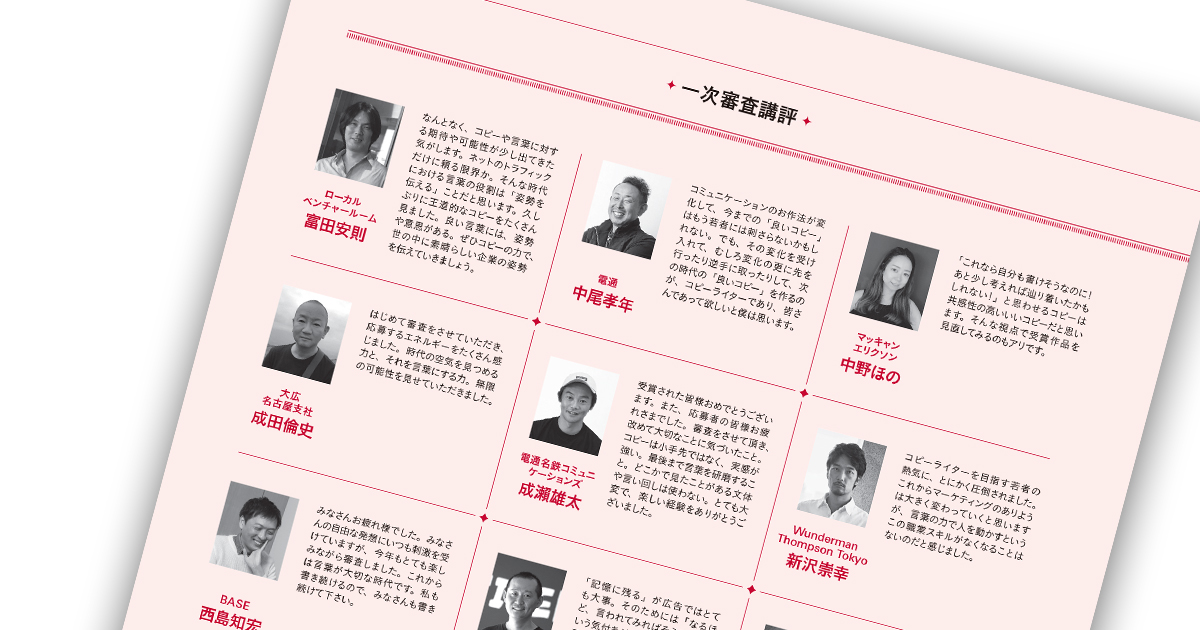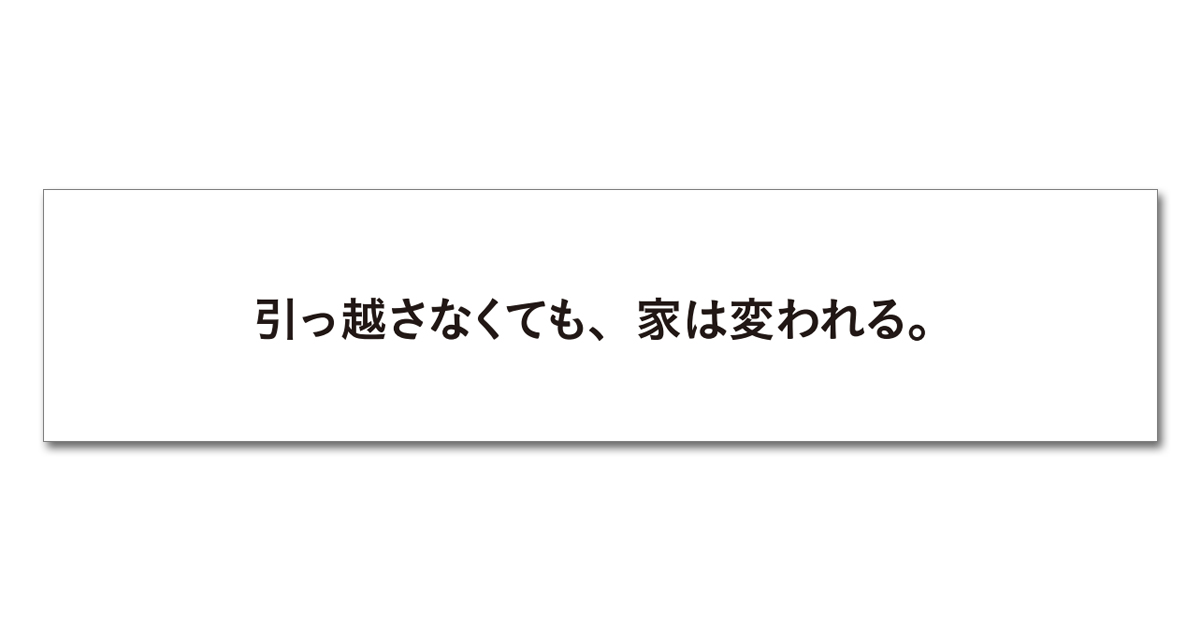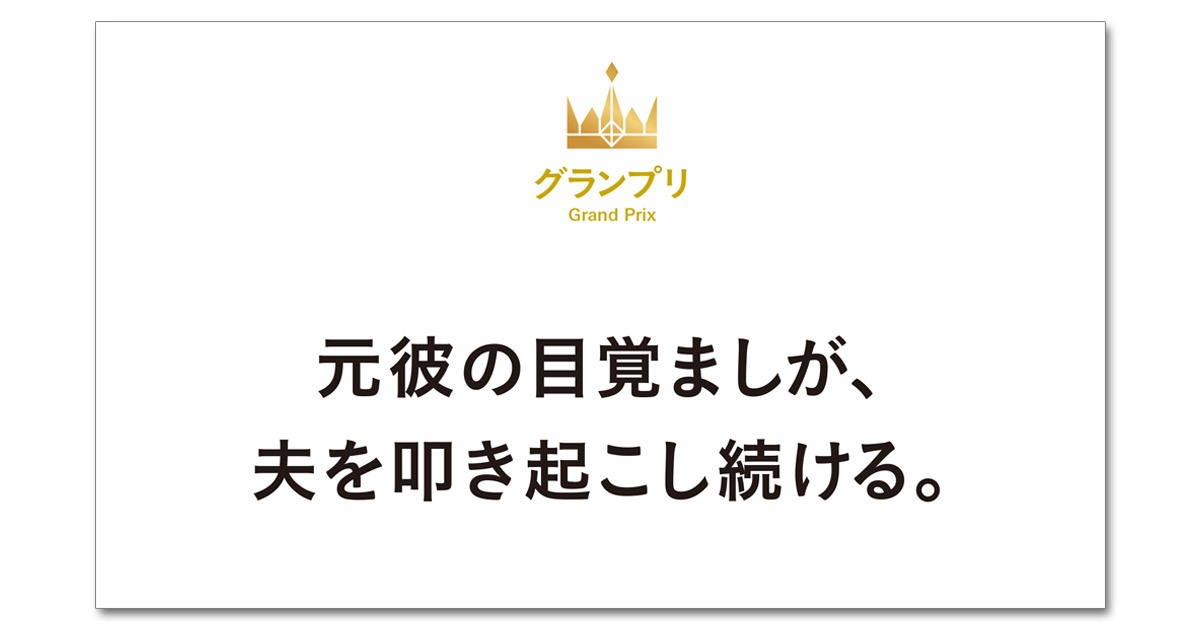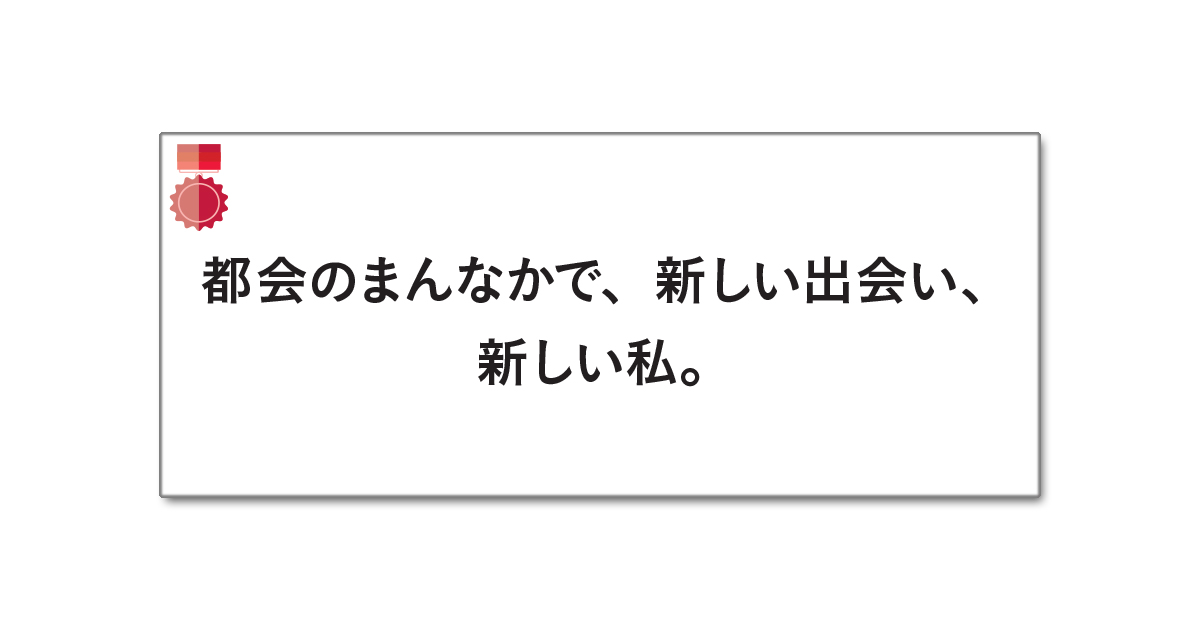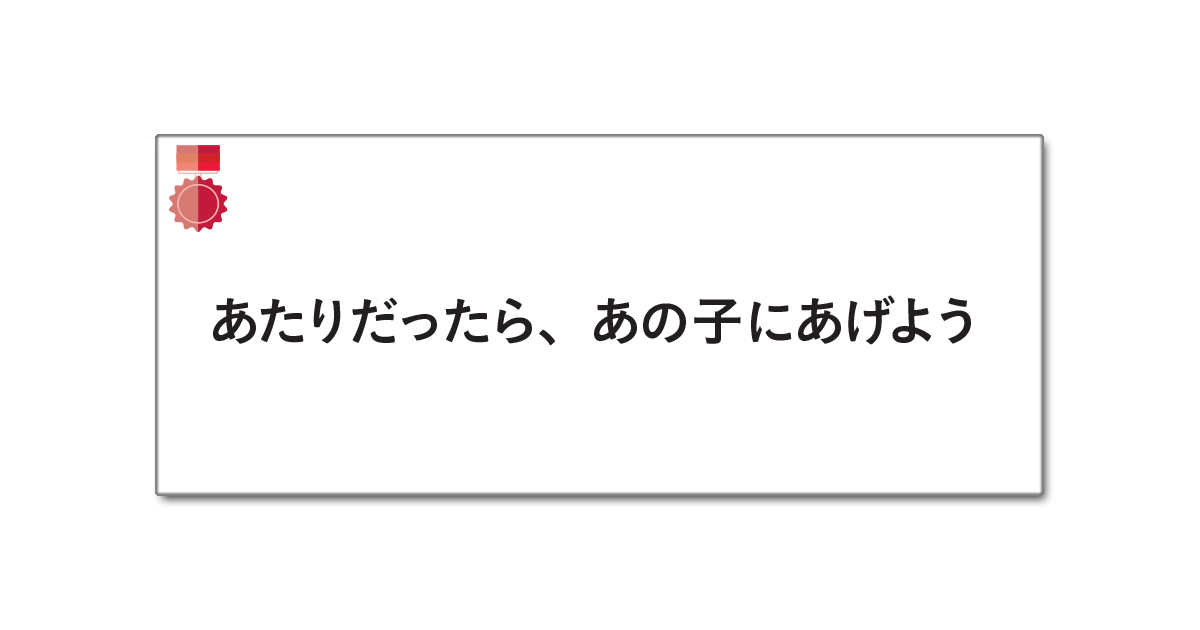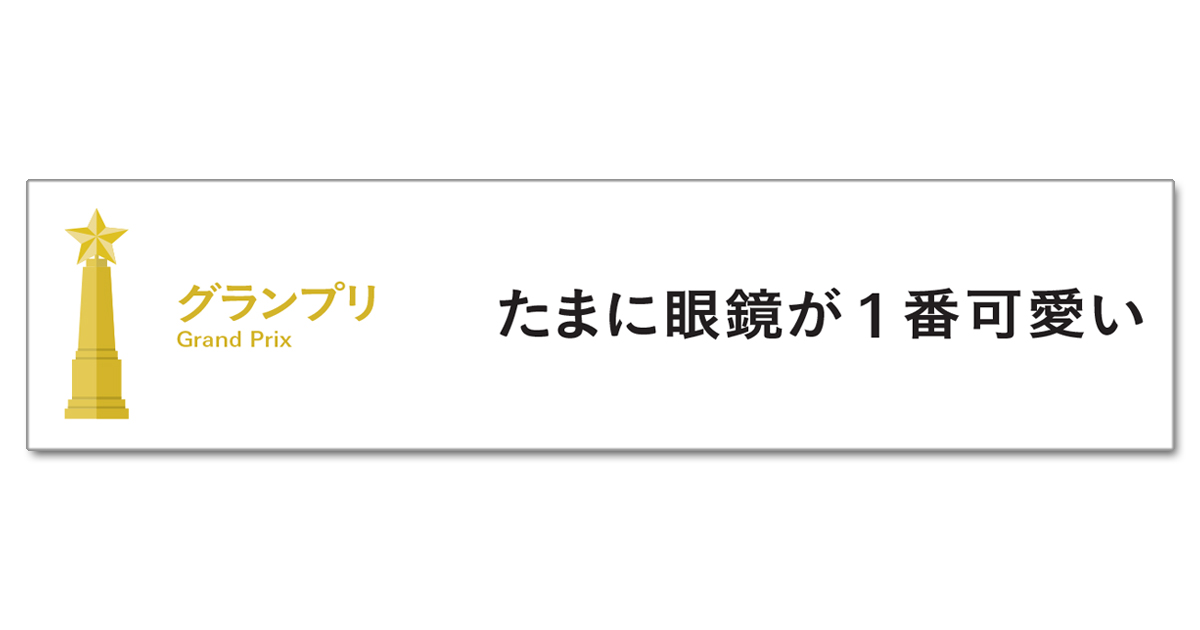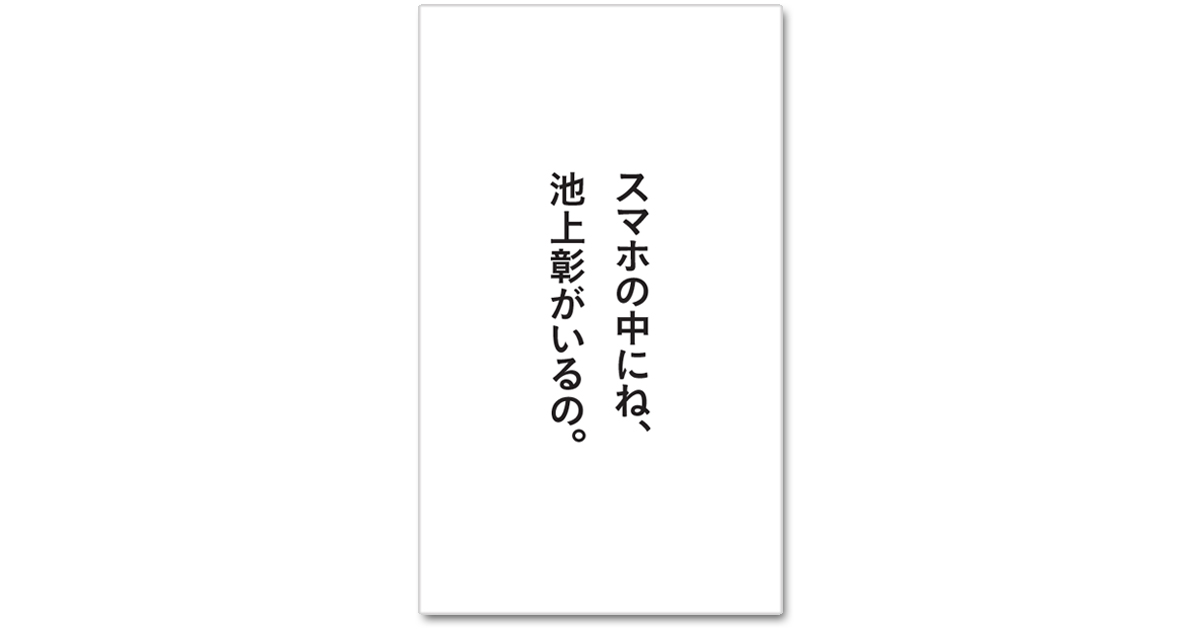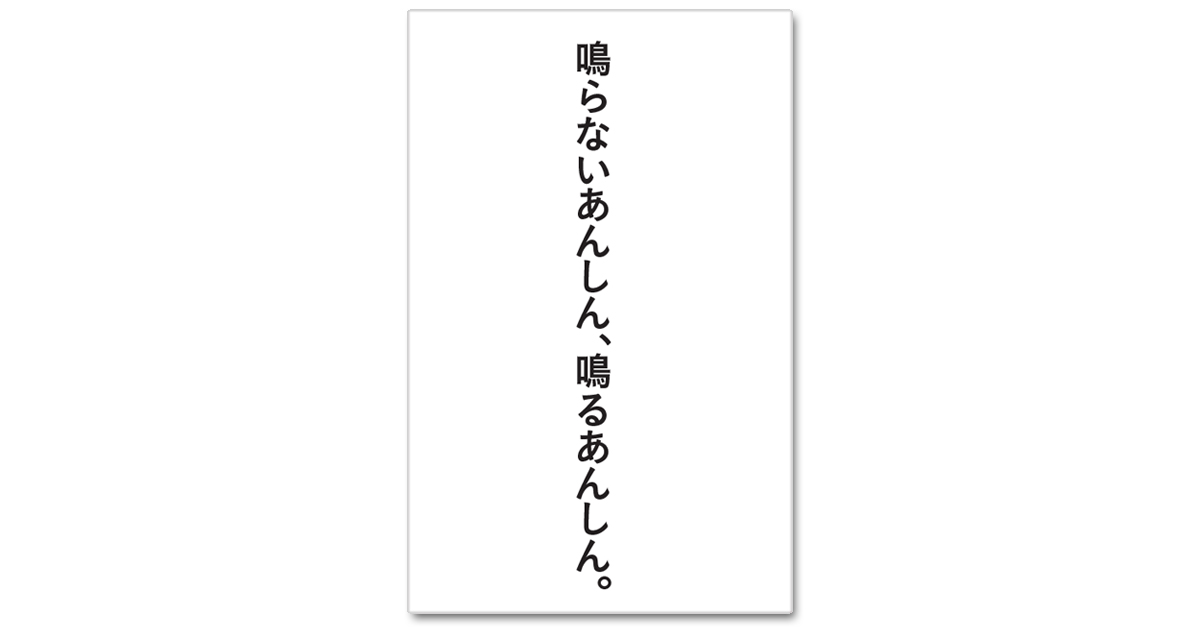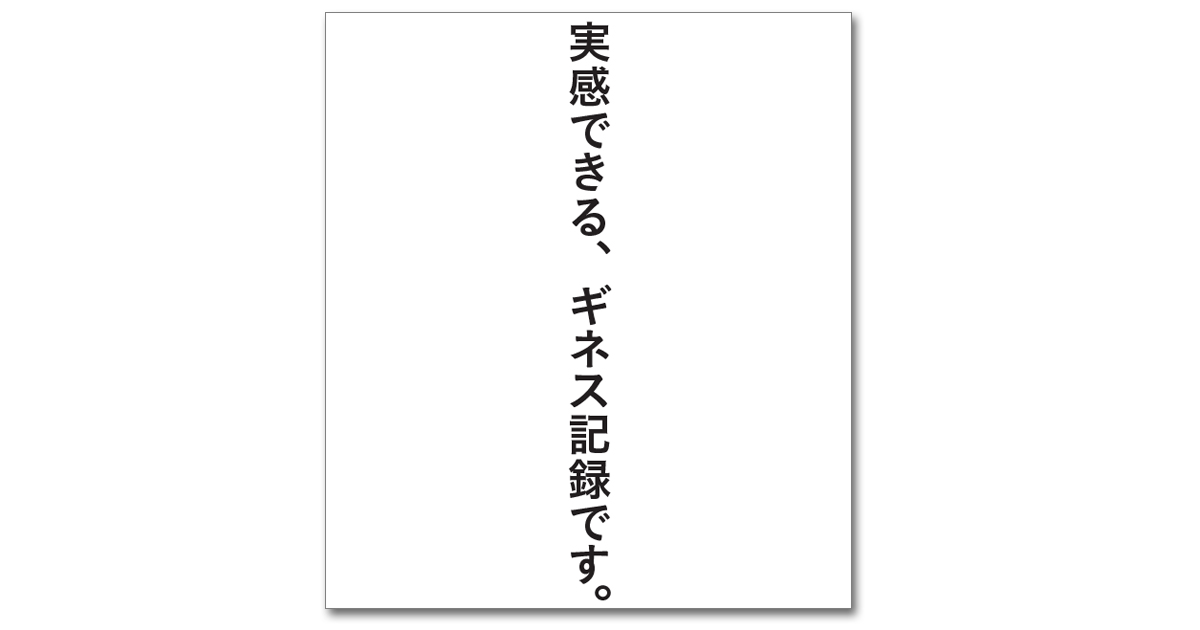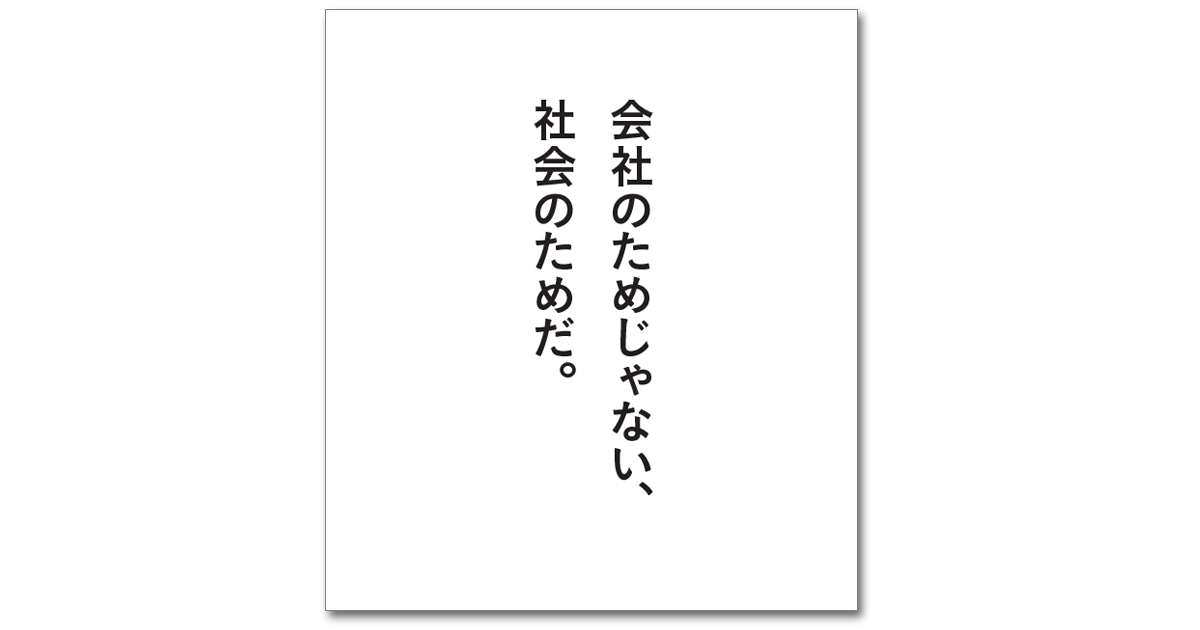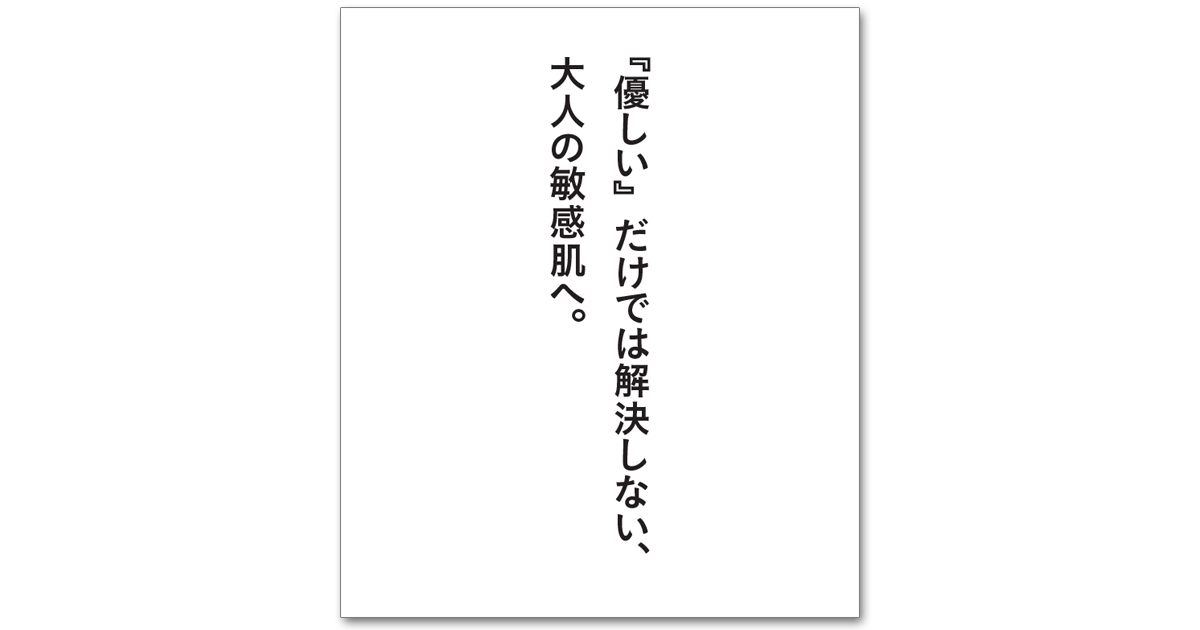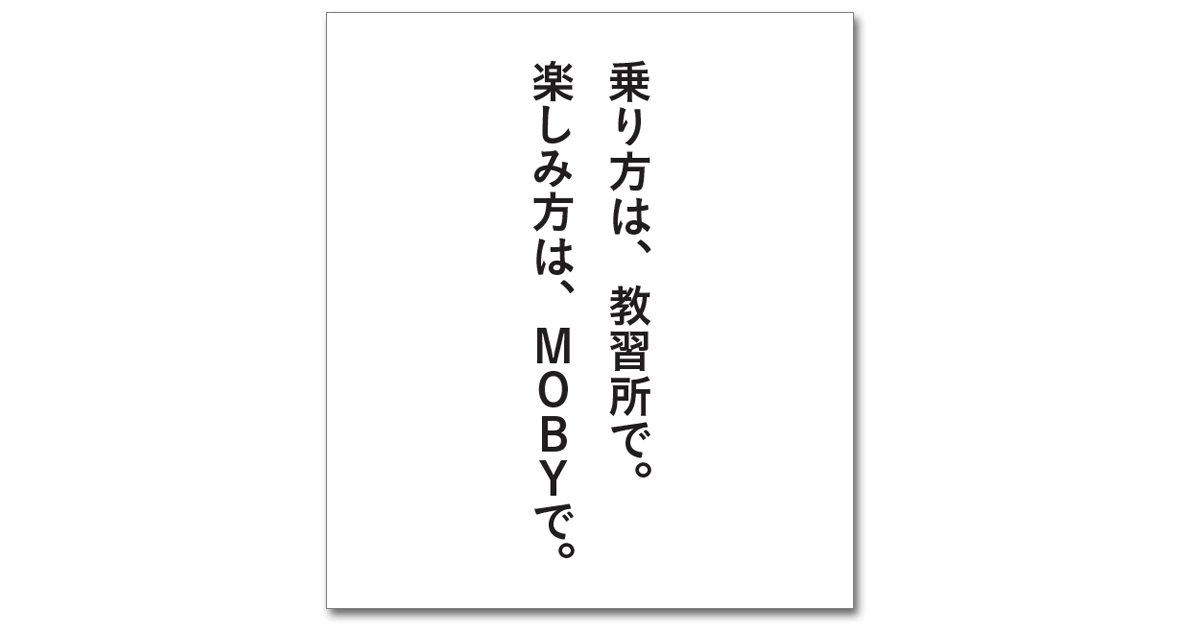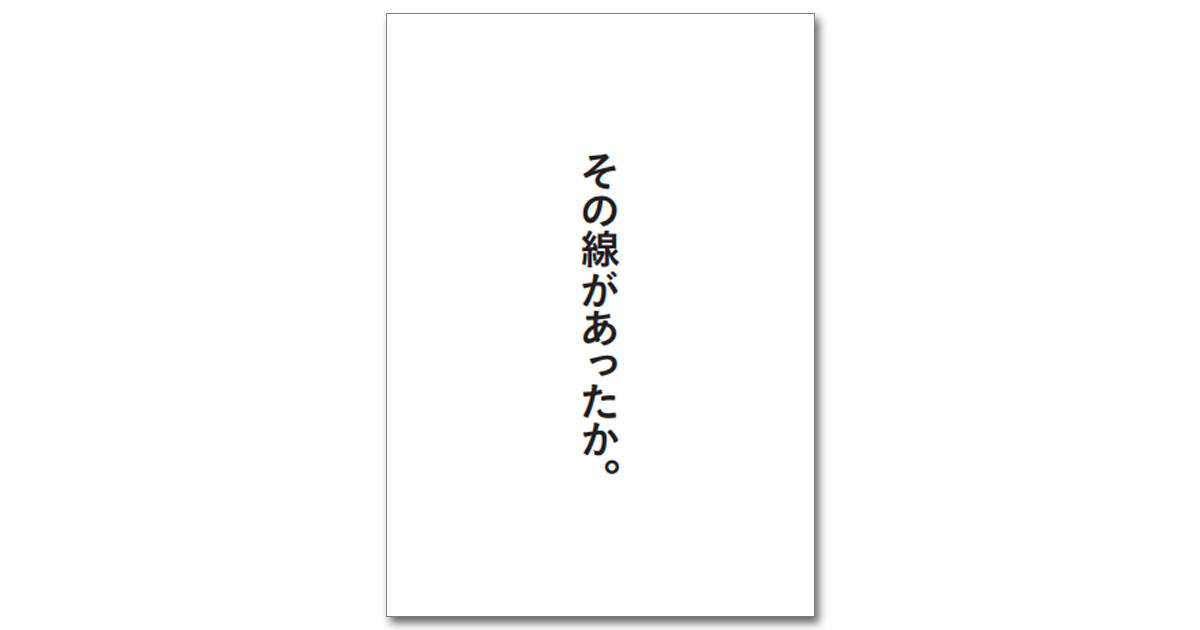『宣伝会議』3月号誌上で発表となった一次審査通過者。全応募作品の中から一次審査を通過したのは、わずか1.04%でした。一次審査を担当した広告界の最前線で活躍するクリエイターの皆さんに、審査講評を聞きました。

CHERRY 青木一真
まず、応募された方の熱意に敬意を評したいと思います。多数の案を拝見しましたが、その8割は類似コピーでした。人が考えることってほぼ同じなんですよね。やはり、他人と被らないユニークな視点を粘り強く追求すること。そのために、数を考える汗と既視感があるものは捨てる勇気が大切だなと思いました。自戒を込めて。

赤城廣告 赤城廣治
商品やサービスの本質を捉えているか?魅力が伝わるか?を考慮して選ばれるという協賛企業賞。その受賞作品の中にも素晴らしいコピーがあります。けど、今年に限って言えば、不思議とファイナリスト作品とは1本も被っていません。いつの日か、協賛企業賞とグランプリを同時受賞するコピーと出逢えることを願っています。

電通 阿部光史
受賞された皆さまおめでとうございます。受賞できなかった皆さまにはぜひ面白さを身につけていただきたく。方法は簡単、自分が面白いと思ったものを集めて、その理由を文章化するのです。コピー・CM・映画・アート、なんでも良いのです。換骨奪胎して自分の表現とすればパクリにはなりません。毎日の筋トレにお勧めします。

電通 池田定博
この頃は、リモートワークとかSNSとか、スマホがあれば何でもできてしまいます。でもですね、たまには鉛筆で原稿用紙にコピーを書いてみるのもいいのではないでしょうか。古臭いかもしれませんが、ゆっくり書くコピーっていいと思います。もちろん親指でも構いませんけど、とにかく1本をじっくり作ってみてください。

インプロバイド 池端宏介
審査員初挑戦。うそがなく、端切れのよいコトバを選ぶように心がけました。見る本数も多く機械的に当落をチェックしていくことになるのですが、本質を突くコトバに出会うと一瞬「おおっ」とうなることがありました。
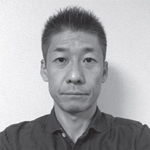
大広 生駒達也
人がモノを買いたいとか消費したいとか思う時の本質って、昔からあんまり変わらないんだろうなと思いつつ、その心理をくすぐる方法はどんどん変わってきていますよね。なので、その本質を見抜くことと、くすぐる方法を探し出すことの、2種類の作業があるという感覚をもって、アイデアやコピーを練ってほしいなと思います。

電通 石田文子
言葉やニュースがあふれている今の時代だからこそ、言葉遊びではない強い"意味"がないと、見過ごされてしまいます。宣伝会議賞も普段の仕事も同じですね。審査をしていると、自分も頑張らなきゃ、と思えていい刺激をもらっています。

サン・アド 岩崎亜矢
コピーを書くのって、楽しくないですか?賞賛や賞金はもちろん嬉しいけど、時間が経って最後に残るのは、あの時、あのコピ―を書きあげた時に掴んだ、なんとも言えない高揚感。あれを経験しちゃうともう元には戻れない。そうやって楽しんだ人のコピーは、読み手を動かします。少なくとも、私の心は動きました。

電通 岩田純平
結構難しいお題のものを2つ審査しました。正直、宣伝会議賞に向くお題と向かないお題があります。どのお題を選ぶか、から宣伝会議賞ははじまっているのだなあ、とあらためて思いました。僕が審査した課題から上位入賞者が出ますように。

電通 上田浩和
何千本の中から十数本を選び出す。ただの何千本ではなく思いのこもった何千本だから、猫背の僕も背筋を伸ばして審査にあたりました。何度も何度も見直し、がんばれよと思いながら二次審査に送り出しました。僕が選んだコピーが受賞しますように。受賞した際には、そのコピー、僕が書いたことにしてもらえませんでしょうか。
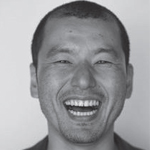
I&S BBDO 上野達生
受賞の皆様、おめでとうございました!ビッグデータが導く切り口より、個人の無意識化思考から出てくる切り口は、発見があり人の豊さと未来を感じます。ますますキレイごとのメッセージは質量がなく人に響かないものになるなぁ、と気付きがありました。

西鉄 エージェンシー 占部邦枝
わー困ったなぁと。レベルが安定していて逆に審査が難しくなってしまいました。だからこそ、お!そうきたか!なコピーはすごく目立ちます。うまいこと言った、で終わらずに、その先を考えてみると、新たな発見があるのではないかと思います。そう自分にも言い聞かせつつ…受賞者のみなさまおめでとうございます。

モノ・カタリ。 大岩直人
広告に、もはやかつての「大きな物語」なんて存在しない。これからの時代のコピーは、いっそ「語らないことを語る」しかないのかな、なんてことまで考えつつ、まずは「語り方」よりも「語られ方」が腑に落ちるコトバを、探してみたつもりです。

電通 中部支社 大塚久雄
「良いな」と思うコピーはもちろんありましたが「やべえ、このコピー超好き!」という一本がありました。そのコピーを書いた人に「ありがとうございます!」と言いたいです。応募する前に、良いかどうかより、好きかどうかで見直してみることも大切かもしれません。

SIX 大八木翼
いいコピーのむこう側には、人間がいる。まだ、出会ったことはないけれど、確かにその場所でまっすぐに生きている、そんな誰か。僕はその誰かのことを、とても、愛おしく思う。今年もいいコピーが沢山ありました。感謝。

電通クリエーティブX 岡崎数也
熱意や野心が、コピーの新しさや強さになるのだとは思いますが、自分の技術披露が優先されているコピーが多かったです。残念。コトバを捻り出すのではなく、商品と社会との「良き関係性」を描くことが大切です。

電通九州 尾形嘉寿
「うまいこと言ったね」というコピーはもちろん素晴らしいのですが、やはり「あ、そんな視点があったのね」とか、「あ、なんてやさしいものの見方なんだろう」というコピーには敵わないのだなあ、といつも思います。良いコピーを書けるようになるには、良い人になるしかないんだなぁ…と、身も蓋もないですが、年齢を重ねるほどに実感しています。

Que 岡部将彦
①「嘘でしょ!」となる程、商品を褒め過ぎている。例:「女優だと間違われた。◯◯を変えただけなのに」 ②商品から連想したことから、さらに発想しているので意味が通じない。例:商品が青色→青空を連想→青空をテーマにコピーを書く。この2つを避けるように意識するだけでも、打率は相当高くなると思いました。

電通 中部支社 岡本達也
他人と違うことを書く。当たり前ですが、これができていないと審査で目立つことはできません。ではどうすれば「生き残れる一行になれるのか」。意外と大事なのが想像力です。その商品を見た瞬間何を感じ、使ってみて何を思い、他人になんと勧めるか。たくさんの違う人がどう反応するか想像し、妄想することが新しい発見につながる。僕は割とそう思っています。
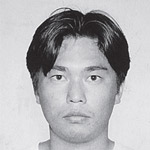
フルボリューム 小川英紀
一次審査を担当させていただきました。いつも次の審査になるべく多くの作品をまわそうと心掛けております。なので皆さまも、次回応募の際は締め切りまで粘りに粘って「コレだ!」と思う一行をひねり出してくださいませ。すぐに締め切りはやってきます …