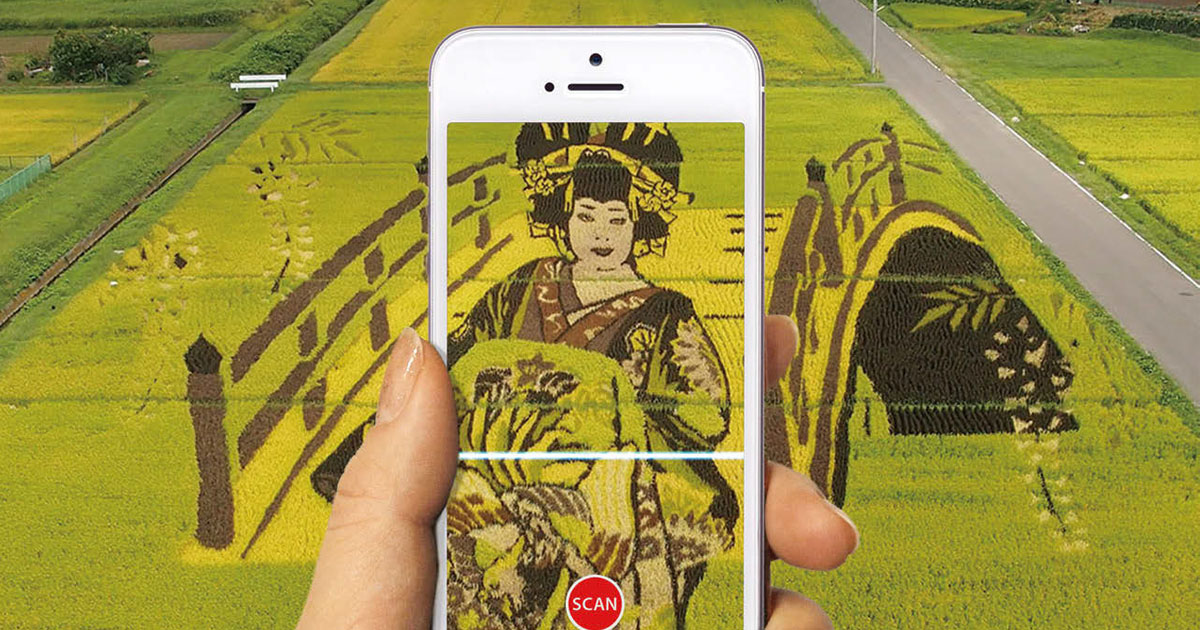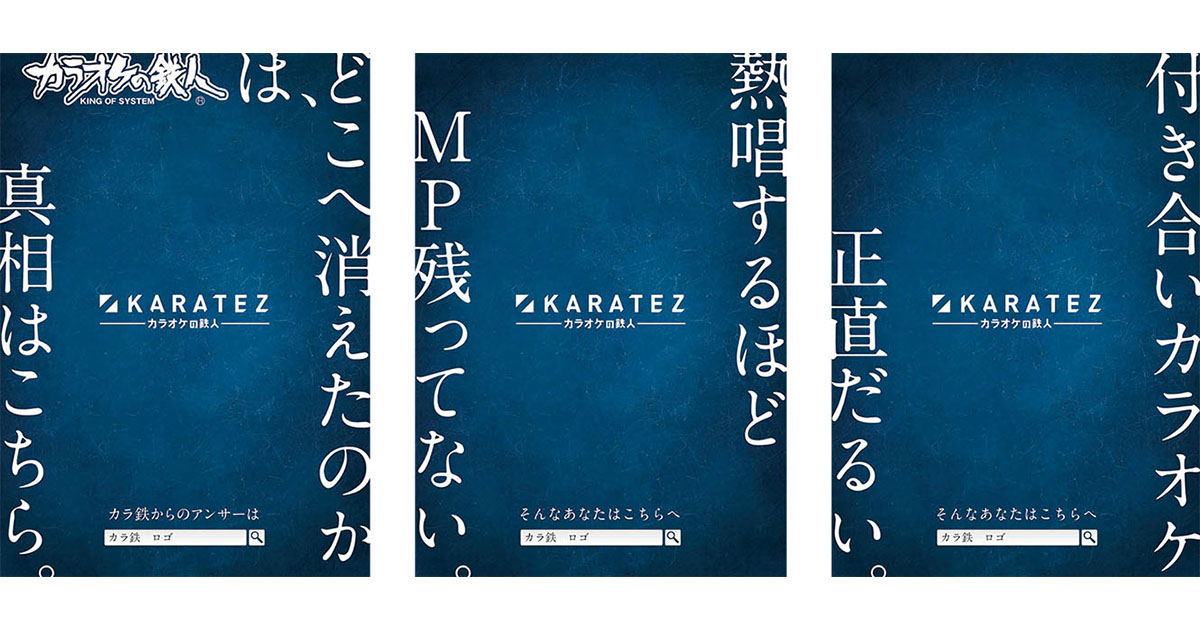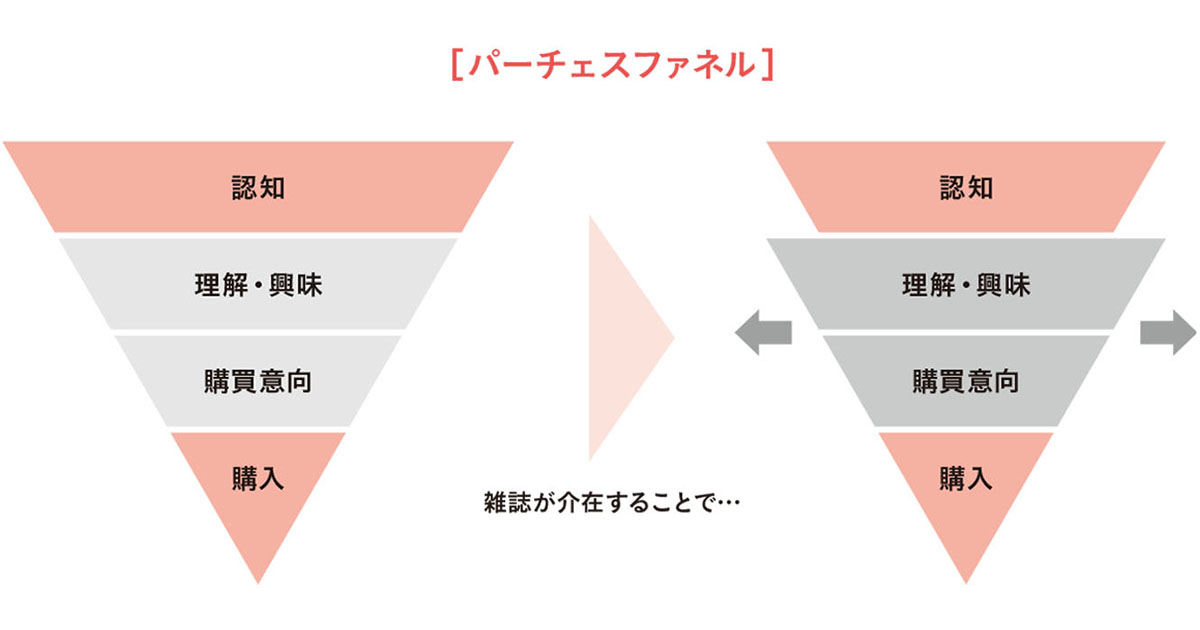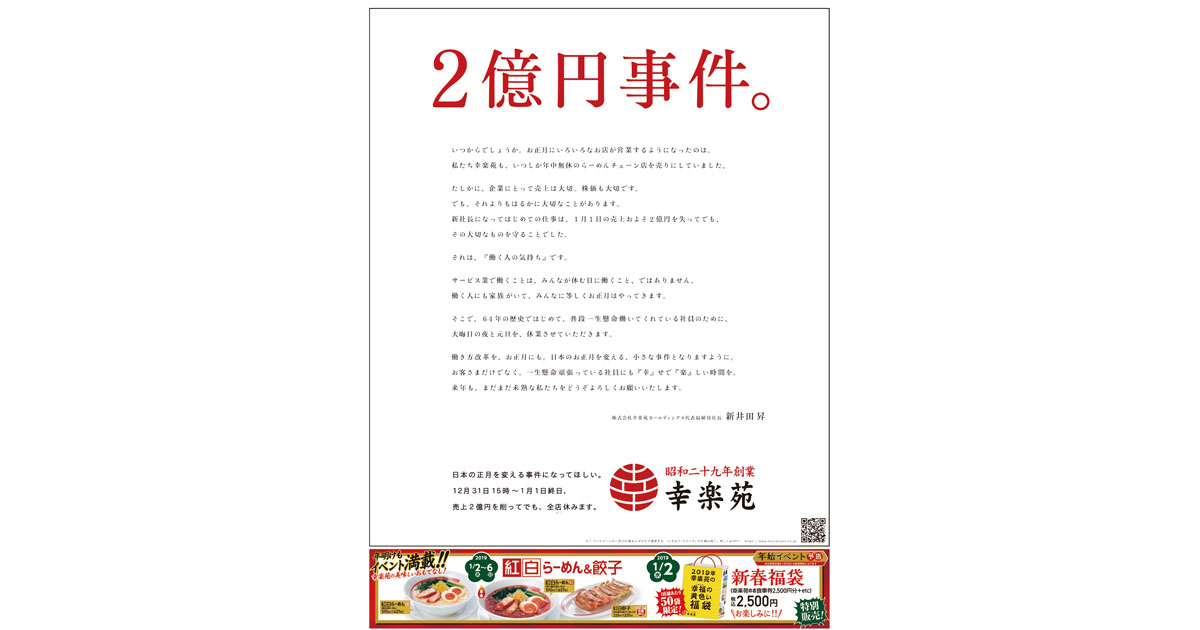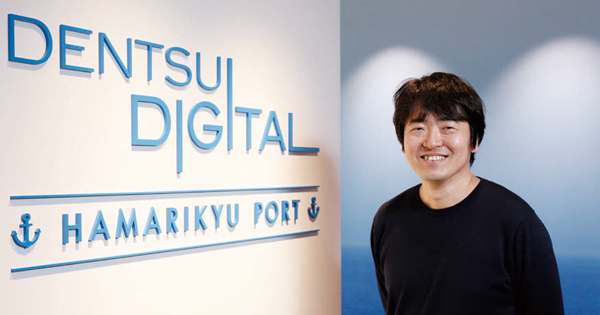この10年でラジオを取り巻く環境は大きく変わり、近年、登場したスマートスピーカーは“音声メディア”としてのラジオの可能性を広げる存在として注目されている。デジタル時代におけるラジオの新たな役割とは。電通・澤本嘉光氏に聞いた。

@123RF
聴くハードルが下がった今 ラジオの可能性が広がっている
2012年から2016年までACCラジオCM部門の審査委員長を務めていた澤本嘉光氏。「7年前、若年層を対象に『ラジオを聴いたことがある人?』と尋ねたら、挙手した人はすごく少なかった。聴いているとしても、タクシーや車中など"自然とラジオが流れてくる"場に限定されていて。若い人はラジオ機器を知らないし、もちろん持っていません。そもそも聴く手段がなかったから聴いていなかった。そうした若い世代もラジオを聴くことができる環境が整い始めたのが、今なのです」。
2010年、インターネットを通じてラジオを聴くことができるアプリ「radiko.jp」が誕生。2012年には聴取エリアを全都道府県に拡大、2016年にはタイムフリー聴取機能やシェア機能の実証実験が始まり、好きなラジオ番組を好きな時に聴いたり、SNSを通じてシェアしたりと新たな聴取スタイルが生まれた。
加えて注目すべきは「スマートスピーカー」の台頭である。主要メーカーの商品にはラジオの聴取機能が備えられており、「ラジオをかけて」と話しかけるだけで、簡単に聴くことができる。「スマートスピーカーは、子どもにとっては魔法の箱。『ラジオをかけて』と言って面白いものが流れてくると分かれば、ラジオにもっと親しむようになる。ラジオを聴くことの障壁は非常に低くなっています」と澤本氏。事実、日本よりも早くスマートスピーカーが家庭に浸透した欧米では、ラジオの聴取率が上向きの傾向にあるという。
さらにラジオにとって追い風となっているのは、スマートフォンやパソコンの普及によって、複数メディアの同時視聴が当たり前になったことである。「テレビなどの映像メディアは『PCを触りながら』『スマホを操作しながら』といった、ながら視聴には向いていませんが、ラジオや音楽などの音声メディアは、ながら聴取に適しています。機械の進歩と、聴取者の変化。時代情勢を見るとチャンスの多いメディアであることは間違いありません」 …