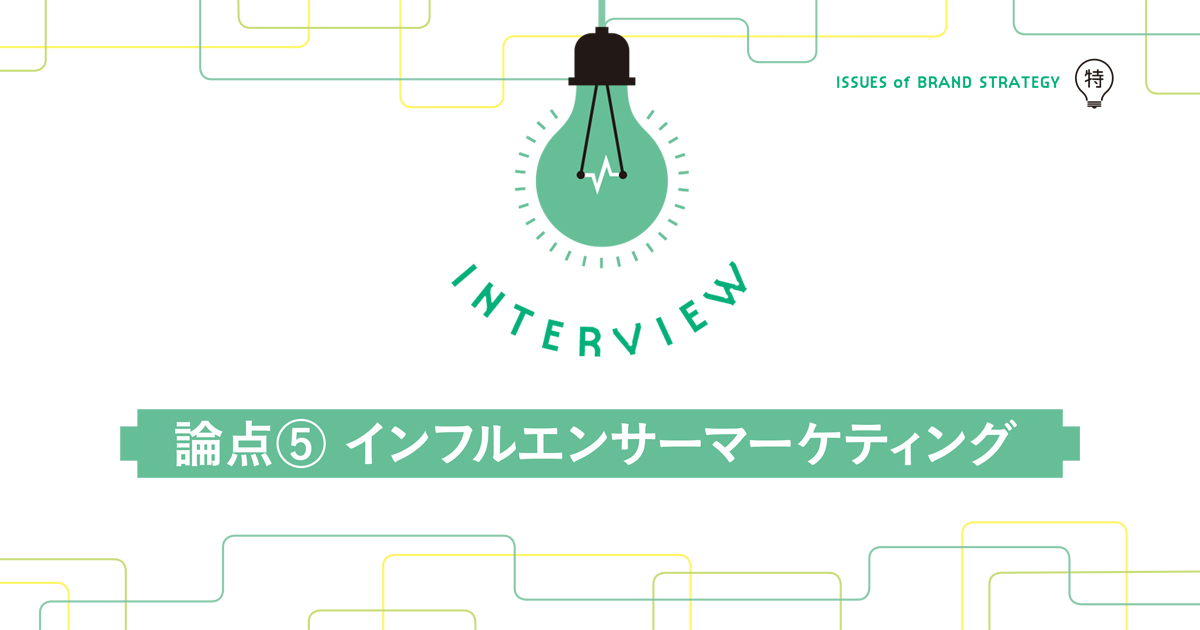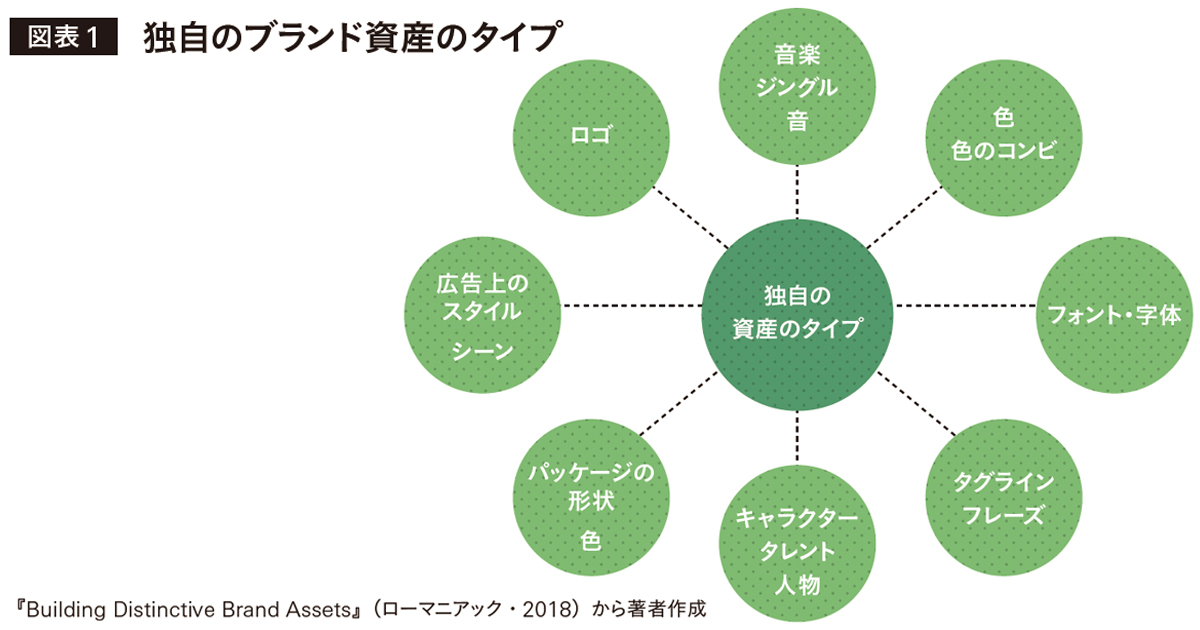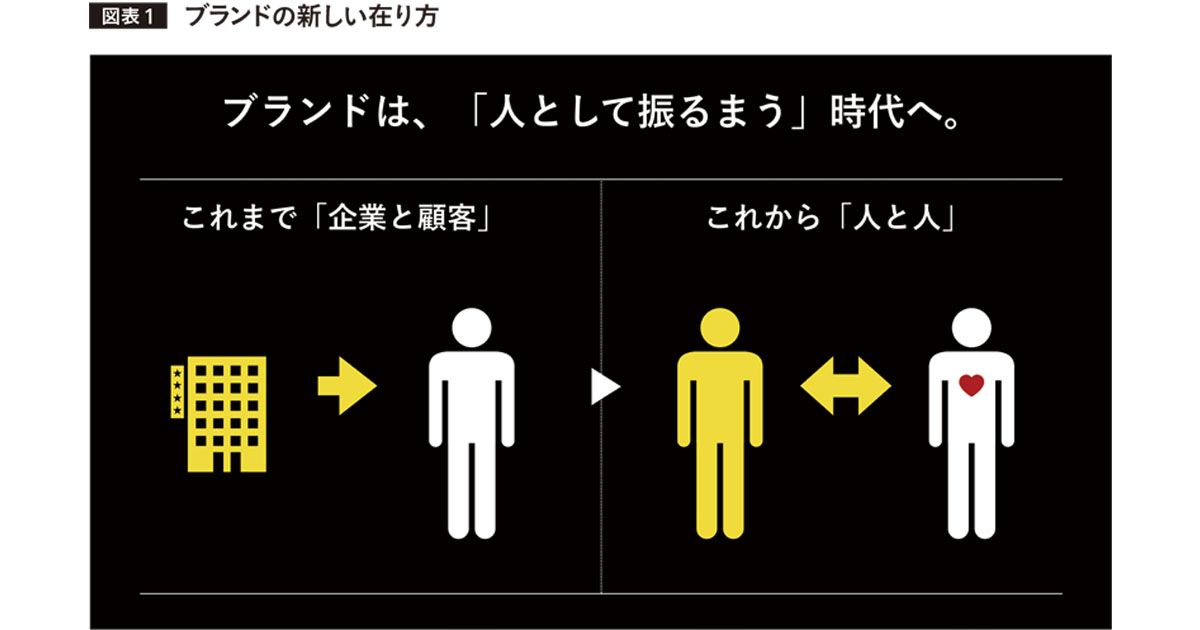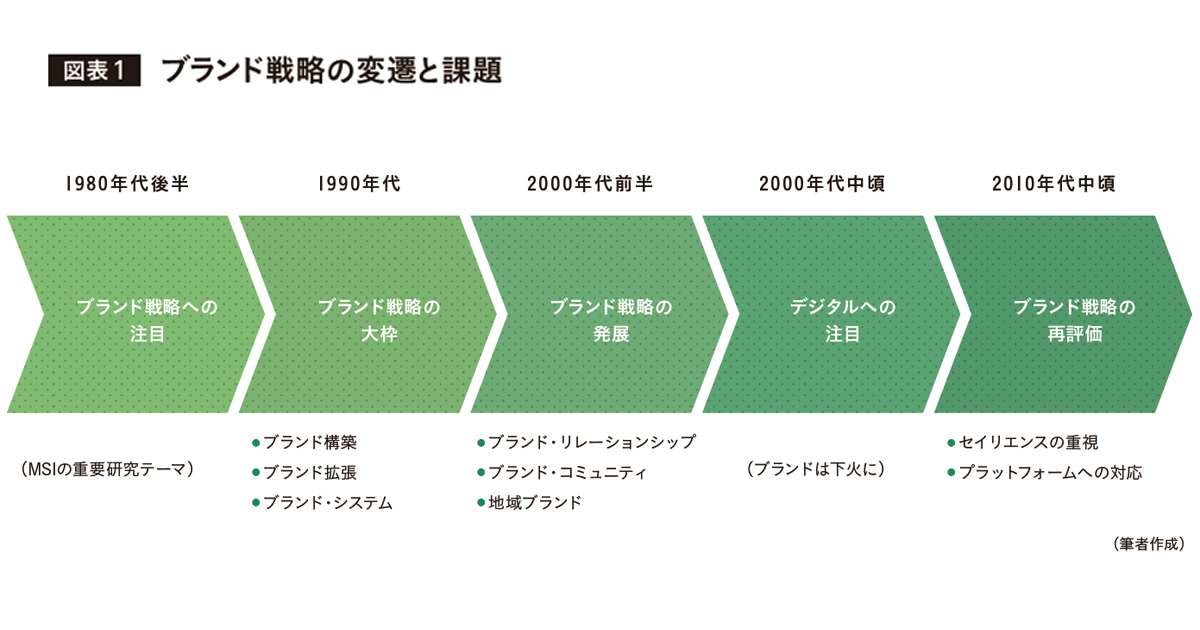「ブランドセーフティ」という言葉が日本の広告界で、頻繁に聞かれるようになる10年以上前から、デジタル広告に対して問題提起を行ってきた大和ハウス工業。ブランド広告主は今、デジタル広告さらにデジタル環境における課題にどう向き合うべきなのか。
POINT
POINT 1 配信先をコントロールできないとブランド棄損の恐れ。
POINT 2 CPA偏重の風土の見直しを検討することも必要。
POINT 3 広告主からも積極的に問題提起し、業界全体の健全化を実現すべき。
求められるのは透明性 デジタル広告が抱える問題点
日本でも広告取引における透明性の問題をはじめとして、デジタル広告が抱える課題に対して、広告主の関心が高まり始めている。
アドネットワークなどを介して配信され、企業が掲載面をコントロールできないことによって起こるブランド毀損のリスク。botなどを使いインプレッション(表示回数)やクリックの水増しをする「アドフラウド」。実際にユーザーがその広告を閲覧できる状態になかったにも関わらず、インプレッションとしてカウントされてしまっている「ビューアビリティ」の問題など、複数のキーワードが注目を集めている。
昨今、急激に関心が高まっているが、こうした言葉が出る10年以上前からブランドセーフティの問題に着眼し、取り組みを行ってきたのが大和ハウス工業だ。
目視と手動で行ってきた地道なブランドセーフティ対応
大和ハウス工業の小林高英氏は、長年こうした課題に取り組んできた背景について「デジタル広告を活用し始めた当時から、掲載面が分かっている他のオフラインメディアなどと異なり、配信先をコントロールできなければブランド毀損の恐れがあることを問題視していたため」と説明する。
そこで同社では配信面が確認できた、広告を掲載してもよいと判断できるWebメディアのみを集めたホワイトリストをつくり、そのリストのみに配信を行ってきた。その作業は、人が目視をするという手間のかかる工程をとってきた …