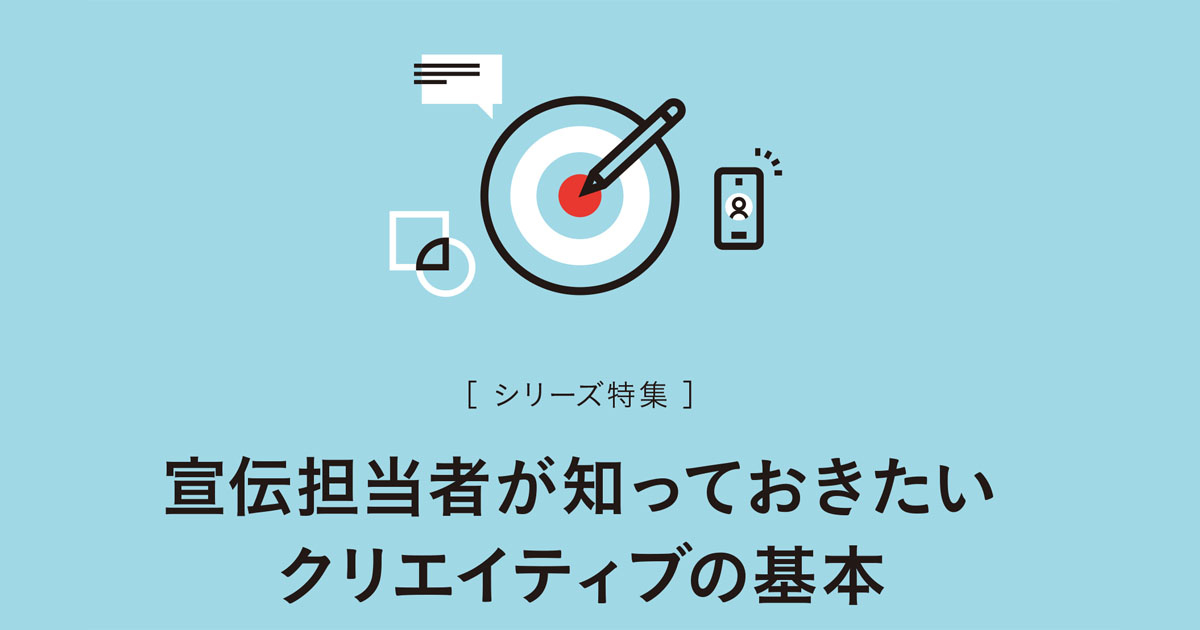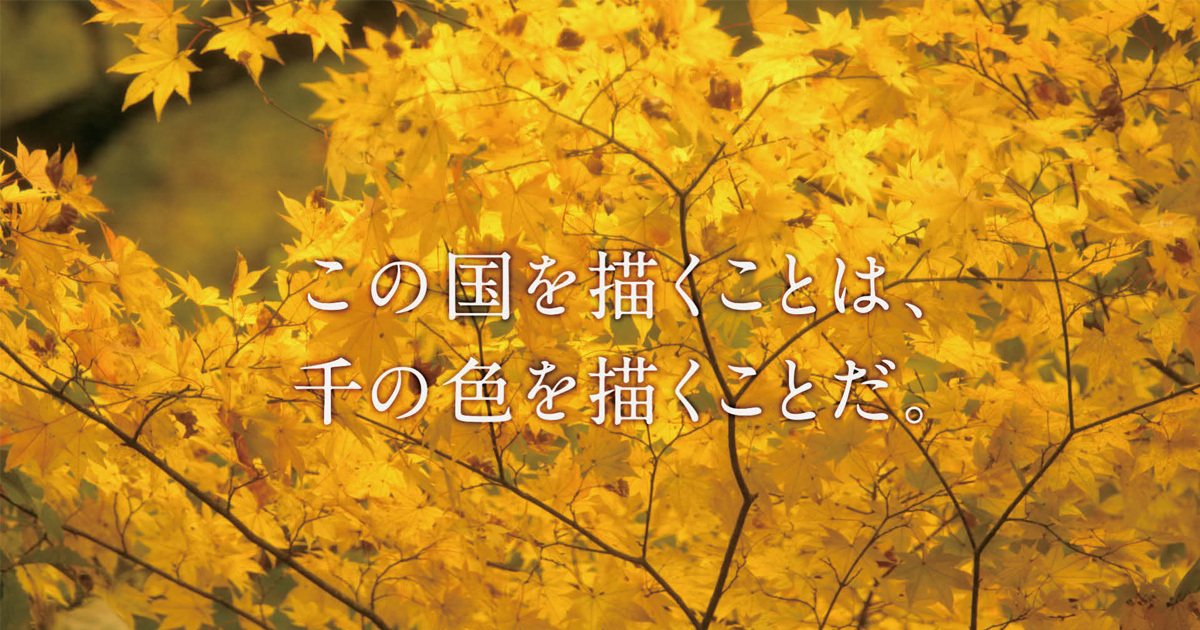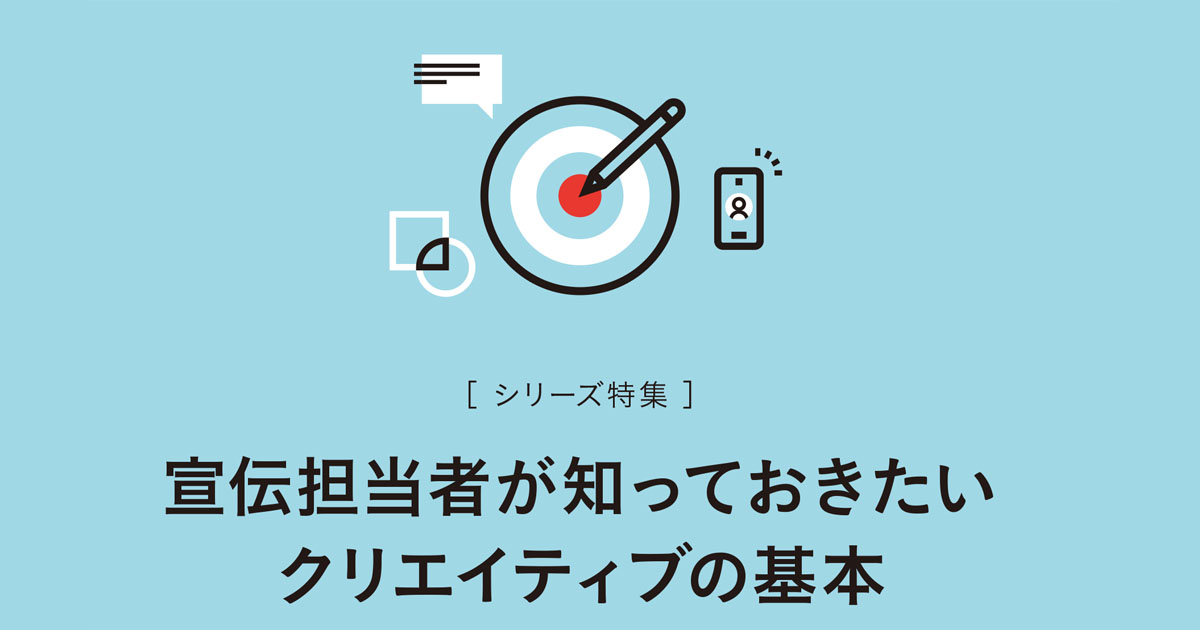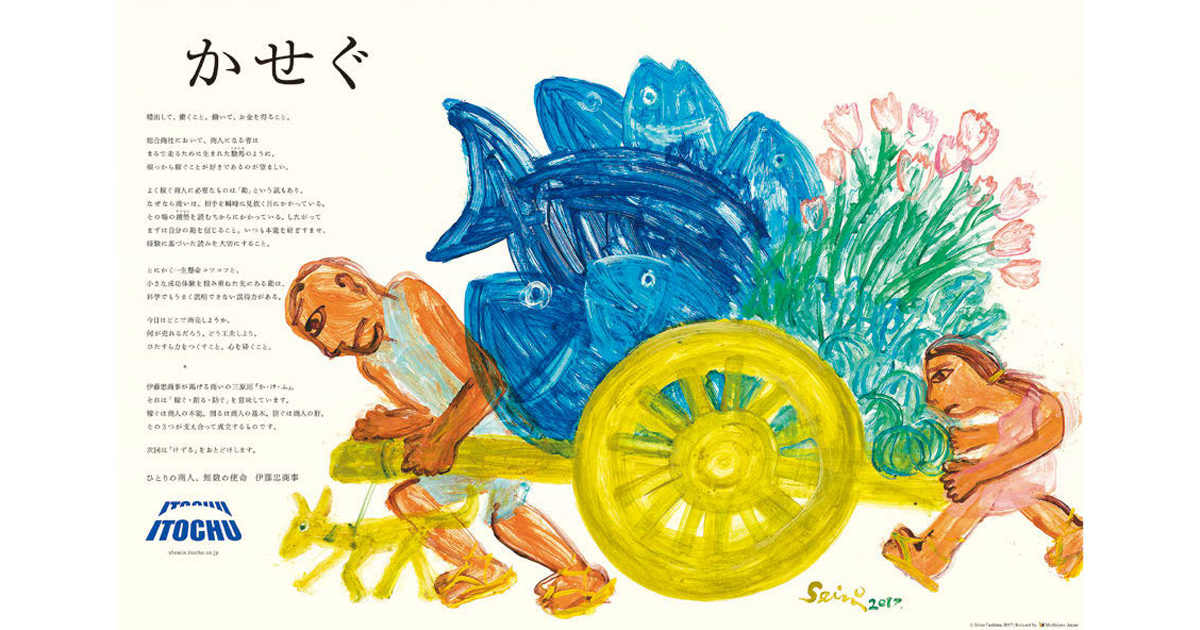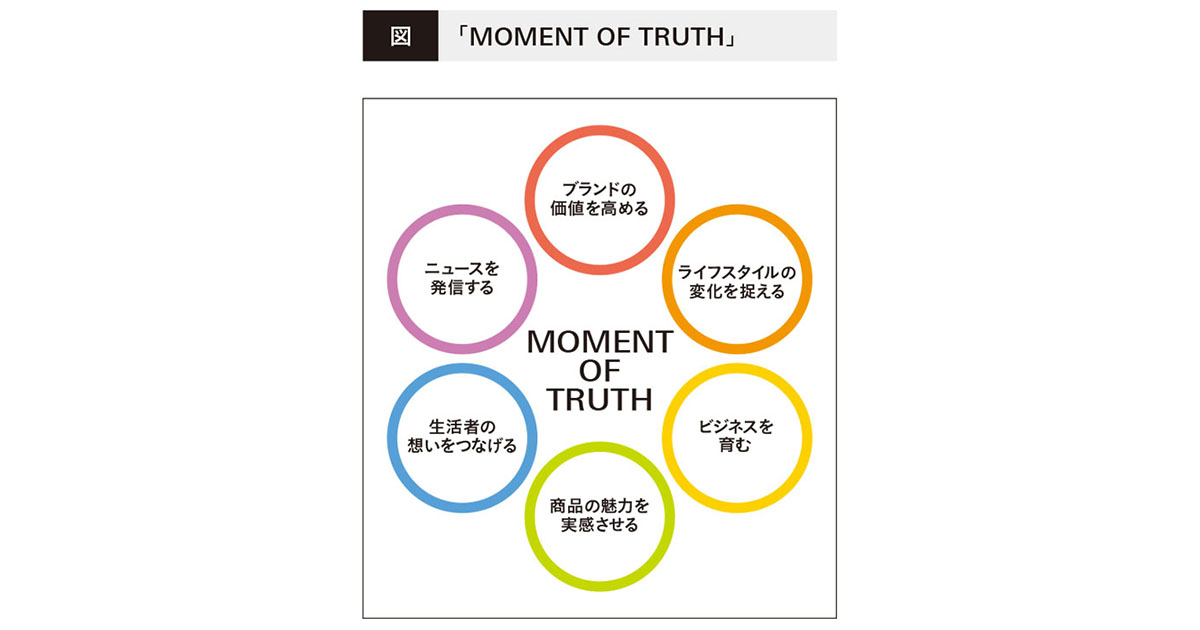今月のテーマ:音のコミュニケーションとクリエイティブ
映像や視覚的要素と並び、あらゆる広告表現にとって欠かせない要素であり続けてきた「音」。昨今のスマートスピーカーや「radiko」の登場により「オーディオアド」を耳にするシーンは確実に増え、広告・マーケティングにおいて、いま注目の分野と言えます。今回は4マスメディア唯一の広告費増の「ラジオCM」と、Web動画で可能性が広がる「広告音楽」のプロフェッショナルが、クリエイティブディレクションのポイントを解説します。
- 結局は人と人とのコミュニケーション。言葉を鵜呑みにせずに、お互いを信頼し合うことがアウトプットの質を高める。
- CMの映像は見られずとも音楽は耳で聞こえる。広告音楽は"引っかかり"を持たせることが役割。
- すべての音に説明責任を持つべき。"言語化できる"音楽はクライアントへの説明の際にも大きな強みになる。
広告音楽制作のポイント!
Web動画市場の拡大 広告音楽のフィールド広がる
初めまして作曲家の近谷直之です。慶應義塾大学を卒業し、ミスターミュージックに入社。3年半勤務したのち3年前に独立。今も広告音楽に携わりながら、ワーナーミュージック・ジャパンより自身のユニットでデビューし、アーティストのプロデュース、ドラマや映画の音楽なども手掛けています。
初めに、広告音楽を取り巻く現在の環境・市況についてお話します。Web動画の仕事は、私が広告の仕事を始めた7年ほど前に比べて確実に多くなってきています。
以前は、Web動画はテレビCMの劣化版という意識を持たれがちでしたが、コンテンツが素晴らしければ、すぐに拡散されて影響力を持ちます。ですので、昨今ではますます「Webだから」というネガティブな意識は薄れてきているように感じます。また、Web動画には"尺の制限がない"という強みがあります。そのため、広告音楽もひとつの曲として表現することができたり自由度が高く、クリエイターとしても挑戦しがいがあります。
また2018年現在では、"6秒動画"の楽曲制作に携わる機会も増えてきました。6秒動画は、YouTubeの動画コンテンツの冒頭や合間に再生されるCMです。Web動画でありながら秒数の制限の中で音をつくるのは、15秒・30秒の世界のテレビCMと似ています。面白いと感じたのは、曲ではなく効果音のようなアプローチでつくっていく案件が多かったことです。
テレビCMの場合、音楽と効果音は別の人が担当し、最後に出演者の声、音楽、効果音でバランスをとり最終調整される場合が多いです。
それに対して6秒動画は秒数の制約上、より内容をシンプルにする必要があります。そのため音楽と効果音を合わせながら、削ぎ落としてゆく作業まで両方担当するのは必然かつ効果的かと感じています。
ディレクターとクリエイター 双方の信頼が仕事の質を高める
より良い広告音楽をつくるために、個人的にはディレクターサイドと私たち音楽クリエイターサイドの、両方のアップデートが重要であると思っています。
"サンプル曲"を例に説明します。広告音楽をつくる前段階には、大抵の場合サンプル曲というものが存在します。サンプル曲(参考曲)があることによって、たくさんのスタッフが関わる広告において制作する広告音楽の指針を示すことができます。しかし、メリットがある一方で、まれにサンプル曲を聞きすぎたために「もっとサンプル曲に似せてほしい」というオーダーに繋がることがあります。つまりディレクターサイドで、サンプル曲は弊害ともなり得るのです。
こうした弊害を避けつつCMの世界観を担保するために、サンプル曲のどの部分が良くて選ばれたのか言語化して曲を分解し判断することが重要になります。それは楽器なのか、リズムパターンなのか、ジャンル感なのか、ミックスの感じなのか。いかに多くの選定理由を汲み取り、サンプル曲以上に映像に寄り添った音楽をつくることが必要とされます。
ですので作曲家として、クライアントや広告会社が本来やりたいことをどこまで汲み取れるかということは、曲をつくる能力と同じくらい必要な能力だと感じます …