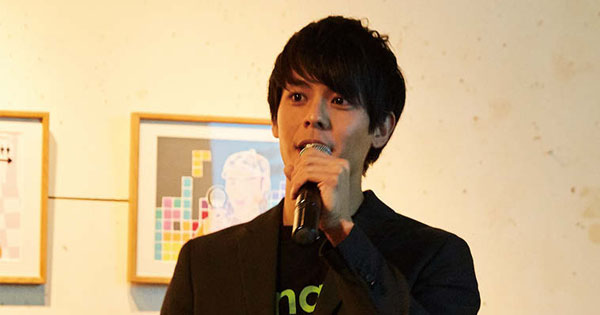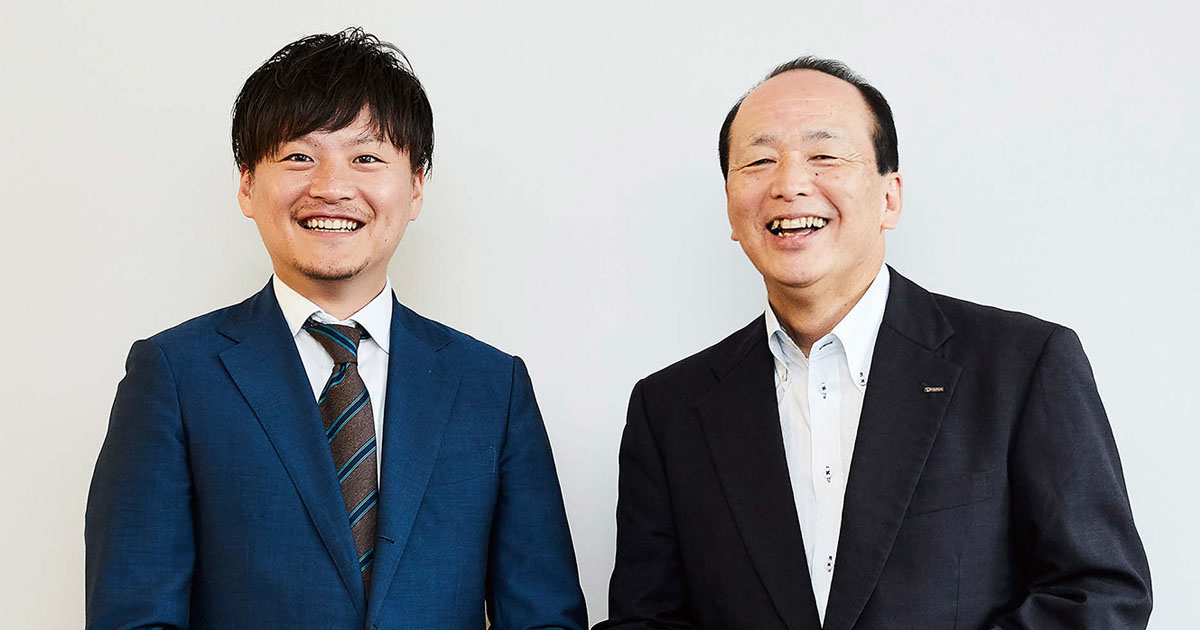「マーケターの集合知で日本に突き抜けた成長力を生み出す」ことを目的に設立された「JAPAN CMO CLUB」。すでに参加マーケターも90名を超えている。定期的に開催している異業種のマーケターが集まる研究会の場で見えてきた、これからの日本のマーケティングが進むべき道とは。

写真左から、近畿大学 総務部長の世耕石弘氏、「JAPAN CMO CLUB」CMOの加藤希尊氏(セールスフォース・ドットコム マーケティングディレクター)、小林製薬 ヘルスケア事務部 マーケティング部 部長の荒木学氏、アダストリア 執行役員 マーケティング本部長の久保田夏彦氏。
総合力が強みだからこそ抱えるブランディングの課題
「JAPAN CMO CLUB」の22回目となる研究会がアダストリア、近畿大学、小林製薬の3社が参加して開催された。若年層をターゲットとする近畿大学、アダストリアの2社が参加をしていたため、今回の研究会ではマーケティング課題の中でも特に「人口減少」に議論の焦点が当たった。
近畿大学の世耕氏は「対象人数が減っていくため、志願者をどう確保していくかが課題。広報活動は志願者の獲得が大きな目的」と話す。
近畿大学は医学から芸術まであらゆる分野を網羅する日本屈指の総合大学だ。しかし大学案内に全ての特徴を掲載すると、ただ厚いばかりの冊子になってしまう。そこで近畿大学では『東京グラフィティ』とコラボレーションして大学案内を制作。「大学側が言いたい、設備や研究成果などは志願者である高校生にとってはあまり興味を持たないこと。志願者の視点に立って、求められるコンテンツを考えた」(世耕氏)。
アダストリアの久保田氏は「当社の場合、グローバルワーク、ローリーズファーム、ニコアンドなど各ブランドの認知度は高いが、会社の認知度が低い。良い人材を確保するためには知名度が必要。個々のブランドの認知拡大に力を入れるか、コーポレートブランドの認知拡大に努めるか、バランスの取り方が難しい。まさに大学の各学部と大学自体の認知度のどちらに注力すべきか、という世耕さんが抱える課題に近い」と話した。
2人の発言を受け、小林製薬の荒木氏は「当社の商品は、困っている人が明確にいて、その人のためにつくっている。いわば、たったひとりのお客さまをターゲットにしている」と自社の戦略を話した。同社では常に200もの商品が開発検討中だというが、全ての商品に共通するのは、「ターゲットが明確」であることの他に「ネーミングとパッケージと広告で、コンセプトを伝える」ことだと荒木氏は話す。「かっこよさを求めるのではなく、わかりやすくすることだけにこだわっている」という。
明確なターゲットに対してアプローチを続ける3社。若者の人口減少という課題を抱えながらも、コモディティ化から抜け出る秘策は、「たったひとりのお客さまを意識する」というターゲットの明確化なのかもしれない。
ディスカッションの最後に、加藤氏は「JAPAN CMO CLUBを、ひとつの会社だと考えると、食、民泊、旅行、ヘルスケア、金融、車など、ひとつの社会を形成する会社と言える。マーケティング予算も1兆円を超えるだろう。その力を集結させれば、日本を動かしていける力があると思っている。皆さんの話を聞き、他社の資源と組み合わせて発信できるような場を提供できるプロジェクトを新たに発足させていきたい」と話した。

「JAPAN CMO CLUB」の活動報告は、随時、宣伝会議運営のWebメディア「アドタイ」にてレポート中です。
http://www.advertimes.com/special/cmoclub/
(本組織はセールスフォース・ドットコムと宣伝会議が共同で設立したものです)