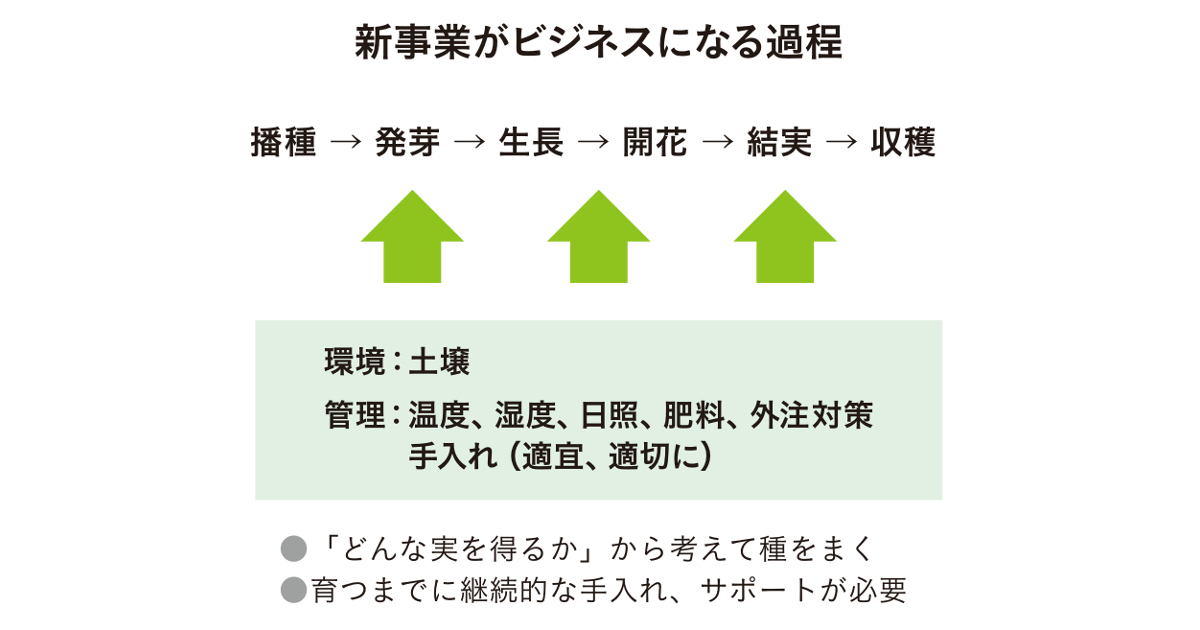6月27日、東京・宣伝会議本社にて「Girls Marketing Collection2018」が開催された。基調講演に始まり、1日で合計7つのセッションが催された本イベントの模様をレポートする。

基調講演の様子。扱う商材の異なるマーケター同士の議論の中には、女性のインサイトに関するたくさんの共通点があった。
1日で7講演を開催 変わるインサイトを捉える
6月27日、東京・宣伝会議本社にて「Girls Marketing Collection2018」が開催された。女性、特に若年女性を対象にそのインサイトに迫ることを目的とした本イベントには、女性向けブランドを担当するマーケターや女性向けのメディアを運営する企業が一堂に会し、日ごろ得ている、それぞれの知見を発表し、さらにディスカッションを行った。
スマホやSNSなどの浸透で、若年女性のメディア接触、そして消費行動は大きく変わっている。つかみづらい、その消費の今を捉えようというのが本イベントの目的だ。基調講演に始まり、1日で合計7つのセッションが繰り広げられた。
基調講演では「マーケターが押さえるべきガールズインサイト」をテーマにパネルディスカッションが開催された。登壇したのは、アダストリアの鈴木真之介氏、カルビーの網干弓子氏、コーセーの小林祐樹氏、ジョンソン・エンド・ジョンソンの亀田真穂氏の4名だ。

基調講演の後は、分科会を実施。女性のインサイトを把握する事業者、メディア企業による講演が行われた。
「ガールズ」の定義とは?マーケターそれぞれの考え
今回のセッションでは主に、アダストリアの鈴木氏は「ローリーズファーム」について、カルビーの網干氏は「フルグラ」について、コーセーの小林氏はネイルブランドの「NAIL HOLIC」について、ジョンソン・エンド・ジョンソンの亀田氏は「ジョンソンベビーオイル」について事例や取り組みを紹介していった。
パネルディスカッションの冒頭では、まず定義のあいまいな「ガールズ」という言葉について、登壇者それぞれの考えが披露された。「若年女性をさす言葉のように思えるが、年齢に関係なく、女性の中にあるひとつの嗜好性と考えている」(小林氏)、「50代でもガールズの心を持ちたいと考えているのが現代。年齢軸では捉えきれない」(網干氏)といった答えが中心を占め、年齢軸ではなく嗜好性や行動、考えの特徴のひとつとして捉えるべきという考えが示された。
それでは、ガールズならではの嗜好性とはどのようなものか。との問いに対しては「カワイイ、おしゃれ、話題の、インスタ映え、女子会といった言葉をイメージする」(亀田氏)との回答が。一方で、鈴木氏からは「ファッションだけに限らないかもしれないが、"ガールズブランド"と表現してしまうと、自分には若すぎるのではないか…と敬遠されてしまうケースも見られる。この言葉の使い方については注意が必要」との考えも示された。
女性たちが求めているのはちょっとアガれる日常の体験
セッションでは各社のマーケティングケースも紹介された。コーセーの小林氏が紹介したのは「NAIL HOLIC」の取り組みだ。同ブランドは価格を300円代に抑え、なおかつ175色の展開で、気分やシチュエーションに合わせて、気軽にネイルを変えて楽しみたいという女性のインサイトを捉えている。あえてテレビCMなどの広告展開はせず、オンライン動画やSNS発信、アンバサダー施策、そして多色展開だからこその店頭での圧倒的な存在感で、売上を伸ばしてきた。
最近の取り組みとしては、ネイルと親和性の高そうな他社ブランドとのコラボ企画を実施している。例えば、今年の夏は靴ブランドの「ESPERANZA」とコラボして、対象のサンダルを購入すると、そのサンダルに合ったカラーのネイル3本セットが当たるキャンペーンを企画。
小林氏は「他ブランドとのコラボは積極的に行っているが、重視しているのは価値交換による新たなお客さまとの出会いになるかどうか。サンダルを履く夏は、特に足元をかわいく見せたいという気分が高まるとき。新しいサンダルを購入したタイミングで、新しいネイルの提案をすることは、お客さまにとっても価値あることだと考えた」と話す。
またアダストリアの鈴木氏からは「Girls Tune FES」という体験型イベントの事例が紹介された。今年で開催3回目を迎えるイベントで、前回は約6000名が参加をしたという …