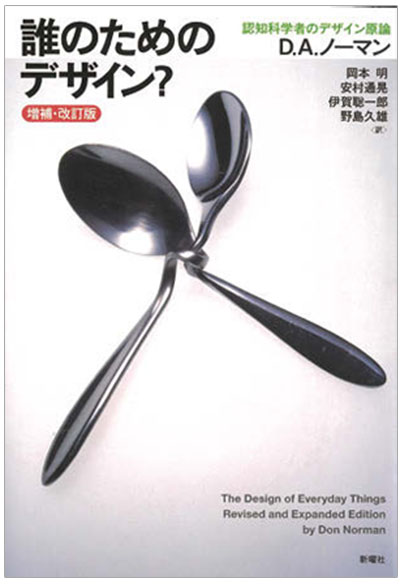
『誰のためのデザイン? 増補・改訂版―認知科学者のデザイン原論』
新曜社/D.A.ノーマン(著)、岡本 明・安村通晃・伊賀聡一郎・野島久雄(訳)
毎日使う道具やシステムがなぜ使いにくいのかに焦点を当て、ユーザーが悪いのではなくデザインが悪いのだと看破した本。わかりやすく情報デザインの基礎知識を学ぶことができる(渡辺氏)。
誰もが使えるウェブへ 教育・研究・実践の三本柱から挑む
東京女子大学の渡辺隆行氏は、ウェブアクセシビリティ向上に結びつく情報デザインの研究・教育・社会活動に取り組んでいる。2010年に策定された「JIS X 8341-3」という障がい者や高齢者が使えるウェブをつくるためのガイドラインの主査を務めたあと、総務省や経済産業省、企業と連携したウェブアクセシビリティ基盤委員会の委員長を務め、現在はNPO法人ウェブアクセシビリティ推進協会の理事長を兼務。企業と協力してウェブアクセシビリティを推進する活動に取り組む。
2016年4月に障害者差別解消法が施行されたこともあり、ウェブアクセシビリティも普及してきているというが、渡辺氏は次のように話す。
「ウェブ制作者は制作の主な目的がウェブアクセシビリティの向上というわけではないので、意識の浸透はなかなか難しいという課題があります。その解決策のひとつとして私が考えていることは、法制化すること。米国ではウェブアクセシビリティ関連の法制化が進んでいますが、日本ではまだ進んでいません …

