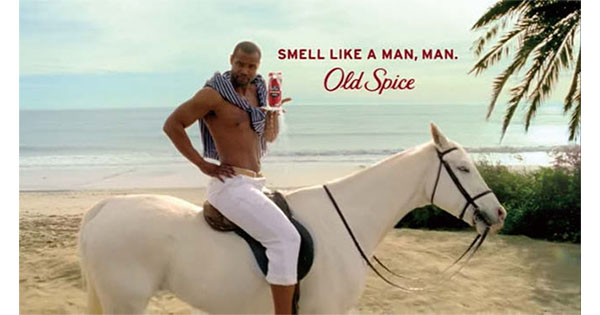好調・堅調に見えるブランドでも、実は「危機」や「苦境」に瀕していたという過去を持つケースが、業種業態を問わず、数多く存在します。ここでは8つのブランドに注目し、それぞれが「再・成長」を遂げて現在に至るまでのエピソードを概観します。
BRAND 01
業界の常識を覆す酒造りを確立
旭酒造「獺祭」

国内外で人気を博す純米大吟醸も、過去には大きな危機に直面していた。旭酒造は、1984年に生産量がピークの3分の1まで低下。さらに新規事業の失敗によって多額の負債を抱え、杜氏にも逃げられてしまう。しかし、これをきっかけに、「酒造りの工程の詳細なデータを蓄積・分析し、フィードバックしながら改良を繰り返す」という独自の酒蔵のスタイルが生まれた。業界の常識を覆す施策により、20年間で約500%の売上増を達成した。
BRAND 02
ターゲットの見直しで人気が復活!
エフティ資生堂「シーブリーズ」
米国生まれの「シーブリーズ」が日本で正式に販売されるようになったのは1970年頃のこと。その後80~90年代にかけて「夏」や「海」のイメージを訴求し、サーフィンをはじめスポーツを楽しむ若者の支持を得たが、認知度・使用経験ともに徐々に低下。
そこで2007年に訴求ポイントを「汗対策」に切り替え、制汗剤「デオ&ウォーター」のターゲットを10代男女に設定、容器の色もカラフルに刷新した。結果、1年で売上は低迷期の8倍を記録。2016年には、色違いのキャップを交換することが高校生の間で流行し、前年比145%の売上を達成した。
BRAND 03
無名だった霧島酒造が、全国区に
霧島酒造

「黒霧島」は、焼酎の消費量が緩やかに減少する中、発売以来、出荷量を伸ばし続けている。霧島酒造の名を全国に広げた看板商品でもある …