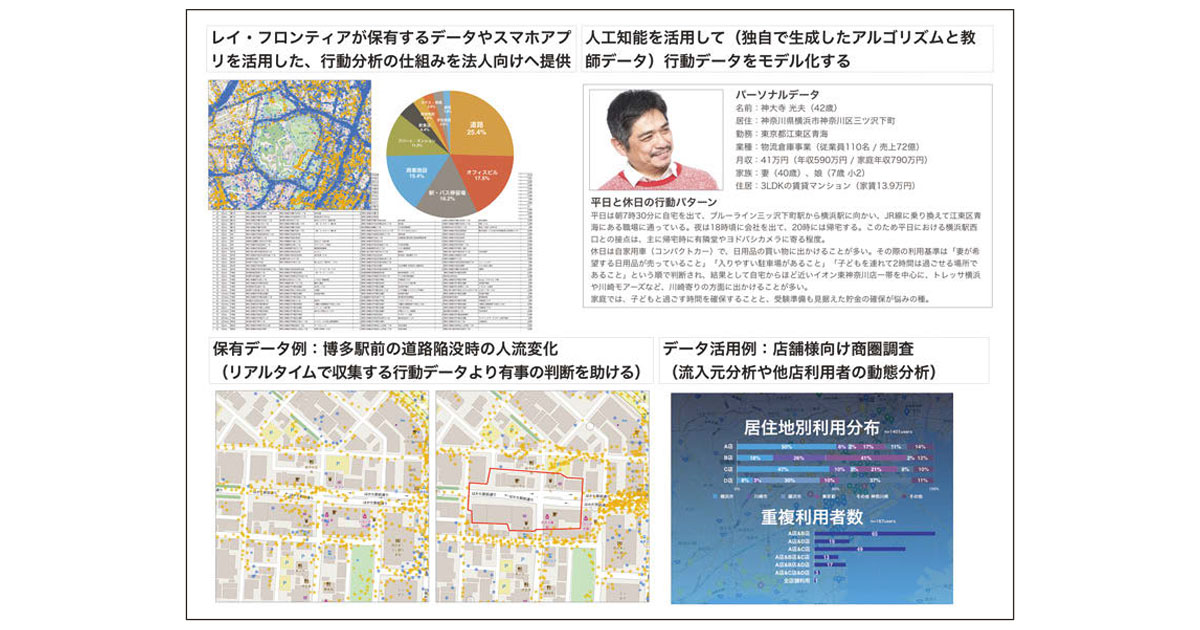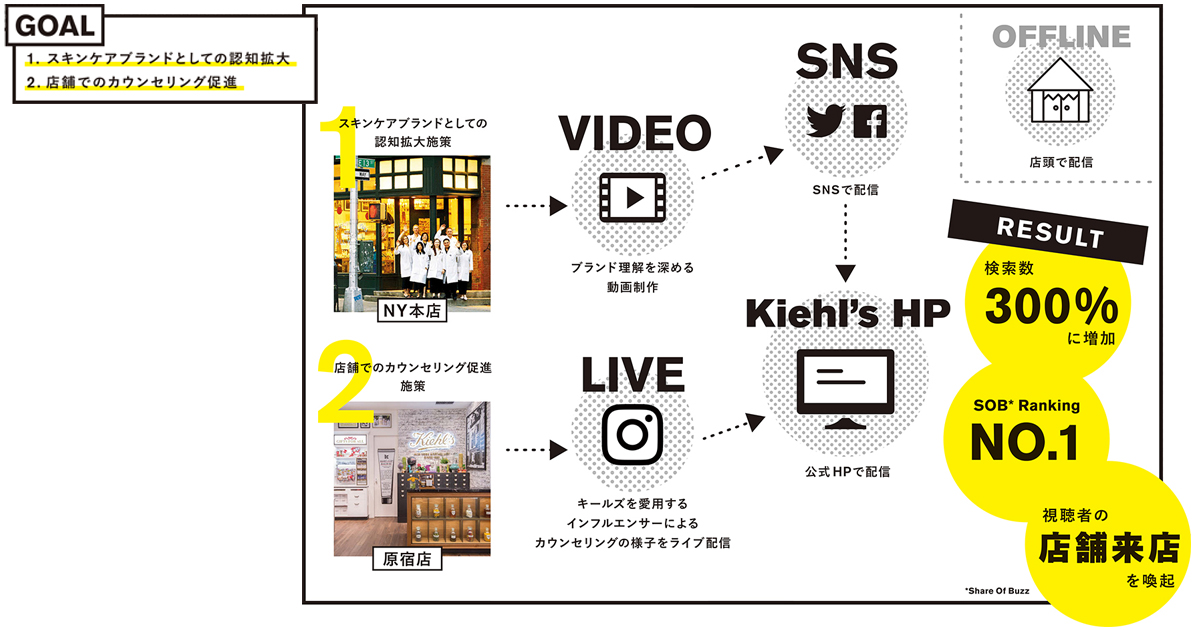「日本のマーケターの集合知をつくる」ことを目的に設立された「JAPAN CMO CLUB」。すでに参加マーケターも70名を超えている。定期的に開催している異業種のマーケターが集まる研究会の場で見えてきた、これからの日本のマーケティングが進むべき道とは。

(写真左から)アサヒグループ食品 食品マーケティング部 部長の林和弘氏、Knot(ノット) 代表取締役の遠藤弘満氏、シャープ IoT通信事業本部 コミュニケーションロボット事業統轄部 市場開拓部長の景井美帆氏、「JAPAN CMO CLUB」CMOの加藤希尊氏(セールスフォース・ドットコム マーケティングディレクター)。
ひとりの中に存在する 多様性に向き合うべき
11月24日に「JAPAN CMO CLUB」の19回目となる研究会が開催された。参加企業はアサヒグループ食品、シャープ、Knot(ノット)の3社だ。扱う商材は異なるものの、3社の共通点は形あるプロダクトを製造・販売しているメーカーであるという点。コモディティ時代に、いかにして機能性だけでない価値をつくれるか、各社の取り組みには共通点も多く見えてきた。
メイド・イン・ジャパンをうたい、職人とのストーリーを大切にしながら腕時計の製造・販売を行うKnotの遠藤氏は「ライセンスウォッチから抜け出して、ものづくりの背景や生産者のストーリーが見えるブランドにならないといけない。これからはそういう差別化が求められるように変わっていくと思います」と自信を見せた。
商品の背後にあるストーリー、またその商品をつくる企業自体の人格も伝わるようなコミュニケーションこそが、コモディティ時代を生き抜く企業に必要な視点ではないか。研究会の議論のテーマは「体験」の価値へと移っていった。
顧客体験について、「リアルな接触ポイントを自社で持つことが大事」とはアサヒグループ食品の林氏の意見。同社の「ミンティア」は、店頭で名前入りシールを制作するイベントを全国約150カ所で開催しているそうだ。「我々が想像した以上に盛況で、お孫さんを連れたおじいちゃん、おばあちゃんが来てくれたり、今まであまりリーチできなかった人たちに試していただけています」。
「ロボホン」も"エバンジェリスト"のような役割を担うオーナーが全国各地でリアル体験イベントを開催している。「20~30名ほどが集まり、情報交換をしたり、ロボホンの自慢をしたり。少し私どもの手を離れ始めているところが良いのではないか、と思います」(景井氏)。
議論から見えてきたのは、商品認知に留まらず、実際に体験してもらう機会をつくることの重要性だ。「知ったつもり」の一歩先、ワクワクするような商品体験の場の設計がマーケターにとって、課題となっているようだ。研究会を終え、加藤氏は体験価値を設計する視点の重要性について言及。さらに消費者にとっての価値を考える際、それぞれの消費者の多様な内面に目を向けることも必要ではないか、と指摘した。
「10~20代は、Twitterも平均で4アカウントほど所有していたり、SNSの活用方法だけを見てもひとりの中に、多様なアイデンティティが共存している。一方で50~60代は外に向けるアイデンティティとソーシャル上のアイデンティティがほぼ同じ。消費者基点、人の心に響く体験やサービスを設計する際には、顧客の多様な内面にまで向き合うべきではないか」と話した。
「JAPAN CMO CLUB」の活動報告は、随時、宣伝会議運営のWebメディア「アドタイ」にてレポート中です。
http://www.advertimes.com/special/cmoclub/
(本組織はセールスフォース・ドットコムと宣伝会議が共同で設立したものです)