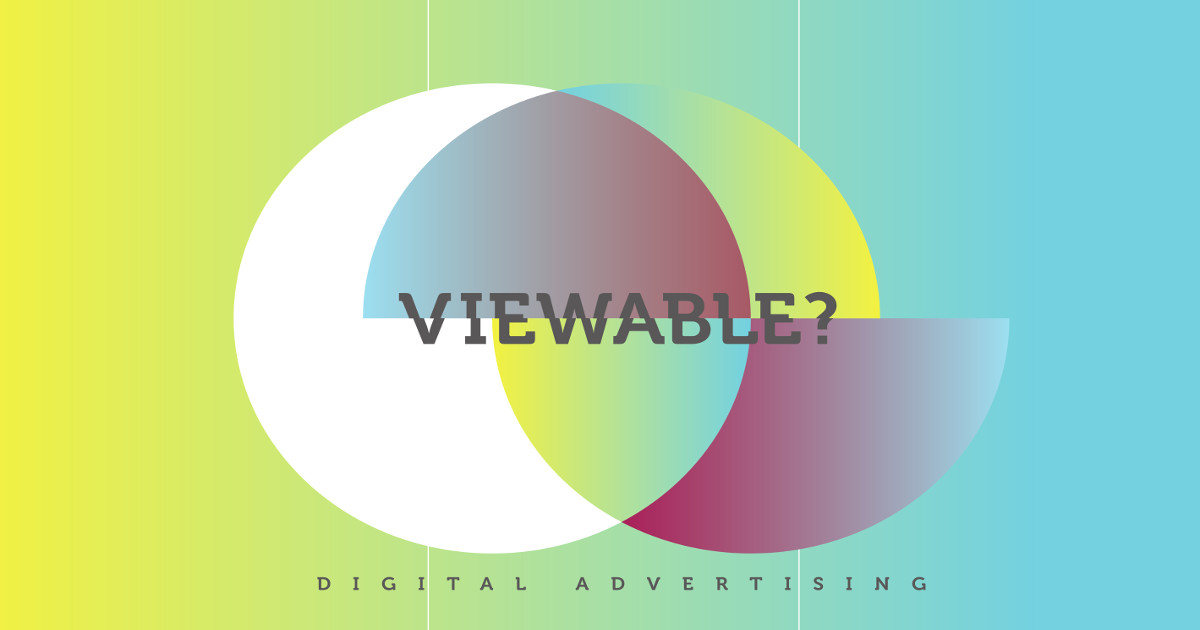国内においても、日本の広告界特有の事情を踏まえながら、議論や対応が進められています。まずは現状を正しく把握することが、業界の健全化への第一歩です。
インターネット広告の測定指標の一つとして注目されるようになった「ビューアビリティ」。技術の進化により、これまでは測定できなかった「広告が可視状態にあるか」を定量的に把握できるようになった。
日本インタラクティブ広告協会(JIAA)の測定指標委員会では、米国の「MRC Viewable Ad Impression Measurement Guidelines」をベースとした、国内のインターネット広告業界における「ビューアビリティ」の定義と測定ガイダンスを発表。広告主・広告会社・メディアレップ・メディア・調査測定事業者に向けて、「ビューアビリティ」という新たな指標を有効活用することを通じた、インターネット広告業界の健全化・活性化を呼びかけている。
「ビューアビリティの計測ができなかった時代にも、Webページの下のほうに表示される広告がユーザーの目に触れにくいということは当然わかっていました。ファーストビューで表示されるものと、そうでないものとは広告価値が異なる。インターネット広告の価格形成は、それを前提に行われてきました。それが、どの広告がどれだけユーザーの目に触れたかが精緻に測定できるようになってきた。広告枠によって価格が異なることの根拠が明確にできるようになったのです。これをインターネット広告の新しい指標として活用することで、業界の健全化や成長につなげていくことが、私たちの活動テーマです」と、JIAA常務理事の植村祐嗣氏と、エグゼクティブエキスパートの金山泰久氏は話す。
ビューアビリティは、インターネット広告の中でも、認知向上やブランディングを目的に出稿される広告の効果を高める上で有効な指標だと、植村氏・金山氏は指摘する。
「日本におけるインターネット広告は、これまで『獲得型』が中心でした。そこでは、効果測定指標としてはコンバージョンがすべて。広告がビューアブルかどうかは、ほとんど意識されてきませんでした。しかし近年、ようやくインターネット広告が“マス広告”として認められ、パーチェスファネルの上部でも活用されるようになってきました。これに伴い、見られるかわからない枠より、確実に見られる枠に表示されることが重要と、ビューアビリティを重視する流れが生まれたのです」。
JIAAでは、ビューアビリティの積極的な測定を促すことで“脱・クリック偏重”を図り、インターネット広告市場の次なる成長のきっかけとしたい考えだ。「これまでインターネット広告の価格は、『ユーザーの目に触れにくい』ものがあることを踏まえて設定されていました ...