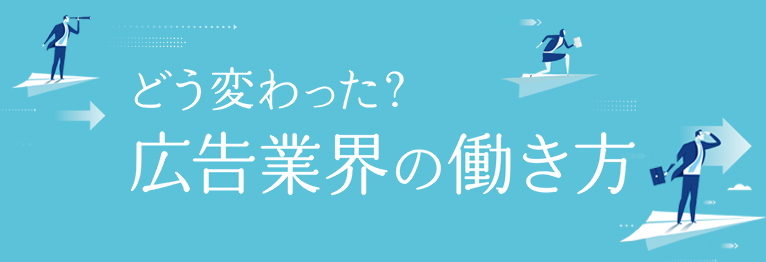外資系広告会社では、国内の広告会社や制作会社よりも働き方の自由度が高く、業務時間の裁量を持っていると聞く。広告業界にとって役立つポイントを探るため、国内の広告会社の動向に詳しいWeb編集者の中川淳一郎氏から、日本で活躍する外資系クリエイティブエージェンシーを率いるクリエイティブディレクターに話を聞いてもらった。

(左から)
編集者/PRプランナー 中川淳一郎氏、Wieden+Kennedy Tokyo 長谷川踏太氏
AKQA クラウディア・クリストヴァオ氏、ジオメトリー・グローバル・ジャパン 三寺雅人氏
フィー制度によって変わるクリエイターの働き方
中川:外資系クリエイティブエージェンシーの働き方は、国内の広告会社と比べると全然違うんじゃないかなと思っています。まずお聞きしたいのは、みなさんがクライアントから得る報酬の形態は、国内で一般的なコミッション(手数料制)ではなく、フィー(作業報酬制)なんでしょうか?
三寺:はい、外資系広告会社は一般的にそうですよね。クリエイティブスケールを広げたりするためにコミッションで仕事をする場合もありますが、基本的にはフィーです。
長谷川:そうですね。年間を通してクライアントと契約を結んで、スタッフがどの仕事を何時間しているのか報告しています。
クリストヴァオ:私もこれまでアムステルダムとロンドン、東京で働いてきましたが、クリエイティブ業務が中心の会社で働くことが多かったこともあって、全てフィーでした。
中川:私はフリーになってから、広告会社と仕事をしていると「予算が10万円しかないんだよ。他に頼めないので、な、な、頼む!」と依頼されることがあります。みなさんも、そういう依頼を受けることはありますか?
長谷川:いや、その仕事は受けちゃいけない(笑)。
三寺:受けちゃいけないですよね。でも、うちのチームであればスタッフがそのプロジェクトに熱意を感じる場合には個人的に受けることを認めることもあります。会社以外に自分の表現の場を持つことを推奨しているので。
クリストヴァオ:重要なのは、エージェンシー自身のポジション付けだと思います。クライアントの単なるベンダーになるのか、それとも一緒に協力し合い成長していけるパートナーになるのかということです。パートナーとしての関係が構築できれば、広告会社の仕事をリスペクトしてくれますし、無理難題を押し付けないと思います。
中川:日本の大手広告会社の場合、テレビCMを年間100億円ほど出稿してもらったので"クリエイティブはおまけ"という感覚があります。みなさんの会社でもメディアを買うことはあるんでしょうか?
三寺:私たちは、メディアエージェンシーではありません。クリエイティブのパートナーとして、アイデアやその実行に対価をいただいています。「世の中にこの商品を出すために何をすべきか」というレベルから考えることが得意なのが、外資系クリエイティブエージェンシーです。
長谷川:クライアントの目的が達成されるのであれば、最終的なアウトプットが、たとえば「街でティッシュ配り」という手法でもかまいません。おそらく100億円をかけることが決まっている仕事は、最初からテレビCMありきになってしまう。クライアントにとってベストなアウトプットとは何かということを、我々は常に考えるわけです。
6日間連続でカンヅメ それって外資系で成り立つの?
中川:10年以上昔、私が広告会社にいたときに、ある不動産会社のコンペで街の再開発プロジェクトに関わったことがあります。私はPR担当として参加していたのですが、クリエイティブも含めて20人以上が6日間連続で企画を考え続けていました。結果的にコンペには勝てたんですが、外資系であればこんな仕事の仕方は成り立たないと思うんですけど。
長谷川:そんなに過酷な話は聞いたことがなかったですけど、規模の大きなコンペであれば、ある程度のリスクをとることはありますが…。
中川:フィーの場合だと、これ以上はやらないで止めておこうといった考え方が働くんでしょうか。
長谷川:基本的に外資の場合は、契約で決めた以上に、スタッフが働く必要があればフィーが発生するため、たとえば「5時間ほど追加しなければいけないのですが、よろしいですか」とクライアントに確認します。広告制作の現場で、写真家を1人追加しなければいけない場合は、当然フィーが掛かりますよね、これと同じことです。
クリストヴァオ:日本ではミーティングに同じようなスーツを着た人が20人以上、何も言わないでずっと座っているということがあります。クライアントに対して親切なのは3、4人程度で一人ひとりの役割が明確化されている状況です。賢いクライアントであれば、それらの人員に経費を払いたいとは思いませんから。
中川:日本の場合、その考えができていないということですね。クライアント側も印刷代などに費用がかかることは理解していますが、人の知能はタダというふうに思っている節があります。
クリストヴァオ:人の知能やアイデアのような主観的で、実体のないものにどのような価値をつけるかということだと思います。日本の文化的な特徴なのかもしれないですが、業務に掛けた日数や関わった人数など「数字」に重きを置くという風土を感じています。もちろんそれらも価値の測り方の一つではありますが、海外の場合、鍵となる数人が生み出す最終的なアウトプットが価値として見られます。
三寺:僕らクリエイティブはいいアイデアを生むために、途中で考えることを止めることはしませんが、フィーの場合、クライアント側が決断しなければ、どんどん追加費用が掛かっていくという仕組みなんです。なのでその分、本当に効果があるクリエイティブかどうかを毎回、真剣に議論ができていると思います。
中川:クライアント側に決断してもらうために、用意しているものはあるのでしょうか?
三寺:そもそもプロジェクトが始まる前に、何をしたいかをまとめたブリーフシートをつくり、お互いにサインするんです。「こういう目的のために、これをやります」という契約書です。進めていく中で、ブリーフシートと違うことが出てくれば、それは依頼内容と違う仕事となります。少しシステマチックではありますが、お互いに目的に向けて、一つひとつ同意しながら積み重ねていくという進め方です。
中川:日本の広告会社の場合、根性や忠誠心を妙にビジネスに持ち込んでしまうことがあるんだなと感じました。
クリストヴァオ:私たちの働き方に忠誠心がないのではなく、日本と海外の広告業界の違いは質の高いアウトプットを生み出す要因が仕事の外にある、という考え方によるものだと思います ...