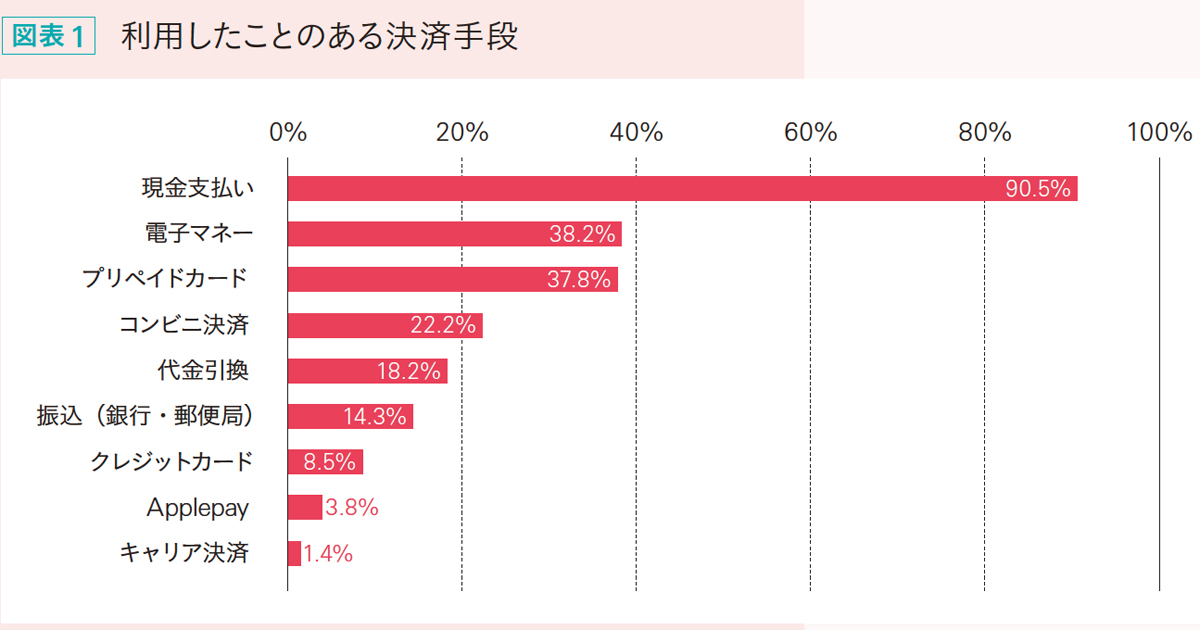FinTechに興味はあるものの、金融業界の専門用語だと思って苦手意識を持っている人も多い。そこで、マーケターが知っておくべきFinTechのキーワードを、FinTech協会の代表理事でインフキュリオン・グループ 代表取締役 丸山弘毅氏に解説してもらう。
keyword 01 FinTech
まずはFinTechについて解説する。「Finance(金融)」と「Technology(技術)」を合わせた造語で、一般的に「金融とITの融合」と言われている。そのジャンルは幅広く、融資・投資・保険といったまさに金融領域から、決済や送金、会計や家計管理といったお金の管理、ブロックチェーンや生体認証などの要素技術、クーポンやポイントと関わるマーケティング領域など、特定の範囲に限定されない。
しかし金融およびその周辺業界では、従来からITを活用してきた経緯があり、事業の全てがFinTechというわけではない。現在のFinTechとは、Technologyの進化を前提に、金融サービスを再デザインすること。大げさな言い方をすれば、Tech業界が金融業界の常識をつくり変える活動とも定義できる。
この常識をつくり変える活動には、大きくは2つの潮流がある。1つ目は、人口知能(AI)やブロックチェーン、クラウド・APIといった技術により業界構造を変革し、利用者にとっての金銭的・時間的コストを下げること。2つ目は、スマートフォンなどの普及に伴う行動の変化に対応し、ユーザー起点でサービスを設計することである。
例えば日本のFinTechの代名詞ともいえる家計簿アプリやロボアドバイザーなどは、AIやクラウド、APIを活用しつつ、必要なサービスだけに絞った直感的で使いやすいUI・UXで利用者を惹きつけている。このようなアプローチにより、金融サービス利用層の拡大および利用頻度の向上など、市場全体を拡大し、活性化することがFinTechの本質と言える。
keyword 02 電子決済等代行業者(銀行法改正)
今年3月に国会へ提出された銀行法改正案において新たに定められた制度になる。消費者からの依頼により、銀行口座に直接アクセスすることができる事業者のことだ。
主に利用者の「口座情報を参照する」だけのサービスと、実際に「口座からお金を移す指示」を行うサービスに分類される。前者の代表例として、口座残高や利用明細を取得する家計簿アプリがあり、後者の例としては貯金用の口座に自分のお金を移す貯金アプリなどがある。
この制度によって、FinTech事業者は「電子決済等代行業者」として登録し、金融庁の定めたルールに対応する必要が生まれた。消費者が安心してFinTechサービスを利用することができ、銀行業界もFinTech事業者とのAPI接続への努力義務が定められているなど、イノベーション促進に向けた環境が整備された。
今後は、多くの企業が「電子決済等代行業者」となり、消費者が望むさまざまなサービスを産んでいくことが期待されている。
keyword 03 銀行API
前述の「電子決済等代行業者」が、ユーザーの指示によって、銀行の口座情報を参照し、振込の指示を連携する技術のひとつとして、API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)がある。
これは、別のプログラムが提供する機能や保有するデータを、自分のプログラムで呼び出し、あたかもひとつのプログラムのように連動させることができる技術のことである。この技術はIT業界では当たり前の技術だが、金融での活用が始まったのが、最近であるために脚光を浴びている。
これまでもAPIを用いずに実現してきたサービスもあるが、銀行がAPIを開放することによって、FinTech事業者は低コストかつスピーディーに銀行と接続することが可能になる。銀行にとっても、どのFinTech事業者にどのようなアクセス権限を付与するかの管理が容易になるメリットがある。また、利用者にとっては ...