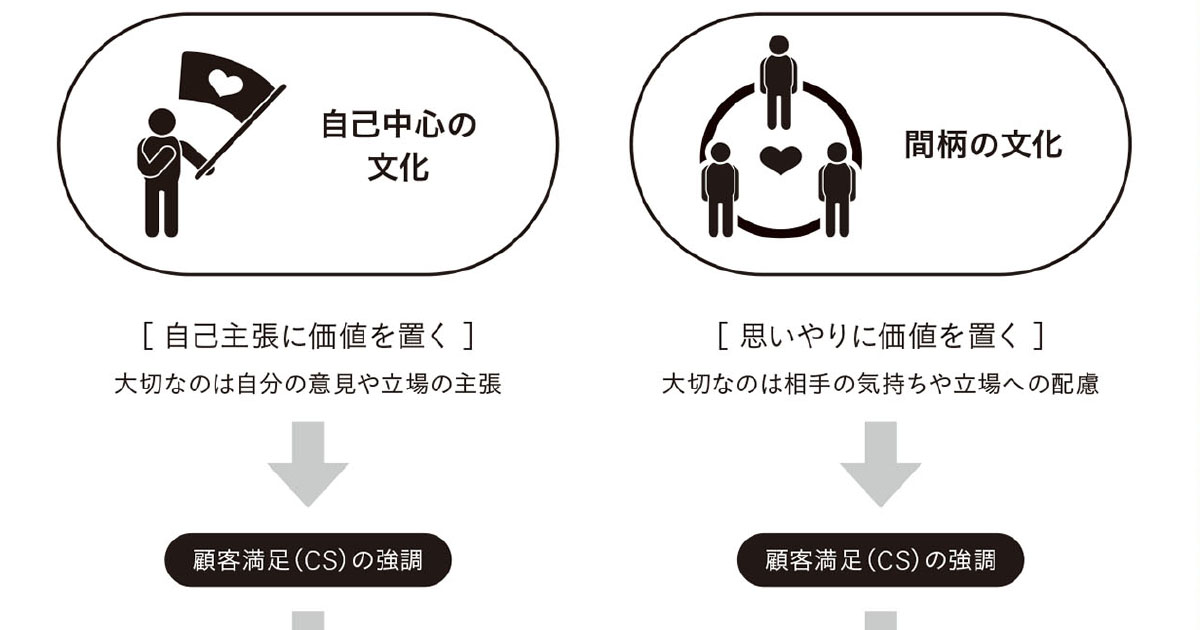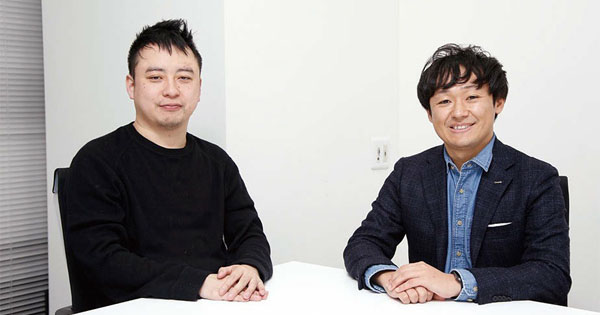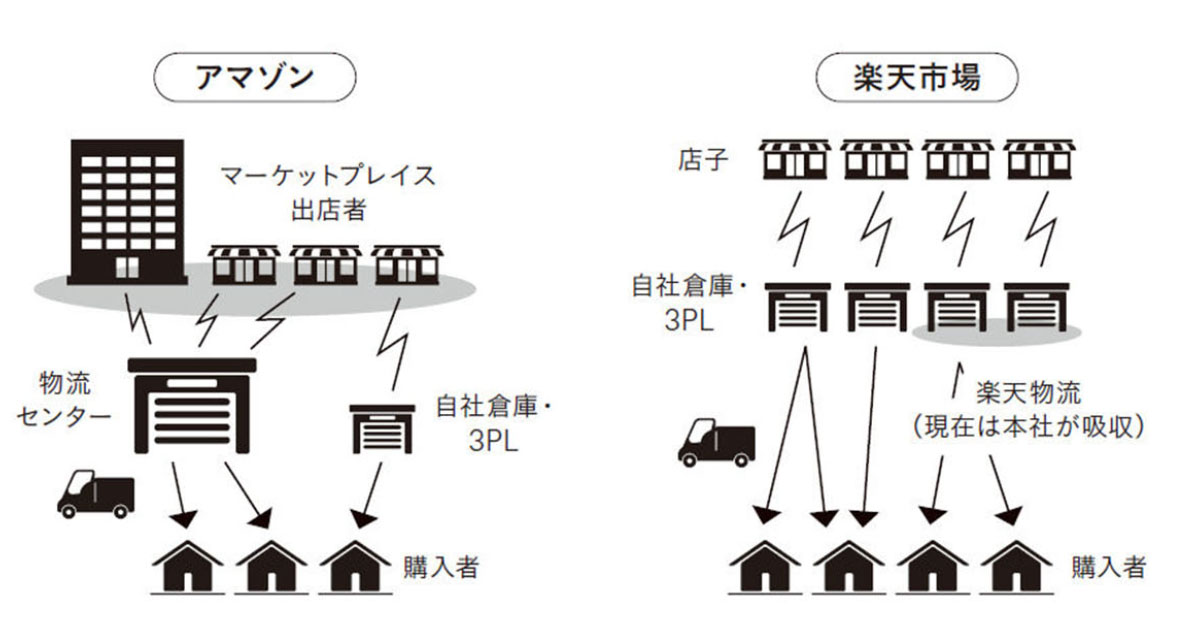2017年のCESでひときわ存在感を発揮していたのがアマゾンだ。アマゾンのような巨大プラットフォーマーが浸透している環境の中で、企業のマーケティングはどう考えるべきか。電通 森直樹氏のCESレポートから、そのヒントを探る。

CES2017の主役はAmazon Alexaだった?
「今年のCESはどうだった?」、参加した多くの人はこの問いに「Amazon Alexaがすごい」、こう答えるに違いない。CESに長く参加している筆者も、多くの方に「今年のCESの特徴は何だ?」と質問されるが、Amazon Alexaの存在感の高さを一番に挙げている。
CESは、LVCC(ラスベガス・コンベンション・センター)を中心にラスベガスの街全体が家電・自動車・ヘルスケアから新興技術に至るまで世界最大規模のテクノロジー発信の場だ。その規模は、幕張メッセで行われる国内最大規模のテクノロジー関連のコンベンション「シーテック」の数倍にものぼる。
そして、これからの大きな方向性としてIoTによる新しいライフスタイルやそれらを支える新商品や新興技術に、展示もしくは、数百以上あるセミナーで触れることができる。そこで発信される領域は大きく3つに分けられるのではないだろうか。
1つは、4K有機ELディスプレイやテレビなどの映像関連、冷蔵庫や洗濯機などの白物家電を中心に、それらがネットに接続されたスマートホーム。2つ目は、自動運転や常時インターネット接続された新しい自動車の世界観としてのコネクテッドカー。3つ目は、さまざまなスタートアップや新興プレイヤーが発信する、ヘルスケア、ウェルネス、フィットネス、住宅、新興IoT関連だ。
驚くべきことに、このすべてのエリアでAmazon Alexaが存在感を示していたのである。例えば、最も大きな会場であるLVCCの入り口は毎年LGが出展している。このLGの出展で、分かりやすく最も存在感があるのが、多くの4K有機ELを配置した映像展示だ。
しかし今年に限って言えば、映像展示と同等以上のスペースを使い家庭用ロボットやネットに接続され大きな液晶が装着された冷蔵庫や洗濯機がAlexaと連携する未来についての"コンセプト映像やプレゼンテーション"が行われていた。
そして、家電展示の隣りにはコネクテッドカーを中心とした自動車メーカーが大規模に展示しているエリアとなる。トヨタ、ホンダ、フォード、フォルクスワーゲン、メルセデス…世界中の自動車メーカーが、自動車のコネクティビティや未来の姿について発信をしている。そこにも、Amazon Alexaの存在感があった。
フォードやフォルクスワーゲンは、Amazon Alexaと連携して、音声対話により家と車がシームレスにつながる世界を発信している。フォードのテレマティクス(車載ディスプレイ)には、Alexaが搭載され、自動車から音声対話によってネットに接続された家電をコントロールする未来を展示で示していた。同社は、自社のテレマティクスサービス「SYNC 3」にAlexaの組み込みを予定しているという。すぐに、数百万台の自動車にAlexaが搭載されることになるだろう。
さらに、別会場ではHoneywell社やWhirlpoolといった、欧米の大手家電メーカーがこぞって、Alexaを中心としたスマートホームのコンセプト展示をしていたり、スタートアップのIoTガジェットがAlexaと連携展示を行っていたり、どこに言ってもAlexaが存在感を示していたのである。アマゾン自体はCESで展示を行っていないが、欧米の家電、自動車、IoT系のあらゆる企業がAlexaとの連携をイノベーティブな試みとして発信していたのであるから驚きだ。
音声対話という新しいUIが実用段階に
さて、これほどまでに今年のCESで存在感を見せた「Amazon Alexa」とは一体何なのかを簡単に解説したいと思う。Alexaはアマゾンによって開発された音声認識技術によるパーソナルアシスタントである。
「Amazon Echo」や最近発売されたEchoよりもミニサイズの「Amazon Echo Dot」やポータブルな「Amazon Tap」、「Amazon Fire TV」などに搭載されており、アマゾンが提供する開発ツールを活用すると、Amazon Echoなどを通じて、ネットにつながる家電やガジェットなどIoT機器を音声で操作できるようになる。
昨年、音声認識をするAmazon EchoやTap、Dotが米国市場で大人気となり品薄状態になったニュースは、読者の皆さんの記憶にも新しいのではないだろうか。すでに家庭内に浸透し始めているAmazon Echoシリーズを使って、音声対話による新しいユーザー体験を提供する開発環境をアマゾンは用意しているのだ。それがAmazon Alexaなのである。
音声対話技術は、決して新しい試みではない。日本でも10年以上前からカーナビなどに音声認識によるUIが導入されているし、NTTドコモは、「しゃべってコンシェル」という音声アシスタンス機能を以前から提供している。音声対話自体は、多く試みられてきた技術なのである。
しかし、なかなか普及してこなかったのは、音声認識精度の問題など、技術的なハードルが、他のインタフェース機能と比較して音声が優位に立つことが難しかったからではないだろうか。しかし、機械学習など新しいテクノロジーが音声認識や音声合成の進歩を促し、実用段階に入ってきたのではないだろうか。
CESを体験した筆者は、Amazon Alexaは、音声対話機能としてコネクテッドホームの中心になる可能性を秘めていると感じている。そして、米国では、日本以上に音声対話の取り組みが盛んであり、その片鱗をAT&Tの取り組みから感じ取っていた。筆者は、CESに加えて米国通信企業の雄であるAT&Tの開発者会議に毎年参加しているのだが、数年前からAT&Tの主要開発テーマのひとつが音声対話であった。
彼らは、ファウンドリーというラボを通じて、コネクテッドカーやコネクテッドホーム分野に多くの投資を行っている。これらの分野に必要な中核技術として、音声対話の技術開発とAPIの公開を積極的に行っているのである。
Amazon Alexa以外だと、グーグルも「Google Assistant」が搭載された「Google Home」を提供している。アップルも「Siri」を通じた音声対話の活用を積極的に展開している。今後、音声対話が、プロダクト、店舗、サービスなどフィジカルな体験と利用者をつなげる ...