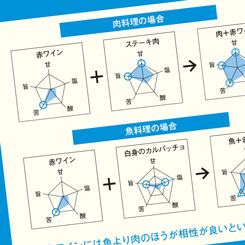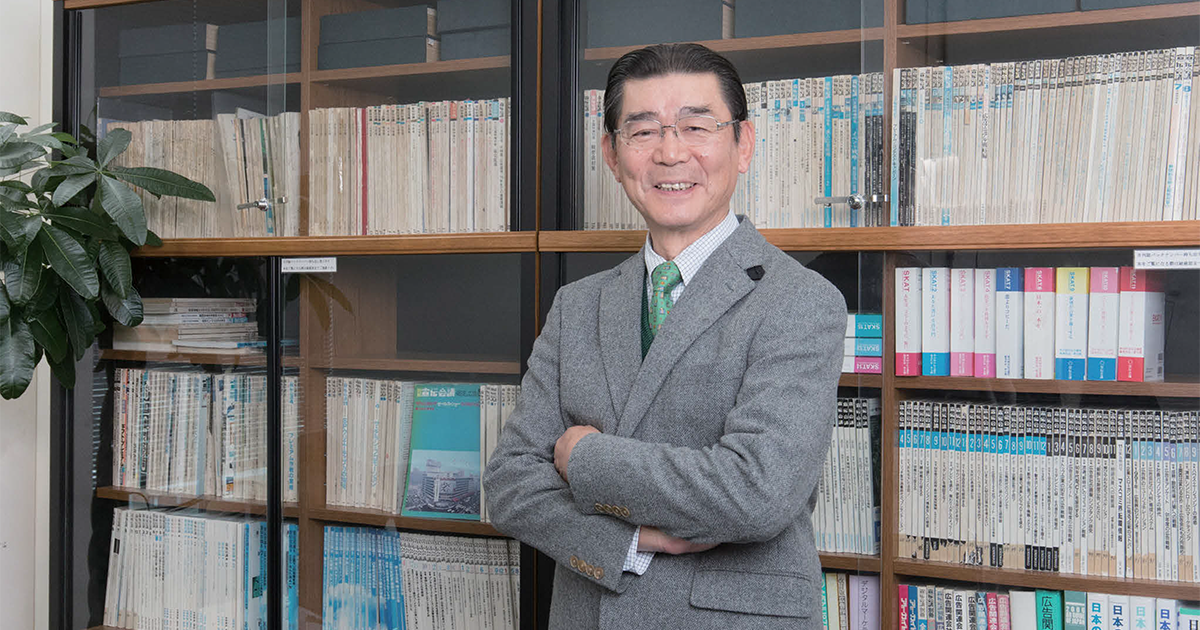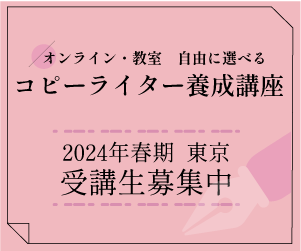食品のおいしさを科学的に解明することは可能だろうか。食品・栄養学をテーマに研究を行う伏木 亨教授は、「現代人は食べ物のおいしさを五感で感じずに、脳で処理できる情報に頼りすぎているところがある」と語る。

伏木 亨 氏(ふしき・とおる)
1994年より京都大学農学研究科食品生物科学専攻教授。2015年より龍谷大学農学部(新設)食品栄養学科教授、龍谷大学食と農の総合研究所付属食の嗜好研究センター長を併任。専門は食品・栄養化学。現在の研究テーマは、油脂やダシのおいしさのメカニズムの解明、おいしさの客観的評価手法の開発研究。著書に、『味覚と嗜好のサイエンス』『人間は脳で食べている』など。
“おいしさ”につながる4つの要素
「蓼食う虫も好きずき」ということわざがあるように、食べ物の好みは人それぞれで、これまで、おいしさを科学的に解明することは難しいと考えられてきました。
しかし、食品・栄養学の立場から、長年「おいしさ研究」を模索するなかで、おいしさとは食べ物そのものの属性ではなく、人間の脳のなかにある一定の快感や興奮からなり、脳の信号伝達の特殊性によるところが大きいことが分かってきました。おいしさを知ることは、脳の科学に近かったわけです。そこで、人間の食行動から、ある一定のルールのようなものを見出し、大きく4つの構成要素に分類しました。
1つ目は「生理的なおいしさ」です。喉が渇けば、まず冷たい水が飲みたい。寒い冬は栄養価のある熱い鍋料理。空腹ならすぐにエネルギーになりそうな揚げたてのコロッケが最高にうまい。つまり、人間の生理状態に対して欠乏している特定の栄養素や物質をおいしいと感じます。
2つ目は、「やみつきを誘発するおいしさ」です。例えば、チョコレートやケーキ類、評判のラーメン、B級グルメなど現代社会に蔓延するおいしいものの共通項を調べると、人間は脂油、甘味、アミノ酸などのダシの旨みを無条件に好むことが判明しました。旨みの成分とは、アミノ酸・核酸を豊富に含むタンパク質。いわゆる脂質、糖質、タンパク質を示す人間の生命維持に必要な3大栄養素で、人間と動物に共通する本能的な味だと理解できます。
ある実験で、マウスの前足や体にレバーが触れると、窓が開いてリッチな油脂が舐められるようにし、そのあとは2回、3回と油脂を舐めるまでに押すレバーの数を増やすようにプログラムしました。すると、最初は見向きもしないのにやがて高カロリーの油脂に執着するあまり、何十回・何百回も面倒なレバーを押す代償を払ってまで舐め続けたという結果が出ました。こうして苦労して得た油脂が口に入ると、おいしさの快感が脳を駆け巡る。要するに、やみつきのおいしさとは、嗜好性食品が圧倒的に多く、脳を興奮させて刺激する「快楽的なおいしさ」ともいえます。
情報依存が加速
人間も動物も、口に入れた経験のない食べ物は警戒し …