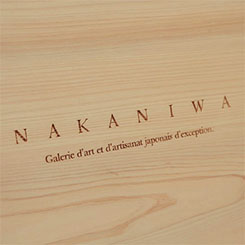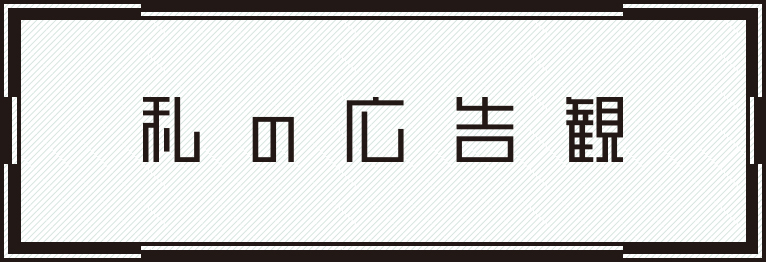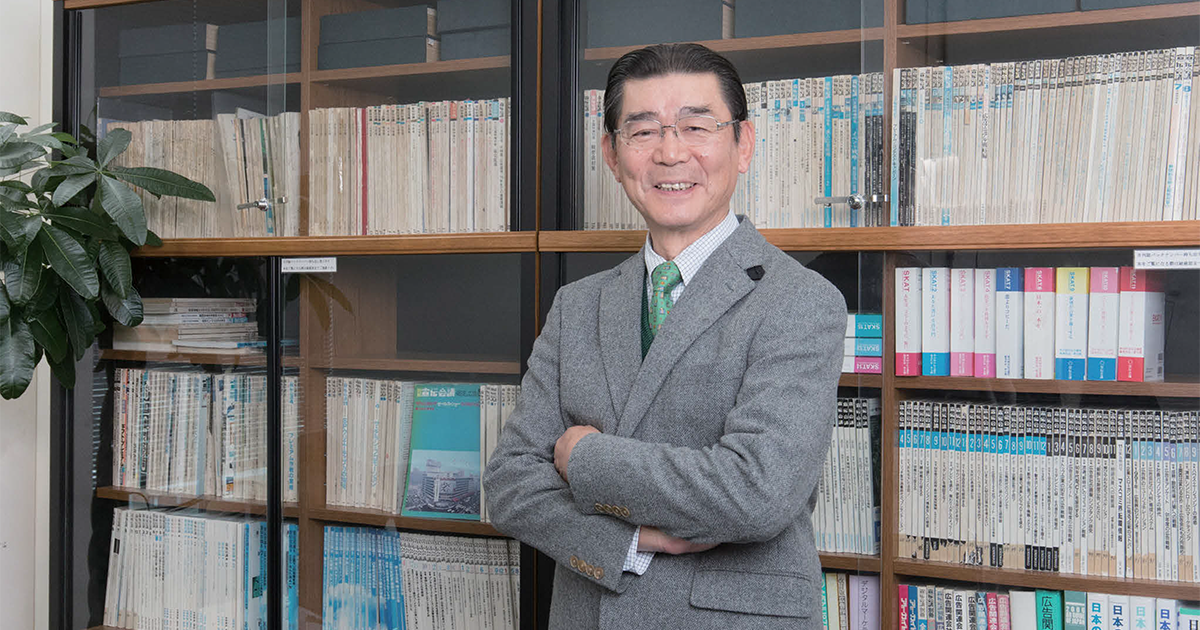日本の伝統工芸品は、品質では一級品、だが時代に合わせた商品開発力やマーケットの開拓力が足りないとこれまで言われてきた。だが、そんな定説を打ち破る、海外マーケットで快進撃を続ける地域メーカーが次々と登場している。既にある商品をそのままPRするだけでなく、進出先のマーケットを分析して現地市場に好まれる商品を新開発する、現地に受け入れられるための戦略を考えるなど、実地にマーケティングを行い、成果を挙げた企業の取り組みを追う。
日本の伝統的工芸品産業の振興を目的に活動する伝統的工芸品産業振興協会が、今年初めてヨーロッパの見本市に単独ブースを出展した。そこにはどんなマーケティングがあったのか、また、日本の伝統的工芸品はどのように受け入れられたのか。この出展を中心になってプロデュースした、デザインディレクターの桐山登士樹氏がレポートする。

左がフランクフルトで開催された「アンビエンテ」(デザイン:トラフ建築設計事務所)、右がパリの「メゾン・エ・オブジェ」(同:ZITOMORI)の出展ブース。
国家戦略としての海外マーケット進出
今年2月、フランクフルトメッセで開催された世界最大の消費材見本市「アンビエンテ」に、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会(略称:伝産協)は初めて単独ブースを出展した。日本の産地で脈々と受け継がれてきた伝統的な技術と技法による工芸品が、海外マーケットの開拓に向けて世界的なデビューを果たした。
経済産業大臣が指定する伝統的工芸品は、全国に218品目(2013年12月現在)ある。しかし、産地の抱える課題は多い。後継者不足=事業承継問題、技の伝承が量産化の困難さの要因にもなり、安価な海外類似品の台頭によるマーケットの混乱、少子高齢化による内需の低迷、そして産地問屋に依存する流通体制の見直しなど、課題は山積している。これらの課題解決なくして、地域産業の再生はないとも言われている。
こうした中、伝産協は経済産業省伝統的工芸品産業室との連携により、フランクフルト、パリ、ミラノでの欧州の見本市を中心にリサーチを開始し、海外マーケットへの進出を戦略事業の一つとした。伝産協は、2月の「アンビエンテ」に続き、今年で20年目となるインテリア&デザインの国際見本市「メゾン・エ・オブジェ パリ」の9月展に出展。主催者のSAFIは出展者をホール1からホール8に振り分け…