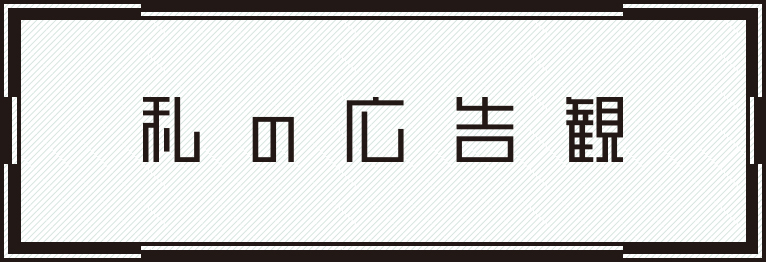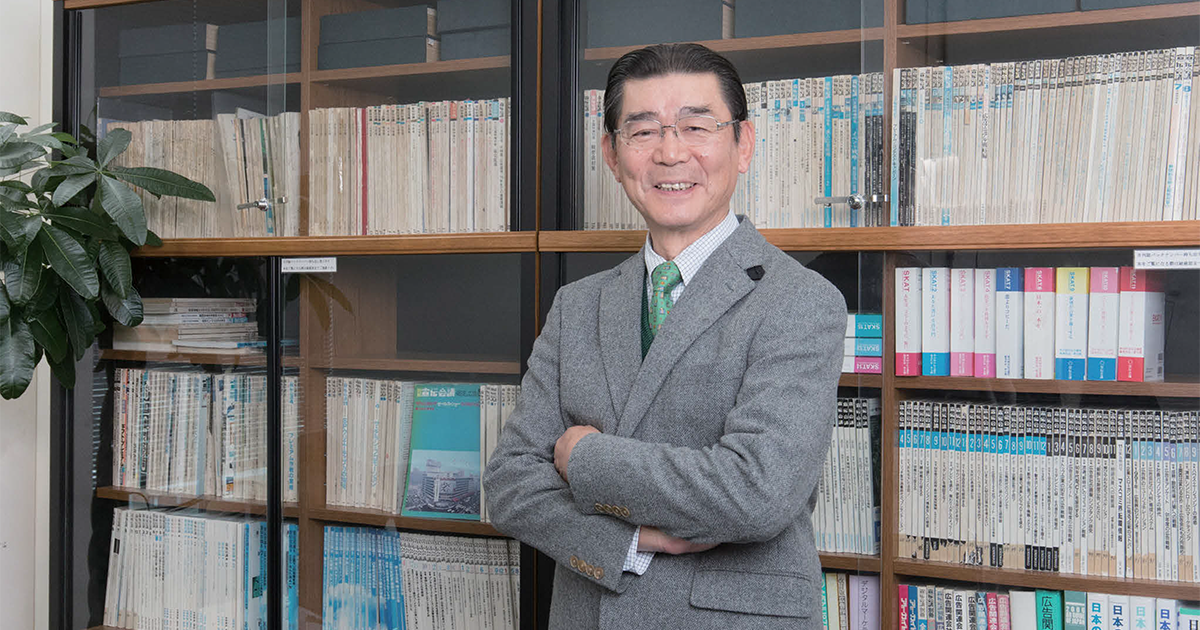日本ではまだなじみが少ないが、欧米で市場拡大している動画ジャンルのひとつに「解説動画」がある。営業や社内情報伝達、教育用途などに活用される数分の動画が一般的だ。世界9カ国に展開する動画クリエイティブ会社simpleshowに、海外での解説動画の活用と今後の日本での展望を聞く。

ベルリン航空 搭乗手続き 説明動画
空港のカウンターと機内で放映。様々な言語を使う空港利用者がターゲットのため、極力言葉は使わずにピクトグラムで説明する。
http://simpleshow.com/jp/use-cases/airberlin-boarding-processes/
文字中心の書類が動画に置き換わっていく
simpleshowは2008年にドイツで生まれた、「解説動画」に特化したクリエイティブ会社。「どんな複雑な製品や情報も、3分間で分かりやすく伝える」をコンセプトに、世界中のあらゆる事柄を動画で解説することをミッションとしている。シンプルなテキストとイラストを使った表現が特徴で、今年1月、日本にも支社を立ち上げた。
「海外で解説動画が普及した背景は、ブロードバンドの普及やデバイスの進化など、環境的な変化が大きいと考えています。動画が手軽に見られるようになったことで、これまでパワーポイントやワードで文字中心に作られてきた資料が動画に置き換わってきています」とsimpleshow Japan 代表取締役 吉田哲氏は話す。
同社の解説動画の用途は、マーケティング、営業・販促、広報、社内情報伝達、教育・学習と幅広く、扱う案件で一番多いのは社内情報伝達のための動画だという。社内の情報伝達と言うと、社内LANにPDFやパワーポイントをアップする例が多いが、欧米ではこうした書類に代わって解説動画を使う企業がここ数年急速に増えている。
特に近年では経済活動がグローバルになり、世界中の従業員に同じマニュアルを理解してもらう必要性が重要度を増している。「特に高度な機械や薬などを扱う企業では、ここだけは絶対にタブーだから守ってもらわないといけないといった、外せないポイントがあります。忙しい人たちに書類を見てよと言ってもなかなか難しい。だから短い時間で要点だけ理解してもらいたい、といったケースで重宝されています」。
成熟した市場では、複雑で難解になったサービスや商品の解説というニーズがあり、逆にインドネシアやインドなど、識字率があまり高くない地域では、教育のニーズが高い。日本では今のところ、最も引き合いがあるのは営業・販促分野で、テレビ局が広告会社向けに媒体資料を動画で制作した例などがある。営業担当者が、商談のときに手元のP Cやタブレット端末で見せたり、説明会での上映に使われている。まず動画で要点・骨組みを理解してもらい、そこから対面での詳しい説明に入る。1本動画を持つことで、優秀な営業担当者を雇うのと同様の効果が期待できるという。
成功体験を共有し共感を生む
同社にはいくつかのストーリーの「型」があるが、最もよく使われるのは ...