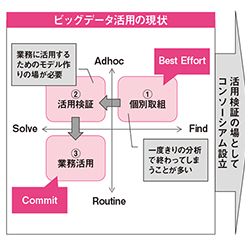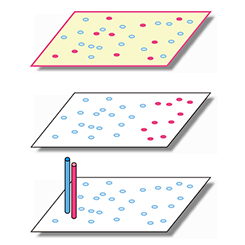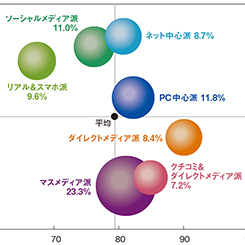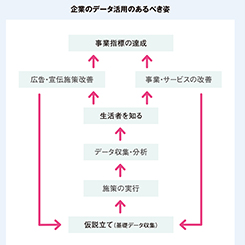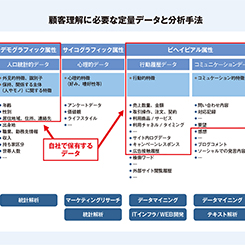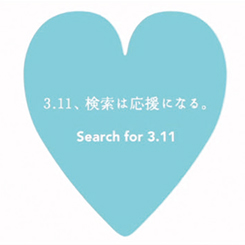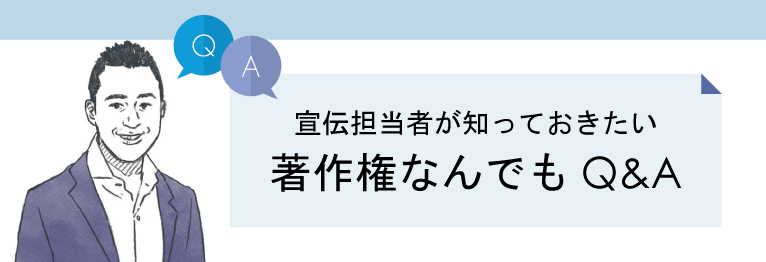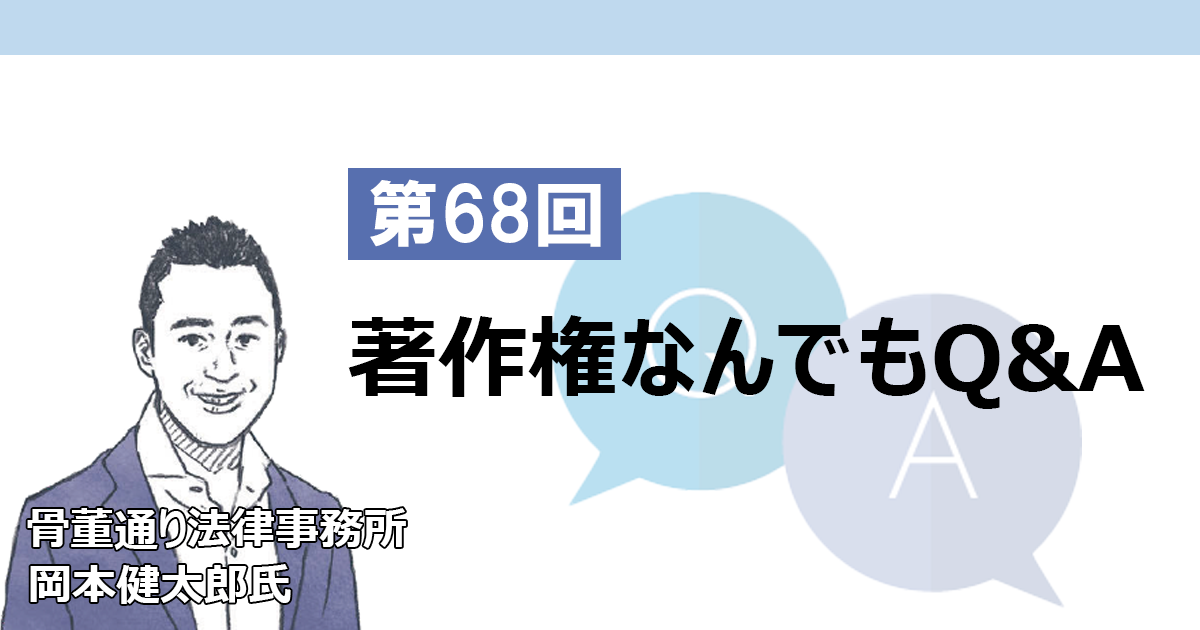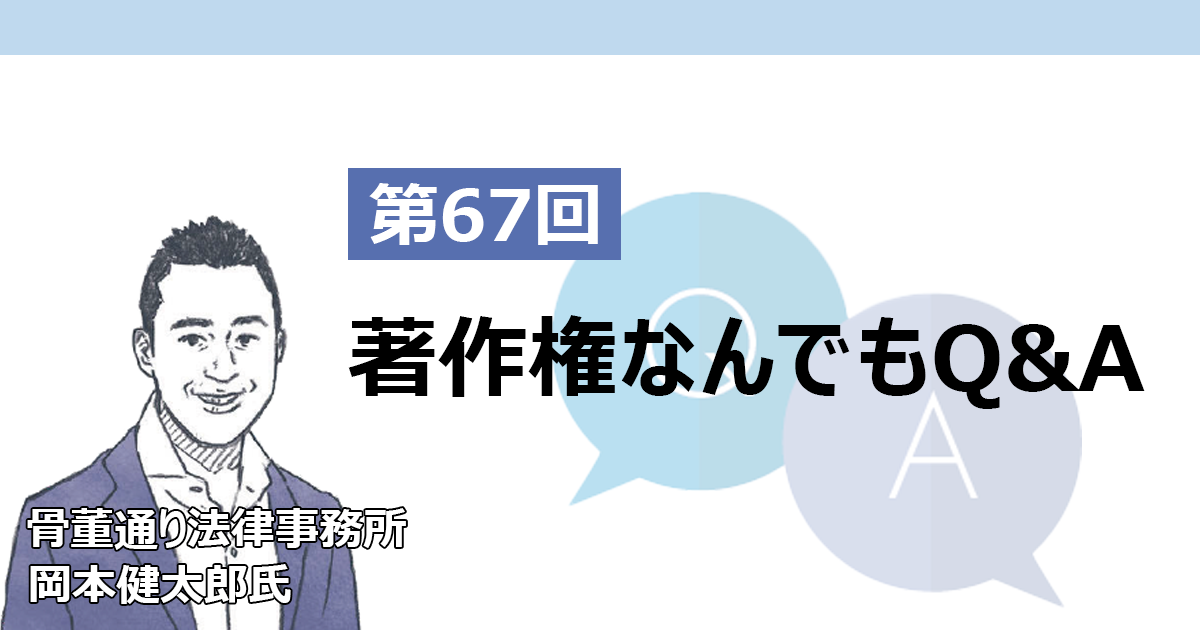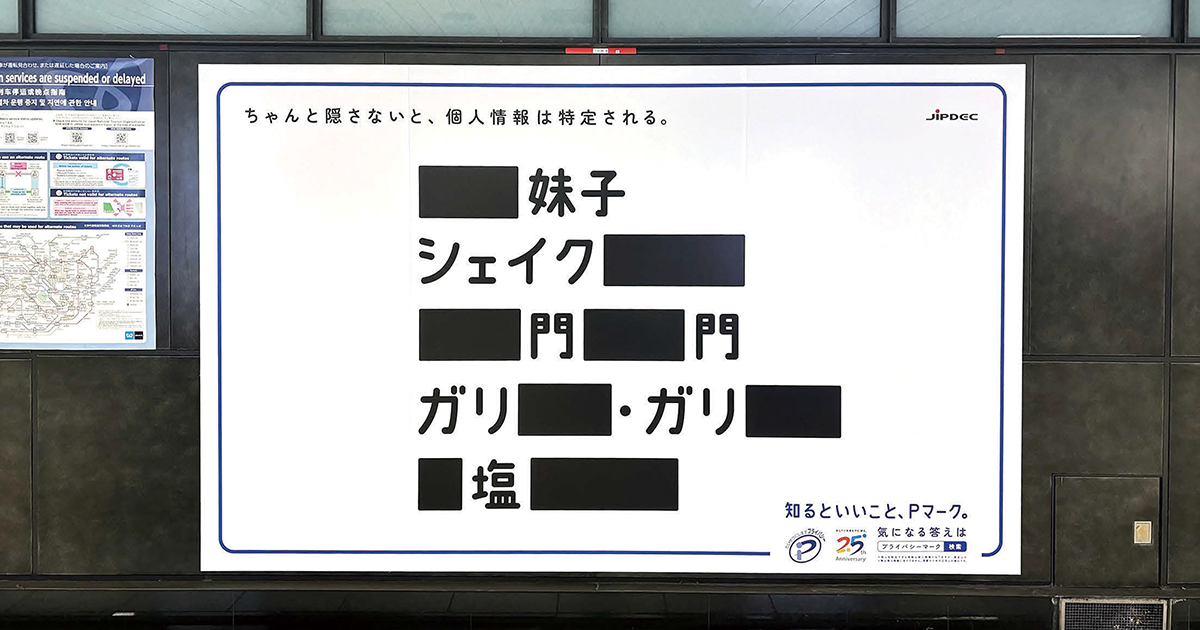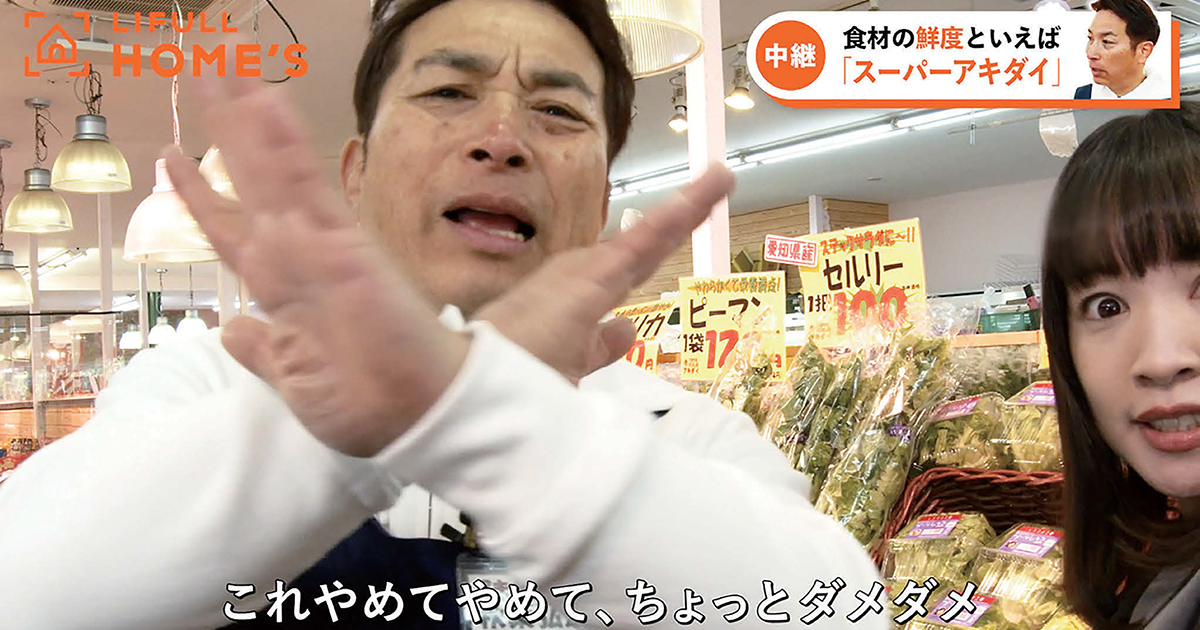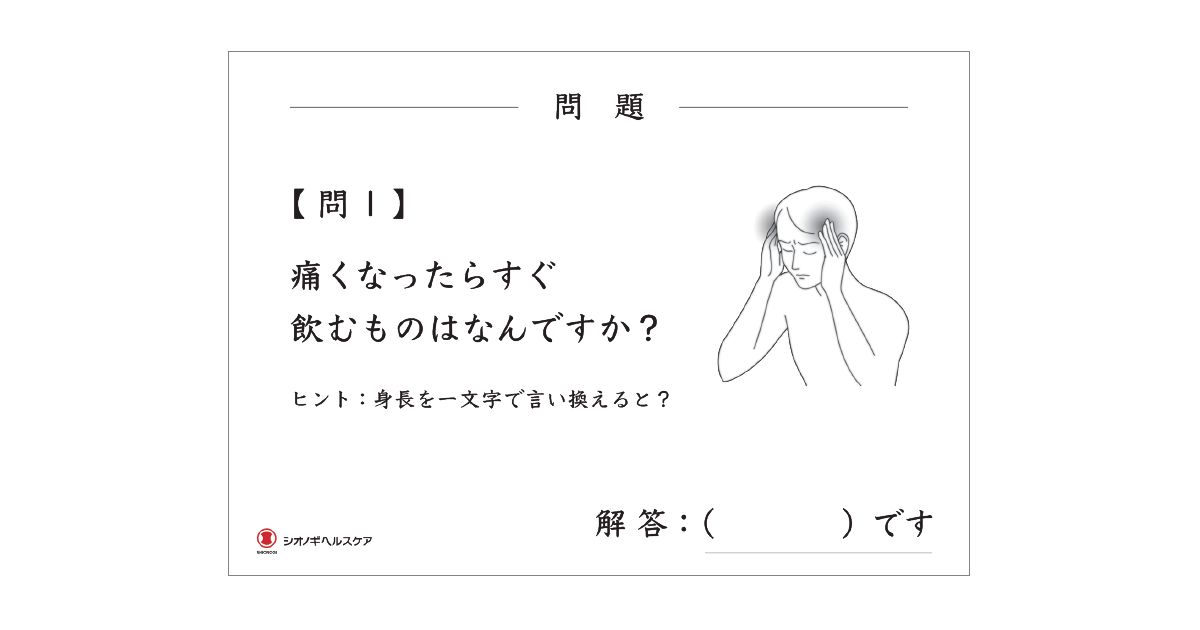アイルトン・セナの走りを走行データから再現した「Sound of Honda / Ayrton Senna 1989」など、電通 クリエーティブ・テクノロジストの菅野薫氏は、データを利用した新しい表現を次々と生み出してきた。データをエモーショナルに解釈し、新しい表現やストーリーを生み出すための発想を聞いた。

菅野薫氏(すがの・かおる)
1977年生まれ。2002年電通入社。データ解析技術の研究開発業務、国内外のクライアントの広告キャンペーン企画、
商品サービス開発などに従事。2014年カンヌライオンズ サイバー部門審査員を務める。
ブランドと人をエモーショナルに結ぶデータ
鈴鹿サーキットをLEDによる光が駆け抜け、設置されたスピーカーからエンジン音が響き渡る。その場にあるのは光と音だけだが、まるでアイルトン・セナという人の存在がそこに立ち上がってくるようで、それが見る人の心を動かす。
セナが1989年のF1日本グランプリ予選で樹立した世界最速ラップを、当時の走行データをもとに、光と音でよみがえらせた「Sound of Honda / Ayrton Senna 1989」はじめ、菅野薫氏はデータを使ったこれまでにないクリエイティブ表現を次々と世に送り出してきた。なぜ、菅野氏にはそれができるのか。そのキャリアをひも解くと、元々、電通総研などの部署の研究職として、電通社内のマーケッターやストラテジスト向けの自然言語処理やデータ解析技術の研究やソフトフェア開発などに従事してきた。いわばデータを扱う“ど真ん中”で活動してきた人である。MIT media labと共同研究プロジェクトの「空気が読めるコンピュータをつくろう」プロジェクトを立ち上げたこともある。
今につながる転機の一つは、2011年の震災後にホンダのインターナビから得られる走行データを公開し、通行実績があった道路をビジュアライズした「CONNECTING LIFELINES」プロジェクトだった。インターナビのデータは、本来渋滞の発見や回避のために開発されたものだが、震災時には「通行の実績があった道の発見」という別の意味を持つことを見つけ、新たなサービスとして表現した。これが、データから新たなサービスや表現の可能性を創造する、「クリエーティブ・テクノロジスト」としてのその後の一連の仕事につながっている。
「自分からそういう立場に職種を変えたというより、クライアントからの要求があって今の場所にいると思っています」と菅野氏は言う。商品の持つテクニカルな魅力をちゃんと理解できる人に、表現を扱ってもらいたい。それが、当時ホンダが求めていたことだった。データサイエンティストとしてのキャリアがあり、MITでの経験なども通じてテクノロジーを使った新しいコミュニケーションを探る活動をしていた菅野氏に白羽の矢が立った。
「CONNECTING LIFELINES」は役立つ意味の発明だったが、「Sound of Honda / Ayrton Senna 1989」はより“表現”としての色彩が濃くなっている。「そのブランドらしいユーティリティを提供することで、データというものが人の役に立ち、ブランドを好きになる理由になるということを証明したのが『CONNECTING LIFE LINES』でした。セナのプロジェクトでは、もう一歩踏み込み、ブランドと人の間にエモーショナルな結びつきを作れるかにチャレンジしました。これまで広告クリエイティブが担ってきたことにデータで挑戦した企画なんです」。
データは無味乾燥じゃないロマンチックなもの
これまで、データはマーケティング活用のために ...