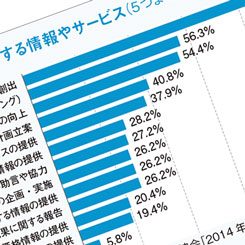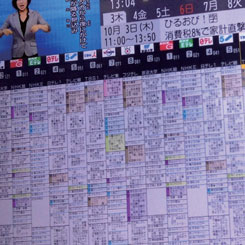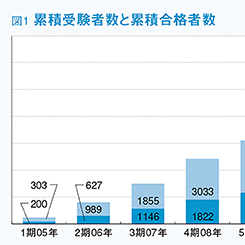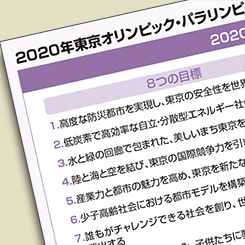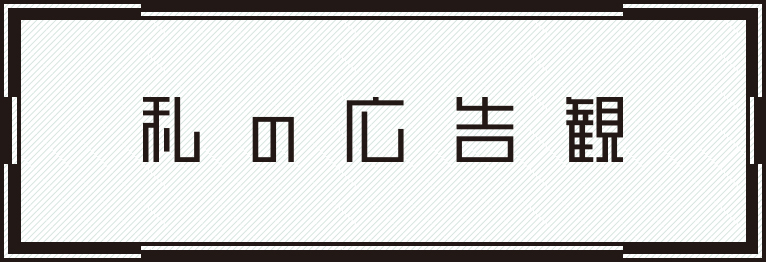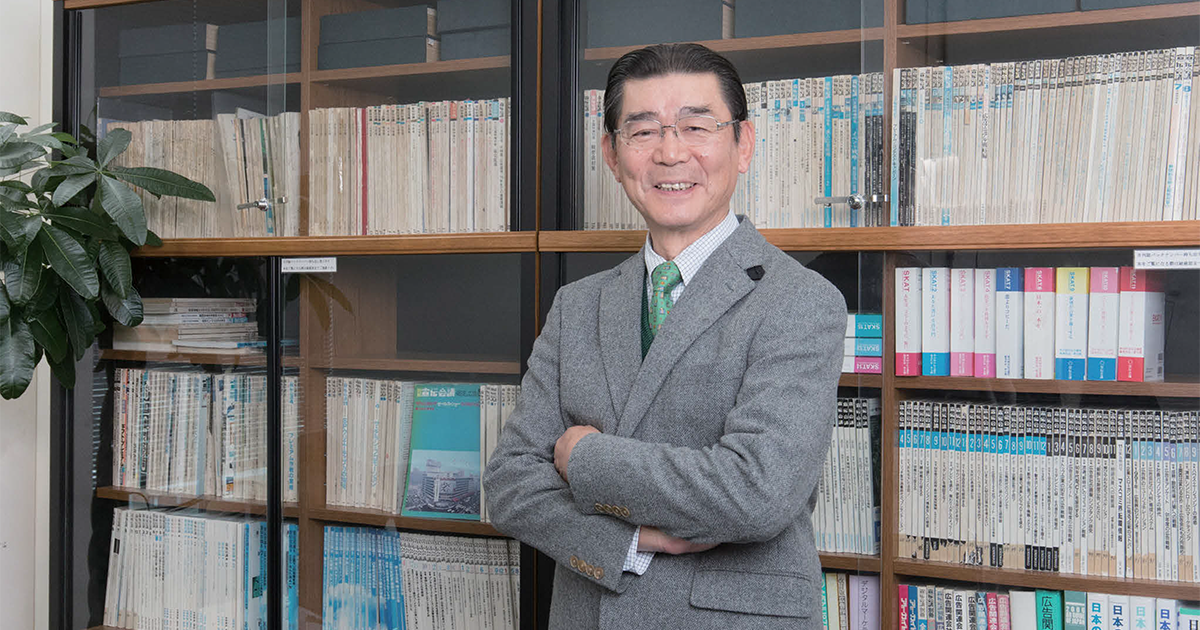放送に関する第三者機関「BPO(放送倫理・番組向上機構)」はこのほど、民放のバラエティ番組とドラマに対して、相次いで意見や考えを発表した。いずれも視聴者への配慮と表現の自由の兼ね合いに難しい課題を投げかけている。
“約束”反故に批判
BPO「放送倫理検証委員会」(川端和治委員長)は4月1日、フジテレビの人気バラエティ「ほこ×たて」で「重大な放送倫理違反があった」とする意見を発表した。
同番組は、「絶対に穴の開かない金属」と「絶対に穴を開けられるドリル」の対決など、“真剣勝負”を売り物とする対決型のバラエティ。問題となったのは、昨年10月に放送された「どんな物でも捕まえるスナイパーvs絶対に捕まえられないラジコン」のコーナーで、ラジコンを一定時間内に狙撃できるかを競った。勝負はボート、車、ヘリコプターの3種で行われたが、実際には、車の対決は行われておらず、編集作業で映像を作っていた。
検証委員会の意見は、テレビ番組は制作過程で「演出」が行われていることは「テレビの裏側」「お約束」との言い方で了解されていると説明。
「ほこ×たて」では制作者と出演者が協力して“真剣勝負”と呼び得る“虚構”を実現し、その成果を視聴者が楽しむ「二重の了解」が成立していたと指摘した。しかし、実際に行われていない対決を編集で作ったことは、制作者と出演者の「約束」に反し、“真剣勝負”を期待する視聴者との「約束」も反故にして信頼を失墜させたと批判。制作会社丸投げによる局内チェック体制の実効性低下、制作者や出演者間の合意形成の低下などを指摘している。
一方、BPO「放送と青少年に関する委員会」(青少年委員会=汐見稔幸委員長)は4月4日、日本テレビ「絶対に笑ってはいけない地球防衛軍24時!」に関して「委員会の考え」を公表。「視聴者、特に青少年がどう見るか、想像力を働かせてほしい」などと指摘した。
昨年末に放送された同番組は、「肛門に粉を詰めてオナラとともに顔に吹き付ける」「股間に向けてロケット花火を噴射」「中年男性のおむつ交換」などのシーンに不快感や嫌悪感を持ったと数多くの苦情が寄せられていた。
同委員会は日本テレビと意見交換を行い、同社から「プロの芸人の芸の範囲内」「安全面に配慮」「時間帯にも配慮した」と説明を受けたしている。そのうえで、「表現上の配慮」として、青少年や女性視聴者への配慮や想像力が不十分でなかったかと指摘。また「放送基準と放送の公共性」として、無料の地上波放送は有料放送や映画以上の配慮が求められると指摘。青少年委員会と放送局の率直な意見交換が必要だとした。
社会的波紋への配慮
青少年委員会は4月8日、“子どもが主人公のドラマ”に関する「委員長コメント」を発表した。「フィクションであるドラマは主題選びや効果的なドラマツルギー選択の判断が表現の自由として制作者に与えられ、そこにドラマの生命がある」として、差別的・暴力的表現や放送時間帯の問題を含め「良し悪しの判断には慎重であるべき」と強調。そのうえで、「社会的波紋への配慮は通常に増して行う必要があった」との考えを示している。
コメントは、具体的な番組名を伏せる形で出されたが、対象となったのは日本テレビが今年1~3月に放送した「明日、ママがいない」。同番組は、児童養護施設の子どもたちをペットショップの犬に例えるなど、傷つける描写があり、児童養護施設の関係者や里親、医師らが強く抗議、同番組のスポンサーがCMを見送るなどの波紋が広がっていた。
同委員会では、3月の会合で「フィクションといえども弱者への一定の配慮が必要」と「社会に問題を投げかけるドラマが作られなくなることへの危惧」の両論を踏まえ、「審議」の対象としないことを決定。委員長コメントにとどめることになった。
一方、同番組については、熊本県の慈恵病院が、BPO「放送と人権等権利に関する委員会」(人権委員会=三宅弘委員長)に対し、人権侵害として申し立てを行っているが、4月15日の会合では審議入りするかどうかの判断を見送っている。
文/明石庸司