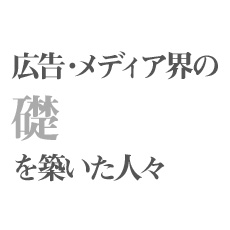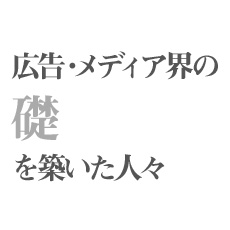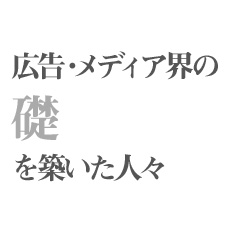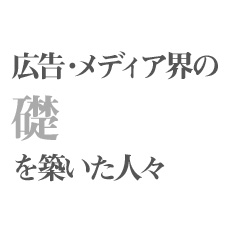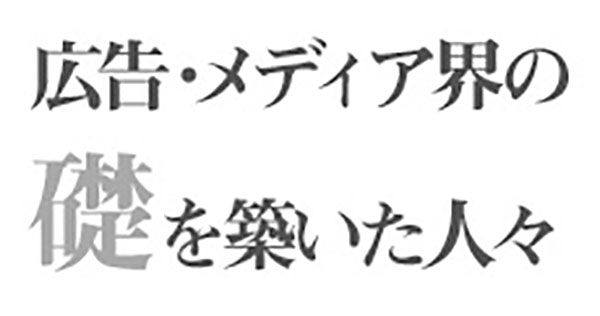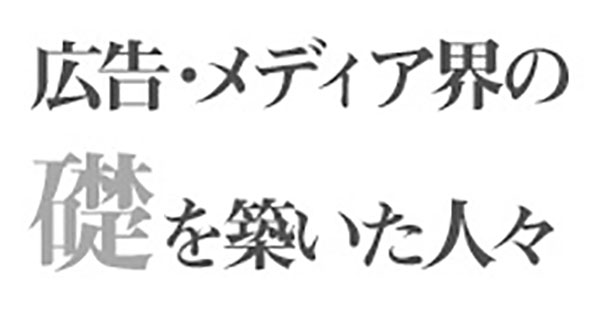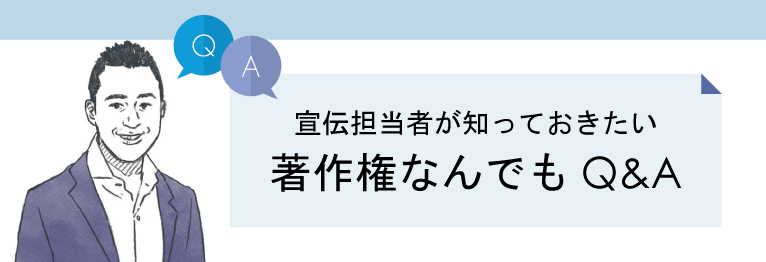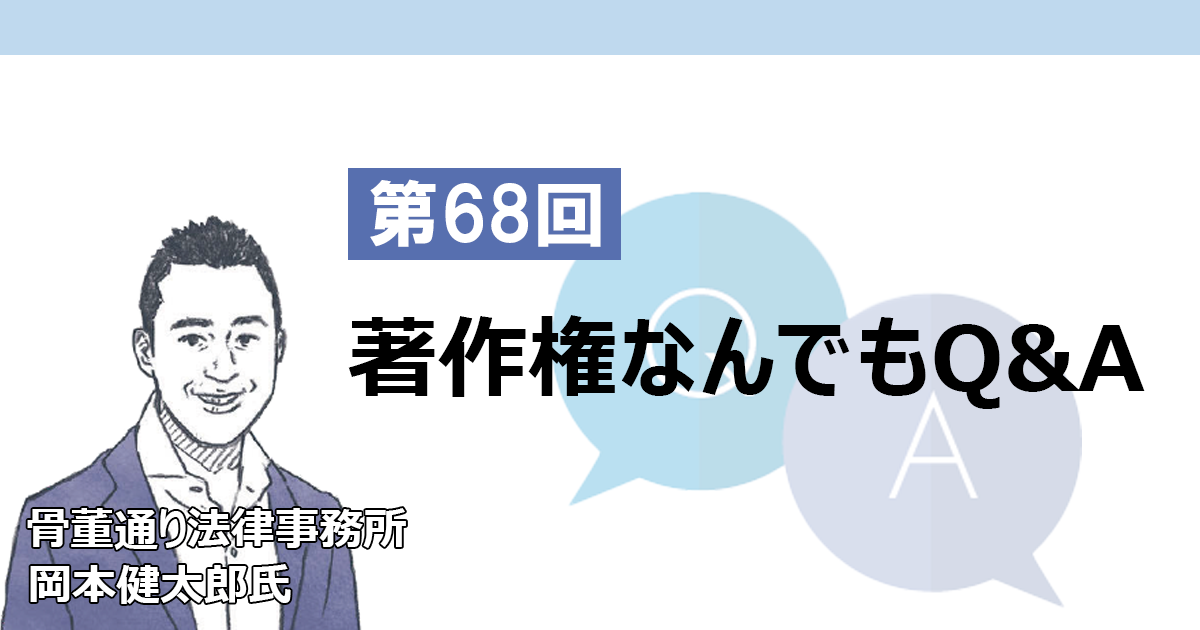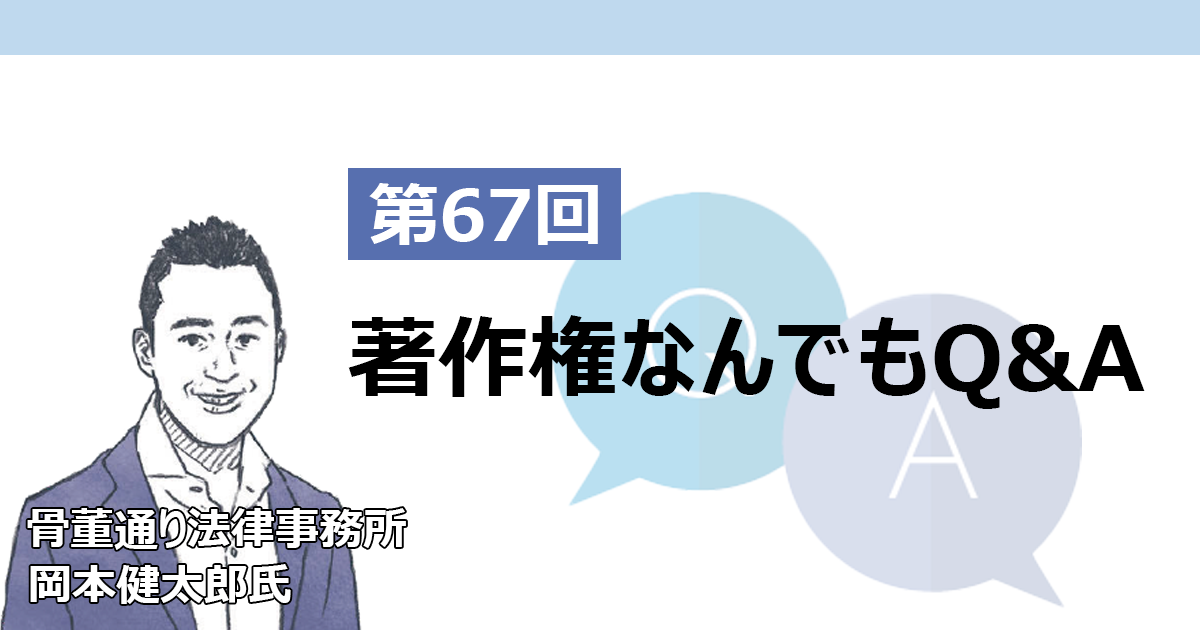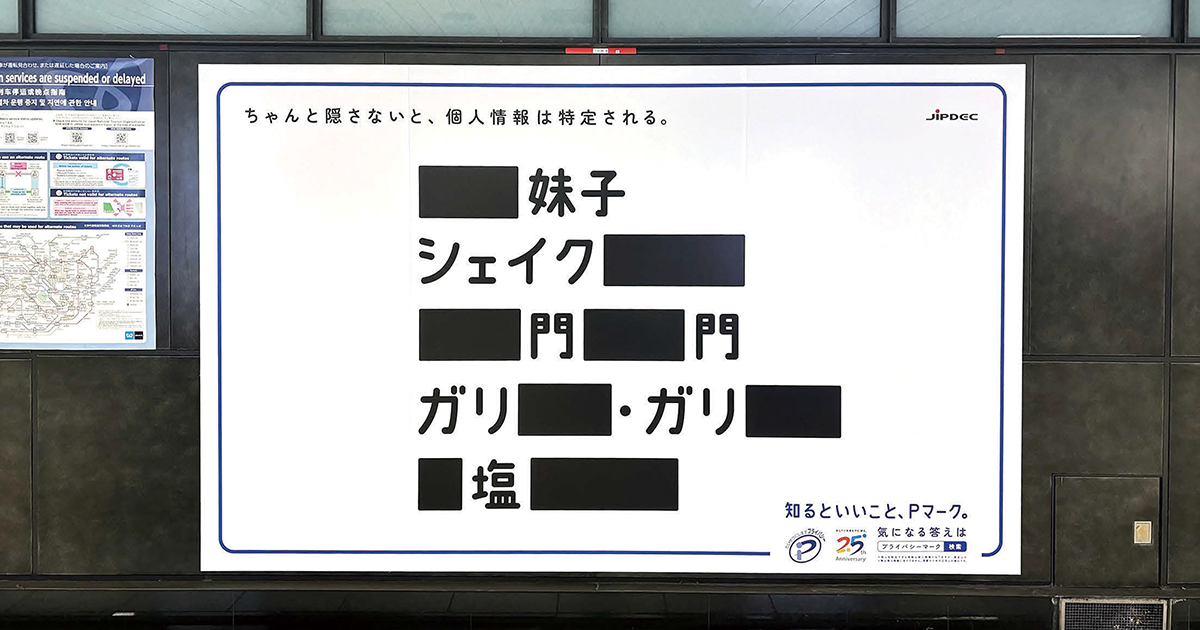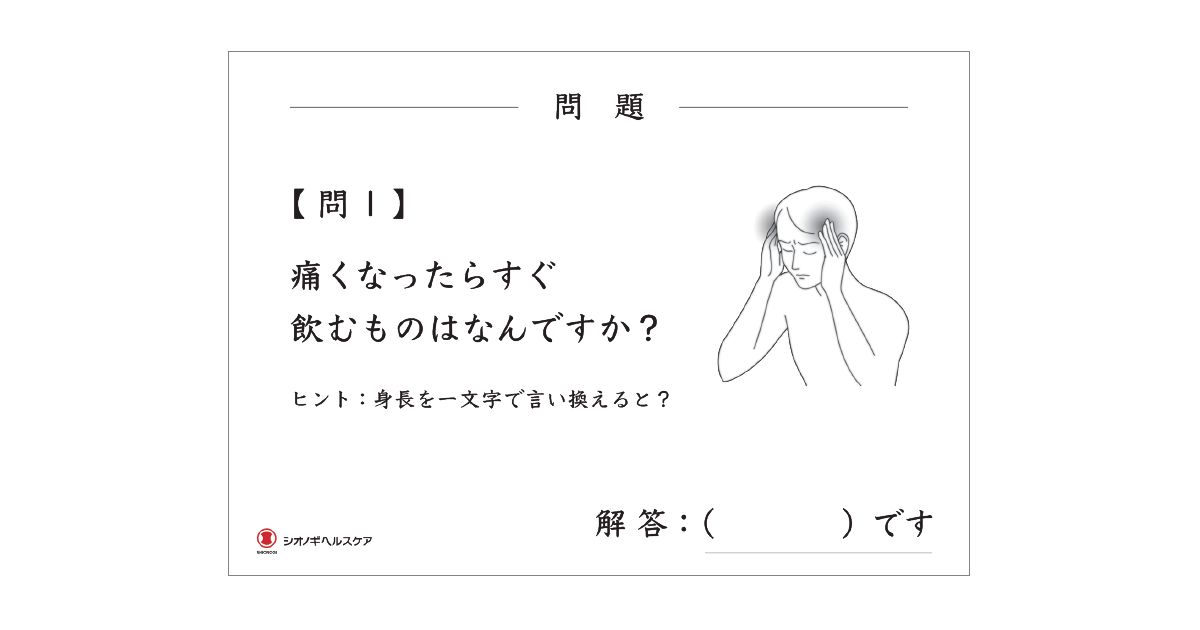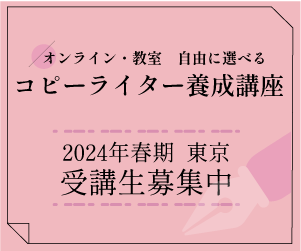広告費の削減や人々のマスメディア離れが言われはじめて久しいが、それでもなお今日の日本において広告・メディアの力はその強さを持ち続けている。その力は、先人たちから脈々と受け継がれてきた精神、そして技術を発展させることによって成り立っているにほかならない。先人たちの優れた功績を見つめ直し、原点に立ち返ることで、広告・メディア界の現在、そして今後を考える。
知的で「考えさせる」読み物
二葉亭四迷と夏目漱石は、ともに朝日新聞社の社員として当時の新興メディアである新聞に小説を書いた。明治・大正を代表する二人の作家の明治39年以降の主要な作品は、新聞に掲載された。二人が「言文一致体」といわれる、読みやすい現代的な文体を模索し、その確立に力を注いだのは、作品が新聞に掲載されるという条件と無関係ではない。
メディアが作品の表現スタイルをつくりだした。夏目漱石の小説は21世紀の今日でも、相変わらず若い人々に読み継がれているが、作品内容の普遍性と共に今に至っても古びない文体が大きな魅力となっている。
先行したのは、二葉亭四迷(本名・長谷川辰之助)(1864(元治1)年2月3日~1909(明治42)年5月10日)である。東京朝日新聞主筆・池辺三山の要請で初めて書いた新聞小説「其面影」第1回が掲載されたのは明治39(1906)年10月10日だった。
「弱弱とした秋の日は早や沈んで、夕映えばかり赤々と西の空を染めたある夕暮れ、九段坂をぶらぶら上がって行く洋服出立ちの二人連れがある。」という都会の情景ではじまり、「相場で儲けたという事で、当人は四十までにはきっと馬車に乗ってみせると力んでいるそうだ。とにかくえらい勢いである。」と、77回で終わる結末まで、現代の社会、人々、事件が生々しく描かれる。理想と現実のギャップ、現代人の苦悩と挫折が表現され、それまでの娯楽性豊かな時代物が主だった新聞小説とは違う、知的で、「考えさせる」読み物を提供した。それは読者である都会の勤め人たちの求めるものだったのかもしれない。
そもそも二葉亭四迷が明治37年3月4日大阪朝日新聞に入社したのは、「東亜経営問題の研究」のためだった。東京在住のまま「日露戦争勃発(明治37年2月)直後のロシアの新聞雑誌を閲読し読者が興味をもつような記事論説があればそれを訳して大阪朝日に載せる」のが任務であり、大阪に原稿を送ればいい、という好条件だったが、あまりにも彼の豊富すぎる知識と真面目すぎる戦局への関心のため、新聞記事として使える原稿が殆んどなかった。日露戦争も終り、社内で無用の存在になってゆく四迷の文学的才能を惜しみ、池辺三山が部下を通じて説得したときも目に涙を浮かべ、「僕は残念でたまらない、世間の奴らが僕を小説家にしてしまって他の事は少しも見てくれない。」と相手をにらんだという。漱石は四迷に出会った時の印象をこう記している。「文学者でもない、新聞社員でもない、また政客でも軍人でもない、あらゆる職業以外に厳然として存在する一種品位ある紳士...」。
後に四迷は「予が半生の懺悔」というエッセイでこう書いている。「これはひどいジレンマだ。実際的と理想的との衝突だ。で、そのジレンマを頭で解くことは出来ぬが、しかし一方、生活上の必要はますます迫って来るので、よんどころなくも『浮雲』をこしらえて金をとらなきゃならんこととなった。で、自分の理想から言えば不埒な不埒な人間となって、銭を取りは取ったが、どうも自分ながら情けない、愛想の尽きたくだらない人間だとつくづく自覚する。そこで苦悶の極、おのずから放った声が。くたばって仕舞え(二葉亭四迷)!」
この自己嫌悪に彼の失敗者としての認識があり、そこに彼の近代人的インテリジェンスがあった。
二葉亭四迷は不思議な人物である。20歳代前半の若さで明治20(1887)年~明治22年に刊行した「浮雲」第1編、第2編、第3編が文学界に大きな影響を与えた。同時代の日本文明を批評し、新旧思想の対立を描く斬新な小説が作家たちに衝撃をあたえた。しかし彼は「田舎の教師になろうと小説家になろうと、どのような道をたどろうと生きるに価する唯一の目的は真理の探究で」あり、「真理の味を嘗めもし人にも嘗めさせ」る小説を書く才能が自分にないと考えた。彼は官報局に出仕してそれで生活できることに心を決めて小説を放棄したのだ。「文学は男子一生の仕事にあらず」と考えるにいたった。そして内閣官報局雇員、東京外語ロシア語教授、日本貿易協会嘱託としてハルピンや北京に滞在するなどさまざまな仕事を経て、大阪朝日新聞東京出張員になったのだ。
その四迷に20年ぶりに小説を書かせたのが東京朝日新聞主筆・池辺三山である。池辺三山は、その前後に朝日新聞に入社することになった新進作家・夏目漱石と二葉亭四迷を二枚看板にして、「知的大衆」の興味にこたえる朝日の文芸欄を世の中にアピールしようと目論んだのである。
新聞小説で才能を開花
夏目漱石(1867(慶応3)年1月5日~1916(大正5)年12月9日)の初めての新聞小説「虞美人草」第1回が東京と大阪の朝日新聞に掲載されたのは1907(明治40)年6月23日だった(10月29日完結)。
「『ずいぶん遠いね。元来どこから登るのだ』と一人がハンケチで額を拭きながら立ち止まった。」と叡山を見上げる二人連れのなにげない会話から始まり、「ここでは喜劇ばかり流行る」と全体を振り返る重い言葉で終わる第127回の結末まで、波乱万丈の筋書の中に新と旧を対比させ日本の文明批評をこめている。これまでの自然主義文学とはまったく異質な虚構性の強いドラマを展開させた。