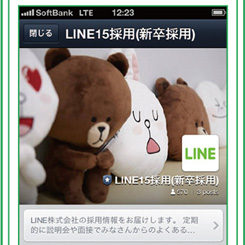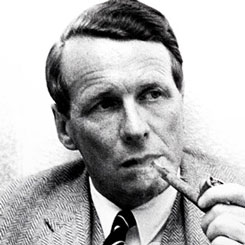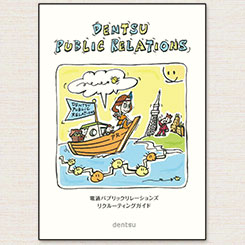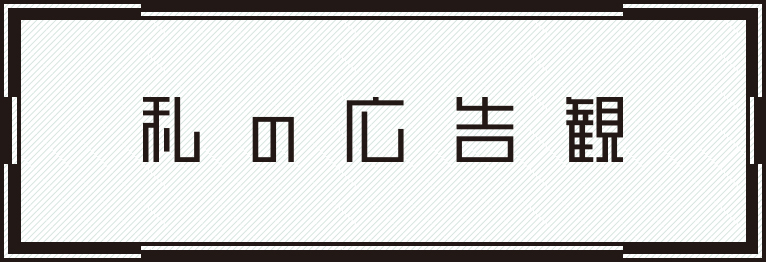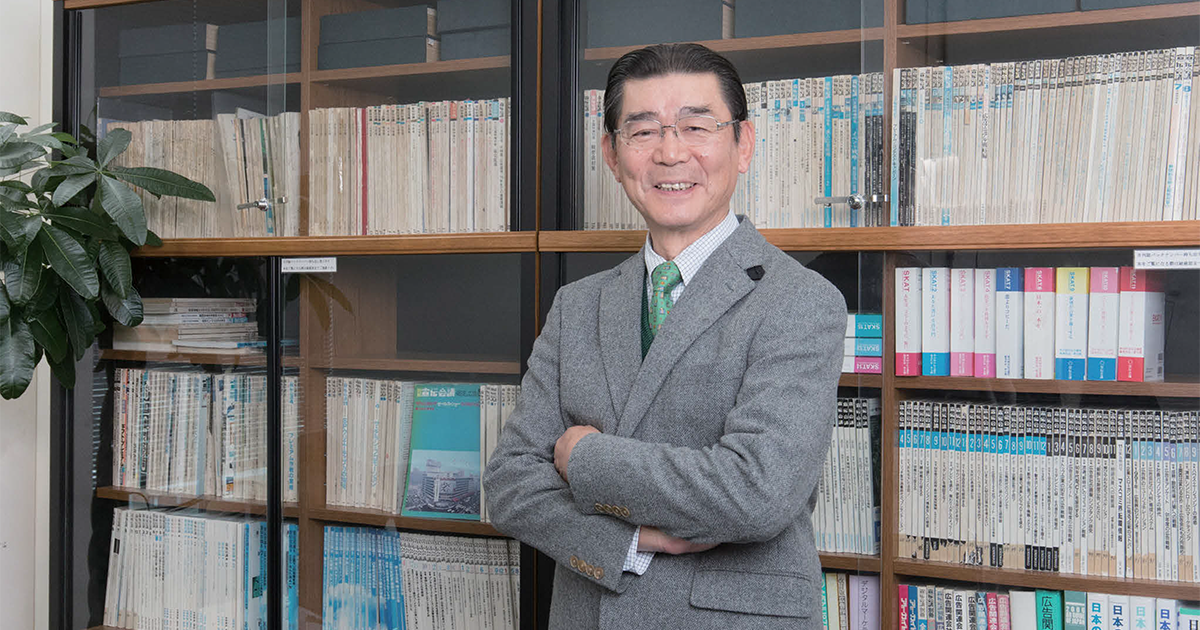海外からも高い評価を受けている、日本のデジタルクリエイティブ。この業界で活躍していくには、どんなスキルや考え方が求められるのか。ワン・トゥー・テン・ホールディングスの澤邊芳明社長に聞いた。

中国の失踪児を見つける顔認証アプリ「Missing Children」。
学生時代に身につけたいスキルは。
スキルはひとつだけ覚えるのではなく、自分なりの"組み合わせ"を作ることをお勧めします。例えば英語とプログラミングなら海外案件を直接担当できるし、先行している国外の情報にいち早く触れられます。PHPやJavaなどプログラム言語は多いですが、単に"書けるだけ"では、今後の活躍は難しい。そのスキルを持った人は、すでに国内外にたくさんいるからです。
実際、IT業界全体で見れば、中国やベトナムにはプログラミングを低価格で請け負う現場があり、日本の企業から発注するケースが増えています。コミュニケーション分野でそうしたところに依頼するのは考えづらいことではありますが...。
とはいえ、グローバルで起きる変化を見据えながら、サバイバルできる自分の成長軸を自ら見つけることが必要でしょう。"受託脳"になって、言われたことだけやっていては消費されてしまいますし、人生も楽しくない。目の前の問題を、自分なりに判断して解釈できる人になってほしいと思います。
社会人になる前に考えるべきことは。
いまの若い人は"やりがいの欠乏感"を、僕らの世代よりも強く抱いているのではないでしょうか。それは、低成長期に生まれ育ち、社会が右肩上がりに伸びる実感を得ていないことが原因かもしれません。技術面から見ても、最近はドラスティックな進歩が意外と少なく、黎明期に比べて新技術を学ぶモチベーションを抱きづらいことは確かです。プラットフォームを欧米に押さえられ、そのルールに従わざるを得ないのも、日本には不利な点。
では、どうするか。いま日本の企業が必死になって探しているのは、次の"消費のあり方"です。クリエイティブに携わる僕たちも他人事ではいられません。人の心を動かす表現を生み出すためには、まずこの点から考える必要があるでしょう。いま活況なのはゲームやアニメといったコンテンツ。心動かされるものには、依然として消費者は対価を払う。最近では映画『風立ちぬ』や『永遠の0』がヒットしました。これは生のリアリティを求める気持ちがあったからではないかと思います。
学生のうちにすべきアクションは。
現在は情報にあふれていますから、注意しないと知識だけの大人になってしまう。どうしたら人が動くのか、実体験を得ておくことが大切です。
アプリなど、ひとつでも形にしてみてはどうでしょうか。自分で作れなくても、プログラムができる仲間を集めればいいのです。仮に社会貢献に興味があるのなら、目指したい世の中を実現するためのアプリを考えてみては。
目新しい技術などなくても大丈夫です。世界三大広告祭の一つ、「カンヌライオンズ2013」で、JWT北京と当社がモバイル部門の金賞を獲得した「Missing Children」は中国の失踪児童を、顔認証技術を用いて探すアプリですが、技術的には誰でもできること。勝負となったのは切り口や視点の新しさでした。
稼働するアプリを作ってみるメリットは、実際に使った人からフィードバックを得られることです。人の目に触れるものを出し、ユーザーからの反響を得る経験をしておくと、社会に出てから違うと思います。
同じ知識でも、現場の空気を呼吸しているかで吸収度が変わります。広告は、コアアイデアを出すだけでは解決したことにはなりません。いかにエグゼキューション(実行)していくか、までが問われるのです。作ってみたものを使ってもらえなかったなら、なぜダメだったのかを考えて、改善を繰り返していけばいい。そうした忍耐力、ある種の"あきらめの悪さ"もこの職業には必要な能力なのです。
 |
ワン・トゥー・テン・ホールディングス 代表取締役社長 1973年生まれ。学生時代に24歳で独立、2012年、4社を吸収し、ワン・トゥー・テン・ホールディングスを設立。海外広告賞を含め100以上の受賞がある。 |