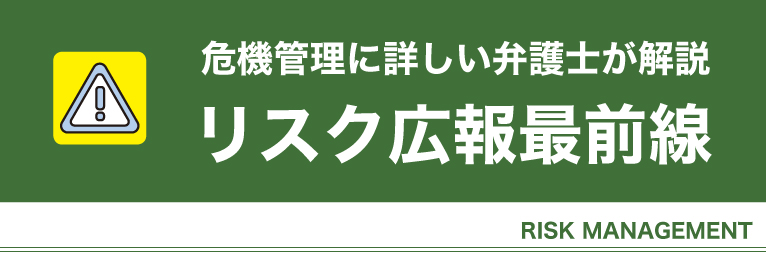複雑化する企業の諸問題に、広報はどう立ち向かうべきか。リスクマネジメントを専門とする弁護士・浅見隆行氏が最新のケーススタディを取り上げて解説する。
問題の経緯
2022年11月8日

興津食品は、ツナ缶虫混入をめぐる判決を不服として控訴。会見を開き「大企業から発注を受けている下請け会社全体に影響を及ぼす問題」と話した。
©123RF
はごろもフーズが、ツナの缶詰に虫が混入していた問題をめぐり、損害賠償を求めた訴訟で、静岡地裁は、下請け会社の興津食品に約1億3000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。2016年、山梨県内のスーパーで販売された缶詰の中から虫が発見され、はごろもフーズは、ブランドのイメージが傷ついたなどと主張していた。
2022年11月8日、はごろもフーズの製造協力工場である興津食品に約1億3000万円の損害賠償を命じる判決が言い渡されました。原因となったのは、2016年10月に発生した異物混入事件です。興津食品が製造したツナ缶にゴキブリと推定される虫が混入していたことが広く報じられたため、はごろもフーズはブランドイメージに傷がつき売上が低下したなどとして、興津食品に約8億9700万円の損害賠償を請求していたのです。
この判決に対し興津食品は11月17日に控訴を提起し、かつ、約11億円の損害賠償をはごろもフーズに求める反訴を提起しました。
今回はこのケースを題材に、訴訟に関わる危機管理広報について検討します。
根拠のある請求のはずが⋯
協力会社と下請取引をする会社(特にメーカー)の多くは、協力会社が製造等した商品に種類、品質、数量などで協力会社に非がある事由が発生し損害が発生したときには、因果関係が認められる限り協力会社に責任を負わせることを、協力会社と締結する契約の中に定めています。
はごろもフーズと興津食品との契約内容までは明らかではありませんが、おそらく似たような条項は定められていたのだと推察できます。そのため、興津食品が製造したツナ缶にゴキブリと推定される虫が混入していたことが判明した後に、それと因果関係のある損害の賠償をはごろもフーズが興津食品に請求することは契約書に基づくものであり、法的には根拠のある請求ということになります。
むしろ、法的に請求する権限があるのに、その権限を行使しなければ、はごろもフーズの取締役は自社に発生した損害を放置したことになり、善管注意義務を果たしていない、との役員の責任問題に発展しかねません。
しかし、11月8日に判決が出た後のメディアでは、「下請け会社に賠償命令」「1億円超の賠償命令うけた下請業者が猛反発」「下請業者の『倍返し』なるか」などと興津食品に肩入れしているように見える論調のものが目立ちました。SNSも同様です。まるで、はごろもフーズが損害賠償を請求したこと自体が悪いかのような雰囲気に...