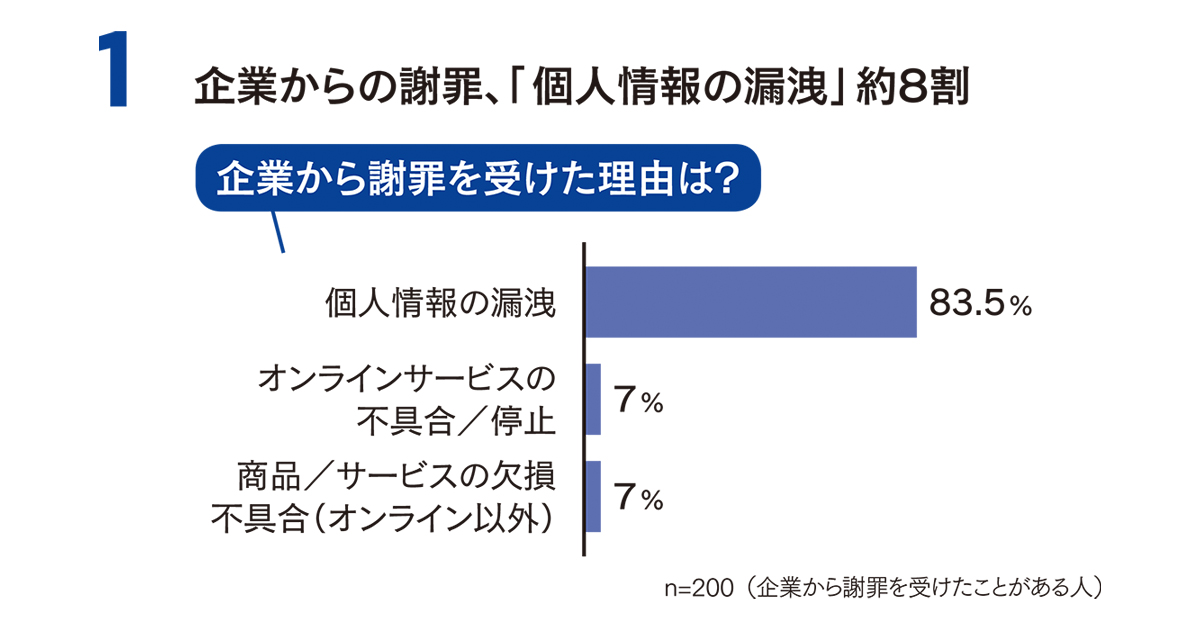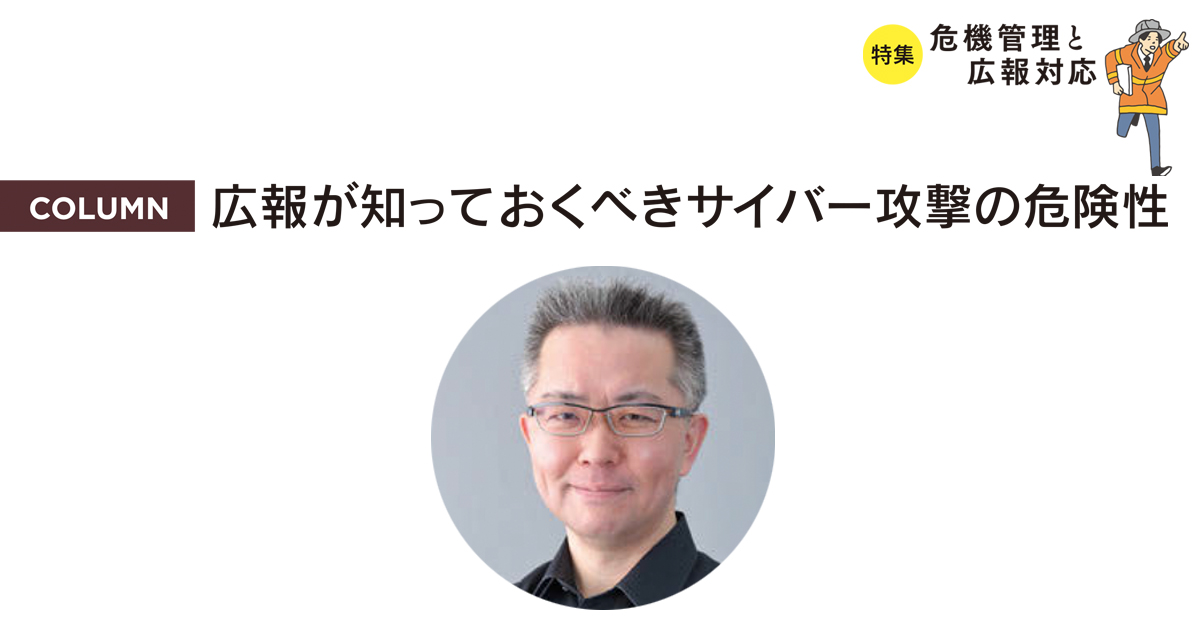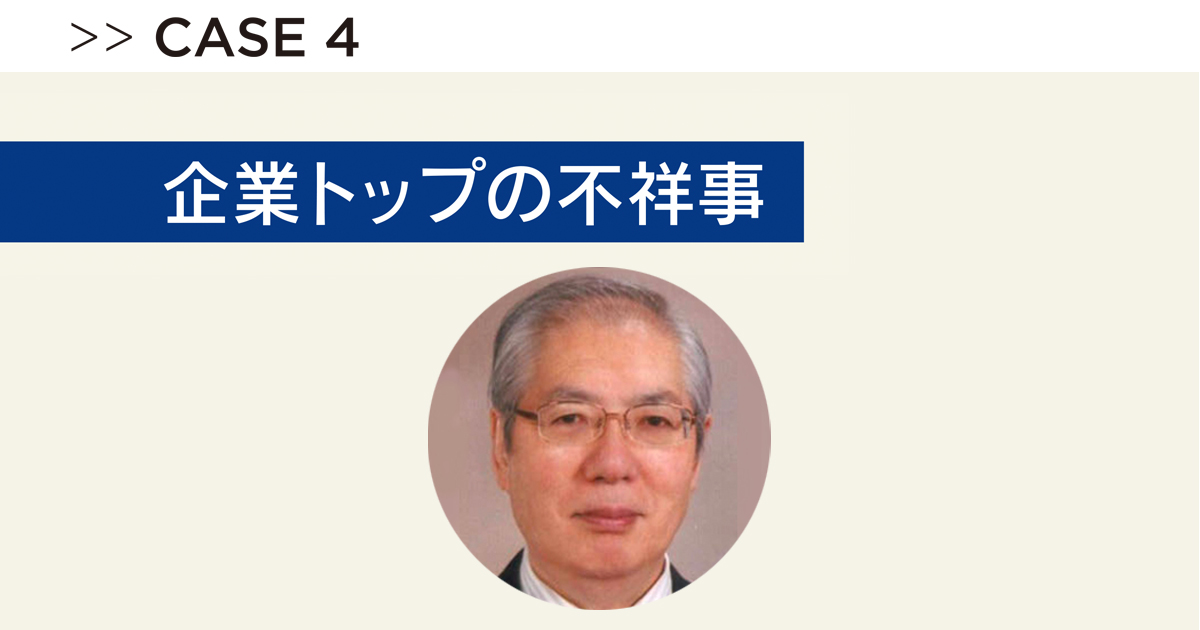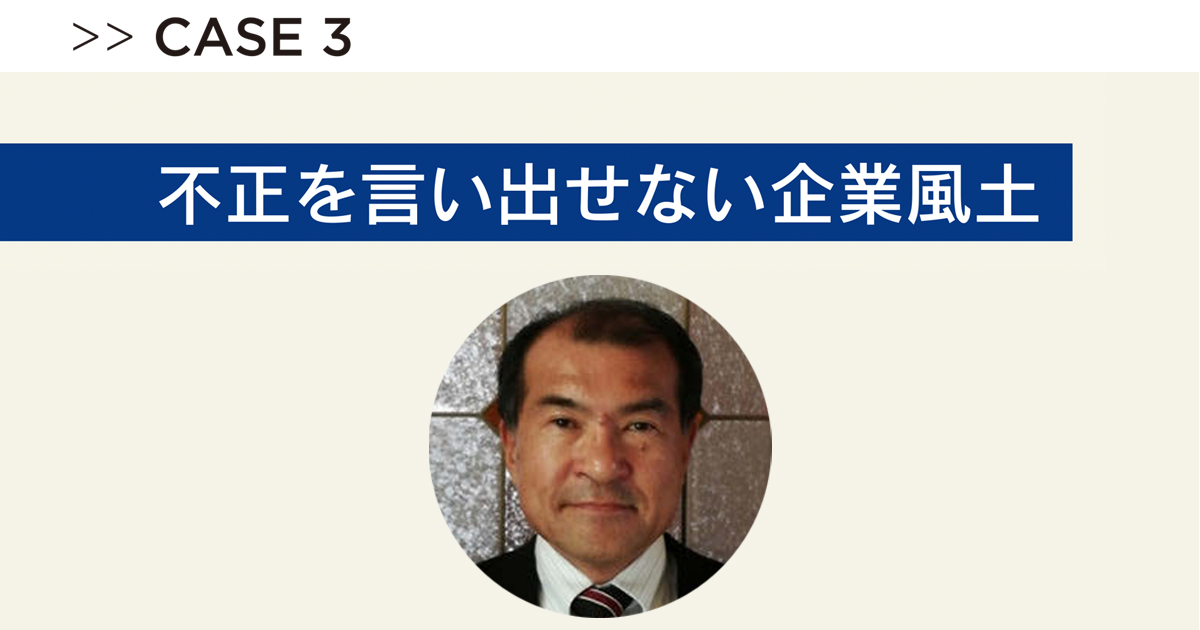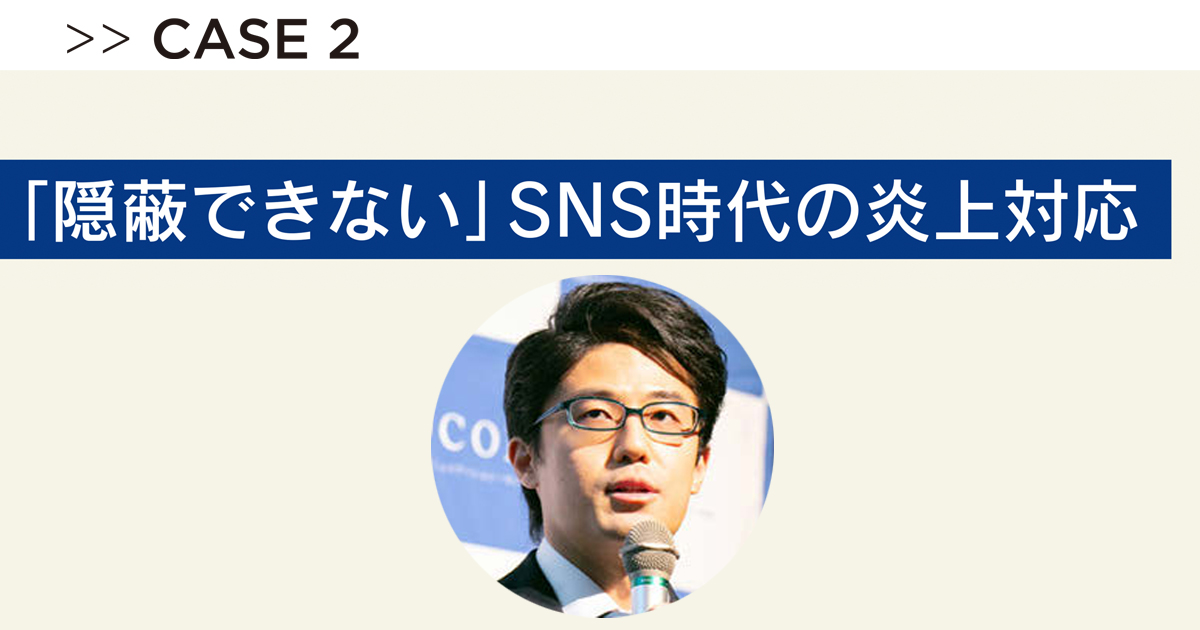2022年は現職の企業トップの逮捕や辞任が相次ぎ、世間の注目を集めた。ここでは、捜査が進んでいることが報道された後、メディア対応や対外発表を行い逮捕に至ったケースを事例に、危機管理広報について考える。
次に紹介する一文は、今から18年前の2004年6月7日の読売新聞のコラム「水平線」に「どう対応したか」という見出しで、保高芳昭記者が書いた記事の冒頭の部分である。
「人は起こしたことで非難されるのではなく、起こしたことにどう対応したかによって非難される」。
名言ではないか。
そして今、これほど味わい深い言葉があるだろうか。
この一文は、数年前に東京商工会議所が作った冊子の冒頭にある。それなりの企業の広報担当者なら知らぬ者はいない、危機管理の要諦(ようてい)だ。
最近相次いで発生している企業不祥事の報道を見て、すぐ浮かんできたのがこの記事であった。
刑事事件のメディア対応
刑事事件に関するメディア対応は、捜査に影響を及ぼす恐れがあることから「この件は刑事事件がらみの事案ですので、当社としてはコメントを差し控えさせていただきます」程度にとどめるようにするのが大原則であり、一般的である。メディア側も刑事事件の取材対象の主体は捜査当局だと分かっているから「取材拒否」とは受け取らないし、批判もされない。報道内容も企業側からの情報より捜査当局からの取材報道が主流になるのが普通だ。
一方、KADOKAWAの角川歴彦会長(当時)は、東京五輪・パラリンピックをめぐる汚職事件で逮捕される直前、報道各社の取材に応じた。
KADOKAWA会長逮捕
KADOKAWA会長(当時)が贈賄容疑で逮捕、起訴された。東京五輪・パラリンピック大会組織委員会の元理事にスポンサー選定で便宜を受けたことへの謝礼などとして計6900万円を提供したとして罪に問われている。報道各社の取材に対して「賄賂を渡した認識は全くない」と強く否定していたが、法務部から事前に「賄賂の可能性がある」と指摘されていたことが判明している。
“独断即決”の応答
疑惑が報道されたことから、同社には報道各社から取材が相次いだはずである。それに対して、角川会長は“逃げも隠れもせず”むしろ堂々と取材に応じていることに違和感を覚えた。必ずしも明快ではない表現ながらも、次のような一問一答をしている。
「賄賂を渡したという認識は?」という質問には「全くありません」と繰り返してきっぱりと否定。さらに「僕は今まで50年もそんな卑しい心で経営をしたことはない」「自分たちの精神を汚してまでも仕事をしろ、とは言いませんよ」と経営者としての心境を吐露した。「(大会組織委員会元理事の)高橋容疑者にはお金は渡っていないのか?」「全部または一部を高橋容疑者に渡してくださいと伝えたか?」という核心を突く質問にも「渡っていないと思う」「一切ありません」と言下に否定している。
メディアが役員に取材申し込みをする場合、その内容の如何にかかわらず広報部を通して申し入れをするのが基本ルールのはずだ。
もし、直接、メディアから役員に取材申しこみがあったとしても、役員から広報部に連絡があり、広報部がそれを判断して、役員に提言するか、役員からの相談に応じるのはどの企業でも半ばルール化しているはずである。今回のような刑事事件の場合にはなおさらであり、当然、取材の場には広報担当者が陪席するはずである。
しかし、角川会長のインタビュー場面では、この「はず」が見受けられなかった。会長の応答はおおむね“独断即決”的なものだった。「賄賂を渡したという認識は全くない」といった説明を聞いていると、「この会長は、本心からそう信じているのでは」という思いを抱いてしまう。起訴に至ってもなお、「一切、(汚職には)関与していない」「無実であることを、全力を尽くして明らかにしていきたい」と主張。KADOKAWAを取り巻いている客観的状況とは無関係に一貫して会長自身の“熱き想い”を訴え続けている。
見方次第では「往生際が悪い」とか「役員としての認識が希薄だ」とか「ない、ないばかりの説明ではないか」といった批判的指摘に事欠かないが、会長自身としてはもろもろの疑惑など、微塵も思わなかったに違いない。