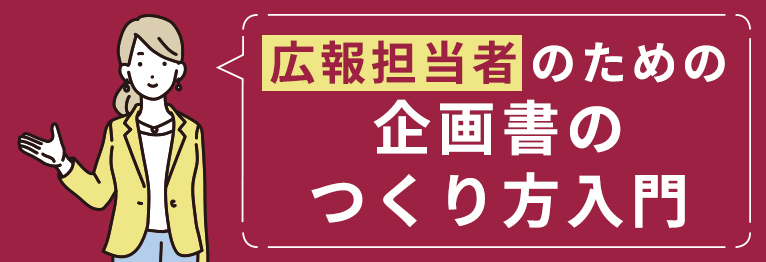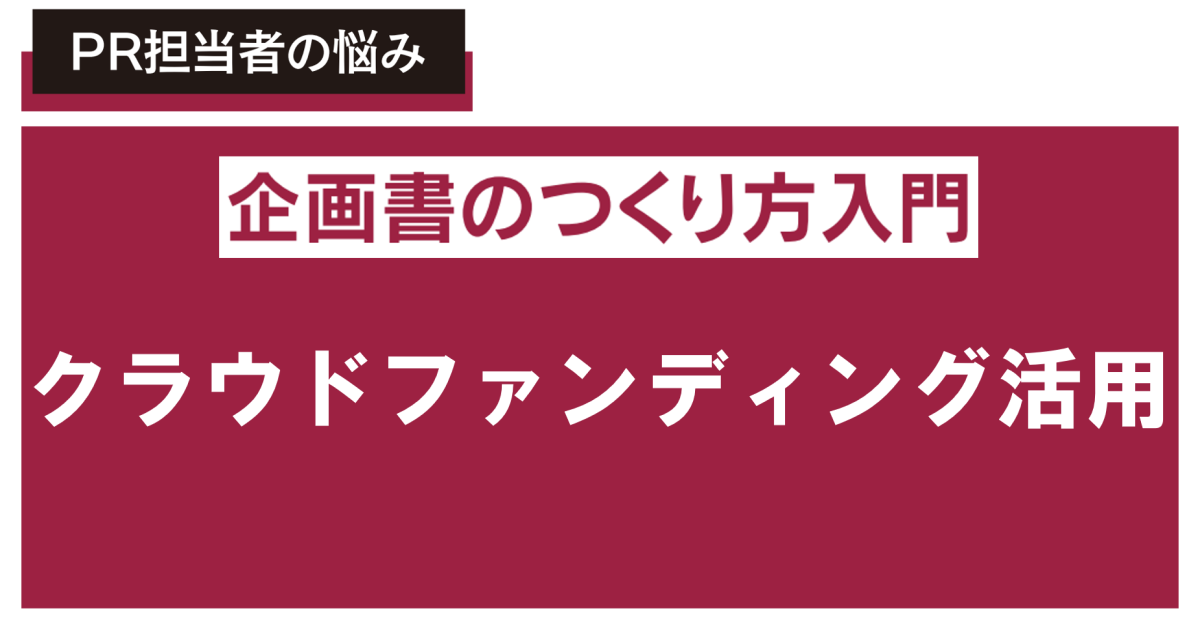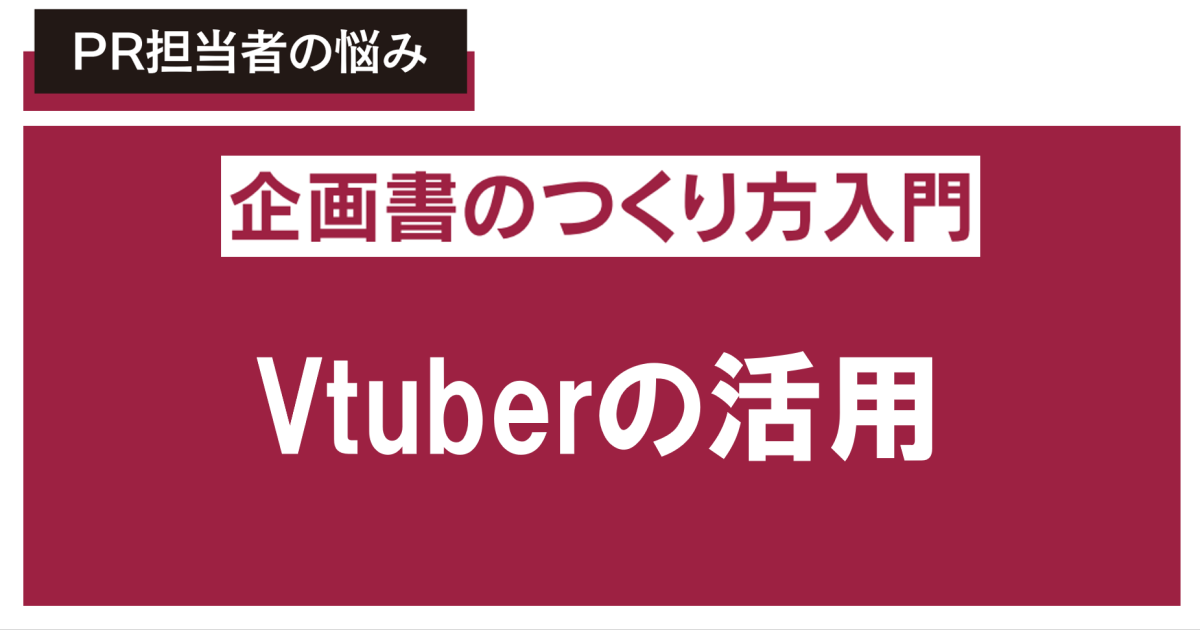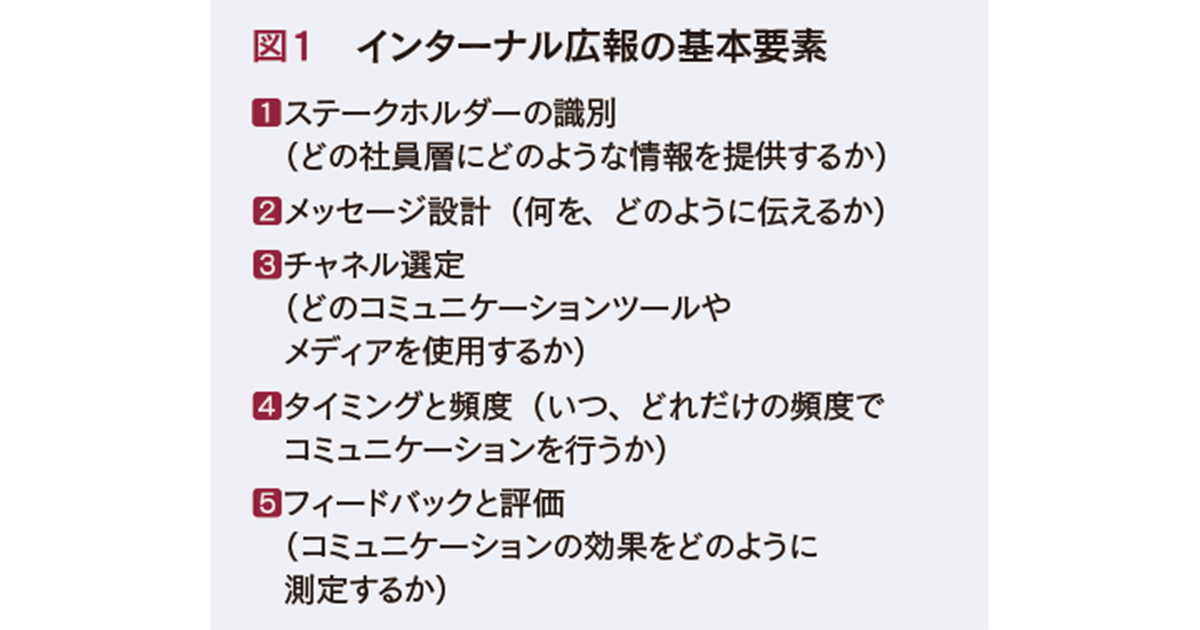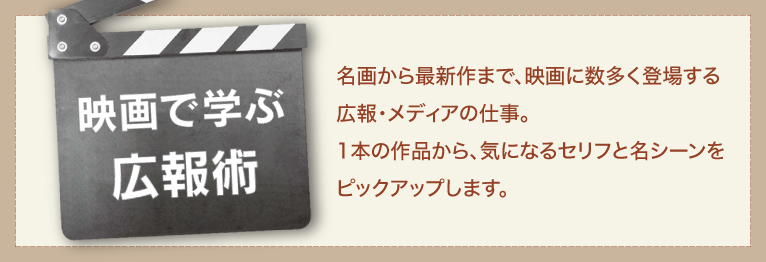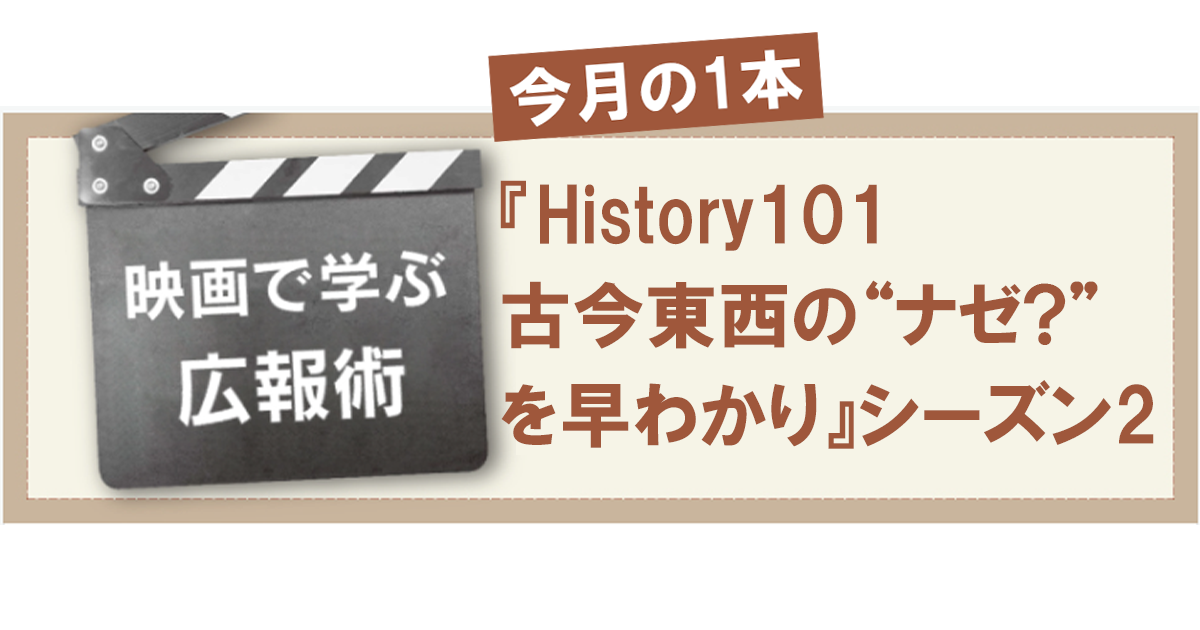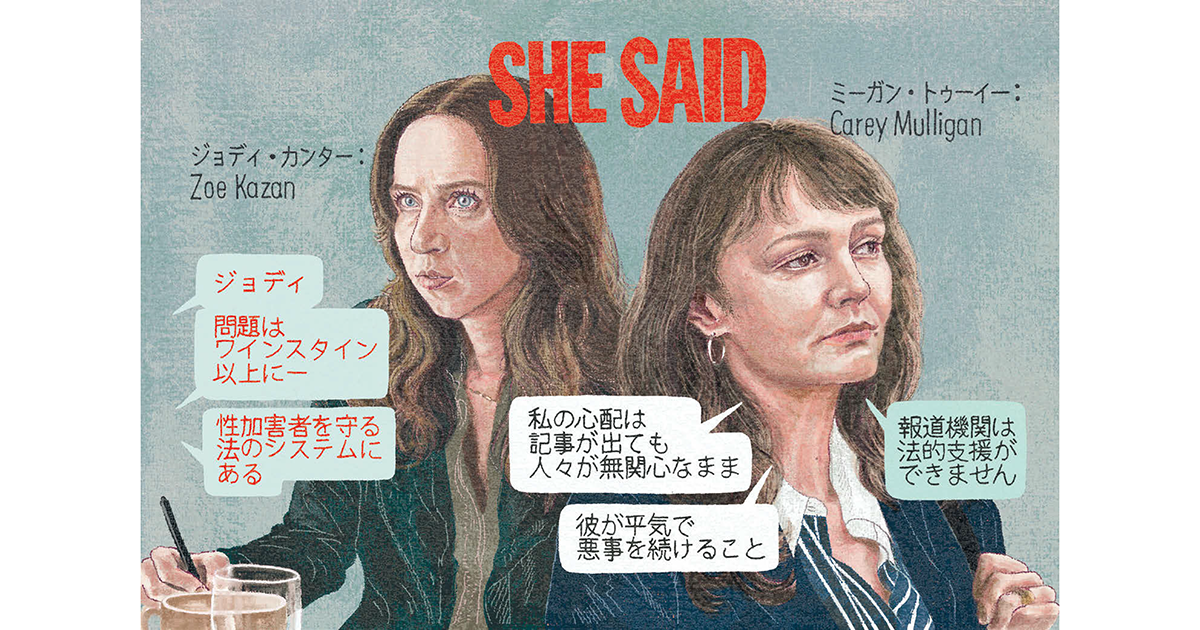メディア研究などを行っている大学のゼミを訪問するこのコーナー。今回は慶應義塾大学の藁谷郁美研究会です。

神奈川県三浦半島で合宿を行った藁谷研究会のメンバー。学部生と大学院生も参加した。
| DATA | |
|---|---|
| 設立 | 1998年 |
| 学生数 | 1年生2人、2年生6人、3年生10人、4年生10人 |
| OG/OBの主な就職先 | マスコミ(テレビ局、新聞社、出版社、演劇関係等)、研究所、金融、メーカー、コンサルタント会社、情報システム関連、教育関連(研究者) など |
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)にある「総合政策学部」と「環境情報学部」では、すべての科目が両学部共通で履修できる。
合わせて約100名いる専任教員は、全員専門分野が異なる。文学研究や言語学研究から情報学、経済学、政治学、建築、デザイン、生物学(ゲノム工学)、身体認知など。学部生も大学院生も自分の問題意識をテーマとし、研究のために必要な履修科目のプランを自分で考え、組み立てる。「○○学を勉強する」という形ではなく、「○○を解明したい(研究対象にしたい)から、△△学と□□学が必要だ」というアプローチで科目やゼミ(研究会)を選ぶ。この学びの視点がSFCの特徴であり、他の教育機関との違いだ。
他者の「ことば」を知り、自分を知る
「他者の言語で発信されたメディアコンテンツを比較すれば、他者の言語圏・文化圏から見える射程を知ることができます」。こう話すのは、「ことばとメディア」を軸に研究会を開く、総合政策学部教授の藁谷郁美氏だ。グローバルな課題について、他の言語圏から見たものを自分の言語圏・文化圏と相対化することで、自分の価値観や世界観をあらためて見直すことができるという。
研究会では、グループワークを通じメディア比較研究を行い、言語によって異なる報道内容を比較分析。個人研究においては、映画コンテンツや文学作品、広告コンテンツ、言語教育などテーマは多岐にわたり、卒業論文には「言語の違いにおけるメディア受容の相違分析」「メディアと言語-3.11報道をめぐる日独英新聞メディアの比較分析」などがある。
共同研究で問題意識を高める
藁谷研究会に集まる学生は、多文化・多言語に興味を持ち、海外生活や留学を経験している人が多い。研究会では、1年生から大学院生までの学生が週に1回ディスカッションする場が提供される。
学期の初めに「メディア比較研究ワーキンググループ」「リサーチワーキンググループ」の2つの異なるグループを形成。学期前半には、メディア比較研究として共通研究対象を決め、グループ内での調査・ディスカッション・発表を継続。同時に、個人研究の構想を発表する。後半には、班ごとにメディア比較研究の最終発表会を行う。個人研究については学期ごとにまとめとしての発表を行い、最後に論文形式でペーパーを提出する。
他の研究室との共同研究が多いのも藁谷研究会の特徴だ。例えば、「ユビキタスドイツ語学習環境デザインの設計・構築・評価」のプロジェクト。情報データベース研究の研究室との共同研究に学部生・大学院生も巻き込み、SFC内のドイツ語授業で運用を実践。国内外でも学会発表を行い、教育工学分野のジャーナルにも執筆した。
藁谷研究会を基盤に「ゲームスタディ・プロジェクト」も立ち上がった。ゲームコンテンツやシステムは、言語圏・文化圏が異なると違いが見えやすいことを発端に、Cygames社との共同研究がスタート。ゲームスタディのテーマで博士論文を執筆・博士号を取得する大学院生も輩出している。「ことばと文化」の研究がゲーム研究にも発展したユニークな活動の例だ。そのほか、JR東日本と慶應義塾大学SFCとの共同研究に参加するなど、他分野の研究とつながり、学生の体験の場を広げている。
「自分の突き詰めたい課題は何か、問題意識を強く意識することが重要です。ゼミに参加する他者の活動を目の当たりにしディスカッションすることで、自分の考えがそれまでの射程を超え、柔軟に気づきとなって多様化します。ゼミ活動を通して研究活動をより俯瞰的に、相対的に捉えられる視点を持つようになってほしいと考えています」(藁谷教授)。

合宿先の研修室で、プレゼンテーションとディスカッション。発表中に同時進行で気づきやコメントをコミュニケーションツールに書き込んでいく形式。
研究環境と学生の橋渡しで「外国語学習環境デザイン」研究へ
外国語学習環境デザインに藁谷教授が興味を持ったのは、SFCに教員として着任したことがきっかけ。多様な研究領域の研究者と共同研究を行う環境が整っているSFCでは、外国語教育も充実しており、現在11の外国語を学習言語として提供している。
「他分野の研究者と共に共同研究を行う視点を得たこと、そして多様な言語を学ぶ学生たちが、新しい研究領域への橋渡しをしてくれました」と話す。ドイツ語学習の学習環境を新たに構築する際は、ドイツ語履修者の視点が新たな研究プロジェクトにつながった。「共同研究、協働学習という新しい活動のあり方によって、それまで単独では決してなし得なかった研究実践へと発展したと考えています」。
現在は、新しい学習デザインの構築や日本の近代化を構築したドイツ語圏における人的ネットワークの構築についての研究を新たに進めつつある。

藁谷郁美(わらがい・いくみ)教授
慶應義塾大学 総合政策学部教授。文学博士(ドイツ・ボン大学)。専門はドイツ語教育、ドイツ文学研究。文学作品翻訳、ドイツ語教材開発、教科書執筆、NHKドイツ語講座講師を担当。マールブルク大学、ケルン大学、ハレ大学、ベルリン自由大学、ボン大学客員教授を歴任。文学研究と並行してドイツオペラの字幕やテロップ等も手掛ける。
ログイン/無料会員登録をする