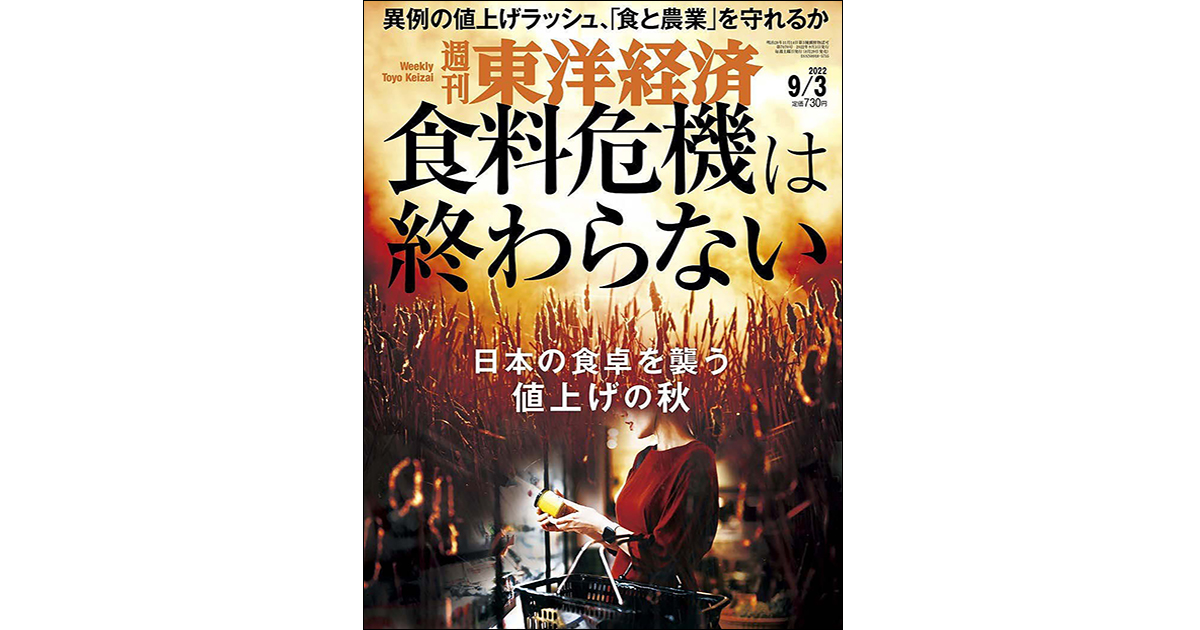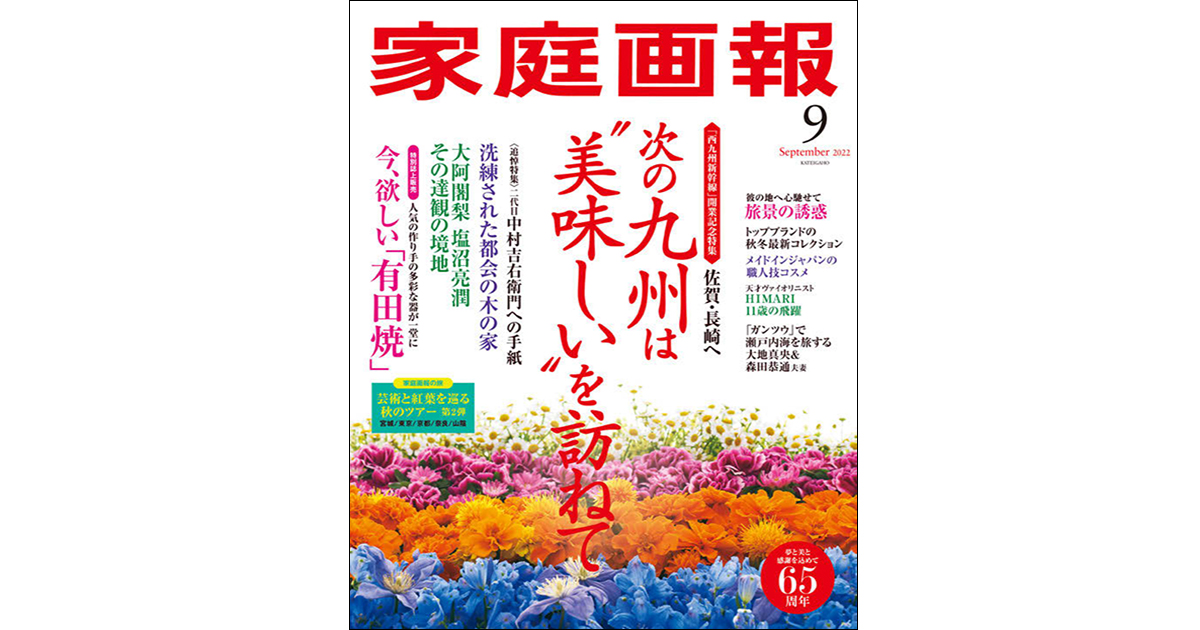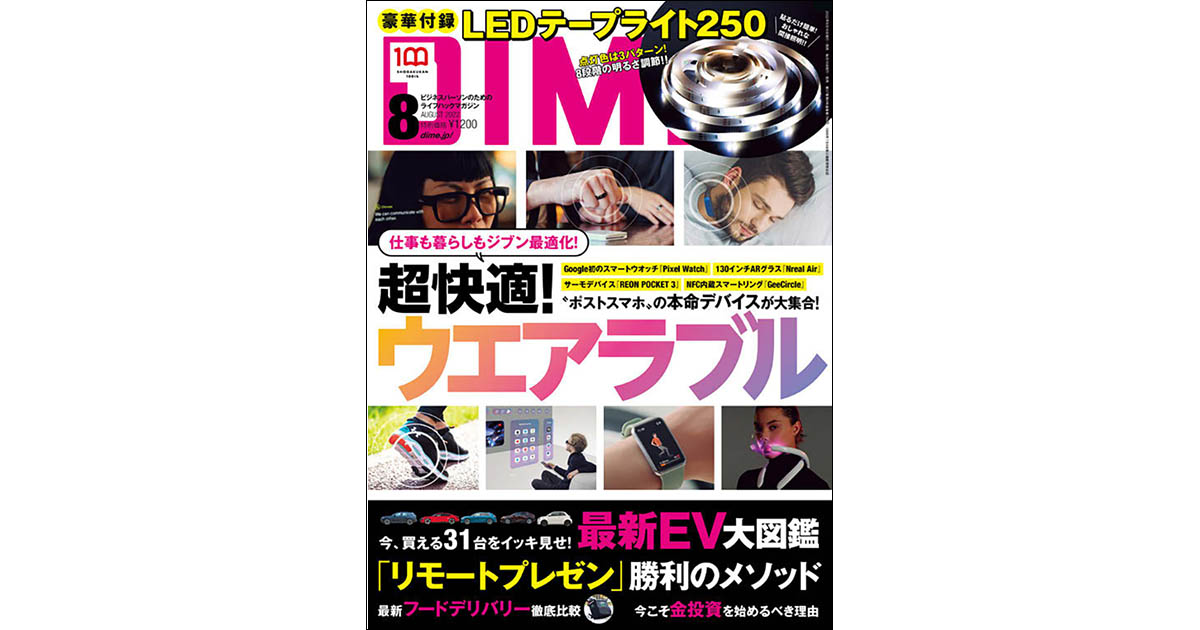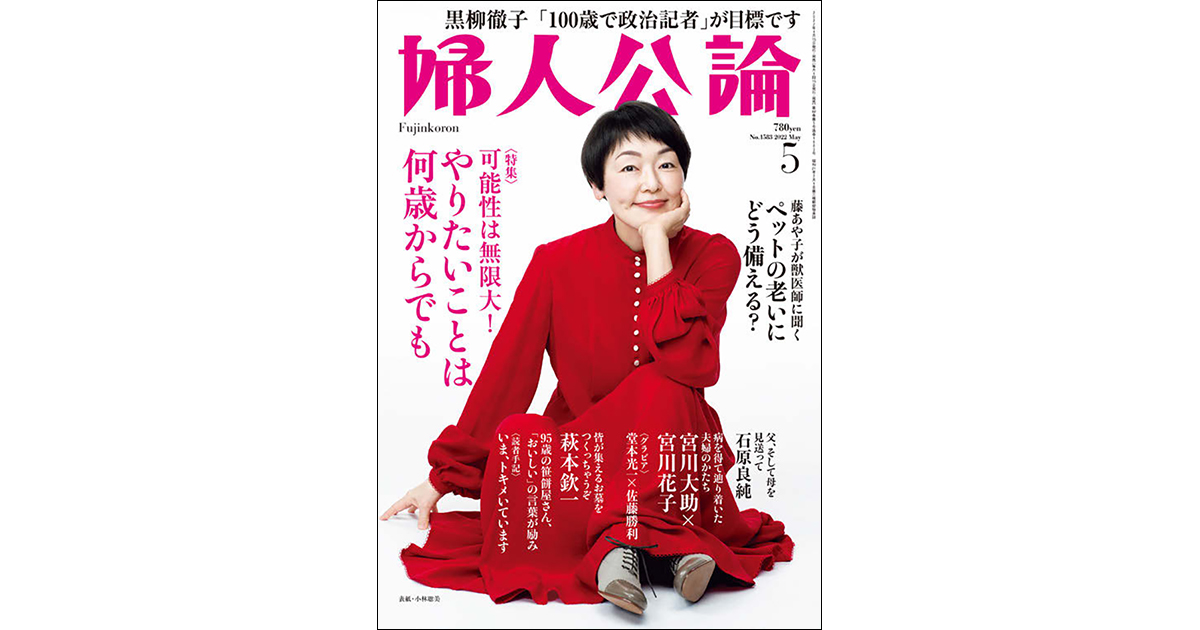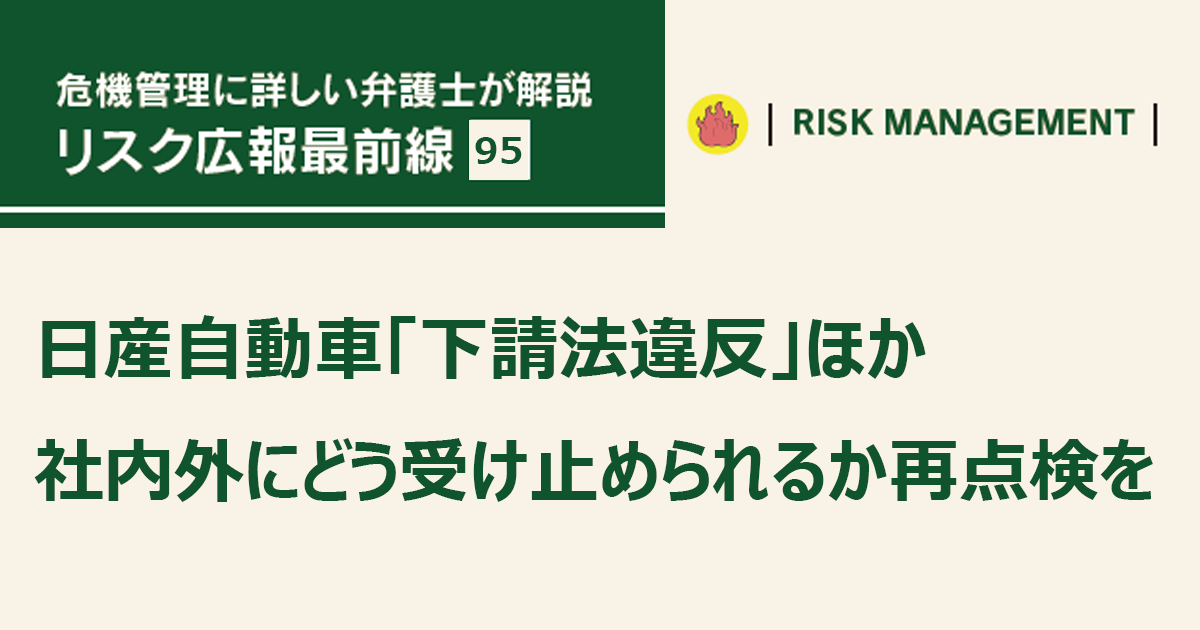報道対応を担当するPRパーソンにとって、気になるのがメディアの裏側。企業取材のスタンスや、プロデューサーや編集長の考えに迫ります。
| 東洋経済新報社『週刊東洋経済』DATA | |
|---|---|
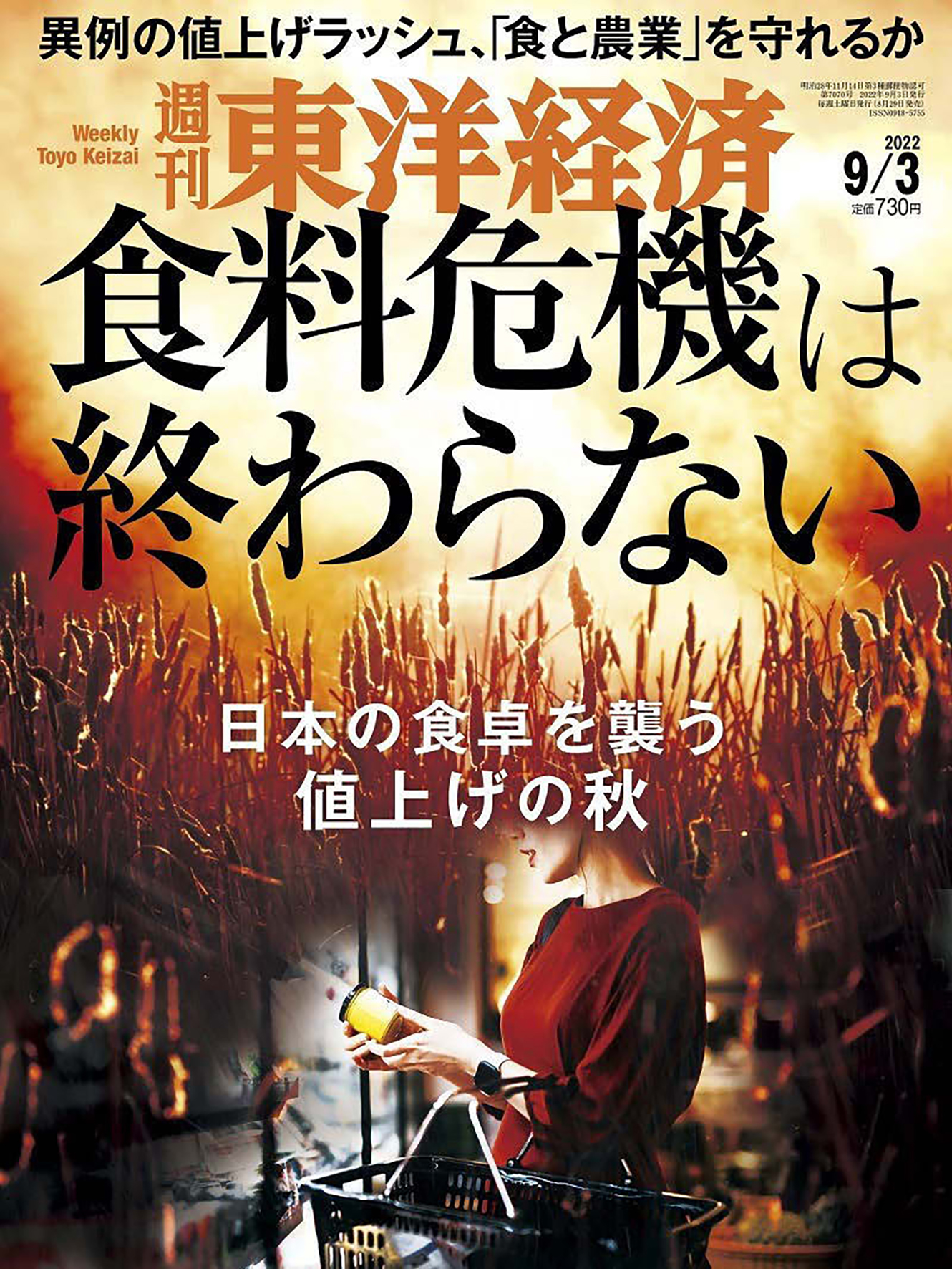
|
|
1895年に創刊し、126年の歴史を持つ総合経済誌『週刊東洋経済』。企業や経済社会を鋭い視点で取材した記事は、多くの経営者や政治家、ビジネスパーソンに読まれ続けてきた。
主な読者層は40~50代の男性。様々な組織の意思決定に関わるポジションの読者に向けて、「考えるヒント」となる有益な情報を届けている。
専門記者集団による取材力
『週刊東洋経済』の特徴は、自社の専門記者・編集者による取材力だ。東洋経済統合編集部に所属する編集記者(約20人)に加えて、業種別に担当を持ち国内外の主要産業・企業の動向をウォッチしている報道部の専門記者(約30人)と、専門性を駆使してニュースの背景を分かりやすく伝える解説部のコラムニスト(約10人)の約40人の専門記者集団を抱える。これらの記者による企業や経済社会の分析力は、『週刊東洋経済』と「東洋経済オンライン」のほか、同社を代表する媒体『会社四季報』でも発揮されている。
2022年4月から東洋経済統合編集部の『週刊東洋経済』編集長に就任した風間直樹氏は、同誌の強みを「定番と見定めたテーマを磨き上げる力と経済誌らしからぬチャレンジングな企画」と語る。トヨタ自動車をはじめとする日本を代表する企業や「産業の米」といわれる半導体といった主要産業、銀行や不動産を巡る動向など、経済誌として必ず押さえるべきテーマは特に力を入れている領域だ。
「数年間ずっとその企業だけを追いかけている記者もいます。そのため、プロジェクト的に一時的に立ち上がってつくられた特集とは異なり、幅広い視点や多面的な分析による特集が可能です。テーマの膨らませ方を日常的にスピーディーに議論できるのも、専門記者集団が社内にいる強みですね」。
“取材拒否”は逆効果
きめ細かい取材や分析に裏打ちされた特集は、ときに特定の企業や業界に対する厳しい視点になることもある。「我々は必ず正面から取材を申し込むことを徹底しています。決して、聞きかじった話だけで構成した一方的な批判記事はつくりません」と風間氏。
企業が厳しい局面にある場合は特に、経営幹部が取材に応じたがらないことも多い。「だからといって『この会社のことを取り上げるのは諦めよう』とはもちろんなりませんし、むしろより内情を取材したくなる。『話したくない』と思うときこそ、門戸を閉ざさないでいただきたいです」。