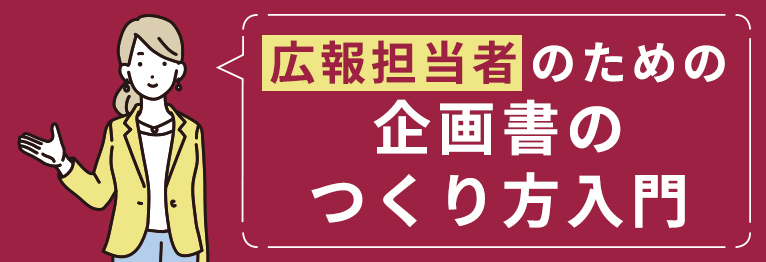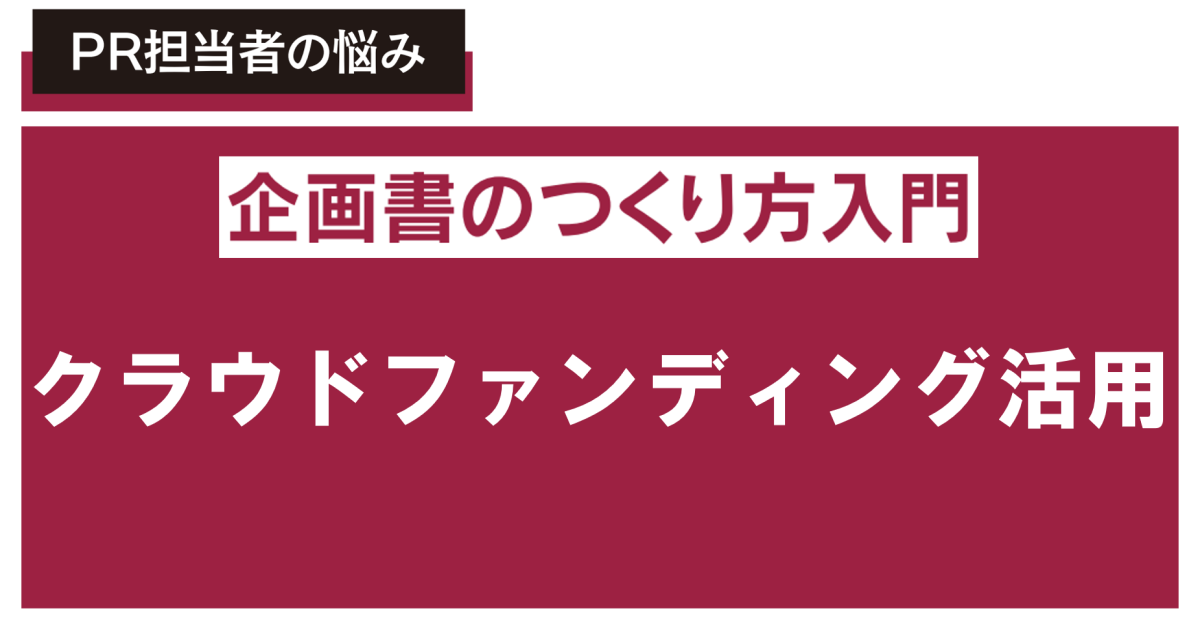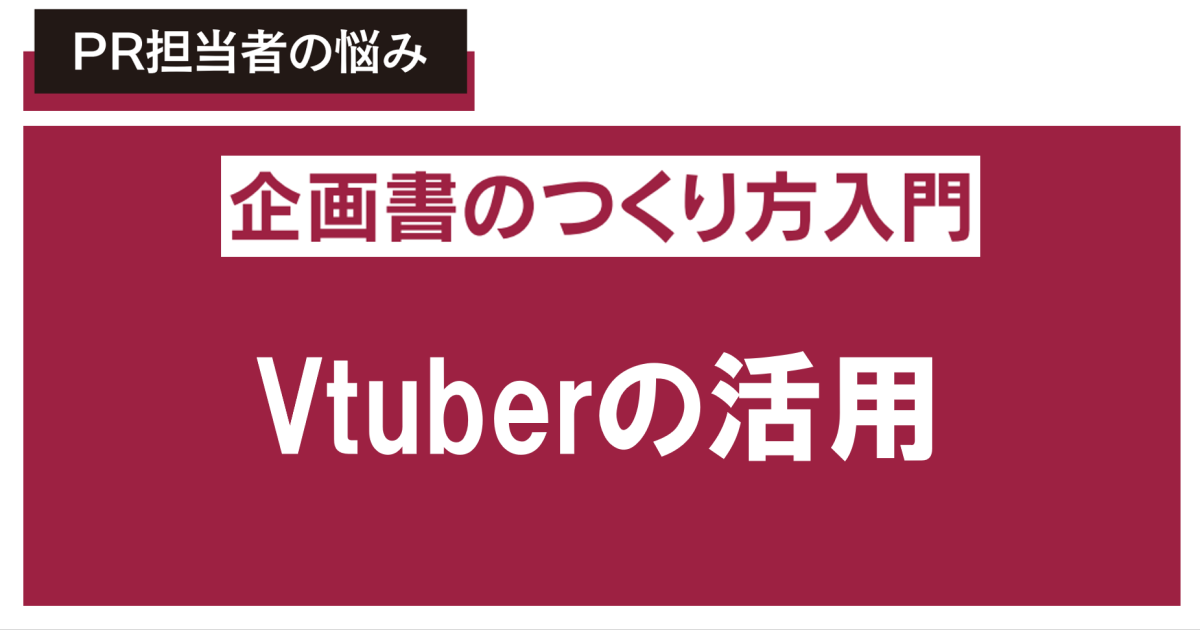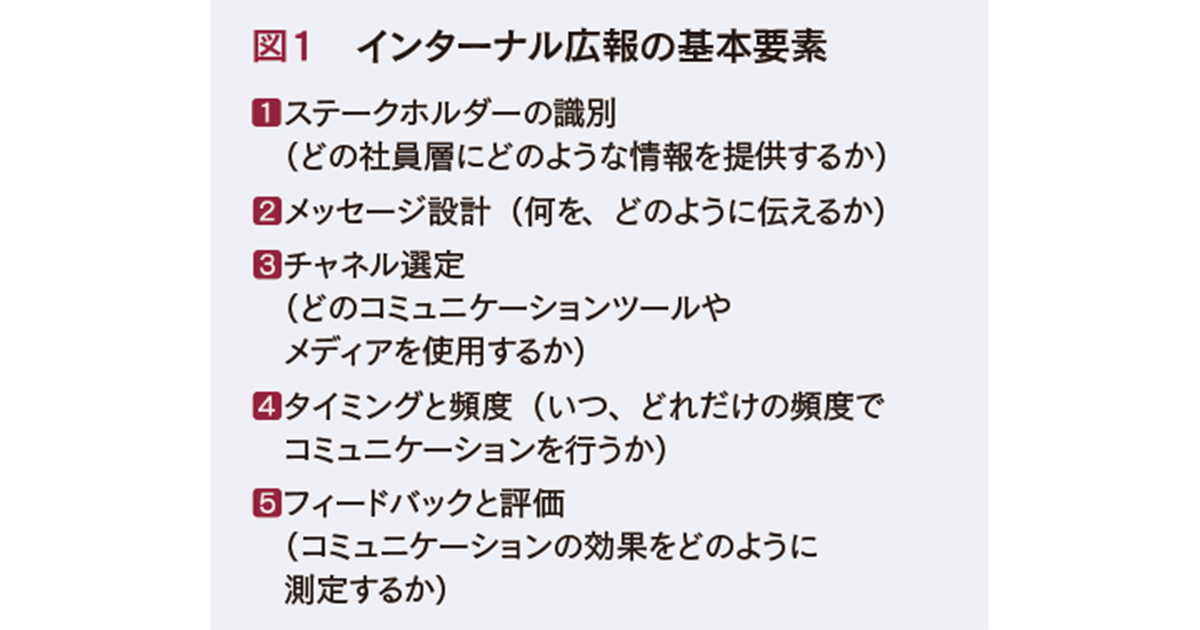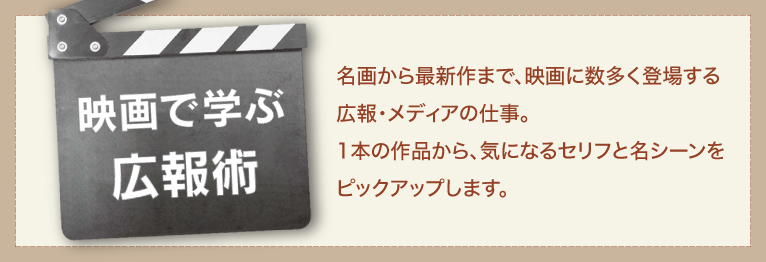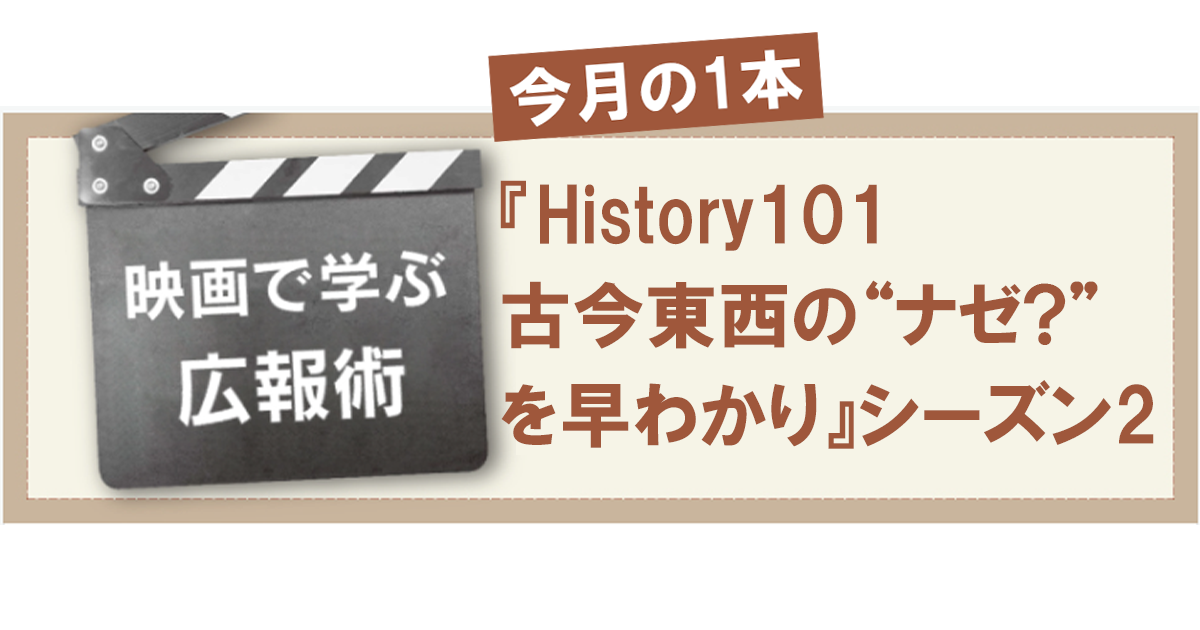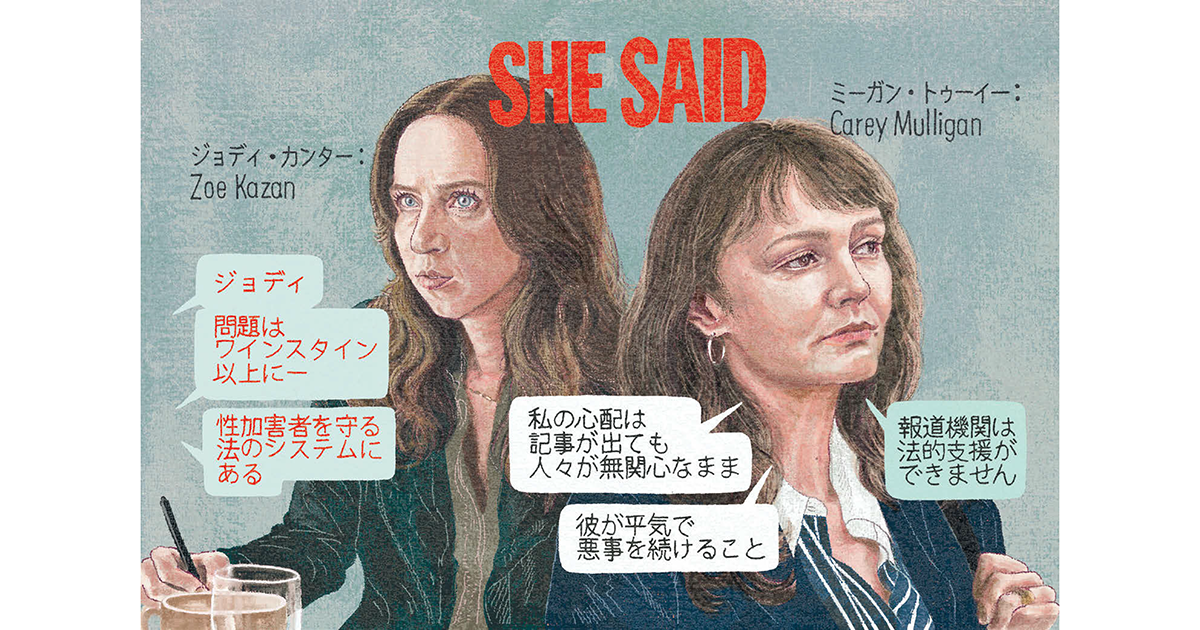迅速な行動喚起が必要な避難指示。その伝達が一刻を争うこともあります。災害情報論の視点から、情報の受け手の心理について考えます。

2022年8月豪雨による村上市の土砂災害
本稿では6回にわたり災害情報論の現在を述べていきます。今回は今年の8月に発生した豪雨災害を例に、災害情報の論点について考えます。
災害情報とは災害に関わる全ての情報を指し、ハザードマップや避難指示といった防災に資するものから、デマやパニックといった社会に害をもたらすものまで様々なものがあります。中でも特に重要なのは、警報や避難指示が住民の避難を促す側面です。
危機感は伝わったのか
2022年8月3日から5日にかけて前線の活動が活発化し、東北や北陸地方で大雨となり、最上川などの河川が氾濫したり、各地で土砂災害が発生したりしました。なかでも新潟県村上市小岩内地区では4日の午前1時ころ土石流が発生し、9軒の住宅が大破(全壊6、大規模半壊3)し、1人が大けがをする災害となりました。
気象庁では3日の11時33分に土砂災害警戒情報、12時3分に記録的短時間大雨情報、13時9分に線状降水帯についての情報などを次々に発し、警戒を呼びかけました。そのうえ新潟地方気象台は何度も村上市長に直接電話をかけ危機感を伝えています。これは、これまで気象庁の危機感が避難指示を発する市町村に届かず...