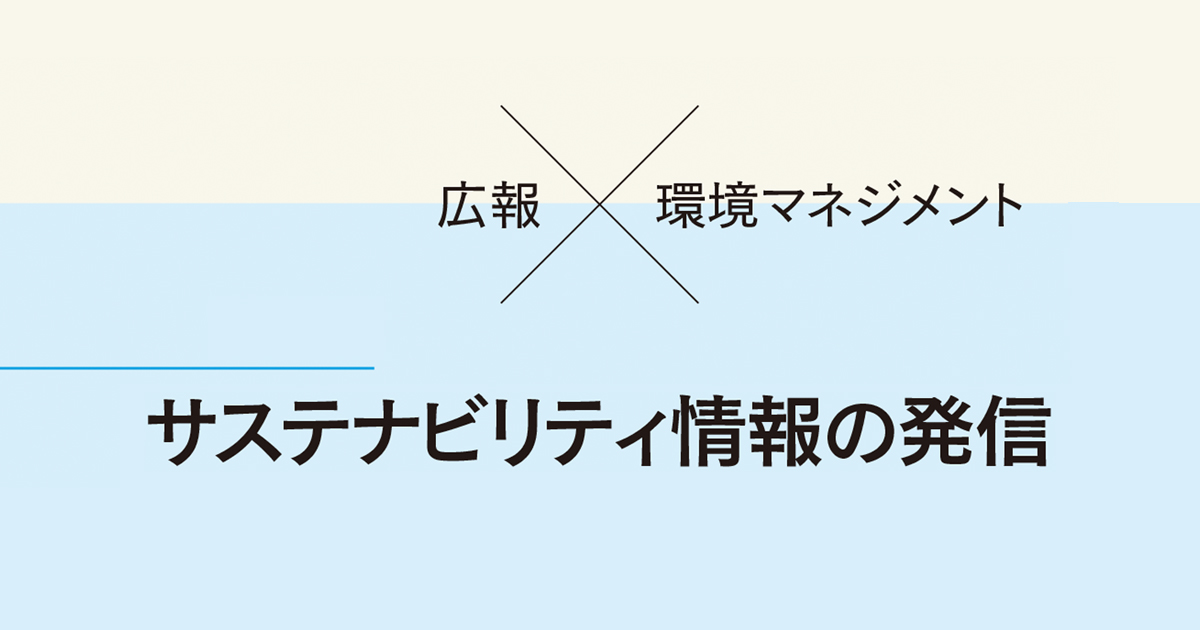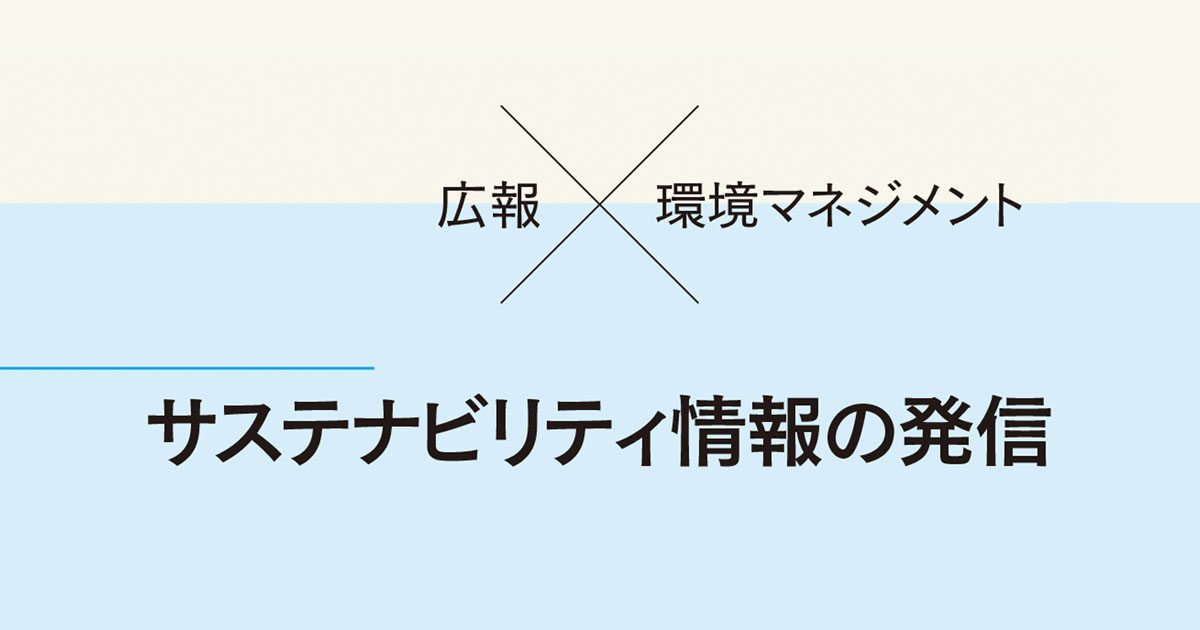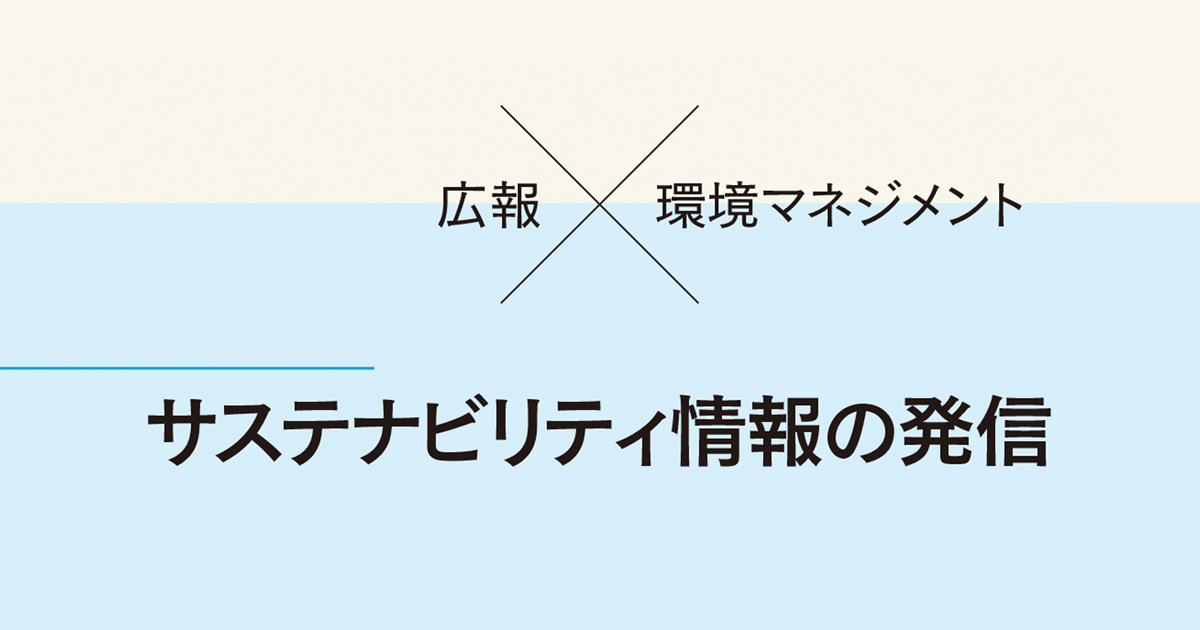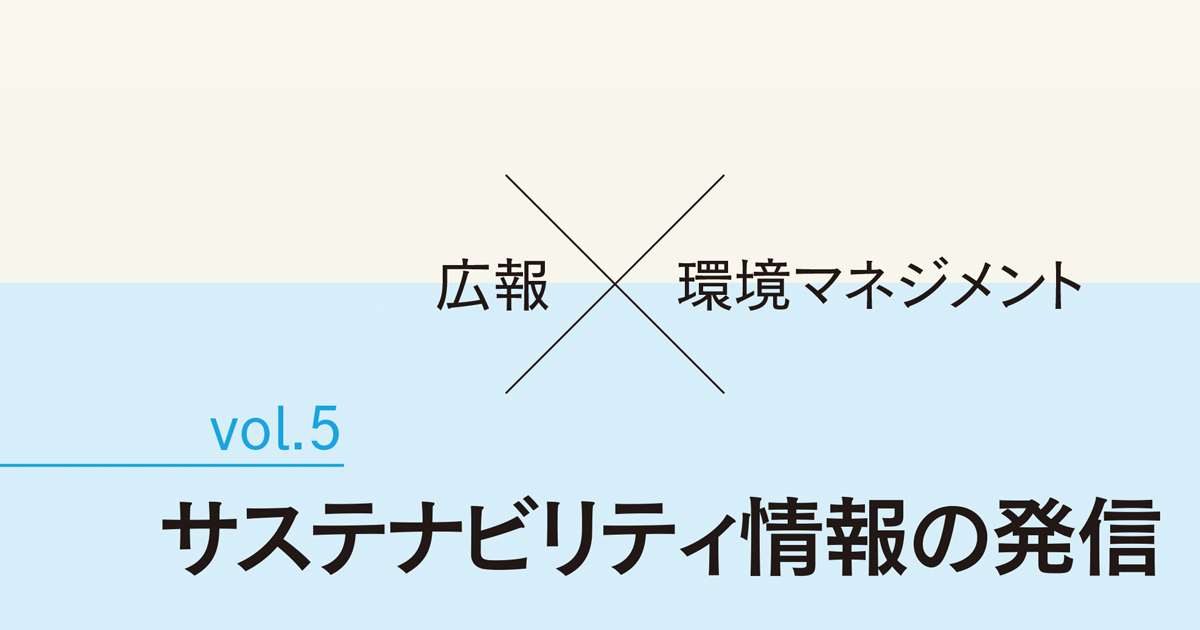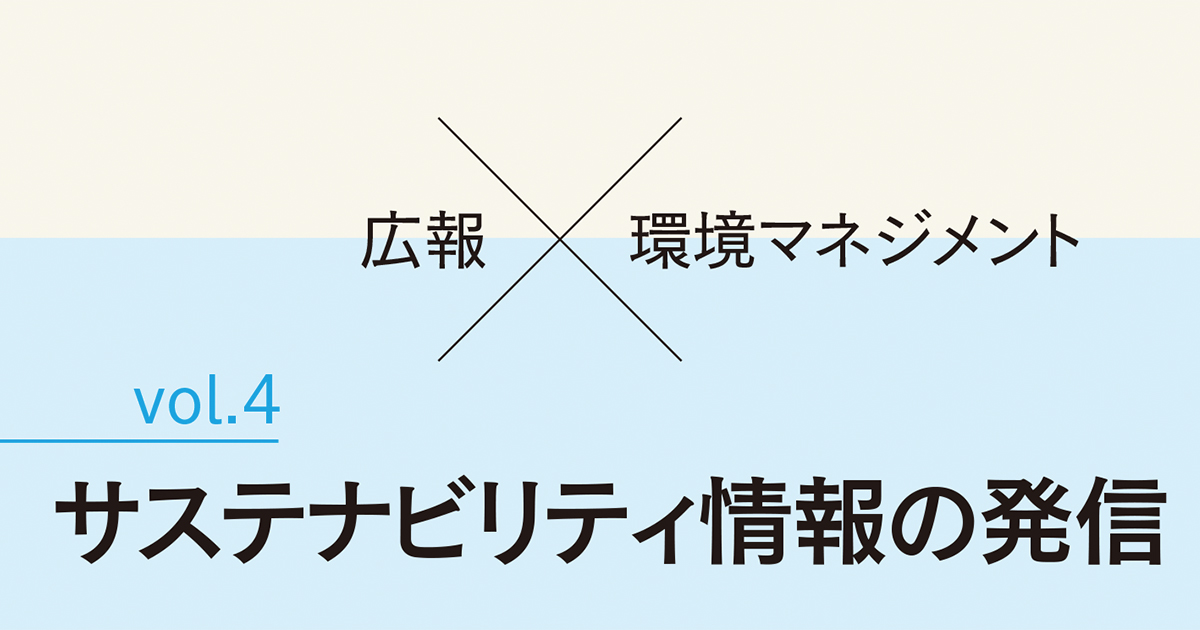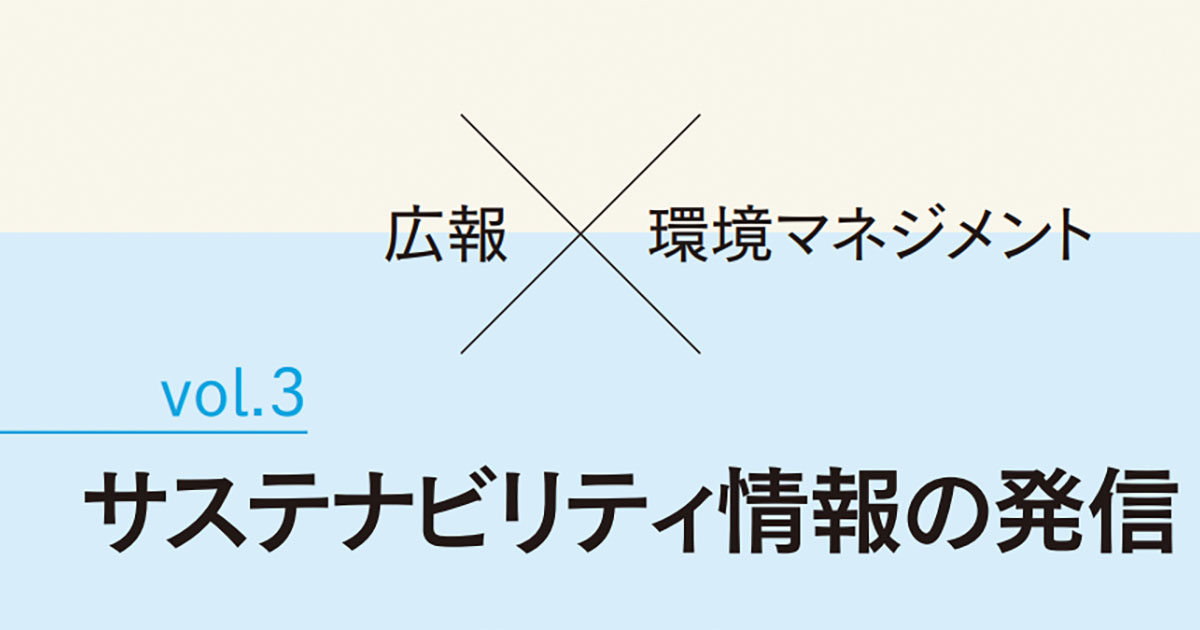環境経営にかかわる動向を解説しながら、企業の本業にサステナビリティを取り込み、コミュニケーションをしていくための考え方を整理します。
日本企業にとってサステナビリティ活動に本腰を入れきれないもどかしさのひとつは、消費者からの支持があまり得られないことにあるでしょう。前回も示したように、日本人は環境問題の解決に対する当事者意識や責任感を抱きにくい状況にあり、気候変動対策は自分たちの生活の質を脅かすものと捉える向きもあります。日本以外の多くの国では、気候変動対策を生活の質を向上させるものとして捉える傾向にあるため、この感情は特徴的なものでしょう。
商品の購入意向に差
このような国際社会との認識の違いは、消費者行動にも表れています。PwCが実施した世界22の国と地域を対象とした消費者意識調査(2021年3月)では、サステナブルな買い物・消費に関する質問に対して日本の回答者は29%が同意するとしていました。これは調査対象の中で最も低く、グローバル平均の45%の半数程度です。
ASEAN地域や中国、韓国の調査ではしばしばヨーロッパやアメリカと比べてより多くの回答者が環境保護を支持する企業からの商品を購入したいと答えており、アジア地域でも日本だけが他と異なる状況にあります。一方でボストン コンサルティング グループが2022年に実施した調査によると、回答者の61%は環境負荷の少ない商品に対して関心はあるものの、実際の商品購入には結びついていません。ただし、こうした消費者層は、きっかけがあれば...