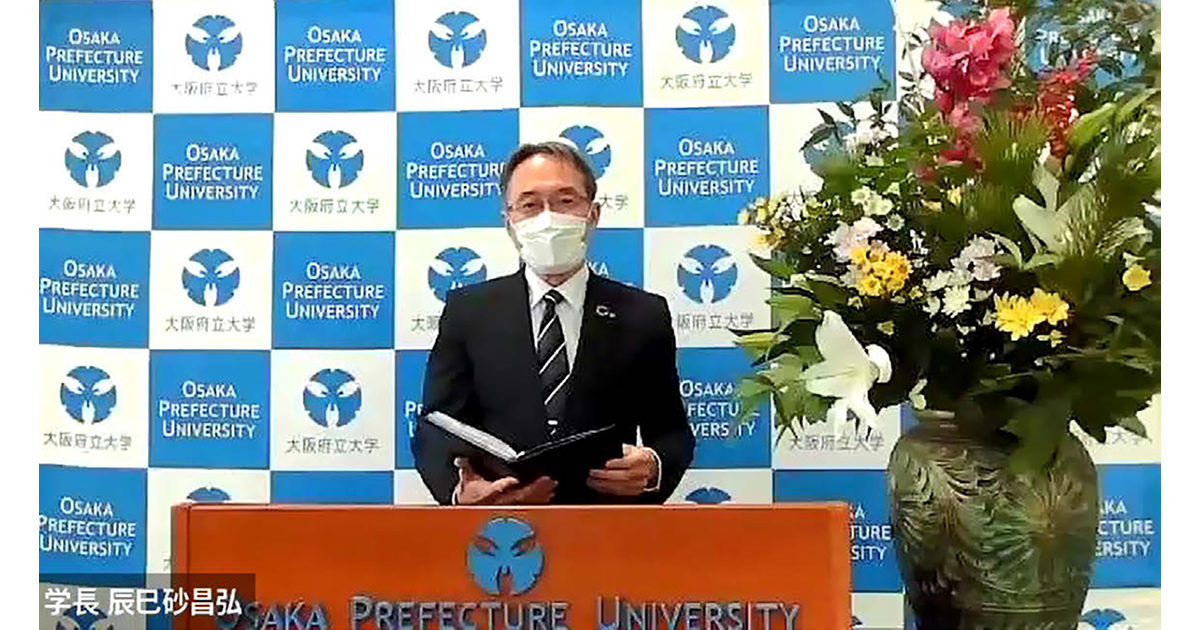今回のテーマは「大学広報」から「入試広報」に軸が少し寄りますが、「学生と連携した広報活動」の効果や意義について、3回に分けて考えてみたいと思います。
仲間として共創する広報
高校生や受験生が自大学の情報に触れる時、在学生からの等身大かつ活気あふれるメッセージは他の情報よりも興味を引き、またその姿を「数年後の自分」に重ねて親しみや共感を覚えてもらいやすいことは、大学広報や入試広報を担当する皆さまも直感的につかんでいるところだと思います。
在学生にとっては逆に、情報発信の対象となる高校生や受験生は「数年前の自分」です。第一志望で自大学に来た学生もいれば、第一志望校は別の大学だったけれど縁あって入学した自大学に対して今は前向きにコミットしている学生、内心はまだくすぶっている学生など、様々な思いを持つ彼らが「今だから高校生(数年前の自分)たちに伝えたいこと」は多々あります。
例えば表面的な「自大学の良さ」や我々教職員が発信するオフィシャルな情報以外に、入学して初めて分かったこと、高校生当時は気づかなかったこと、さらには高校までとは類が違う「大学で学ぶということ」、「自ら学び続けること」の本質的な意味など。
また在学生にとって自大学は、かけがえのない「私たちの母校」です。伝わっていない良さがあるなら自らの言葉で伝えたい、納得して私たちの大切な母校を進学先に選んでもらいたいと、「自分ごと」の気持ちで発信したいと願う学生が潜在的にいます。そんな在学生たちの「自分ごと」の気持ちにうまくドライブをかけて発信するお手伝いをしながら、学生を「使う」のではなく一緒に「走る」仲間として共創する広報活動であると、学生連携広報を捉えてもらえたら嬉しく思います。
筆者は幸いにも、これまでの経歴の中で学生と連携・並走して広報活動を行う機会を何度か得ることができました。ただし、約12年の大学広報担当者キャリアの中で、常に学生と共創できた訳ではありません。それが叶ったきらめきの時間は、偶然が重なったほんの一瞬でした。
学生の本分はあくまで学ぶことや研究すること。広報担当者が学生と一緒に広報しようと思っても、時と状況が合わなければできません。また広報活動に学生を「使おう」という気持ちで企むこともお勧めしません。ぜひ、その時々の学生の気持ちを主体に...