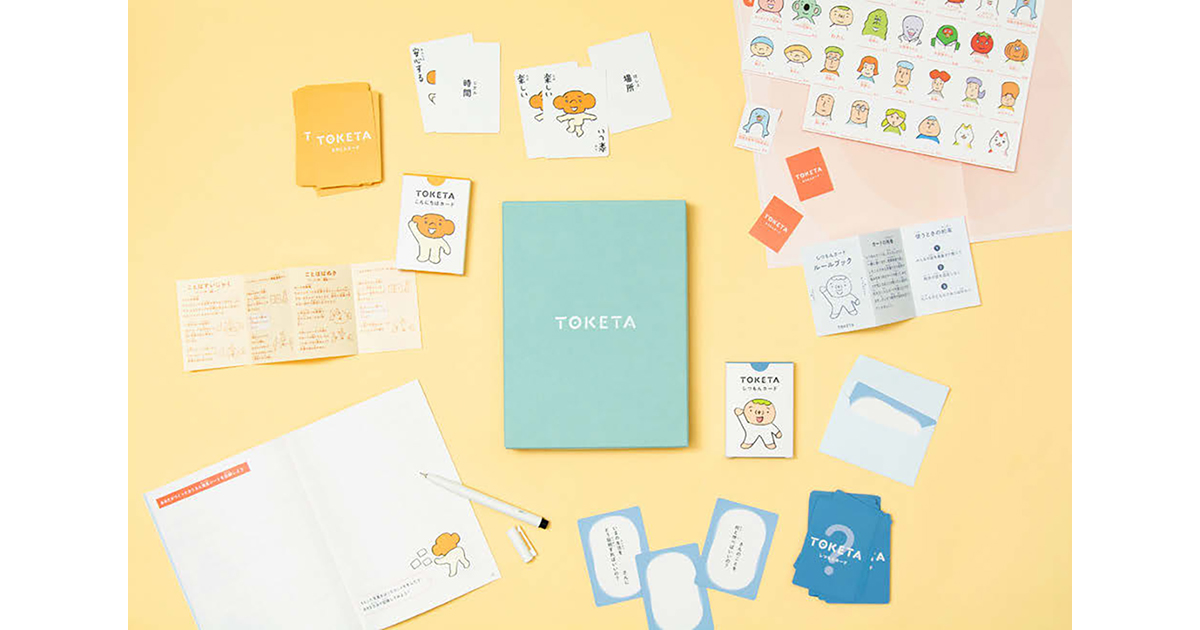まちの情報発信において「ウイルスとの闘いで生まれたニーズ」を見てきた本連載。最終回は、住民や外部のまちのファンが熱を広げていく事例を紹介します。

北海道猿払村職員・新家さんのTwitter
すでに50回以上開催されているプレゼント企画は猿払村の冷凍ホタテやプリン、いちごジャムなどさまざま。新家さんのTwitterアカウント「たくろう┃地方公務員マーケター」をフォローし、企画のツイートをリツイートして当選を待つ仕組みです。当選者がおいしかったと写真つきで投稿し、さらにそれを見た方が猿払村の存在を知り、まちのファンが増え続けています。「猿払村のことを伝えたい思いがあるので、実名のほうが信用性は高いだろうと、村役場で働いていることもプロフィールに記載しています」。
コロナ禍における「まちの情報発信」では、連載1回目や2回目で書いたように、情報を伝える相手である住民との関係づくりが大事だと考えています。テクノロジーの力について3回目で触れましたが、新しいツールを使って情報を伝えていくには、職員が汗をかいて取り組んでいるところを住民に見せることも大事です。またビデオ通話などを使えばコロナ禍でもつながりの幅が広がるのは、4回目で紹介したとおりです。これまでの連載を振り返ると「まちのファンをつくる」がキーワードとして浮かんできます。
まちのファンの熱を広げる
庁内に住民とコミットしていく職員が広報担当者以外にも増えていくと、伝えたい情報が広がりやすくなります。一方で、これまでの自治体の体質や仕組みを考えると、内部の意識を変えるよりも、まちのファンをつくって、住民や外部のまちのファンに熱を広げてもらったほうが良い循環が生まれる印象があります。佐久市のSlackを活用した「リモート市役所」などはまさにそれで、住民とのかかわりが可視化されることで、庁内の職員にも役立つ情報手段なのだと認識され、じわじわと広がっているようです。
ウェブツールを活用して情報を広げ、まちのファンをつくっている例として、北海道猿払村職員の新家拓朗さんの取り組みを紹介します。猿払村の人口は2621人(2022年2月1日時点)ですが、新家さんのTwitterは1万人以上のフォロワーがいて、すでに村の人口を超えています。注目されるようになった背景にはどのようなことがあったのでしょうか。
「コロナ禍になって保育園に通えなくなった子どもたちに向けて何かできないか、という保育士さんからの相談がきっかけでTwitterを活用しました。先生たちが歌って踊る動画を村の公式YouTubeに投稿し、各ご家庭の子どもたちにお届けしました。村の公式Twitterはなかったのですが、個人のアカウントを...