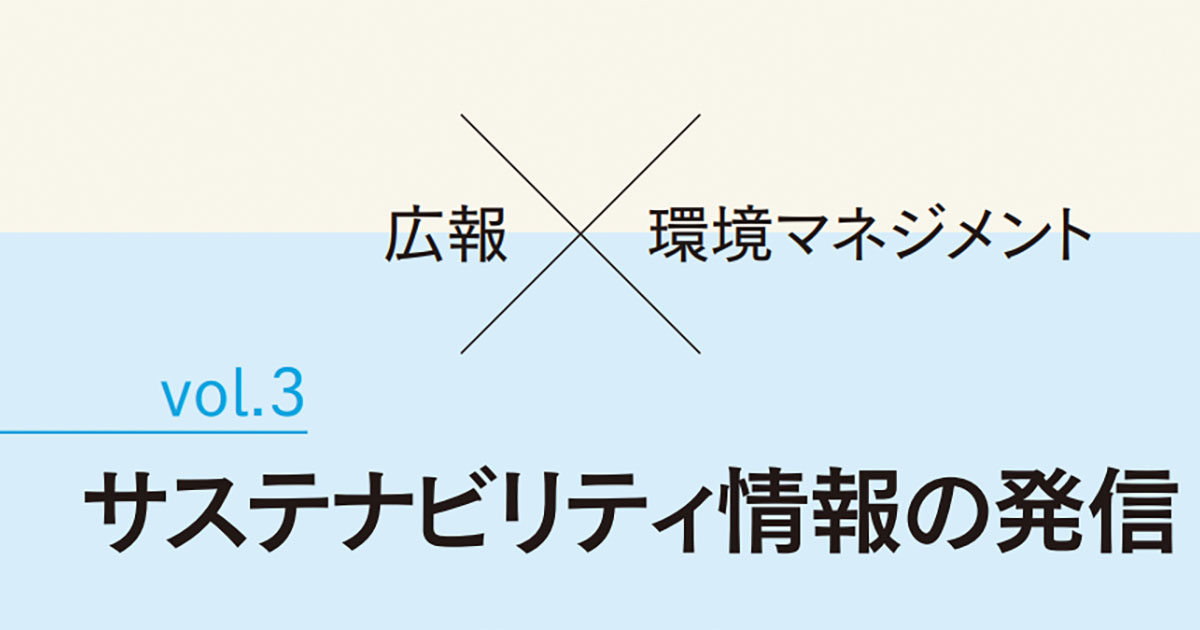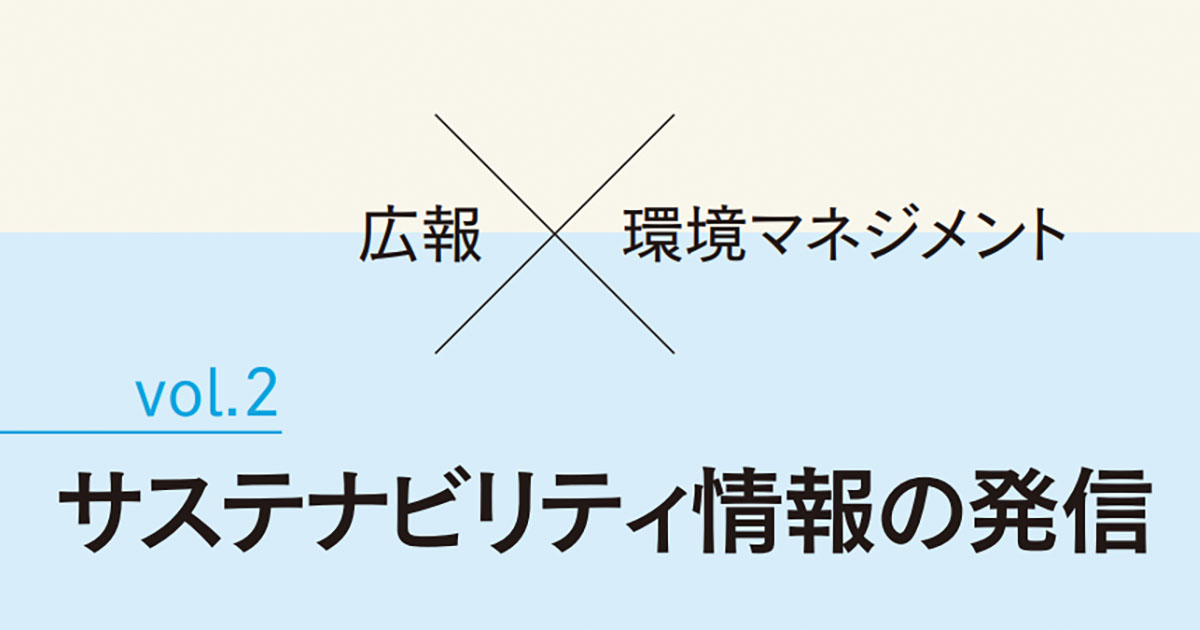環境経営にかかわる動向を解説しながら、企業の本業にサステナビリティを取り込み、コミュニケーションをしていくための考え方を整理します。
サステナビリティへの取り組みは、絶えず新しいテーマを追加しながら発展してきました。近年でも、サーキュラーエコノミーに関連して物質のトレーサビリティへの要求が高まっていたり、ウイグル関連の人権問題への対応が求められたり、話題が尽きません。従業員は「また余計な仕事が増えた」という気持ちや、「自分の仕事がこんな社会問題に関係していたのか」という気持ちなど、様々な感情を抱くことでしょう。
環境や人権に対する配慮のような制約は、もちろんコストの増加要因となる厄介なものです。ただし程度の差はあれ、ライバル企業も同じ状況に直面しています。問題にうまく対処できれば市場への参入障壁にもなりますし、そこで生み出される工夫は新しいイノベーションのきっかけになることもあります。今回は現場の担当者が前向きに、高いモチベーションで新しい問題に取り組むための職場環境のあり方について考えてみましょう。
考え納得する段階が必要
「センスメイキング」(日本語に訳すと意味付け・納得)の考え方をヒントに、社内にサステナビリティの考え方を浸透させていくプロセスについて考えてみましょう。センスメイキングは組織心理学者のカール・ワイクを中心に発展してきた理論であり、先行きが不透明で状況の予測が困難な状況においてイノベーションを導くための条件の一つとなります。
サステナビリティ・マネジメントの文脈では...