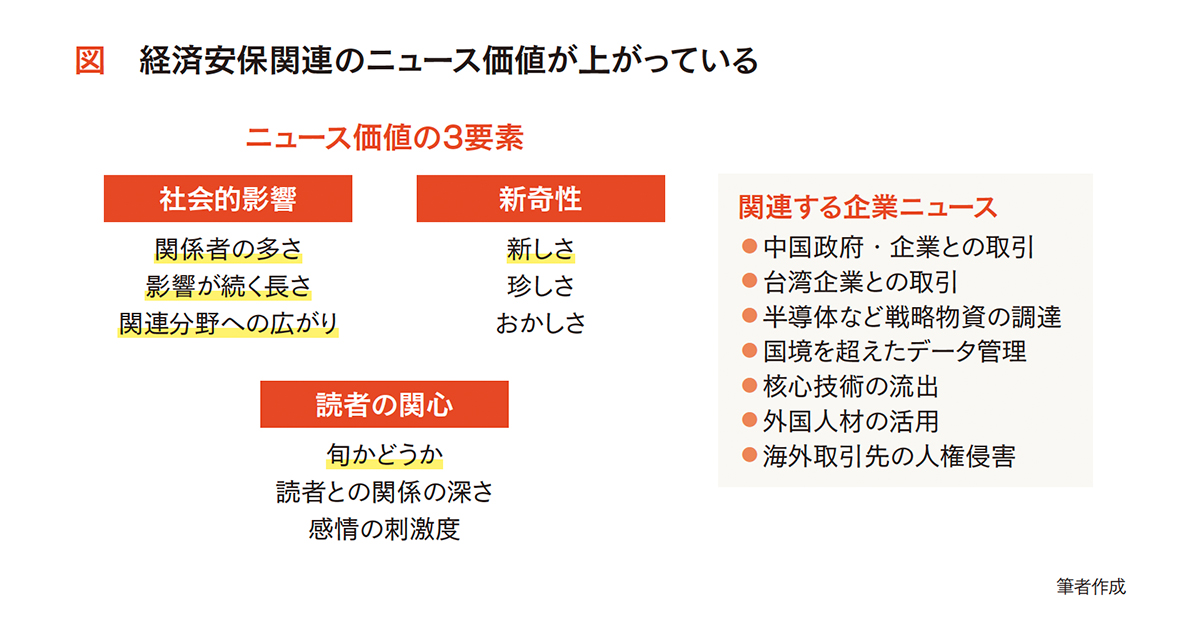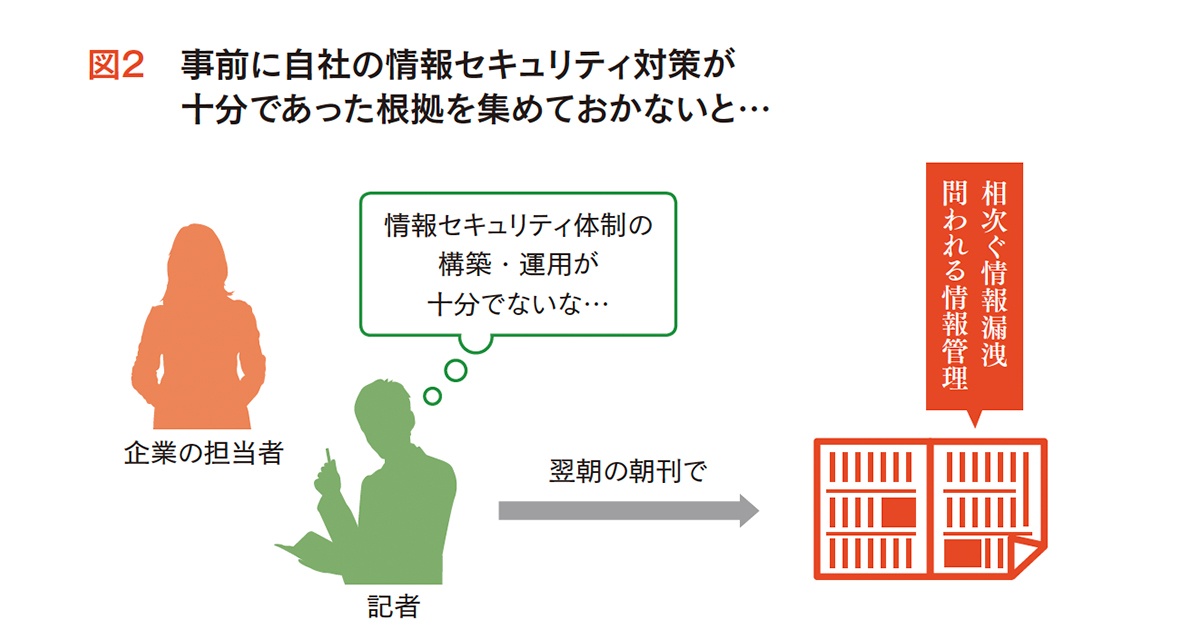コロナで生活者の価値観も変わり、何が炎上の種になるか分からない時代。「うちは大丈夫だから」ではもう通用しない。平時にいかに解像度高く状況を想定できているかが鍵だ。本稿で、ぜひその一助としていただきたい。
監修/佐々木政幸 アズソリューションズ 代表取締役社長
事件の概要
○○○○年○月○日
国内大手電機メーカーの七樹電機に関し、ある日、「七樹電機が検査不正」とする見出しが全国紙の夕刊に載った。三〇年以上にわたり生産した空調設備の検査数値をごまかし納入していたことが詳細に記事にされており、組織的な不正を糾弾している。広報部には問い合わせの電話はなく寝耳に水だった。広報部の固定電話が鳴り始めた⋯⋯。
*この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
クライシス発生!
STEP1 初動対応
発生もしくは事件を把握~3時間以内
初動の3時間で8割が決まってしまう!
事件が発生したら30分以内に対策本部を立ち上げる。また、SNSでの拡散速度は想像以上に速い。ここが成否を分ける。この時点で最悪の事態を想定しておこう。また、平時に予め、社内ナンバー2がすべてを仕切る、などコントロールタワーを決めておくのも必要だ。
初動対応のフロー
❶対策本部を30分以内に設置する
POINT 対策本部のメンバーはどこにいても必ず出席させること(今の時代、リモート出席も可能)。
❷事実関係を迅速に把握する
POINT 平時からあらかじめ役割分担を決めておく。その場合、広報担当を含め部門横断的に配置する(非常時に、「仕事が忙しいから」などとできない言い訳は通用しない)。
情報収集班➡ほんの些細な情報でも必ず共有する
※「こんな情報いらないかなあ」と個人で判断するのが一番危険。個人では絶対に判断させてはならない。
情報収約班➡共有した情報を時系列、内容等、項目毎にまとめていく
情報整理班➡想定問答(Q&A)として作成していく
❸メディア向けにコメントを準備しておく
POINT 平時にあらかじめひな型を作成しておく(各社数+パターンはあるはず)。メディアから必ず求められる。
❹公表手段を検討する
POINT 資料配布で済むのか、説明が必要なのか、を判断(※下記のCOLUMNを参照)。広報なら“最悪”の事態を考えよう。会見を開く場合、オンラインかリアルか。コロナ禍にあってすべてのメディアを会場に入れるわけにはいかない。その場合、入場は「1社〇名まで、会場に入れる最大人数は〇名まで」と決めておく。
STEP2 電話対応
発生2・3時間後~半日後
マスコミから問い合わせが殺到
よく電話口で記者に対して「会見ですべてお話ししますので」という常套句が使われるが、広報が答えることは会社の発言そのもの。電話であっても「逃げ」と思われる姿勢を見せてはいけない。
チェックリスト
☐電話対応時、企業名や対応者名を必ず相手(記者)に告げる
☐「言っていいこと」「言ってはいけないこと」を明確に整理しておく
POINT 前段の情報整理班がまとめた内容をもとに精査しよう。
☐分からないことは「分からない」と回答する
POINT「~だと思います」という憶測を含む回答は危険。その場しのぎで回答せず、確認して折り返す時間を決めて一旦電話を切ろう。約束した時間は必ず守りたい。
☐言えないことは、「言えない」とはっきり言う
POINT ただし、言えない理由をしっかりと説明する。
☐電話は必ずペアで
POINT 電話対応者を1人きりにしてはいけない。回答できずにうろたえていないかを、隣で誰かがサポートしていないと、万が一問題が起きたとき、対応した個人に責任を押し付けてしまいがちに。
☐状況をしっかりと理解し、自分の言葉で回答する
POINT「想定問答」が手元にあると心の支えになるが、棒読みはNG。声に抑揚がなくなり、電話先の記者に見透かされてしまう。求められている情報と開示できる内容を解釈し、自分の言葉で話すこと。
☐想定問答に頼り過ぎない
POINT「法的に問題ない」はお客さまには通用しない。
STEP3 資料作成
電話対応中~半日後
会見まで時間がない!何を発表する?
発表用リリースの作成時間は30分だ。電話対応中から作成担当者を決めて取りかかりたい。「誰に向けた資料なのか」「何のための資料なのか」「被害者の立場に立った内容になっているか」の3点がポイントだ。
チェックリスト
☐発表資料の冒頭で謝罪の文言は記載しているか
☐事案の内容は簡潔に記載しているか
☐時系列は分かりやすいか
☐原因について明確に記載しているか
☐応急措置策(当面の措置)は記載しているか
POINT 被害者やマスコミが最も知りたい部分だ。抜けのないように。