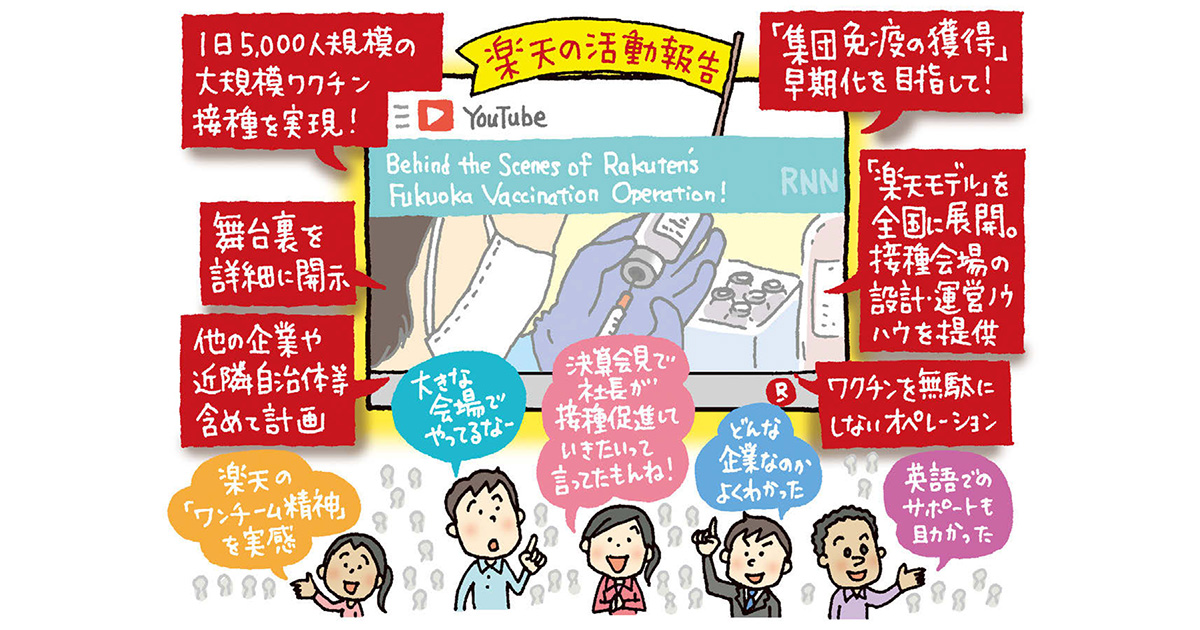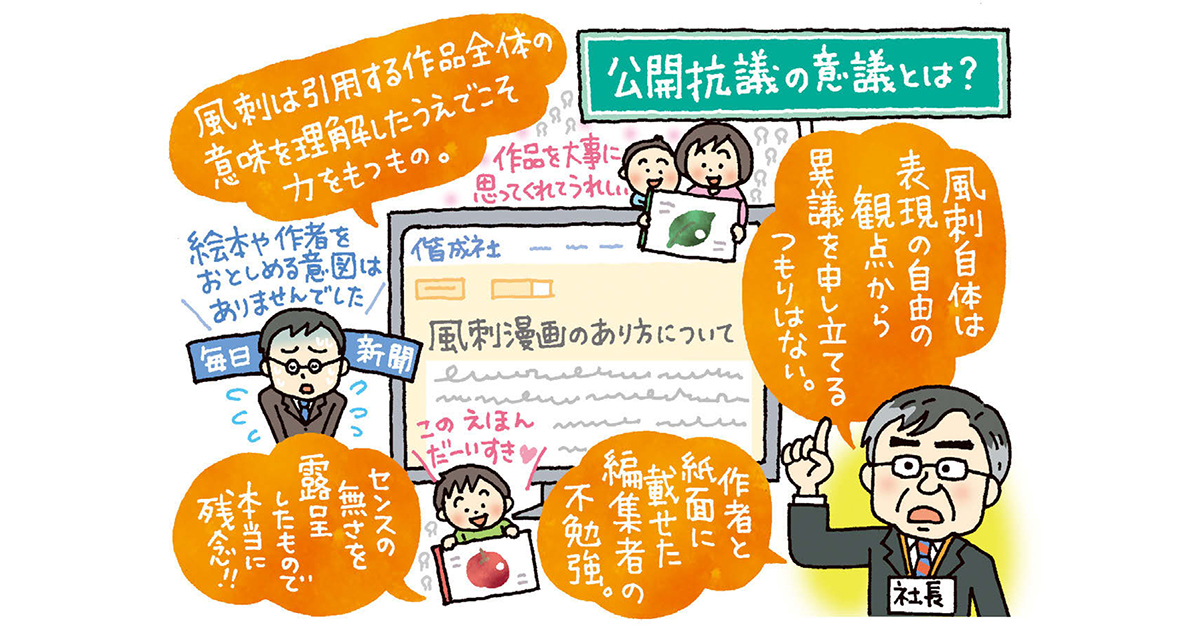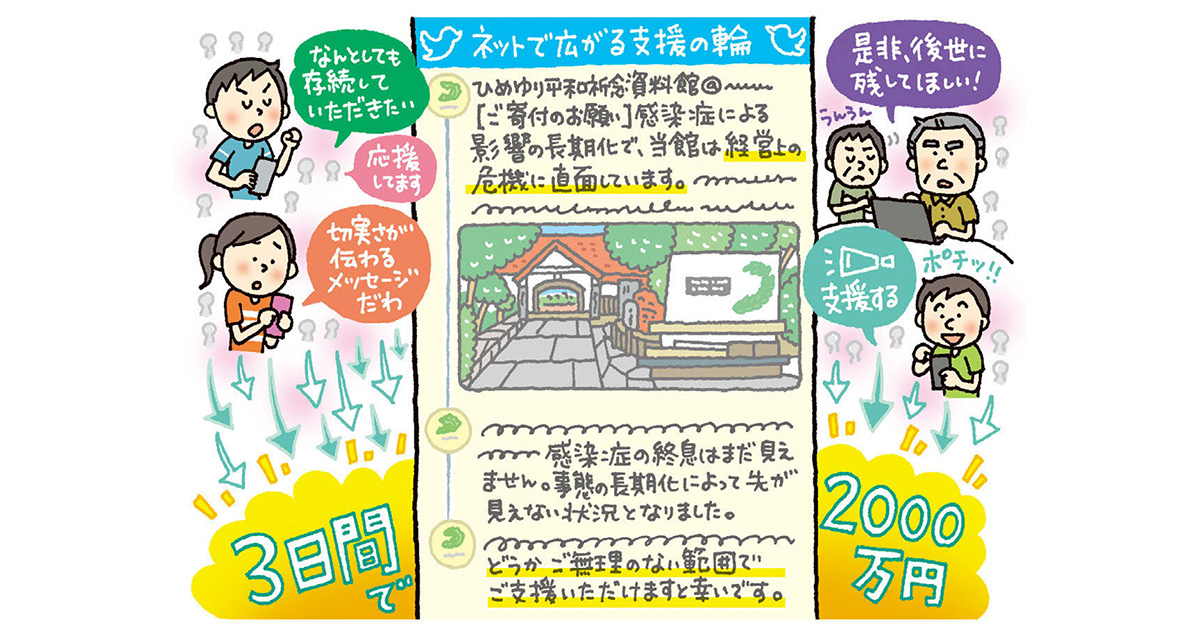ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

イラスト/たむらかずみ
炎上で欠かせない広報の視点
防衛省で予算増を狙い芸能人らインフルエンサーを味方につける目的で「厳しい安全保障環境」を説いて回る取り組みの計画があることが9月に報じられた。
9月、「防衛省、芸能人らインフルエンサー100人に接触計画予算増狙い」と題する記事が出て、ネット上で大きな話題になった。防衛予算の大幅な増額を実現するため、省全体を挙げて「国民に影響を有する防衛・安全保障が専門ではない学者、有識者、メディア関係者」に働きかけるなどと書かれており、反応としては否定的な声が圧倒的に多かった。いわゆる炎上である。
ちょうどその日、社会情報大学院大学で「ICTと広報」という授業があり、危機管理も含めて学んだ受講生たちとこのテーマで議論した。記事から読み解けることや、広報としての対応などを中心に考えを聞いたところ、思いのほか自分自身の注目点以外に思いを巡らせることの難しさを感じた人たちが多かった。そこで今回は、ネット炎上に触れた際に広報の実務者として持っておきたい基本的な観点とアプローチを整理していくことにする。
まずは論点整理を
物事の見方は立場で大きく変わる。授業でまず出たのは、ユーチューバーなどにお金が行くのかと考えて納税者として憤慨したという声だった。広報担当なら炎上を収める対処を考え、予算の担当なら世論の影響に関心が向かうかもしれない。
まずは様々なステークホルダーをイメージして、それぞれの注目しそうなポイントに思いを巡らせたい。多様な視点が最適なコミュニケーションを考える出発点だ。
そして論点整理をする。注目が集まる点それぞれに論点があるだろう。インフルエンサーへの接触はダメなのか?世論工作と理解を得る取り組みの違いは何か?拒否感が強いのはどこか?自分自身の思いが強く感情的になると視野が狭まるので、全くテーマに詳しくない人に状況を説明してみたり、異なる立場や発想を持つ人と意見交換すると整理しやすくなるかもしれない。
先を見通せるように
報道だけではもちろん全ては見えないが、逆に報道をもとに背景を考えるのは、先の展開を予想する練習にもなる。ニュースの裏側にどんな人たちのどんな思惑があるかを想像し、この先、①何が起きるか ②どうしたいか ③そのために何をするか、を考える。
今回の記事は、防衛省による公式発表ではなく内部からのリークがきっかけで出たものだった。広報も即座にコメントしなかったことから組織全体のスタンスを固められなかったことも分かる。組織内の反対派は何に反対なのか。どんな続報が出てくるか⋯⋯。
効果的なコミュニケーションを考えるには、答えを導き出す前に、問いをしっかりとまとめることだ。どれだけ多くの問いを考えられるかが、いざという時に対応力の差につながる。それは日ごろ、取材や会見に際してQ&Aをつくっている人たちなら、きっとよく理解してもらえることと思う。
社会情報大学院大学 特任教授 ビーンスター 代表取締役社会情報大学院大学特任教授。日本広報学会 常任理事。米コロンビア大学院(国際広報)卒。国連機関、ソニーなどでの広報経験を経て独立、ビーンスターを設立。中小企業から国会までを舞台に幅広くコミュニケーションのプロジェクトに取り組む。著書はシリーズ60万部のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。個人の公式サイトはhttp://tsuruno.net/ |