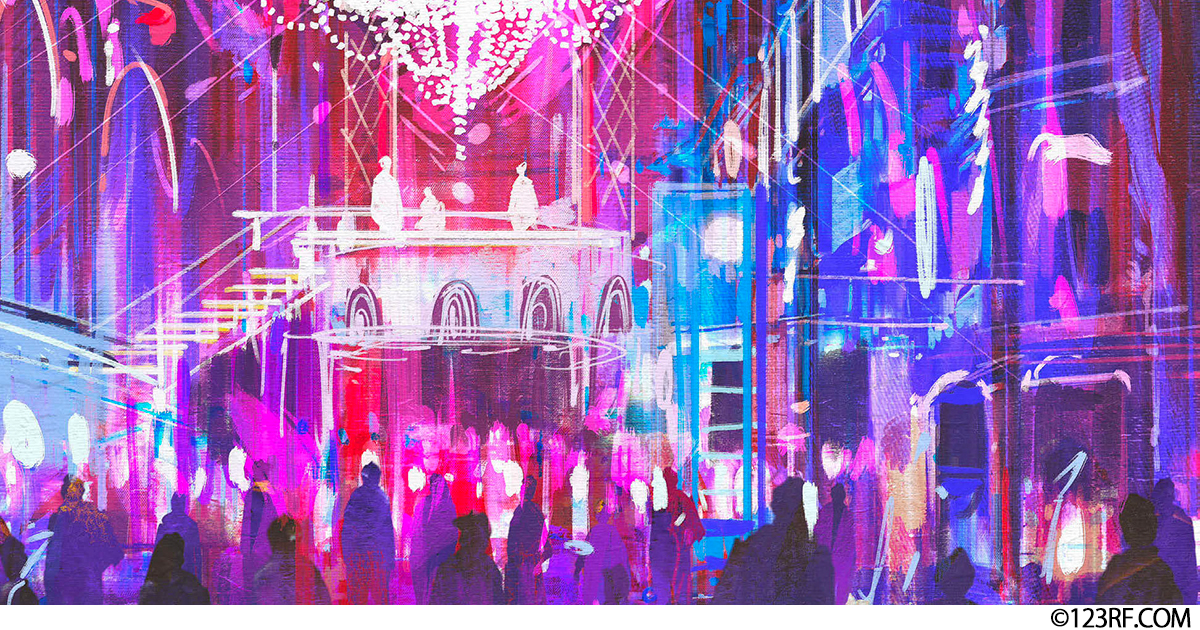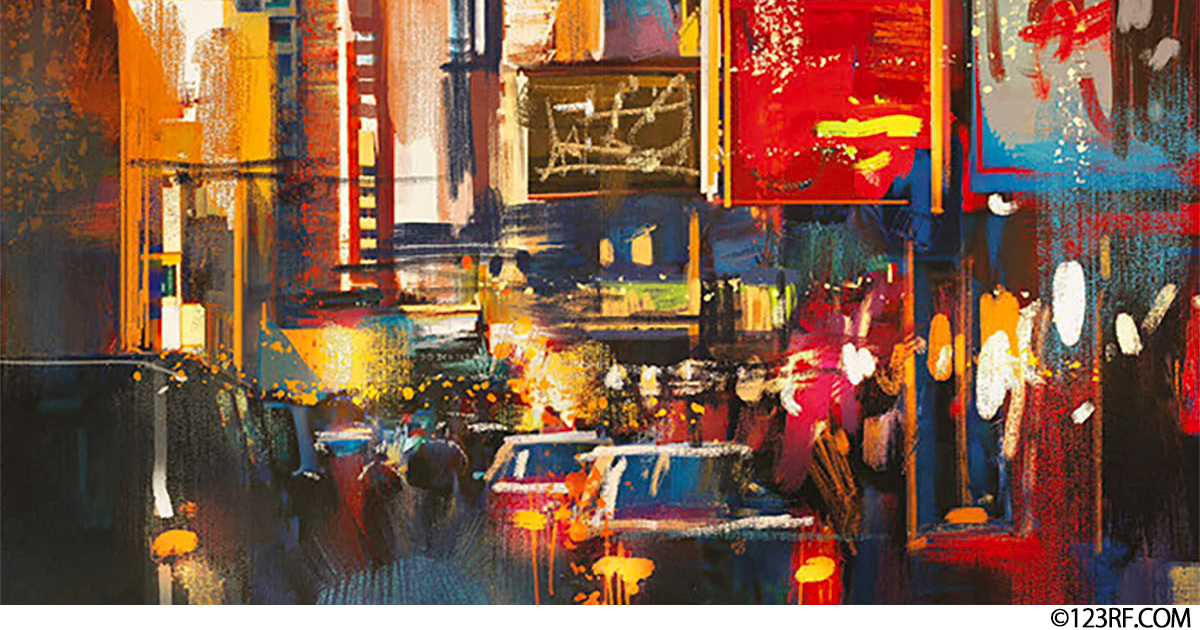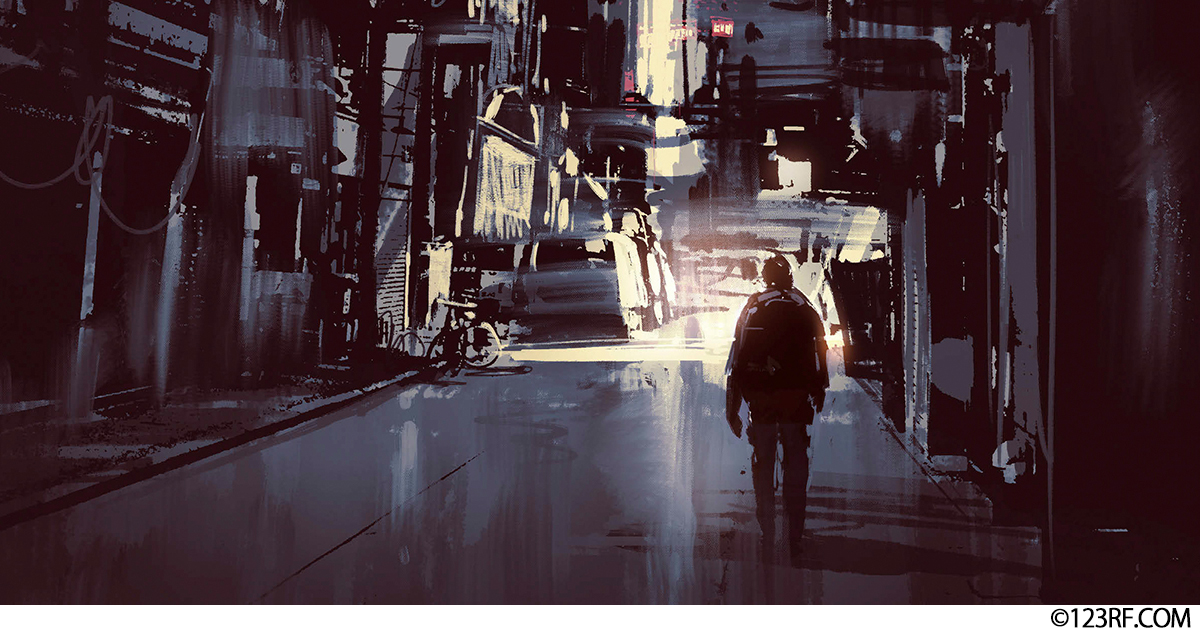【あらすじ】
東証二部上場企業の糧食フーズで広報として働いていた津島千太郎は突然、福岡の子会社である長与食品への出向を命じられる。出向先では経理部長の田谷征四郎から目の敵にされながらも、淡々と仕事をこなして1年半が過ぎた。ある日、人事部の大城恵奈の何気ない一言から、津島は田谷に疑惑を抱くようになる。

©123RF.COM
不都合な“部外者”
「いつもありがとうございます!」キッチンカーの中から弁当が差し出される。アジア料理好きにはたまらない味なので週に二、三回は通っている。公園のベンチで手にした弁当を開ける。「いつも美味しそうだなあ」おもわず笑みがこぼれる。今日はナシゴレンにパクチー山盛り。
「津島さん、ここいいですか」人事部の大城恵奈が声をかけてくる。たしか入社三年目だ。「ああ、どうぞ」「ナシゴレンですか。わたしは弁当です」大城が恥ずかしそうな笑顔をつくる。「手づくりですか。美味しそうですね」「節約です。晩御飯の残りを詰めただけですから」福岡に単身赴任となって一年半。津島千太郎はまだ一度も自炊をしたことがない。
「いつもこちらで食べているんですか?」「そうですね。一人が好きなもので」まだ温かいナシゴレンを頬張りながら軽い冗談のつもりで言ってみる。「福岡は本社とは雰囲気が違うんでしょうね」土地柄なのか会社の雰囲気なのか、真意を汲み取れず「そうですね」と曖昧に返してみた。
「津島さん大変そうだねって、みんなで話しているんです」「みんなで?」「はい、同期の子たちで。三人しかいませんけど」屈託のない笑顔を向けてくる。「大変そうに見えます?」「見えますよ、っていうかいつも経理部長に怒鳴られてますよね。しかも田谷部長、わざと怒鳴ってるし」
経理部長の田谷征四郎は津島が本社から赴任して以来一年半、敵意をむき出しにしている。津島も初めは本社から来た奴に舐められないようにしているのだろうと捉えていた。「みんなで話しているんです。何か都合の悪いことでも隠してるのかな?って」「だから威嚇していると?」津島が疑問で返すと大城が首肯する。「津島さんが広報だったことも関係しているかもねって」若い子たちは想像力がたくましい。
「広報だったことねえ」「広報って会社のこと何でも知ってるイメージがあります。それに新聞記者さんを相手にするんですよね」間違ってはいないが正解でもない。「そんなイメージがあるんですね」「広報って憧れます、なんかこう颯爽としていて」広報に対するイメージが彼女たちの中で勝手に膨らんでいるのだろう。現実を知ったらさぞ落胆するだろうなと考えると、おもわず苦笑いしてしまう。
「あ、すいません。一人で話してしまって」「いえいえ、楽しいランチでした」空になったランチボックスをみせる。「私もです。ありがとうございました」感謝されることは何もしていないが⋯⋯。「私、先に戻ります。一時から会議なんです」弁当箱を片付けた大城が小走りに去っていく。
「都合の悪いことか⋯⋯」大城の言葉がよみがえる。この一年半、津島に対する田谷の態度は異常なほどだった。会議で罵倒され、入力ミスを大声で怒鳴る。津島の部下が決算資料を作成した際に数字の記載ミスをしたときは「お前がしっかりチェックしないからだ!俺に恥をかかせるつもりか」と顔を紅潮させながら迫ってきたこともある。部下のミスは自分の責任でもあるが、作成段階のミスは失敗ではない。修正できたのだからチェック機能が働いている。「まったく出向の身分はいいよな、気楽で」と言われたことさえある。
糧食フーズ。グループ従業員数三九三七名、支店数一〇、子会社七、資本金三一〇億円、グループ売上高は二八〇〇億円、東証二部上場。津島は出向命令が下りるまで五年間、糧食フーズの広報部でメディア対応をしてきた。出向の辞令がでたとき「なぜ自分が」と絶句した。メディア対応でミスをしたわけでなく、仕事の出来が悪いわけではないと自己評価もしていた。メディアのうけもよかったと思っている。「どうして津島さんが出向なんですかね、しかも福岡だなんて」後輩も同じように思っていることに少し救われた。
出向先は福岡市内にある長与食品という子会社だった。配属されたのは経理部経理課長。畑違いもいいところである。赴任して数日間、社内の雰囲気をみていたが“歓迎されていない”空気を感じた。津島をみる周囲の眼が冷たかった。なかでも経理部長の田谷は明らかだった。赴任初日に「よろしくお願いいたします」と挨拶すると「ああ」と不愛想な態度をとられ、以来それは変わっていない。本来なら二人三脚で経理部を支える立場だが、津島が何を訊いても無視されることが多く、肝心なことは津島以外の社員に任せている。
田谷はもちろん部下も経理畑の社員がほとんどで、経理が素人の津島はむしろお荷物扱いされているように思えた。大城は何かに気づいているのではないだろうか。「都合の悪いこと」同じ言葉をつぶやいてみる。自分に知られてはまずいことがある?
長与食品は創業から八〇年。福岡では老舗の食品加工会社といっていい...