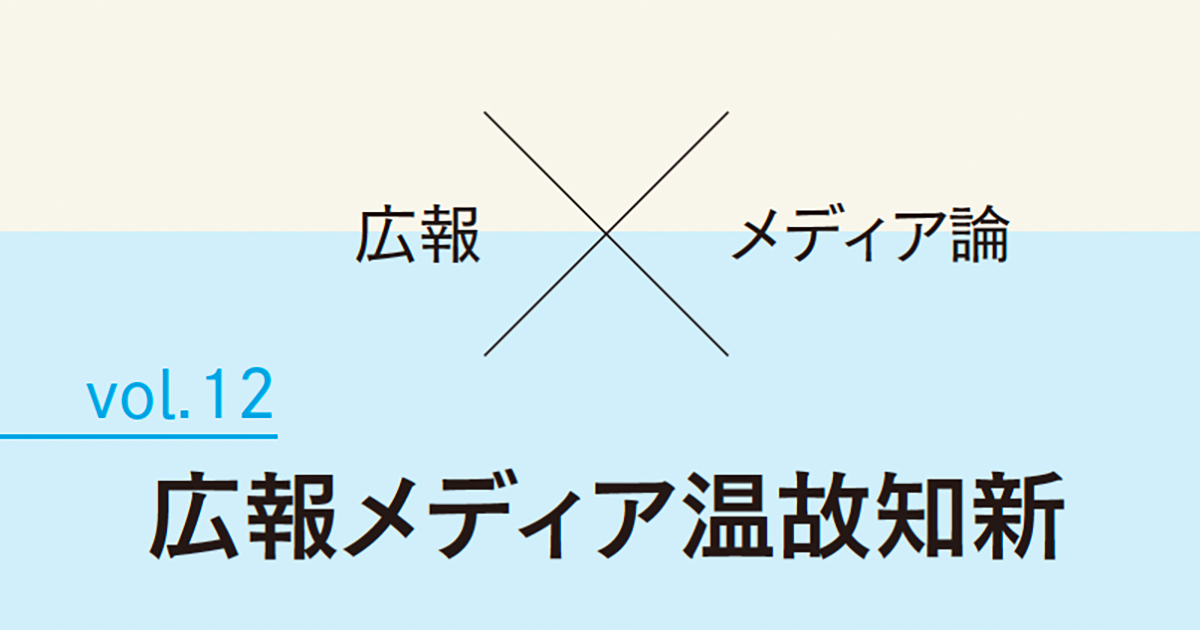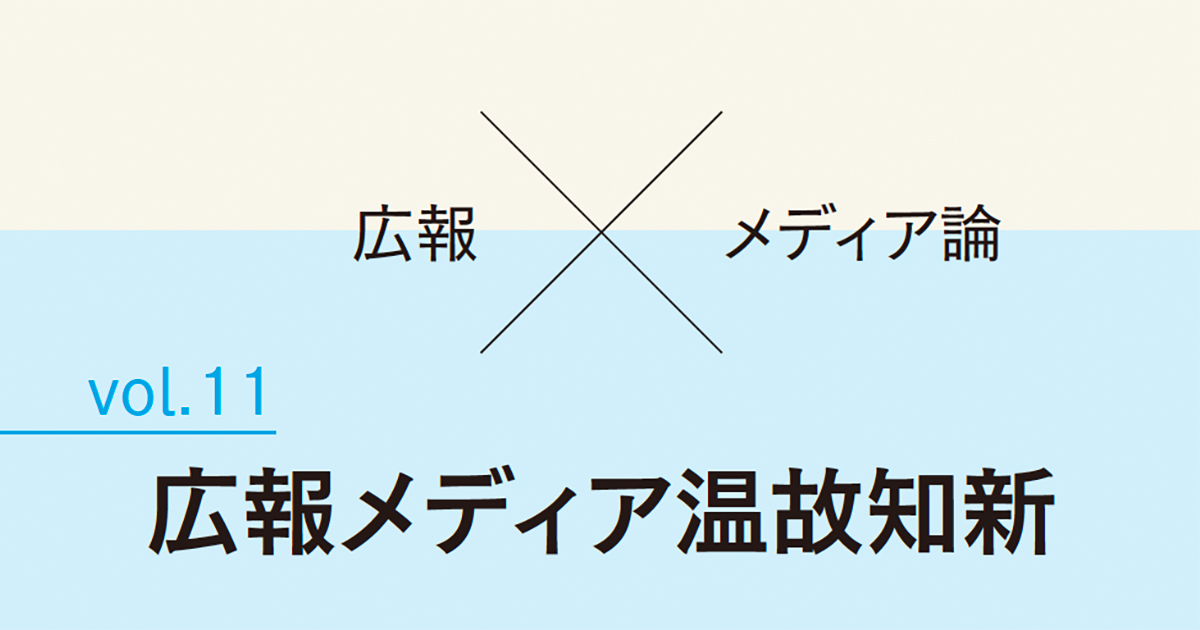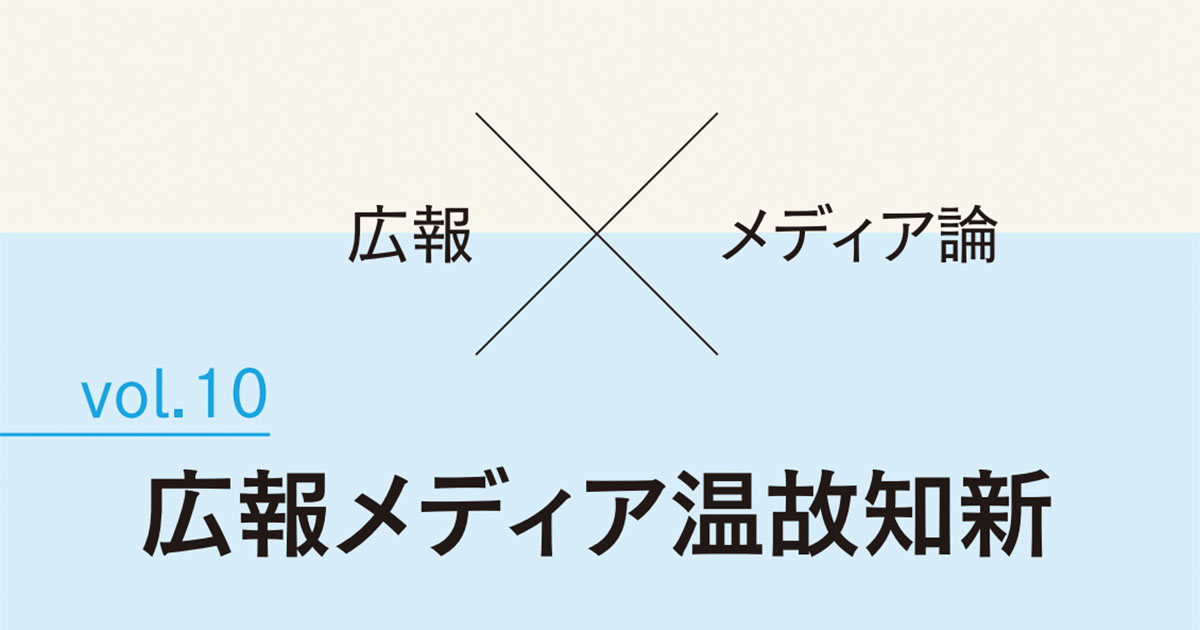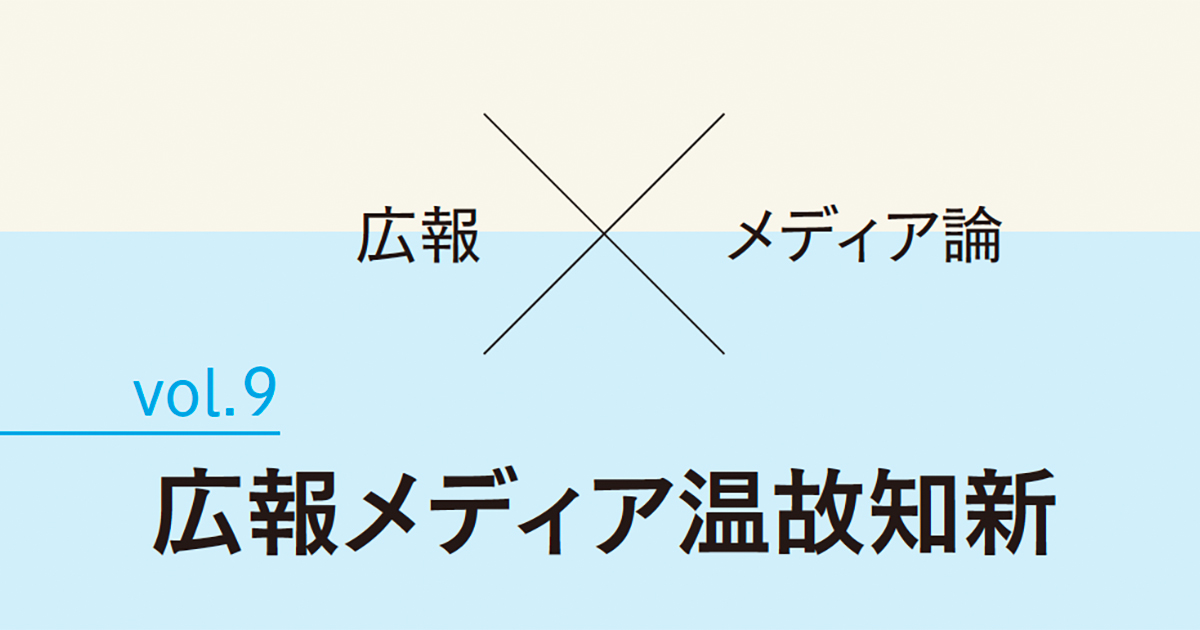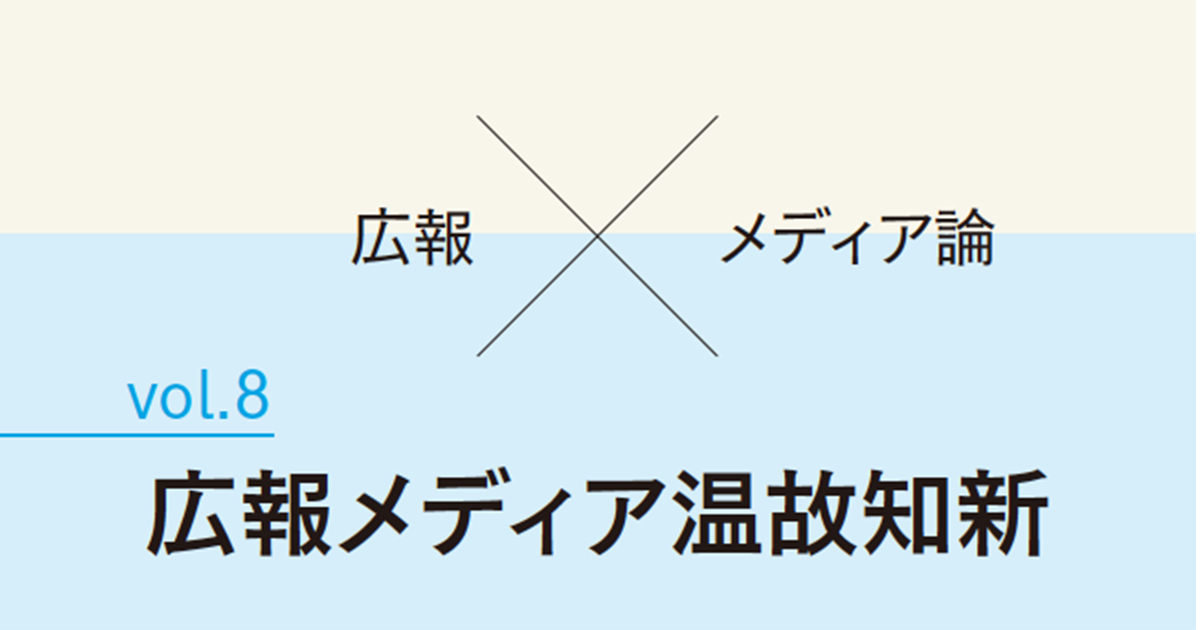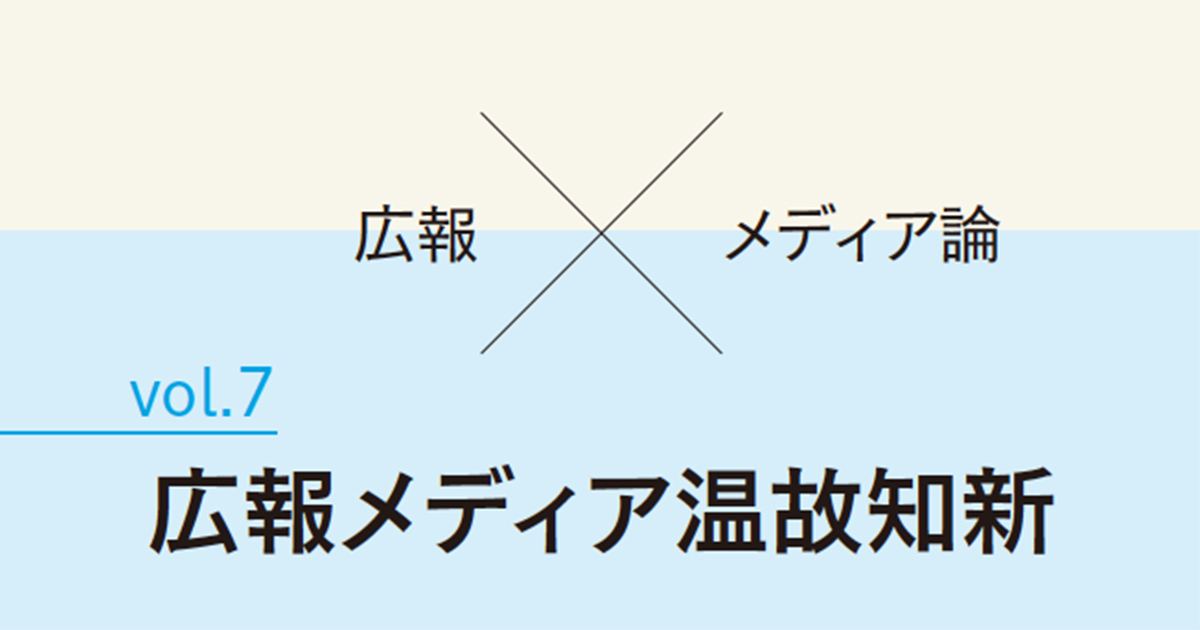広報活動には、様々なメディアが積極的に活用されています。メディア史の観点から考察すると、どのような期待のもと、メディア利用がなされているのか、その本質が見えてきます。
先日、趣味でZINE*1を制作する20代の社会人2人組から取材を受けました。テーマは1990年代リバイバル。筆者が2018年、研究仲間と作った『現代文化への社会学─90年代と「いま」を比較する』を読み、お声がけいただいたようです。
*1 同人誌やミニコミ誌のこと。fanzineの略語。日本ではマンガ・アニメ文化の影響が色濃いものを「同人誌」、その他の雑誌やフライヤーに近いものを「ZINE」と呼んで区別する傾向があります。
繰り返される文化
音楽、アニメ、ファッション⋯⋯90年代リバイバルは多岐にわたりますが、インターネット文化もそのひとつと言えるかもしれません。近年、読者のコミュニティ形成に焦点をあてた「スロージャーナリズム」、批評家の宇野常寛さんが提唱する「遅いインターネット」*2などの取り組みが注目を集めていますが、このような試みは、ウェブというニューメディアが、雑誌のような読み物を志向していた90年代中頃までの状況を彷彿とさせます。
*2 https://slowinternet.jp/
スマートフォンが普及した2010年代を通じて、いわゆるモバイルシフトと相まって、ペーパーレス化が急速に進んだにもかかわらず、若年層の間でZINEが依然として根強い人気があることも、無関係ではないでしょう。
アメリカ西海岸では1988年頃、Macintoshの普及に伴うDTPと相まって、ZINEの制作が流行現象となり、1994年には...