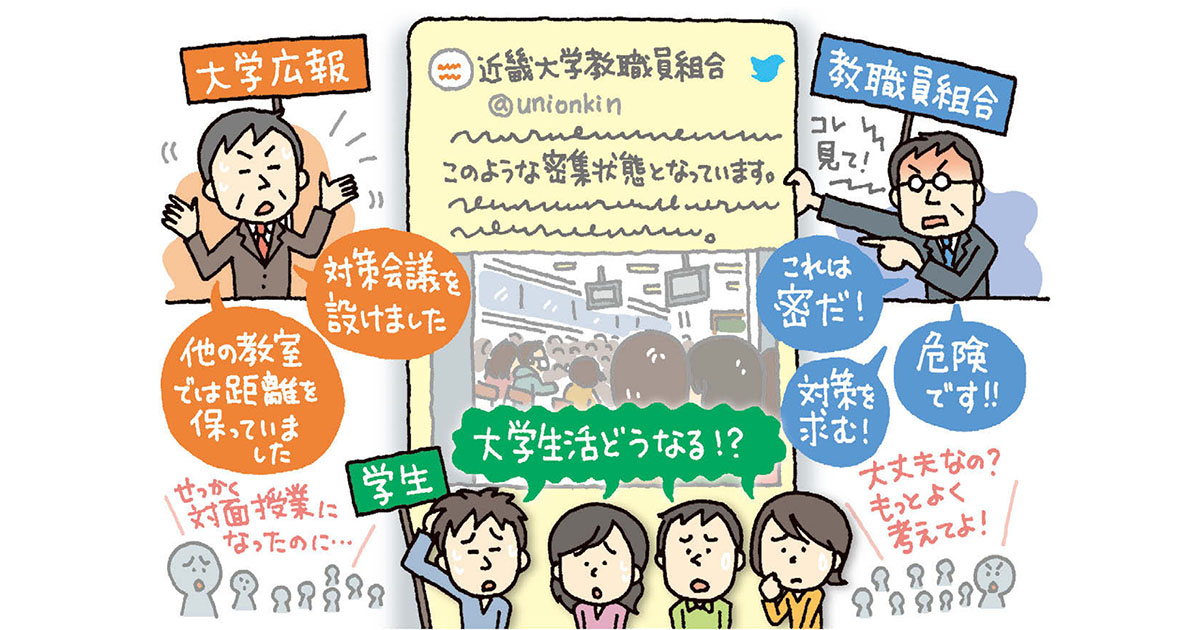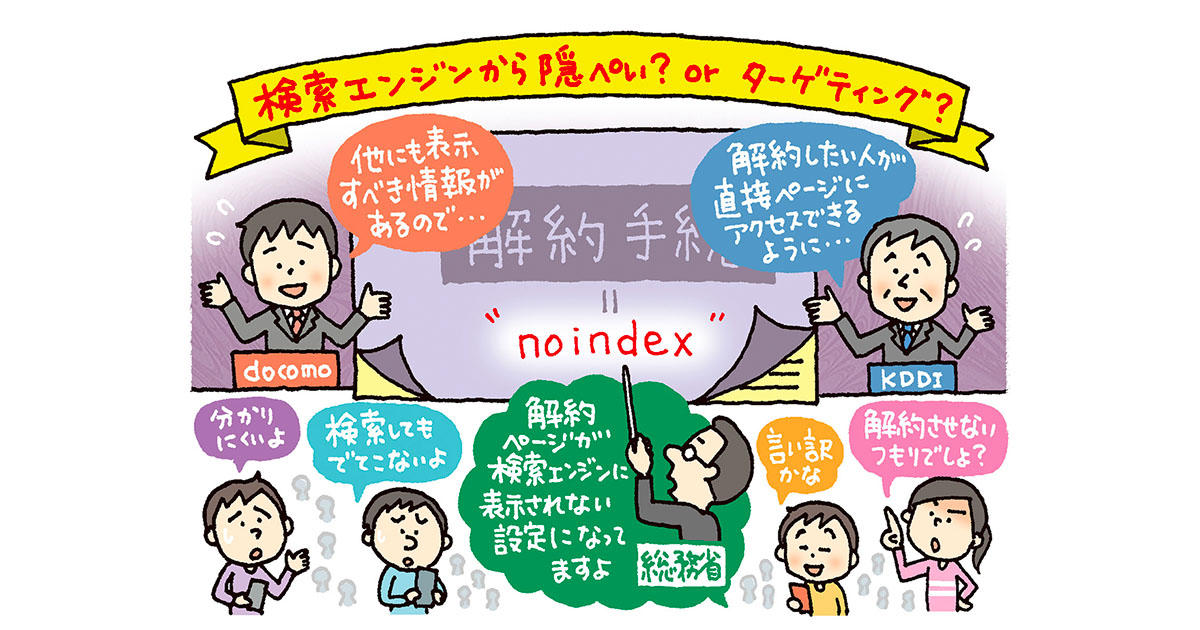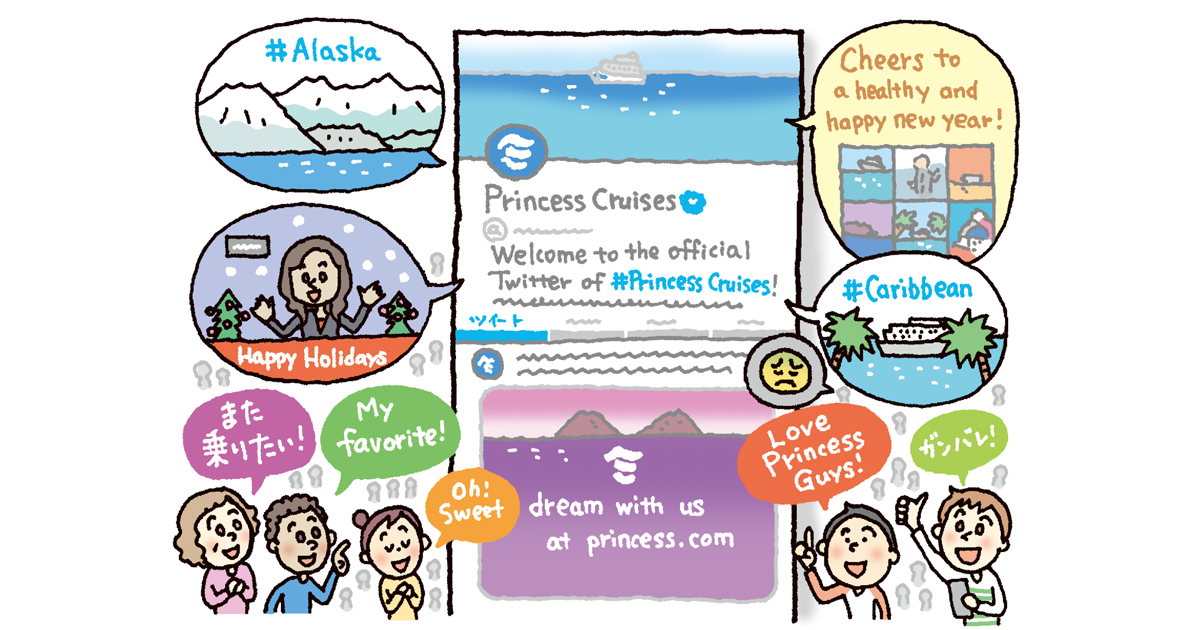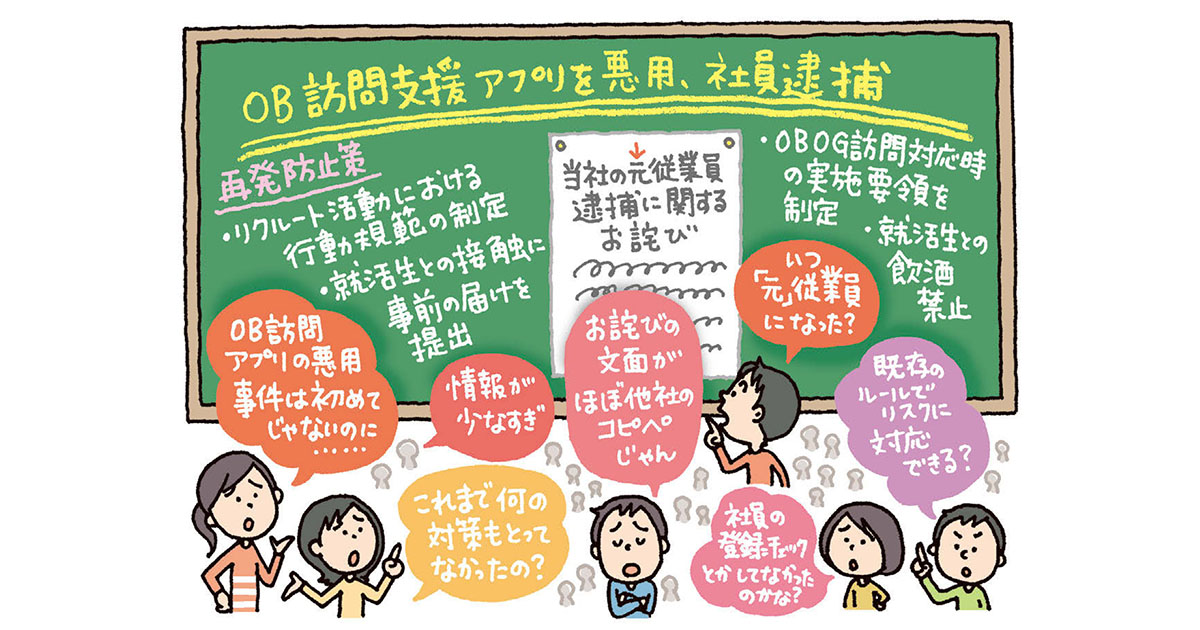ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

イラスト/たむらかずみ
個人への誹謗中傷に共同アクション
4月下旬、複数の英スポーツ競技団体が、選手などに向けられたネット上の誹謗中傷への抗議として「ソーシャルメディア・ボイコット」を表明、SNS使用を一斉に凍結した。
ソーシャルメディア・ボイコットは、まずイングランドサッカー協会が、プレミアリーグや女子スーパーリーグ、プロ選手協会などとともに、選手に向けられる誹謗中傷への抗議として、TwitterやFacebook、Instagramなどの使用を4日間凍結した行動。スコットランドのサッカー協会や男女クラブもこれに賛同した。
テニス、ラグビー、クリケットなどの各競技団体もこの動きに加わり、グローバルな行動へと広がってきている。いずれも、世界中のスポーツ選手やコーチ、審判などに、日々、人種や性別、外見などに関する罵詈雑言が届いており、中には殺害予告も少なくないことを明かしている。それらは決して許容できるものではなく、SNSの運営会社にもこうした誹謗中傷をやめさせるよう行動を呼びかけている。
今回のように競技の垣根を越えてネット上で共通の行動を起こすことは珍しく、それほどまでにこの問題が深刻化していることを窺わせている。
組織が個人を守る問題
5月初旬、米プロバスケットボール協会(NBA)ウィザーズに所属する八村塁選手の弟で、東海大の八村阿蓮選手が、自身と兄に対する人種差別的なメッセージがSNSで届いていることを明らかにした。また同じ頃、水泳の池江璃花子選手が、自身のSNSに東京五輪代表の辞退を求める声が多く寄せられていることを明かし、どちらも注目を集めた。
「無視すればいい」「見なければいい」などと本人の対処を促す声もあるが、自ら死を選ぶほどまで追い詰められるケースも決して少なくはない。冒頭の例を踏まえて、ネット上の誹謗中傷はもはや個人で対処できるレベルではなく、所属組織や業界が力を合わせて個人を守ることが求められている問題だと認識すべきであろう。
相談窓口や対策部門の設置
各競技団体のソーシャルメディア・ボイコット発表文には、相談窓口の連絡先が書かれている。これが恐らく組織的な対策の第一歩になるのではないか。本人がひとりで抱え込んでしまわないようにするということだ。
フジテレビは4月末、SNS上でのリスク管理や炎上時の対応をする「SNS対策部」を新設したと発表した。2020年、リアリティ番組『テラスハウス』の出演者がネット上の誹謗中傷で命を絶った問題で、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送人権委員会が3月末に「出演者の精神的な健康状態に対する配慮に欠けていた」などとして「放送倫理上の問題があった」と認定していた。
SNS対策部は、SNS上での炎上や誹謗中傷を防ぐための番組制作におけるリスク管理や炎上時の対応、弁護士や精神科医など専門家による出演者・スタッフへのケア体制の構築などにあたるという。
大切な仲間をネット上でも孤立させないような対策は取られているか?組織内の対策とともに対外的な連携も積極的に模索していきたい。
社会情報大学院大学 特任教授 ビーンスター 代表取締役社会情報大学院大学特任教授。米コロンビア大学院(国際広報)卒。国連機関、ソニーなどでの広報経験を経て独立、ビーンスターを設立。中小企業から国会までを舞台に幅広くコミュニケーションのプロジェクトに取り組む。著書はシリーズ60万部のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。個人の公式サイトはhttp://tsuruno.net/ |