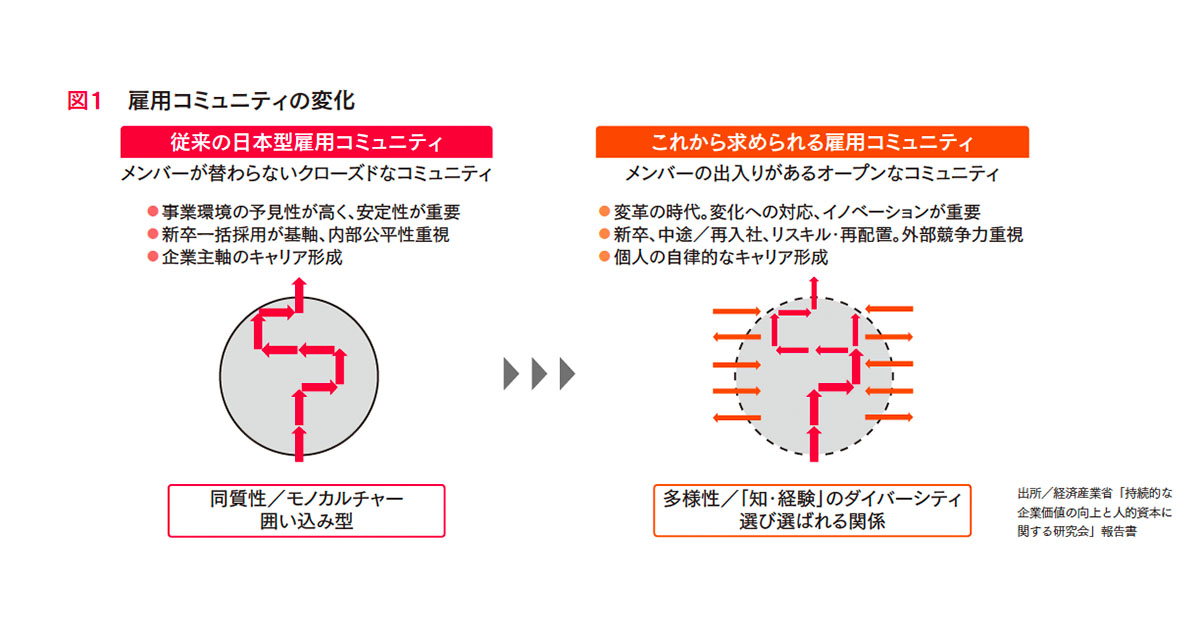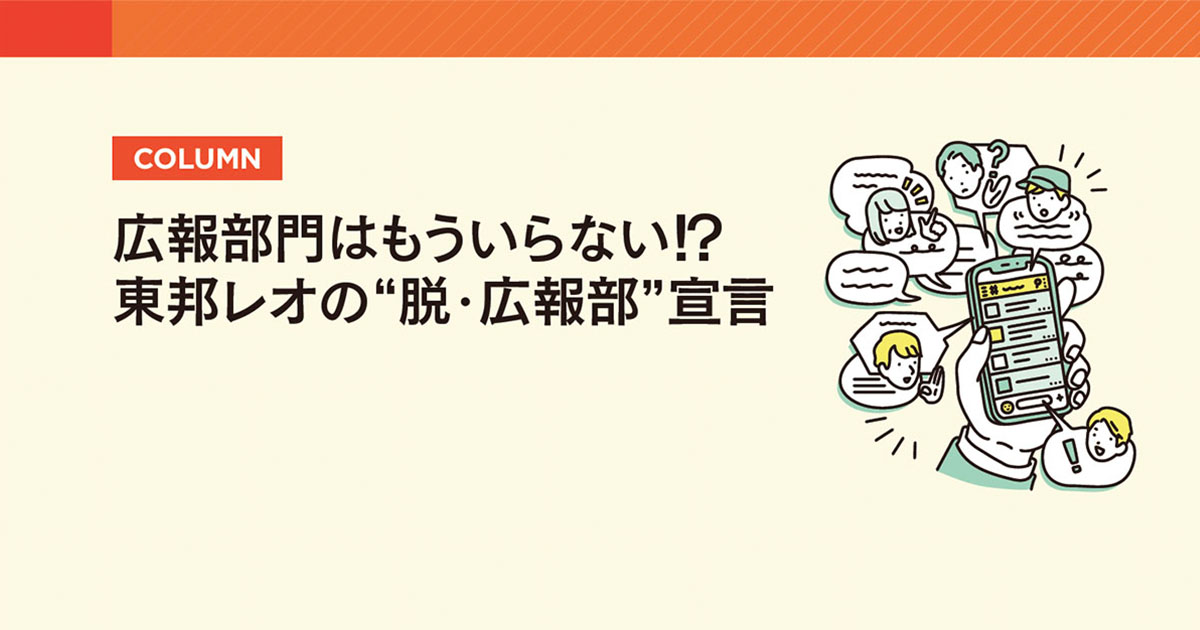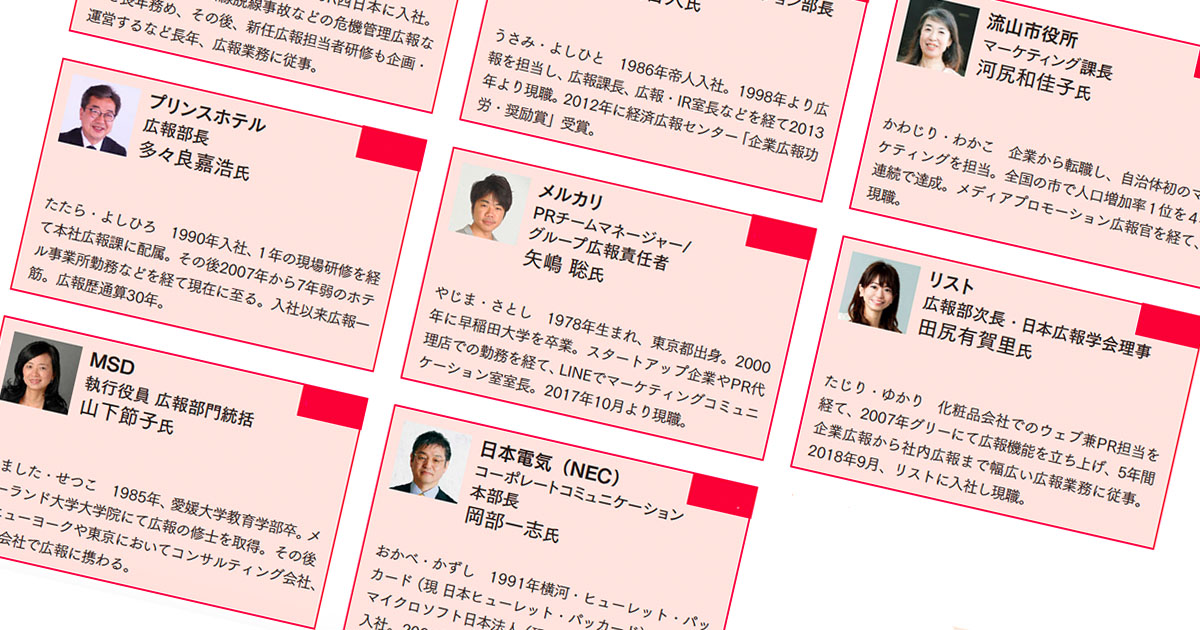アテネ五輪体操男子団体、トリノ五輪の荒川静香選手金メダル獲得の名実況で知られ、その言葉には聞き手の共感を呼ぶ力がある。38年以上、言葉でスポーツを“伝える”ことに取り組んだプロが行きついた極意と広報観とは?

刈屋富士雄(かりや・ふじお)氏
1960年生まれ。1983年NHKに入局。主に大相撲やオリンピック中継など、計約28競技のスポーツ中継・解説を担当。2004年アテネ夏季五輪の体操男子団体決勝の日本金メダル、2006年トリノ冬季五輪のフィギュアスケート競技で荒川静香選手が金メダルを取った際の実況はいずれも名実況と評されている。2020年4月NHKを定年退職。翌5月から立飛ホールディングス スポーツプロデューサー。アマチュア相撲の国際大会実施など次世代に向けたスポーツ支援、広報に力を入れている。
社会に自社の価値をいかに伝えるか。近年、広報の「伝える力」の重要性は増すばかりだ。SDGsの取り組みをはじめ、企業は社会的な価値を積極的に開示する傾向にある。ただし新事業、商品・サービスの社会的な意義についての発信も、他社の追随ではニュース性や共感を見出すことは難しい。加えて次々登場する新たなリスクに対しては、タイミングを逃さない迅速な危機管理広報が求められる。
今回、広報の本質である「伝える力」について、元NHKスポーツ実況アナウンサー、刈屋富士雄氏に話を聞いた。
言葉自体は重要ではない
刈屋氏といえば、2004年アテネ五輪体操男子団体で日本の28年ぶりの金メダル獲得の際、実況を務めた。「伸身の新月面が描く放物線は、栄光への架け橋だ」「体操ニッポン、日はまた昇りました」というセリフを耳にした人も多いだろう。今尚、テレビ史に残る名実況と評されている。
そんな言葉を扱うプロは、伝えることについて「重要なのは、言葉自体ではない。伝わったかどうか」と明言する。「日本語の文法はぐちゃぐちゃでも、たった一言でも、最終的に聞き手に“伝わった”かどうか。結局それがすべてです」(刈屋氏)。
では、“伝わる”ために何が大切か。刈屋氏は「タイミング」と「言葉の選択」だと話す。
まずタイミング。「刻々と展開が移り変わるスポーツの世界では視聴者が実況に耳を傾けるのは一瞬。その瞬間を逃さない反射神経と、視聴者側に寄り添った冷静な判断が必要です」。