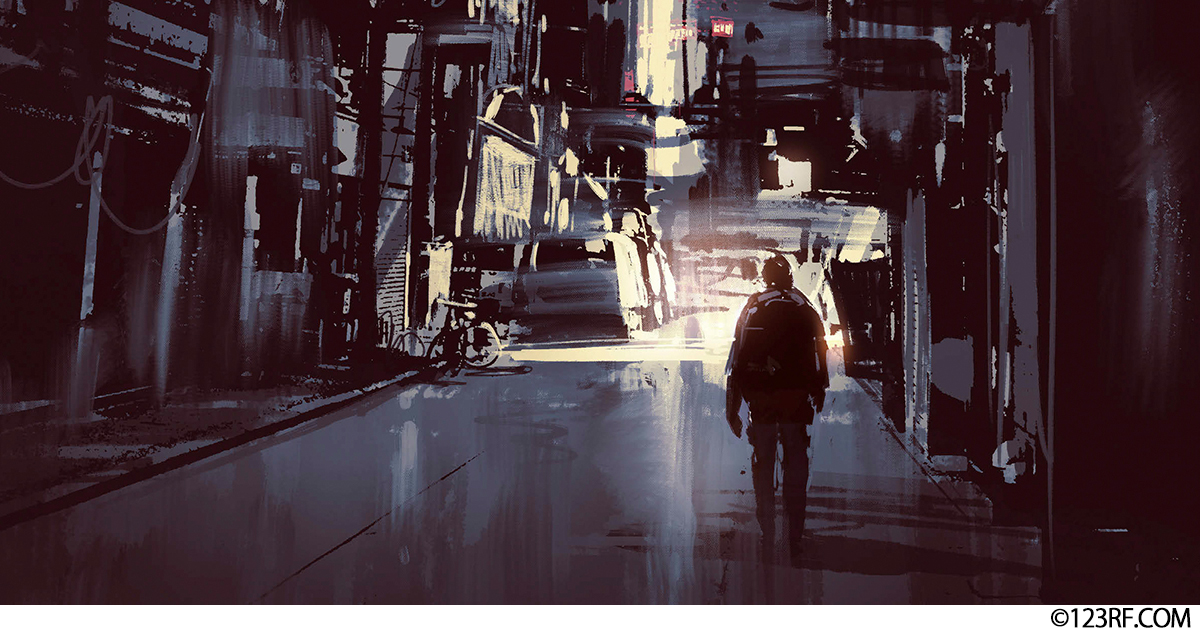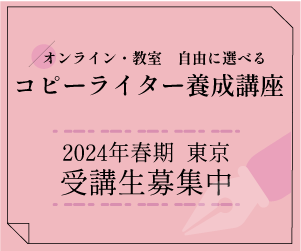【あらすじ】
高校時代の春休みに旅した北海道で、星空の美しさに感動して映像作家となった高峯江紀。仕事にも恵まれ、観た人たちに感動してもらえる作品を撮り続けることが自分にできる唯一のことだと信じてやってきた。そんなある日、助手である片岡力から「取り返しのつかないことをしてしまった」と告白される。
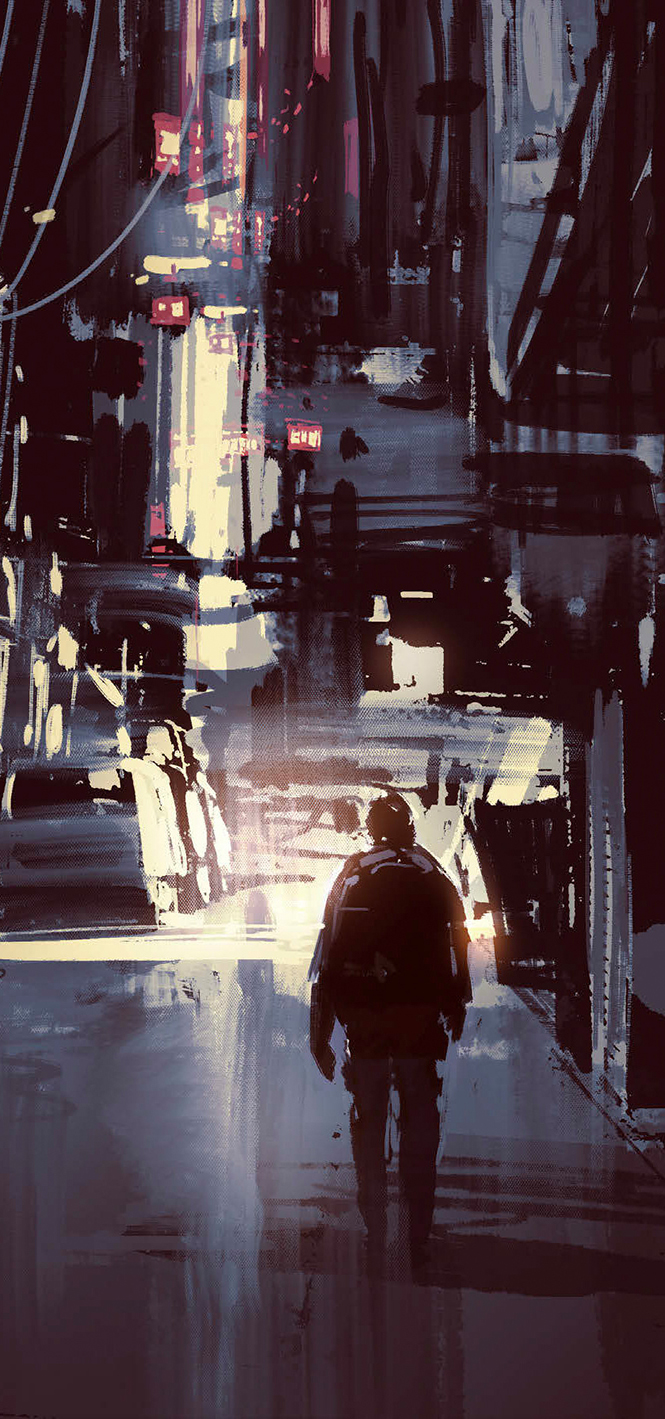
©123RF.COM
自分にできる唯一のこと
高峯江紀は悩んでいた。一日も早く実家を出たかった。植木職人の父の背中を見ると誇らしい一方、自分の不甲斐なさを痛感する。将来を悲観しているわけではないが、先の見えないトンネルに入り込んでいるようで焦りばかりが募った。
「コウキ、継ごうなんて思うなよ」「継がないよ」父親の言葉に即座に反応したが口から出る言葉は内心とは真逆だ。江紀は父親の笑った顔を見た記憶がなかった。褒められた記憶もない。その父親が手酌でビールを注ぎながら「そうか」とだけ言うと柔和な笑みを浮かべた。
「大学はどこに行くんだい。そろそろ受験勉強もしないとね」キッチンに立つ母親が父親の言葉を継ぐ。大学に入ればどこかの企業に就職して安定した生活が送れる。高校二年の息子を持つ母親の想いは江紀にも分かっている。だが⋯⋯やりたいことが見つからない。「ごちそうさま」茶碗をシンクにおく。母親の不満そうな視線から逃げるように階段を上がり、自室のドアを閉めた。
「高峯さん、お願いします」スタッフが呼びにくる。「すぐ行きます」控室の扉を開けると日差しが眩しかった。前日まで降り続いた雨がやみ、キャンバスを青く染めたような空が広がっている。宮古島の海はいつ見ても美しい。
「橋を中心にしたカットでお願いします」撮影監督が指示する。宮古島市の北部にある宮古島と池間島に架かる池間大橋は、沖縄でも上位に入る美しいロケーションとして知られる。「了解です」橋を背にヴァイオリニストの二人が立っている。華やかなドレスが似合う姉妹だった。宮古島の海の美しさは“宮古島ブルー”と言われるが、この日はまさにその色だった。
「では、いきまーす」スタッフが声を張り上げる。「ドローンから入ります」高峯が告げると助手がスイッチを入れる。ドローンは風と戯れるように高度を上げていく。合図とともにヴァイオリンの音色が周囲を包んでいく。「オッケー!」厳しい目つきで画面をにらんでいた監督の表情が緩む。「いいですね」右手の親指を立てる。「ありがとうございます」高峯も頬が緩む。
自動車メーカーのコマーシャル撮影は今回が初めてだった。高校卒業後、映像の専門学校に進学してカメラの基本を学んだ。専門学校に入るまでカメラを手にしたことなどなかった。高校三年になる直前の春休み、アルバイトで稼いだ金で北海道を旅した。目的があったわけではない。行けば自分を変えられるんじゃないかと思っただけだ。
「急に変われるわけないよな」二泊目に泊まった民宿の部屋の窓から空を眺めて呟いた。光がちりばめられた星空が降ってくるようだった。見たことのない美しさに感動した。観た人が感動する映像を発信できたら⋯⋯。この世界に入った原点だった。
「オールオッケーです!」レンズをのぞく高峯に撮影監督から声がかかる。高峯がフーッと息を吐く。「素晴らしい映像でしたよ」監督が笑顔で言う。もっといい画が撮れたのではないかという欲が生まれるが、ありがとうございますという言葉とともにのみ込む。横浜に戻ればすぐに新しい撮影が待っている。気持ちの切り替えは大切だ。前の仕事の感情を引きずったまま現場に行けば、いい画は撮れない。
機材の片付けをしている助手の片岡力に声をかける。「明後日の撮影、許可は取ってあるよな」「大丈夫です!」軽い言葉に一瞬不安を覚えたが、“こんなに綺麗だったんだなあ”レンズ越しにのぞいていた海の青さが視界に入ると、不安よりも感動が勝った。「よし、戻ろう」声をかけると車のイグニッションボタンを押した。
デスクトップのモニターに宮古島の美しい海が広がっている。「まだ一カ月前か」時間の感覚とは曖昧なもので、もっと昔のように感じる。宮古島は空港と撮影場所を往復しただけだが、それでも海を見たときの感動は残っていた。自分の感動をコマーシャルでどれだけ伝えられるか。モニターをにらみながら高峯は考えている。
“どんな仕事でも感動がなければいい仕事などできない”二十五年前、星空を見たときの感動を忘れたことはない。宮古島から戻った二日後の撮影も、心の中で感動をテーマに撮り続けた。横浜市内にあるイタリアンレストラン。食材からはじまり皿に盛りつけられた料理の数々。コロナ禍でも果敢にオープンした店だった。
手を抜こうと思えば抜けた。適当に撮影しても喜んでもらえただろう。だが、手は抜かない。相手の人生がかかっている。二十五年前の自分には戻りたくない。「素晴らしい映像ですね。自分の店じゃないみたいです」オーナーシェフが破顔する。高峯はこの瞬間が好きだった。お金がなければ食べることはできないが、お金のためにレンズをのぞきこんでいるわけではない。相手の笑顔のために撮影しているのである。
「高峯さん、本当にありがとうございます」オーナーシェフが両手を差し出してくる。「こちらこそ撮影させていただき光栄です」差し出した両手に力を込める。店の奥で助手の片岡が機材を片付けていた。ゴツッ。床に何かがぶつかる音がした。「片岡...