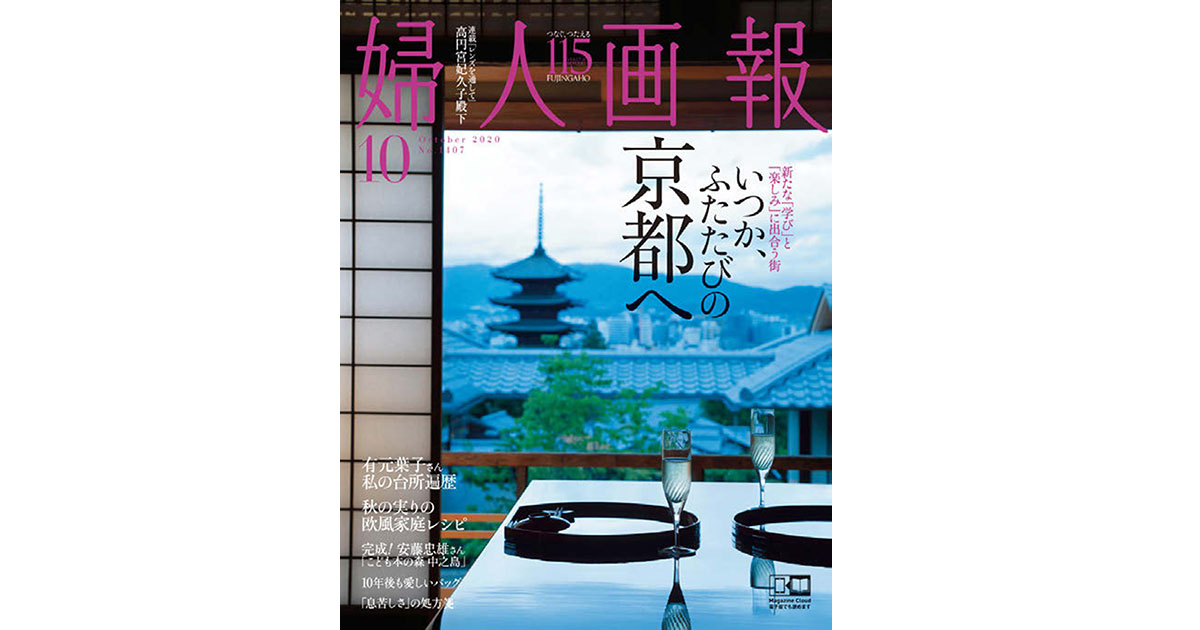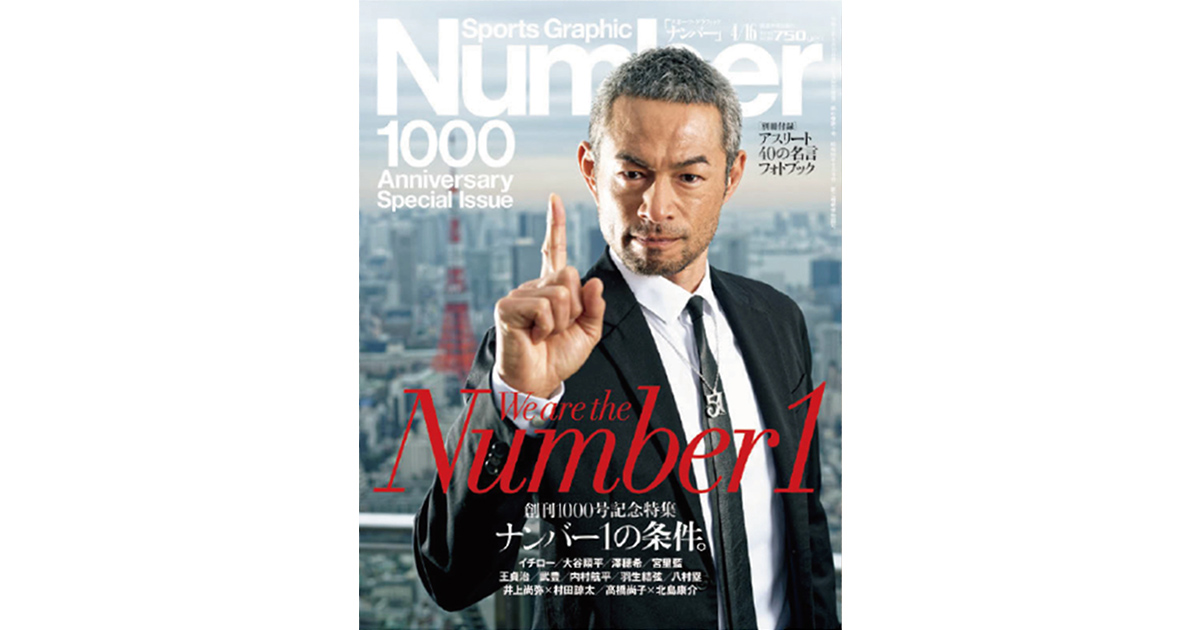報道対応を担当するPRパーソンにとって、気になるのがメディアの裏側。企業取材のスタンスや、プロデューサーや編集長の考えに迫ります。
| ハースト婦人画報社『婦人画報』編集部DATA | |
|---|---|

『婦人画報』2020年12月号 |
|
1905年、初代編集長の国木田独歩が創刊した『婦人画報』。今年で創刊115周年を迎えた、ハイカルチャー婦人誌の草分け的存在だ。創刊当時から「日本のよきヒト・モノ・コト」として、ファッションや旅、グルメなどの選りすぐりの情報を発信し続けてきた。メインの読者層は、ハイクラスな首都圏在住の50代前後の女性。定期購読が売上部数の約40%を占めるという。
いち早く「京都」特集で好調
日本で最も歴史ある女性誌を束ねるのは、編集長の富川匡子氏。2017年に編集長に就いてから、編集方針として3本の柱を掲げている。「1つ目は、旬のコンテンツで、読者に寄り添う内容であること。2つ目は、日本の最高峰で、選りすぐりのものをお伝えすること。3つ目は、日本の伝統やスピリットを次世代にきちんと伝えていくことです」。
情報収集力や誌面レイアウトのクリエイティビティなど、編集者はあらゆる能力が試される。しかし、同誌編集者に特に求められるのが企画力だ、と話す富川氏。グルメや旅、皇室などの安定した人気を誇る企画も多いが、「星の数ほどあるアイデアの中から、どのように時勢や読者のニーズに合ったものを選び抜いていくか。まさに編集者のセンスが問われていると思います」(富川氏)。
展覧会や周年イベントに合わせるため、1年前から企画が決まっていることも多いというが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響は大きかった。富川氏は「前々から決めておいたものは1度見直して、今のニーズに合うように特集を新たに組み立てています」と話す。
2020年9月号(8月1日発売)では、人気企画のひとつ「お取り寄せ」をコロナ禍での動きに合わせ、アップデートして特集。新たにお取り寄せを始めた名店や、医療従事者への支援をしたシェフの取り組みなどを紹介した。「食や旅は、人間の普遍的なテーマです。それを時代に合わせてどのように“調理していくか”が重要です」と富川氏。
コロナ禍で発売された号は、順調に販売部数を伸ばしている。在宅時間が長くなり、じっくり雑誌を読む人が増加したことも要因のひとつだが、富川氏は...