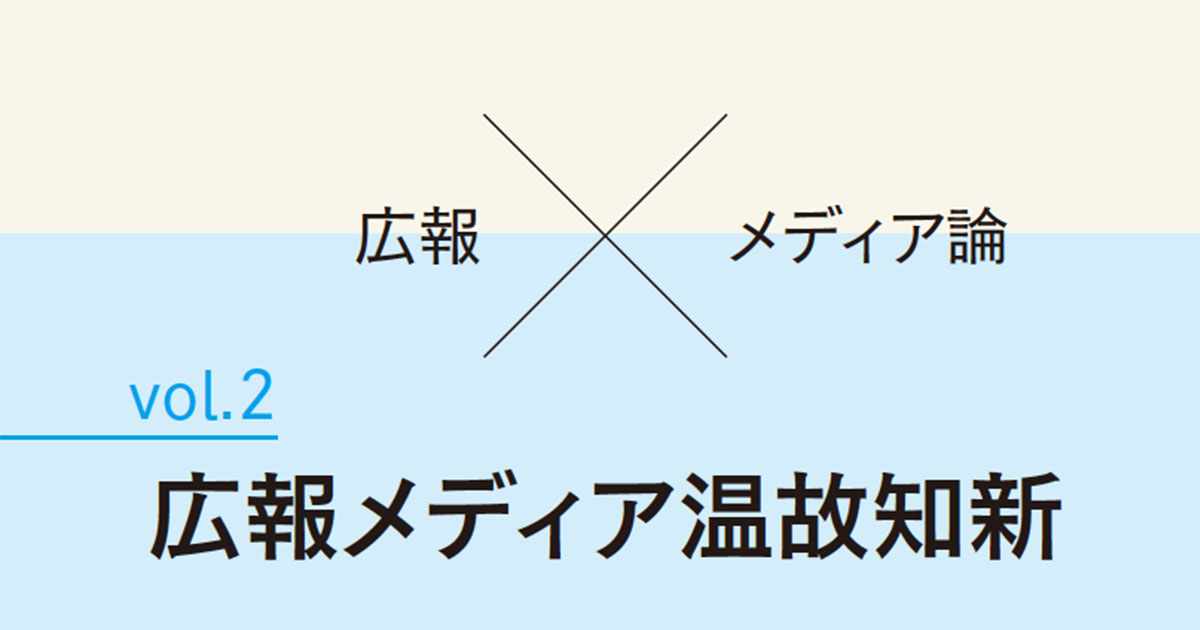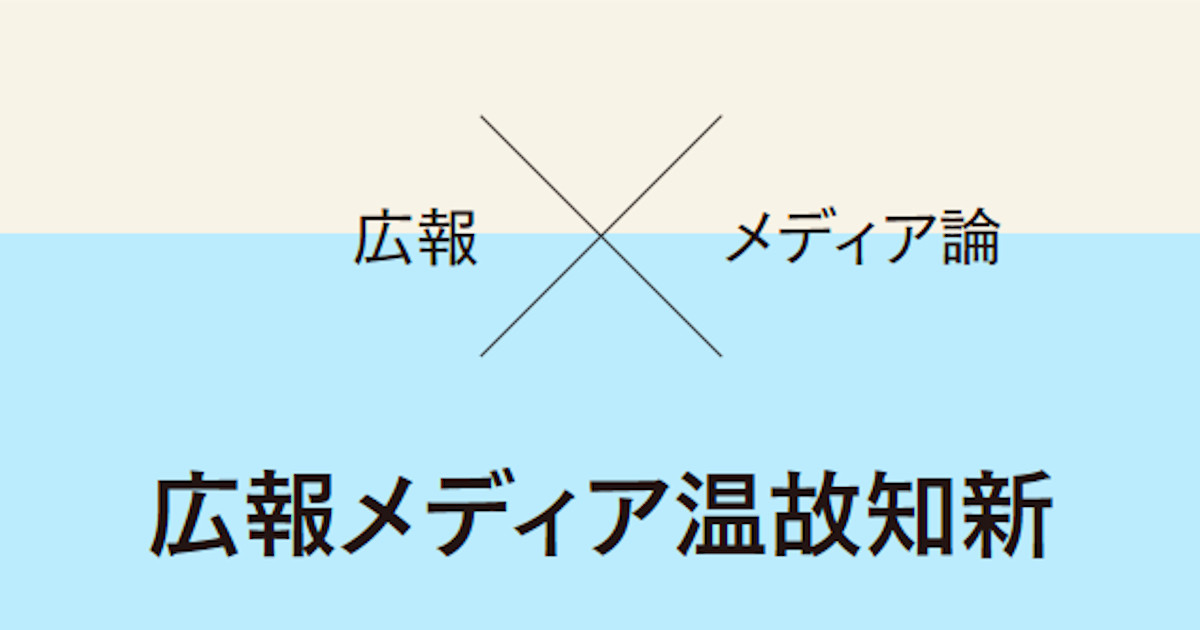広報活動には、新しいメディアが積極的に使われています。メディア史の観点から考察すると、どのような期待のもと、メディア利用がなされているのか、その本質が見えてきます。
コロナ禍における企業広報のあり方のひとつとして、noteを活用した「オープン社内報」が注目を集めています。在宅勤務が定着した一方、社員同士のつながりが希薄化しかねないなかで、離れていても連帯感をはぐくむ手段として、noteを活用する企業が目立ちます。noteではSmartHR社が、2019年3月から「#オープン社内報」というハッシュタグを利用していて、今ではnote公式のおすすめタグに指定されています。
想定される読者は社員だけではありません。例えば、採用活動としての企業訪問や企業説明会なども制限されるなかで、コロナ禍での企業活動の積極的な開示は、就活生の興味を引くことにつながり、逆にミスマッチを防げる利得もあるでしょう。
もはや社内報とは呼べないのではという疑問も頭をよぎりますが、昔ながらの社内報も、想定読者は必ずしも社員だけではありませんでした。
社員の家族との交流
日本における社内報の歴史は明治末期まで遡ることができますが、経営理念の近代化とともに、その役割は大きく変わっていきました。1950年代後半から60年代にかけては、企業の大規模化にともなって、「PR」や「HR」、「社内コミュニケーション」の重要性が広く謳われ、「社内報ブーム」と呼ばれる状況が生まれました...
あと66%