PR会社などで活躍する若手・中堅のPRパーソンが現場の仕事やPRの未来像を語ります。
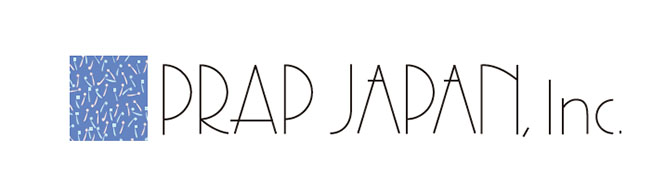
| DATA | |
|---|---|
| 創業 | 1970年 |
| 代表者 | 鈴木勇夫 |
| 沿革 | 豊富な経験と実績を持つコミュニケーション・コンサルティングカンパニー。日本・中国・東南アジアを中心に国内外でPR戦略からデジタル領域まで、あらゆるコミュニケーションコンサルを提供。 |

住川智香(すみかわ・ともか)
2014年入社。輸入車メーカー、IT、製薬会社など、主に外資系クライアントを担当。虹色PRパートナーメンバー。

松尾 陽(まつお・あきら)
2014年入社。BtoC案件をメインに企画立案・実行を担当。デジタルPR研究所研究員を兼務。
2020年9月に創立50周年を迎えたプラップジャパン。長年を通して蓄積した知見と、プロフェッショナルなコンサルタントの確かな手腕で、これまでも多くの企業の課題を、包括的なコミュニケーションアイデアで解決してきた歴史あるPR会社だ。
同社の第一線で活躍する住川智香氏と松尾陽氏は共に2014年の入社。住川氏は大学時代、理系の学生が自らの手で車をつくって走らせる「学生フォーミュラ」のサークルに所属し、メディアも訪れる大規模イベントでフォーミュラそのもののPRを手掛けたことが、業界を知るきっかけとなった。
「同級生からの『この活動をいろいろな人に知ってもらえて嬉しかった』という言葉が印象的。PRは、情報を受け取ったメディアだけでなく、彼らのようなつくり手にもやりがいや新たな発見を見出すチャンスになるという気づきが得られました」と住川氏は言う。
一方松尾氏は、メディアや社内メンバー、地域住民などあらゆるステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、PRは幅広い課題解決ができるのではないかと業界そのものに可能性を感じ、同社へ入社した。
「特にSNS分野のプロジェクトを担当することが多いです。なかでも炎上対策は個人的にも関心の高い領域。当社ではオリジナルの炎上事例のデータベースを活用し、過去事例を参考にしながら炎上リスクを推察しています。こうしてデータも活用しながら、できる限りプロジェクトの初期段階でクライアントに炎上リスクのアドバイスができるよう心掛けています」(松尾氏)。
コロナ禍を通じ、クライアントからの相談にも変化が生まれていると両氏は言う。特に、リアルの場で実施することが当たり前であった新作発表会や記者会見などの代替措置をどうするか、頭を抱える企業は少なくない。プラップジャパンでは3月、早々に「リモート記者会見パッケージ」も用意し、メディアとのつながりの場を絶やさないよう、オンラインも活用した提案を続けている。
「輸入車メーカーの記者発表では、せっかくオンラインでやるならばオープンなイベントにしようと、一般の視聴者も受け入れました。ただ、記者発表会ではメディアだけが知れる情報も必要なので、イベント終了後にオンラインで囲み取材も実施するといった工夫も凝らしました」と住川氏。松尾氏が担当したリモート記者会見の案件でも、オフライン以上に記者が参加しやすかったこともあって、出席率は過去開催時の2倍以上になった。
コミュニケーションの形が大きく変わろうとしている今、PRの存在価値は間違いなく大きくなっている。「PRは一般的にパブリシティを指すことも多いが、SNSなどあらゆるコミュニケーション手段を用い、トータルで課題を解決できるコンサルタントになりたい」と松尾氏。住川氏は、ダイバーシティにまつわるコミュニケーションの課題を解決する「虹色PRパートナー」としても活動していることから、PRの力を通して、社会課題の提案とその解決の糸口も提案できるような働きをしていきたいと意気込む。
お問い合わせ
株式会社プラップジャパン
https://www.prap.co.jp/
〒107-6033 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル33階
















