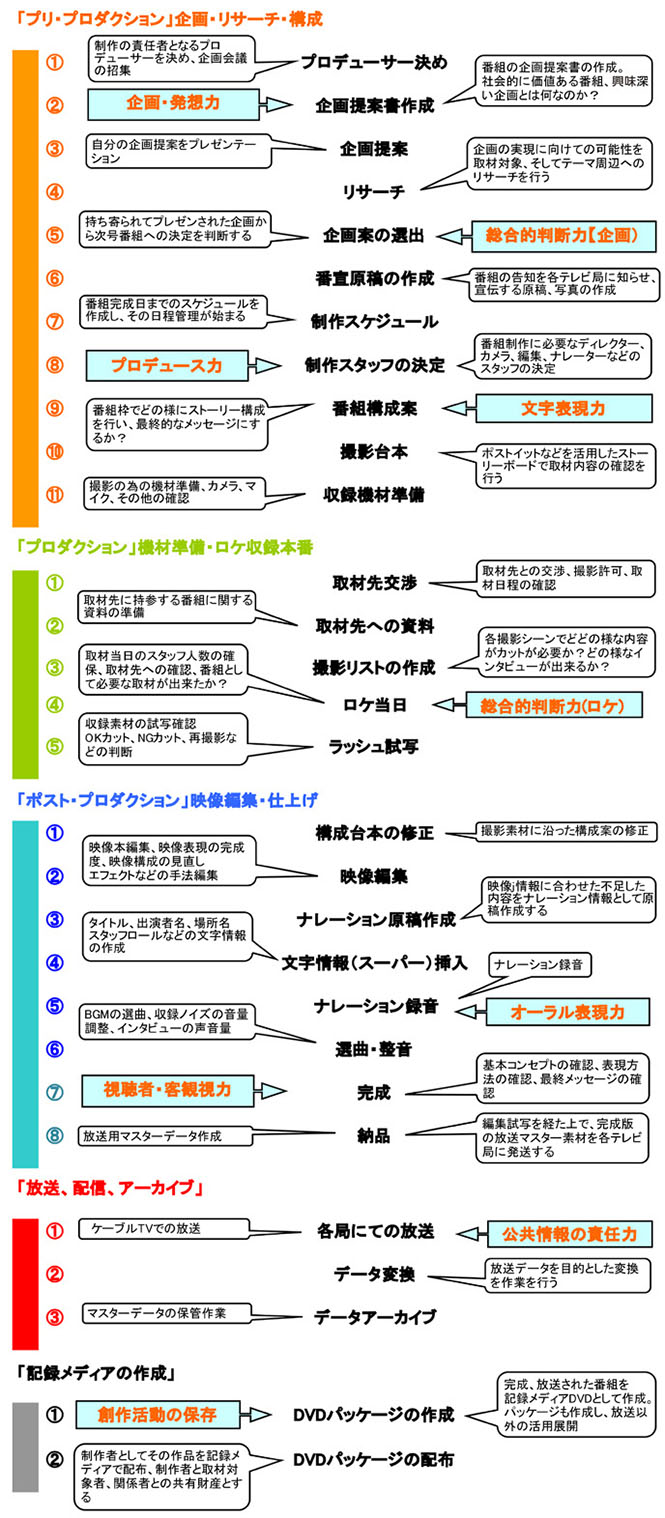メディア研究などを行っている大学のゼミを訪問するこのコーナー。今回は東海大学の五嶋正治ゼミです。

特別ドキュメンタリー番組『大船渡こどもテレビ局2013夏』。現地の仮設住宅で上映会も行った。
| DATA | |
|---|---|
| 設立 | 2006年 |
| 学生数 | 2年生10人、3年生6人、4年生8人 |
| OB/OGの主な就職先 | テレビ朝日、新潟総合テレビ、湘南ケーブルネットワーク、TBSスパークル、ザ・ワークス、ハウフルス、アトリエNOA、ジーズ・コーポレーション、ビー・ブレイン、ヌーベルバーグ、東急エージェンシー、びびあっぷ、インピッシュ、東京ビデオセンター |
東海大学 文化社会学部 広報メディア学科は全国でも数少ない、メディアだけでなく広報・PRの専門知識が学べる学科である。「報道」「生活・エンタテイメント情報」「PR・広告」の3分野について総合的に学ぶことができ、実践的な教育では、テレビ局とも連携し、実際に放送される番組制作を行っている。
コロナ禍でできる番組のアイデア
同学科で教鞭をとる五嶋正治教授のゼミ室では、ドキュメンタリー番組『ミネスタウェーブ』、インタビュー番組『東海Book Café』の2つの15分番組を隔月で制作し、年12本のテレビ番組を全国15ケーブル局で放送している。番組放送のキー局でもある地元平塚市のテレビ局には、五嶋ゼミ室出身のOBが就職しており、今ではゼミ生の教育活動や番組制作に携わってもらうなど、ネットワークが構築されている。
3月末からは新型コロナの影響でキャンパスが閉鎖。しかし、今まで先輩が続けてきた番組制作を止めてはいけないと、遠隔・リモートによる制作にスイッチした。「会えない距離でも取材できたり、これまで取材した人のその後を取材するアイデアが生まれるなど、工夫や発想次第で、リモート取材ならではの利点を感じました」とゼミ生。一方で、「画面越しだと軽い相談や意思疎通が難しい。制作の面では、報連相が十分に行われず、仕事量が偏ったりしたこともありました」とその難しさを語った。

ゼミはZOOMで実施。
ゼミ生企画の特別番組
ゼミ授業では、学科での学びを活かしつつ「過去と今を映像メディアで伝える」を目標に掲げ、1年間をかけて実際に番組制作を行っている。その内のひとつが『大船渡こどもテレビ局~10年の軌跡~』だ。これまで五嶋ゼミ室では2011年に起こった東日本大震災を受け、毎年3月11日に2時間の特別番組を制作、放送してきた。岩手県大船渡市への被災地取材を数十回行ってきて築き上げてきた信頼関係と10年の軌跡を撮った映像をもとに、番組を再構成する予定だ。
「コロナ禍でもできるテレビ番組の企画を考えていた中で、今までの五嶋ゼミの先輩方が築き上げてきた映像資料を使わない手はないと思いました」。現在はテレビ局への企画プレゼンに向け、ゼミ生一丸で準備を進めている。
番組制作を通じて成長を
映像制作の過程を通じて「コミュニケーション力」と「人間力」を学んでほしいと五嶋教授。「ものをつくり出すにはひとりでは難しいのが今の社会。どんなに壁にぶつかっても、アイデアを出しあい、協力しあうことで解決されることでしょう。番組はその成果物にすぎません。取材や制作の仲間とのコミュニケーションを通じて、人間として成長してもらいたいです」。
2011年から継続してきた被災地取材の集大成
前職でドキュメンタリーの国際共同制作に携わり、海外テレビ局との日本紹介番組や海外取材を経験してきた五嶋教授。「次の世代の若者たちに“国際的に評価される映像制作”を託したい」との想いから、教育現場にシフトした。
「『大船渡こどもテレビ局~10年の軌跡~』は10年間のゼミ活動の集大成でもありますが、私にとっても教員生活のいいまとめになると考えています。教員生活15年間で培ってきた教育の基盤、またメディア制作の“難しさ、曖昧さ、苦しさ、楽しさ”を今後も継続してもらえるよう、指導に全力を注ぎたい」と意気込む。

五嶋正治(ごとう・まさはる)教授
前職は、日本文化を海外に紹介するドキュメンタリー番組の制作に長く携わり、20年間で50カ国以上の国々のテレビ局スタッフとの国際共同制作で100以上の番組制作を担当。2002年から教育現場とも関わる。東海大学では、「皆既日食中継」「震災特別番組」「One Minute Videoコンテスト中継」など毎月定例放送している番組指導をしている。