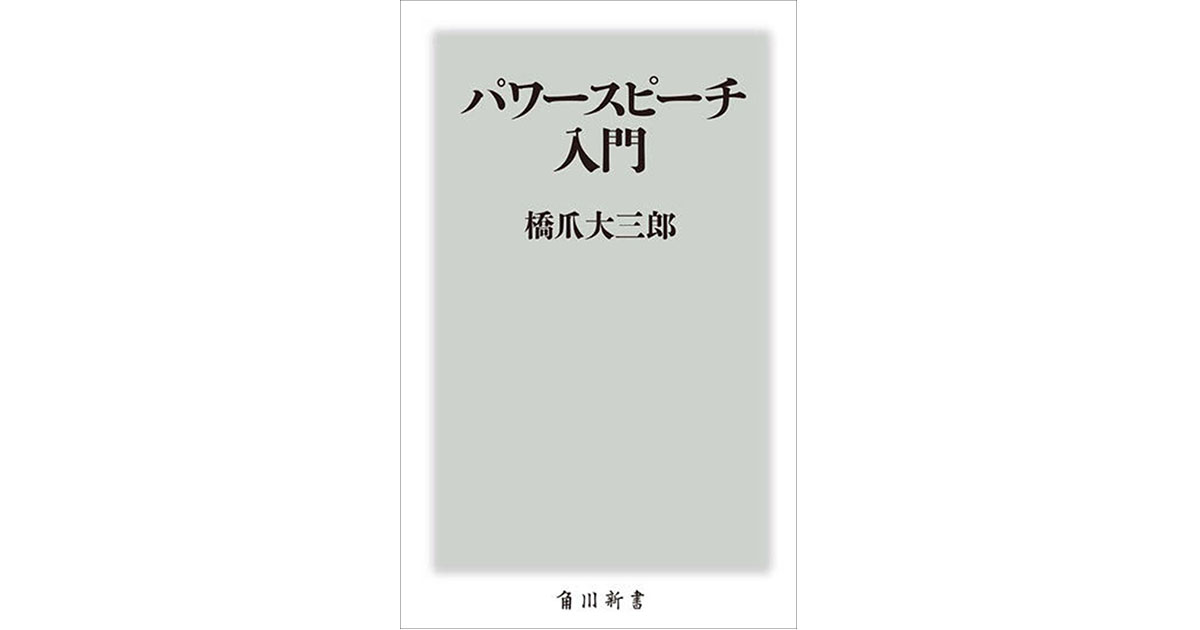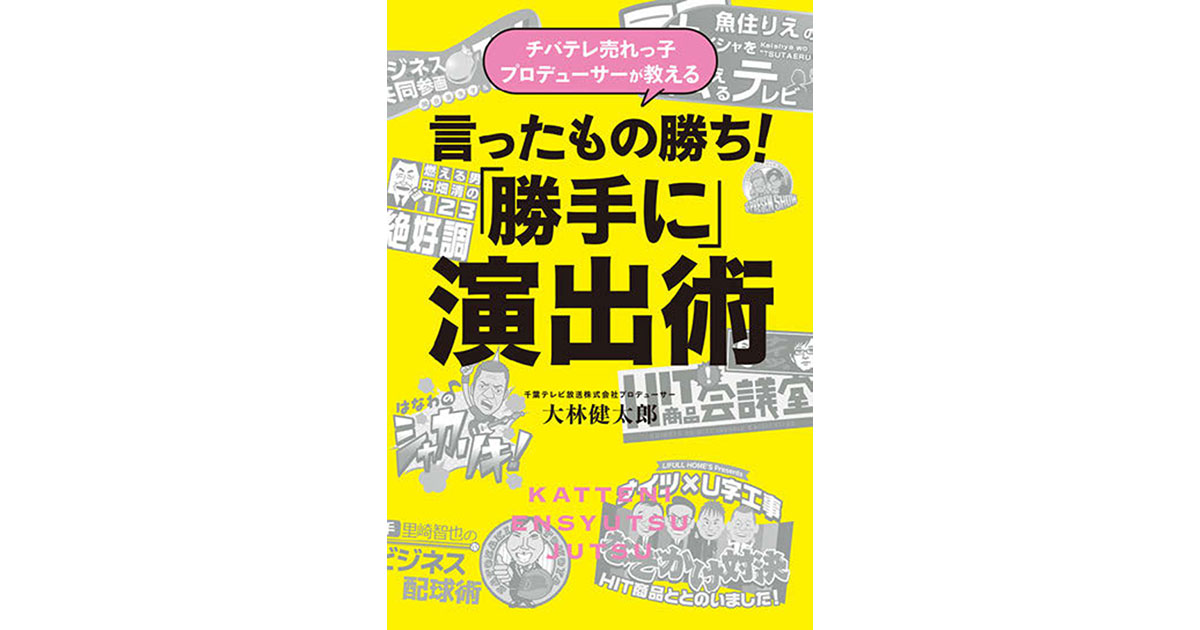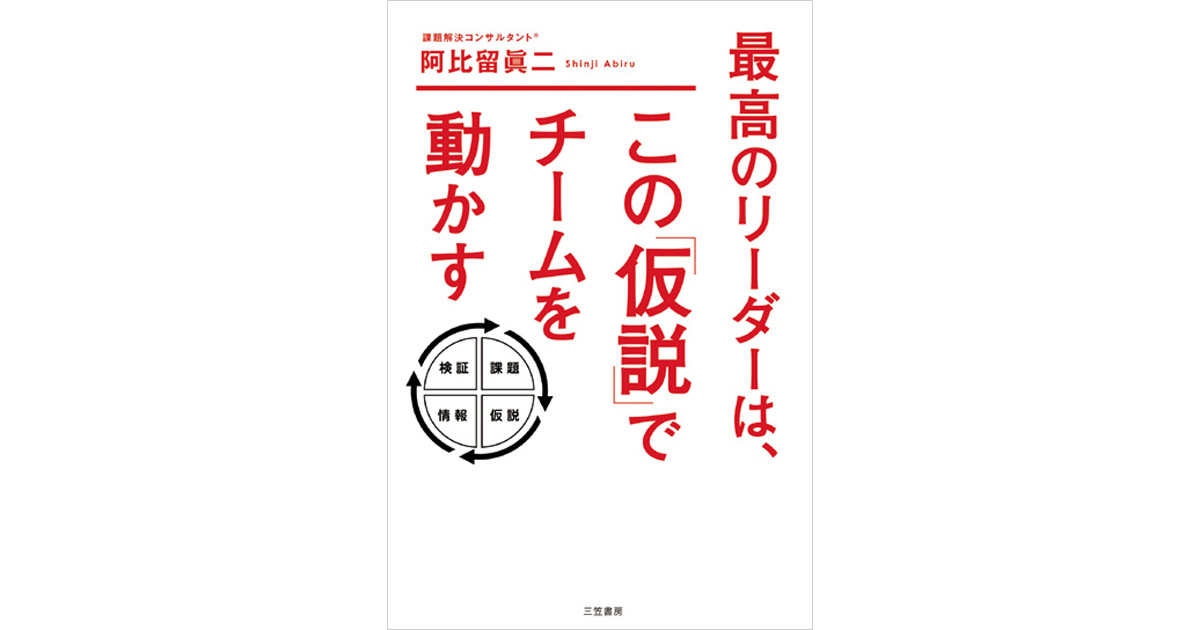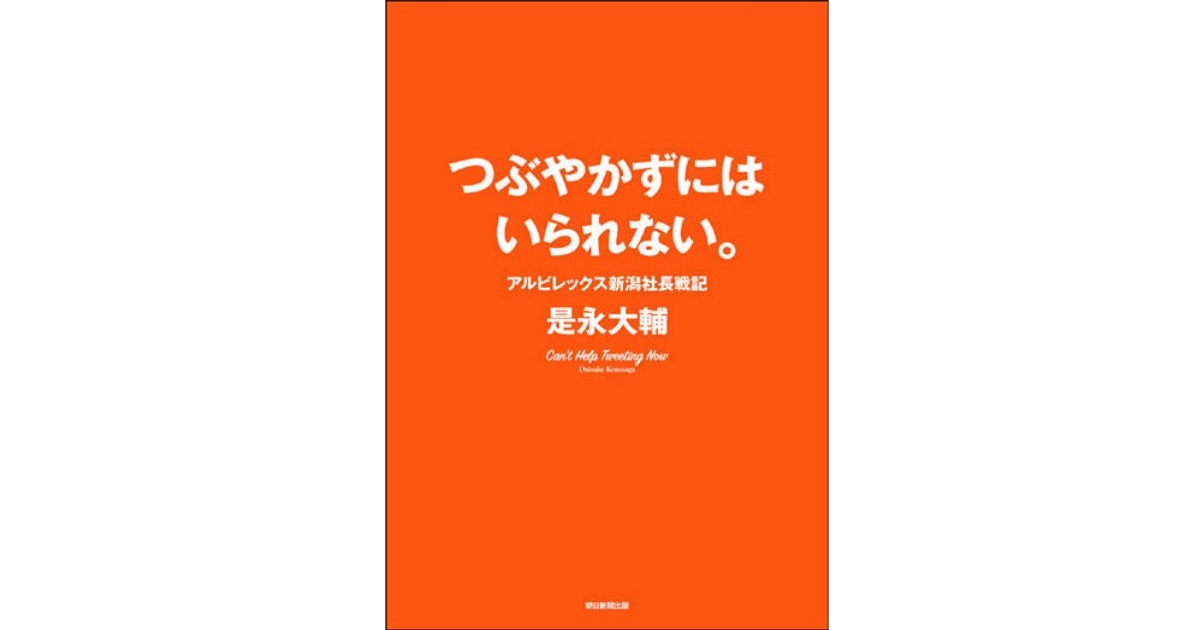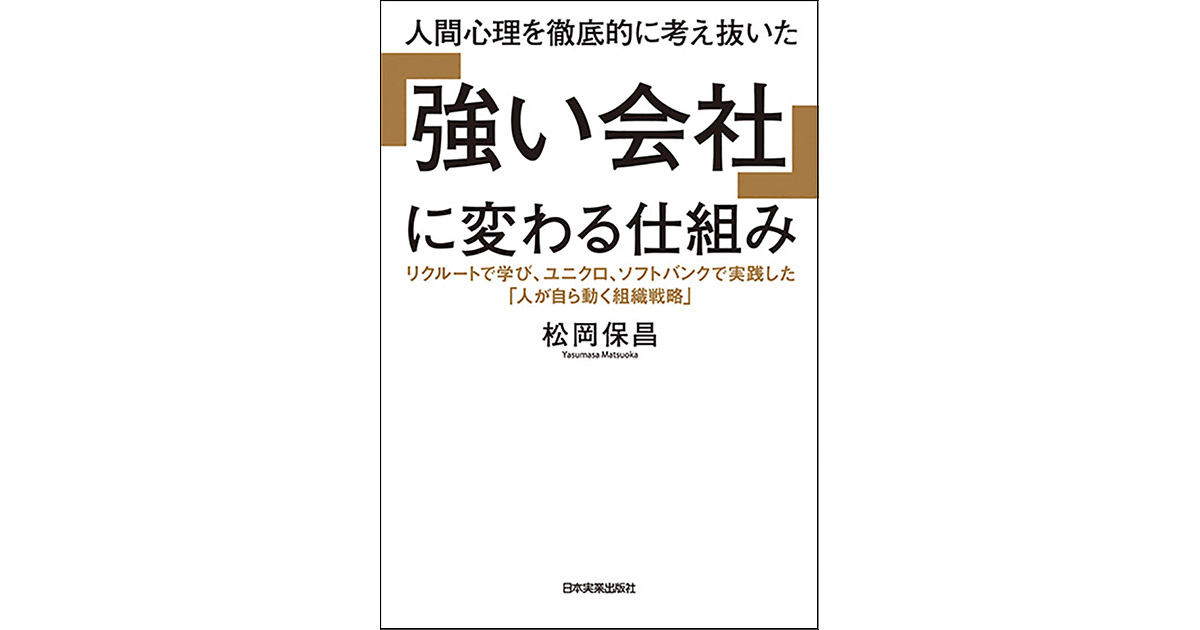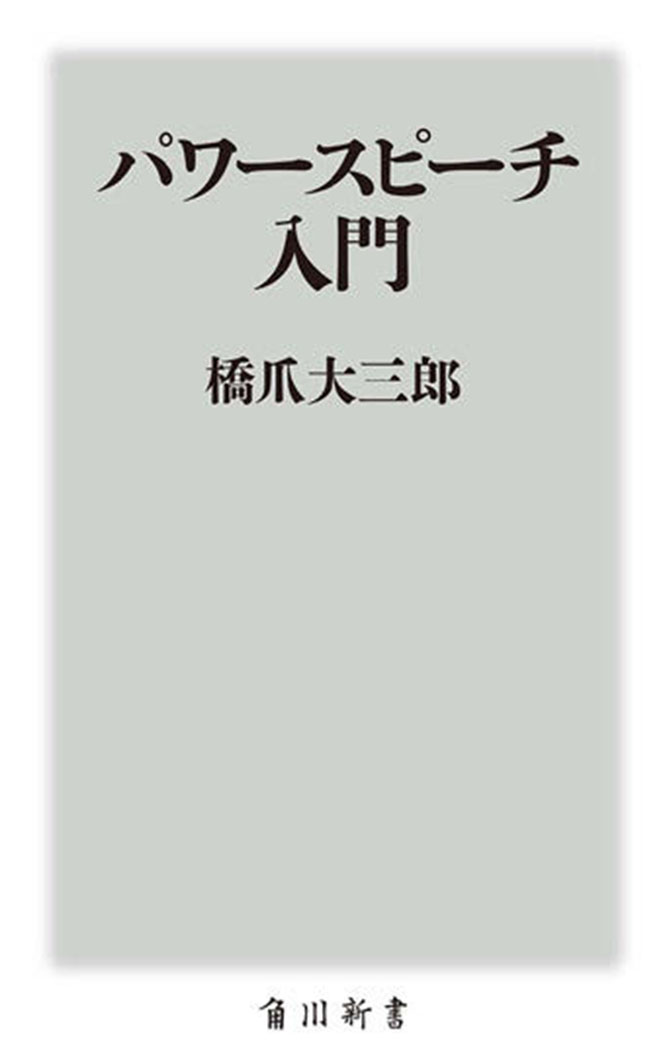
パワースピーチ入門
橋爪大三郎/著
KADOKAWA
304ページ、900円+税
本書のタイトルにもなっている「パワースピーチ」。それは、「力強いスピーチ。人を動かすスピーチ。勇気が湧いてくるスピーチ」のことだと、著者の橋爪大三郎氏は言う。今回のコロナ禍のように、大変な危機に陥った場合には、リーダーが何をどう言うかが重要だ。それがパワースピーチであるためにはどうしたら良いかを、各国の事例や歴史をふり返りながら、丁寧に解説。ついでに最近の“とある”スピーチも大胆に添削している。その明快な語り口に、読者も明日から実践してみたくなること請け合いだ。
“明快さ”がポイントに
本書がパワースピーチの典型として挙げるのが、クオモNY州知事だ。クオモ知事は、州内でコロナの感染が初めて見つかった3月上旬から連日、会見を開いている。「前半はデータ、後半は意見」が、基本パターンだという。まず、「最新のデータを紹介。州内のコロナ感染者、死者の数や病院の状況を、順に説明。それが済んだら、自分の考えを述べます」。
さらに、英語が分かりやすいのだという。小学校高学年レベルの語彙を使用している。「NY州の人びとは英語がよくできるとは限らないから」とは著者のコメントだ。「科学にもとづく現状の認識」を踏まえ、「めいめいの考えを意見交換」し、これから何をするか、方針を決めよう。そんなメッセージがはっきりと伝わってくるクオモ知事のスピーチは、聞いているうちに「安心感が湧いてくる」という。
ほかにも、ドイツのメルケル首相の演説や、その昔、第二次世界大戦が勃発した翌々日のチャーチルの演説も取り上げて、パワースピーチのパワーの秘密を、掘り下げている。スピーチスキルを向上させるヒントが満載だ。
そもそも、なぜ今「スピーチ」?
そもそも、なぜ今「スピーチ」なのか。そう尋ねると、こんな答えが返ってきた。「スピーチは、“口頭”で考えを伝えますよね。そもそも近代は、“文字”(文書)が基本の社会なんです。職場でも学校でもそうです。でも、“口頭”のコミュニケーションが大事な場面もある。たとえば軍隊。戦場では文書をつくっている暇がない。あと、政治がそうです。議会で演説し、街頭でも演説して、人びとに訴えかけ、考えを変えてもらう。軍隊も政治も、限られた時間で事柄の本質を伝え、相手を動かす点は共通なんです。
そして実は、すべてのリーダーがそう。今回のコロナ禍。目まぐるしく変わる状況の、本質を取り出して、的確に伝える能力が求められました。ところが、そういった文字に頼らないコミュニケーションが、日本人は苦手なんです。それを何とかしたかった」。つまり、日本人のスピーチスキルを底上げして、社会をよくしようという提案だ。
これは広報にも大きく関係するという。「広報は、社内でやりとりしている言葉を、どうやって外の人びとにも分かりやすい言葉に“翻訳”するか、そして、その会社のファンをつくれるかがカギでしょう。本書は、リーダーの演説のあるべき特徴を取り上げましたが、ちょっと味付けを変えるだけで、広報の担当者が紡ぎ出さなければならないコーポレートストーリーのヒントになるはずです」。なるほど、と思わずうなずいてしまった。

橋爪大三郎(はしづめ・だいさぶろう)氏
1948年神奈川県生まれ。社会学者。大学院大学至善館教授。東京工業大学名誉教授。1977年東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。『4行でわかる世界の文明』(角川新書)、『はじめての構造主義』(講談社現代新書)、『皇国日本とアメリカ大権』(筑摩選書)など著書多数。