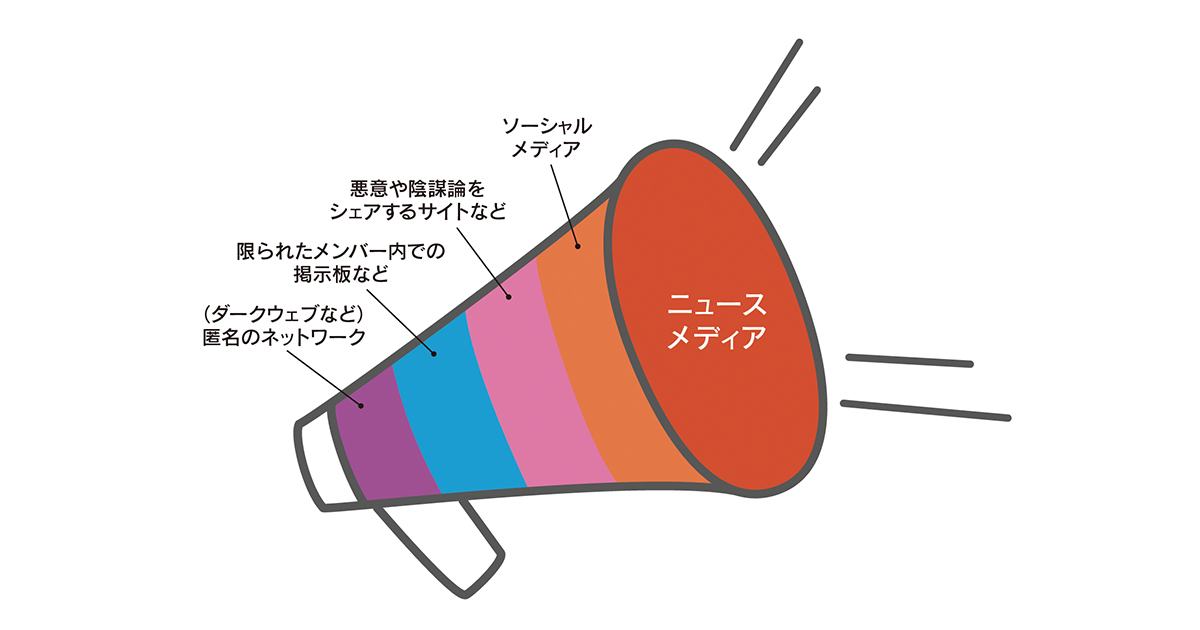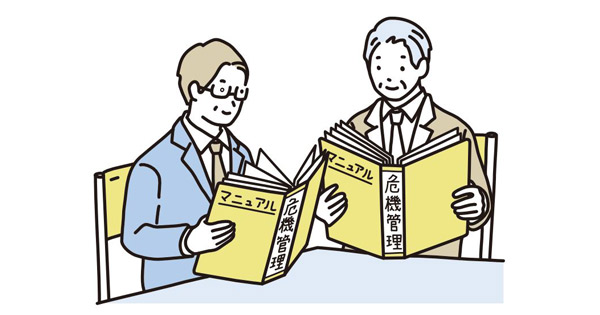緊急事態宣言後の広報の対応事例は、有事のリスク回避対策として学ぶべきところが大きい。ウェブリスクに詳しい著者が、コロナ禍で情報開示を行い、信頼を得た事例、批判を受けた事例とその傾向を解説する。
コロナの長期化が誰の目にも明らかになった。見通しの利かない中で、多くの人が不安とストレスに苛まれている。ネット上では考えの違いから衝突が増え、情報発信にはこれまで以上に気をつかうようになっている。本稿では、このコロナ時代に特に意識したいポイントを3つのキーワードを軸に考えていく。
Keyword ❶ 「安心」を伝える
記者会見で明らかになる感染拡大の状況、様々な専門家による解説と主張、そしてネット上にうずまく感情的な言説に、不安を掻き立てられることが少なくない。
そんな中で、少しでも心を落ち着かせられるような、「安心」につながる情報を社会は求めている。安心が得られない場合にはこれまで以上に強い不信感や反発を引き起こしやすい。
安心を生むには、新型コロナウイルスで不安視されている安全性・信頼性・透明性に特に配慮した情報や表現が必要だ。順に見ていこう。
安全性
これまでの日常では、安全であることは当然のことだった。それが新型コロナウイルスの感染拡大で「見えないもの」への恐怖が増大し、安全は意識して選択・獲得するものへと認識が変化したと考えられる。
さらに踏み込んで言えば、安全であることを確認できる情報を積極的に探す人が増えていく。
コロナ時代に何よりも重要で、必要不可欠なキーワードが「安全性」と言ってもいいだろう。そこで、安全のための取組みをこれまでよりも意識的に、そして具体的に伝えるようにしたい。
たとえば、店舗のレジで、従業員の安全確保のために飛沫感染防止の透明ビニールシールドの設置や防護マスクの利用を始めたといった感染拡大防止に関する直接的な情報はもちろん、在宅勤務が広がる中でも個人情報の漏洩が起きないための仕組み、現場スタッフ減でも事故防止を徹底する体制など、コロナの緊急事態においても、毎日のオペレーションが安全に滞りなく進められるための工夫は重要な情報だ。
信頼性
コロナ以前は、知名度やブランド、売上規模やシェアなどそれ自体が「確かである」ことの一定の説得力を持っていたが、今や未知のウイルスの前に、感染経路も検査の精度も経済支援の効果も、「よく分からない」ことがあちこちで起きている。同じ感染症の専門家と呼ばれる人の間でも、異なる主張を展開するのを見聞きする毎日だ。
こうした状況の中で、「何が本当なのか」という不安感・不信感の高まりが生まれていることを理解しておきたい。見方を変えれば、テーマを問わず、伝えている内容それ自体が、本当だということを明らかにする情報が必要になっている。
根拠としている論文は実在するのか。素材や組織などの固有名詞に誤植はないか。監修者の経歴に詐称はないかなど、これまで以上に確認をした上で情報を発信したい。
透明性
透明性とは、購入や利用などの判断に重大な影響を与える情報を隠したりすることなく、組織内の決定プロセスや進捗・経過などを明らかにすること。これは先に述べた信頼性にも関連のある概念で、組織が発信する情報が、内部スタッフから見ても嘘がない状態になっていることを示すことでもある。
さらに今、求められている透明性は、単に可視化を進めることだけではない。施策やその方向性が持続可能(サステナブル)なのかどうか、そしてコロナの時代に負けない強さがある(レジリエント)かどうかも含めて説得力のある伝え方を検討したい。
参考例として紹介したいのは、1900人を解雇することになったAirbnbのCEOが社員に出したメッセージだ。1900人は同社の約25%に及ぶ規模だという。
チェスキーCEOは「我々は信じられないほどの困難に直面しているが、会社を去らねばならない人たちにはさらに厳しいことだと理解している」「どのようにこの決定に至ったか、去っていく人たちにどんなケアをするか、そして次に何が起きるのか、できる限り多くのことを伝えよう」とし、具体的な情報を書いて、それを一般公開もしている。隠し事なく伝えるという姿勢はもちろん、この先続く困難を生き抜くための考えを力強い言葉で綴っている...